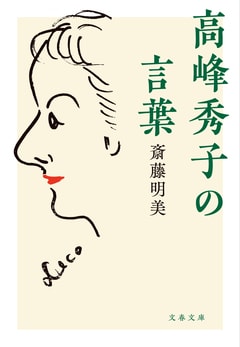川端康成や小林秀雄、白洲正子らにあつい信頼を寄せられていた京都の古美術商・柳孝は、中里恒子の魅力について、比類ない端的なことばで表現している。曰く、「眼すじの良い方」(「眼すじの良さ」、『中里恒子全集 第18巻 月報』、一九八一・三、中央公論社)。中里恒子が柳孝の店を初めて訪れたのは、後に歴史小説『閉ざされた海』(一九七二、講談社)としてまとめられることになる宇喜多秀家やその妻・豪姫について、構想を巡らしていた一九六〇年代後半にあたる。桃山時代の茶人や武将の消息(手紙)を求めて来店したのだが、その折の中里恒子の品選びに対して得た印象が、骨董商の用語である、右記のことばであった。
この「眼すじの良さ」こそ、本書に収録された随筆すべてに貫流している中里文学の特性であると言っても過言ではない。それを育んだ要素が無数にあることは承知の上で、いま、試みに次のような三点に集約してみる。一点目は、豊かな暮らしに醸成されつつ、それを根底から見詰め直す経験を重ねてきたこと。二点目は、文学修業の中で多くの優れた文士たちと交流し、彼らの去就を見届ける役割を果たしてきたこと。そして三点目は、衣食住の隅々にまで行き渡る充実や洗練――いうところの文化資本の蓄積と暮らしにおける実践を、何者かになった証しとしてではなく、年齢に囚われず、新たな存在へと踏み出す起点とする発想を持ち続けたことである。
中里恒子は一九〇九(明治四二)年に、神奈川県藤沢市に父・万蔵と母・保乃の次女として生まれている。中里家は代々、呉服太物問屋として栄えた富豪であったが、父が書や和歌・俳諧、古美術蒐集に傾倒したことにより、恒子が小学校に上がるころには破産して店を手放すことになった。一家は伊勢佐木町一帯の地主であった父方の叔母に助けられつつ、過ごすこととなる。長兄は横浜財界の重鎮・増田嘉兵衛が経営する貿易会社に勤務し、ロンドン支店に派遣され、また長兄と同じ会社に勤めた次兄もシドニー支店への転勤を命ぜられる中、恒子は横浜紅蘭女学校(現・横浜雙葉学園)に学んだ。
一九二三(大正一二)年、経済恐慌のあおりで増田嘉兵衛の営む貿易会社が倒産し、帰国命令を受けて次兄は帰国、長兄はイギリス婦人と結婚して後に帰国した。関東大震災により、家も学校も倒壊したことで、恒子は暮らしの原点を見詰め直す経験をする。被害が少なかった川崎実科高等女学校に転校し、同校を卒業した。
読書好きの少女が、本格的に文学を志す契機となったのは、母方の縁者であった菅忠雄(当時、文藝春秋社勤務)の紹介で、永井龍男の知己を得たことである。菅忠雄は恒子の文才を認め、作家修業の手解きを行い、一九二八(昭和三)年、「創作月刊」(六月号)にデビュー作「明らかな気持」が掲載された。以後、永井龍男の推挽で堀辰雄や竹山道雄、神西清らの文芸同人誌「山繭」に参加し、また渡辺千春伯爵未亡人・とめ子が主宰する文芸同人誌「火の鳥」にも活躍の場を拡げる。「火の鳥」に掲載された作品群によって、後には横光利一や川端康成にも注目される存在となった。恒子が兄の友人の弟である資産家・佐藤信重と結婚したのは、こうして作家として歩き始めた年の暮れ、一九歳のときである。佐藤家には、義兄の結婚相手であるフランス婦人がいた。結婚翌々年には長女・圭子が誕生している。
本書の冒頭を飾る「閑日月」(「火の鳥」、一九三三・一)が発表される前年、軽い肺結核を患った恒子は、新婚生活を送った東京を離れ、養生のために逗子町桜山に転居した。幼少時から縁のあった同地に魅せられた恒子は、ここにサンルーム付きの家を建て、以後生涯を通じてここで暮らし、執筆活動をすることとなった。実兄や義兄の連れ合いであった西洋婦人たち、その子どもたちである姪や甥たちとの交友の舞台となった家でもある。戦後、夫と離婚した後も、この家を離れることはなかった。「女三界に家なし」ということばが当たり前のように使われていた時代、ヴァージニア・ウルフが女性が小説を書く必須条件として「私だけの部屋」の必要性を説いた時代に、自分の居場所をひっそりと死守して書き続けたのが、中里恒子であった。本書の「I 日々の楽しみ」に集められた作品群によってその暮らしの中で磨かれた感性や洞察力に惹かれた読者は、ぜひ『わが庵』(一九七四、文藝春秋)をご一読されたい。
一九三九(昭和一四)年、前年に「文學界」(九月号)に発表した「乗合馬車」他によって第八回芥川賞を受賞。女性初の快挙であった。「乗合馬車」は異国暮らしを余儀なくされた外国人の親族たちとの触れ合いを綴った作品で、後に連作小説『まりあんぬ物語』(一九四七、鎌倉文庫)として中里文学の中軸を担うものとなった。本書の「II 旧友たち」に収録された「横顔」の横光利一、「生涯一片の山水」の川端康成、「河上徹太郎さん逝く」の河上徹太郎のいずれもが、「文學界」の同人であり、恒子の才能を高く評価して畏友として彼女を育ててきた人々である。ことに横光利一からもたらされた「書き過ぎてはいけない」ということばを恒子が生涯大切にしたことはよく知られている。素直に導かれ、面白さを知ると静かに徹底した努力を重ね、手解きをした者が想像もしなかった境地に至る――川端康成や河上徹太郎ら、横光利一よりも長く生きて、中里恒子の文学者としての成長を見守った人々は、瞠目したに違いないのである。「III 本と執筆」には「俳句と小説の差(抄)」が収められているが、俳句の世界に恒子を導いたのも横光利一であり、恒子は後に「銀座百点」の忘年句会のメンバーを長年にわたって務め、句作の妙味も味わい尽くしたようである。
一九五六(昭和三一)年、アメリカに留学していた一人娘・圭子がアメリカ人と結婚するという知らせを得てショックを受けたが、「わが庵」に一人で暮らし、書き続ける決意を固めた後に待っていたのは、ゆっくりと止むことなく晩年まで続く円熟の季節であった。
それぞれに年を重ねた男女の恋を清新な筆致で描いた『時雨の記』(一九七七、文藝春秋)はベストセラーになりドラマ化や映画化されたことでもよく知られている。が、同年に刊行された『ダイヤモンドの針』(講談社)と題する、恒子自身の結婚と離婚の経緯を冷静で精緻な筆運びで綴った懺悔録、この二冊が併せ読まれてこそ、中里文学の真価が解ると言っても過言ではない。自由恋愛などとは無縁に、生きる方途として制度としての結婚を選び、真摯に生きて来た人々の中に在る、一世一代、好む人と好むように生きることへの希求。中里恒子が七十代を前に至りついた一つの文学的境地は、大人の恋を愛欲の場としてではなく、出会った二者の言葉遣いや振る舞い、佇まい、暮らしの隅々に行き渡る気配の交響として描き切ることにあった。書画骨董の好みや、歌舞音曲、茶や花のたしなみについてやりとりする恋人たちは間違いなくスノビズムに陥るものだが、『時雨の記』や『綾の鼓』(一九八五、文藝春秋)がそれを免れているのは、趣味趣向が自身の出身階層や地位を語るものではなく、彼等自身が自在の境地に在る証しとして描かれているからに他ならない。「IV おんならしさ」に収録されている「今朝の夢」が「婦人之友」(一月号)に発表された一九七八年は、『ダイヤモンドの針』と『時雨の記』が刊行された翌年に当たる。二十二年振りに渡米し、娘が彼の地に永住する意志が確固たるものであることを知った後、中里恒子は書斎の増築を実行している。七十歳を目前にした決断であった。「ひとの世の思いは深くなる、まだ未来がある」というマニフェストに違わず、中里恒子は七十七歳の死の直前に至るまで、「わが庵」での暮らしを慈しみながら、旅を楽しみ、ペンを執り続けたのである。