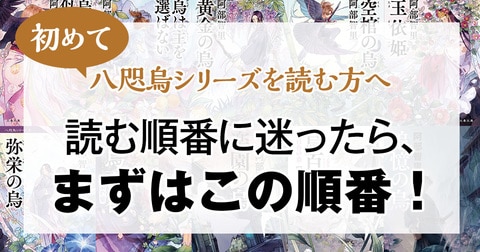NHKアニメ『烏は主を選ばない』の后選びは驚愕の展開…罪の深さを思い知る八咫烏外伝「はるのとこやみ」を全文無料公開!
ジャンル : #エンタメ・ミステリ
第13話で明らかになったアニメ『烏は主を選ばない』の后選びのゆくえは、皇太子・若宮の后候補」として登場していた、ヒロイン・あせびの意外な一面が明らかになり、ネットでも騒然となっています。しかし実際には、もっと深い闇が阿部智里さんの原作「八咫烏シリーズ」外伝の「はるのとこやみ」(『烏百花 白百合の章』所収)において描かれています。
あせびの母親・浮雲の知られざる過去とは? あせび出生の秘密とは? 本作をきっかけに「八咫烏外伝」にもぜひご注目いただきたく、「はるのとこやみ」期間限定(~2025年2月27日まで)で特別に無料初公開します。併せて謎の多い浜木綿については、同じく外伝「すみのさくら」をお読みいただければ幸いです。
八咫烏シリーズ 外伝
「はるのとこやみ」
阿部智里
「お前の音は、どうにも濁っている」
別室から聞こえていた笛や太鼓の音が、一気に遠くなる。
師匠が眉根を寄せて漏らした声に、伶は心胆が冷たくなるのを感じた。
春先の光は未だ固い。
よく磨きこまれた板の間には庭先の小石に反射した明かりがうっすらと差し込み、師匠の顔に刻まれた深い皺をぼんやりと浮き上がらせていた。
「申し訳ございません。自分にはまだまだ修業が足りず……」
「お前が誰よりも励んでいることは、よくよく承知しておる。これは力量の不足といった問題ではあるまい」
慰めるようなその言い方は、平素の師匠からすれば信じられないほど優しいもので、それゆえ余計に残酷であった。
「では……?」
竜笛を持つ手に汗が滲み、喉がからからに渇いていく。声に必死さが滲む伶に、師匠は憐れむような眼差しを寄越した。
「竜笛は、天と地を繫ぐものだ。山神と交信し、山内の陰陽を整える御神楽の先駆けぞ。結果としてそれを耳にする者の心を高揚させることがあったとしても、その逆はあってはならんのだ。喜怒哀楽を音に込めるは、雅楽にあらず」
――お主のそれは、俗楽だ。
愕然とする伶にため息をつき、師匠は眼差しをその隣へと向けた。
「倫。手本を示してやりなさい」
はい、とどこか戸惑いがちに応えたのは、自分と瓜二つの顔をした弟である。
手馴れた所作で横笛を構え、そして流れ出した音は、師匠が「手本」と呼ぶにふさわしいものであった。
滑らかな音の高低は神楽笛よりも落ち着いており、篳篥よりもしっとりとして、深く豊かな味わいがある。
すうっと空気が澄み、心の臓を直接つかまれたかのように大気が振動するのを感じる。
外から吹き込む風さえもその色を変え、きりきりしていた伶の気持ちすらも、さっとやわらかな羽の先でひとなでされたようになってしまう。
外からの弱い照り返しを受けて、色素の薄い瞳も、伏せられた長い睫毛も、くるくると癖の強い淡い茶の髪も、正確無比に動く指先も、自らが発光しているかのように輝いて見える。
一心に竜笛を奏でる弟の姿は崇高で、美しかった。
自分と弟の容姿はよく似ている。それこそ、見た目だけならばどちらが伶で、倫か、分かる人はほとんどいないはずだ。
だがひとたび竜笛を与えてみれば、その違いはこんなにも明らかだ。
どうして同じ卵から生まれた兄弟で、こんなにも違うのか。
――本当は、痛いほどにその理由は分かっていた。
「気にすることはないよ。裏を返せば、技量は十分だということだもの。あとは気持ちの問題だとお師さまはおっしゃりたかったんじゃないかな」
宴の支度のため、緋毛氈を二人して運んでいる最中のことである。
それほど落ち込んで見えるのかと思うと屈辱ですらあったが、倫は不出来な兄を慰めようと必死で、こちらの思いにはとんと気付いていない様子であった。
「その気持ちが、ついてこないから問題なんじゃないか。俺は、自分に出来ることは何でもやって来たつもりだ。この上、一体何をしろって言うんだ!」
嚙み付くように言って、伶は濡縁に緋毛氈を乱暴に落とした。
八つ当たりされたにもかかわらず、倫は困ったように眉を八の字にするばかりである。
伶と倫の兄弟は、山内は東領、永日郷の宿場町に生まれた。
貴族達からは山烏と蔑まれる生まれでありながら、こうして大貴族東家のお膝元で楽人見習いとして日々励んでいられるのは、東家の施策によるものだ。
この山内の地を四分割する四大貴族のうち東家は、楽家として中央に名を馳せた家である。関連して、東家当主は朝廷において儀礼、式典の諸々を一手に司り、それに必要な人員を東家系列の貴族で固めている。東家は本家、分家問わず、それぞれに得意とする楽器を持っており、儀式の要である神楽の奏者や舞手は、東家に連なる高級貴族達が花形を務めているのだ。
同時に、東家は東領全体に音楽を推奨し、身分を問わず才ある者は宮中に召し上げることも約束していた。主要な式典で演奏が出来るのは貴族だけであるから、実力さえあれば山烏出身であっても、当代限りでそれにふさわしい身分を与えられる場合もあった。
結果として、東領では楽を身の助けとする者が非常に多く、山内中から腕に覚えのある者が集まるようになっていた。
伶と倫の母親も、もとは東家お抱えの舞姫となることを夢見て東領にやって来た流れ者である。自身が取り立てられることは叶わず、楽人であった夫とも早々に死に別れたが、少しでもよい師匠につけるようにと東本家直轄地に居を移すほどに双子の楽才を見込んでいた。その努力は実を結び、双子は名のある竜笛奏者の推薦を受け、十三にして東本家の擁する楽人の養成所、外教坊に入ることを許されたのだった。
涙を流して喜んだ母は、現在、城下町で三味線奏者として働きながら、双子が宮仕えに成功し、自分を中央に呼び寄せる日を待ち望んでいた。
外教坊に入ってすぐの頃は、竜笛以外の吹物、弾物、打物と、雅楽に用いられる全ての楽器を一通り経験させられた。果ては舞や歌の手ほどきまで受けさせられ、それまでひたすらに竜笛を自分のものにすることに必死になっていた二人は、大いに困惑したものであった。
だがこれは、先々を見据えてのことであったと後で思い知らされた。
東家のお抱えになったからと言って、そのまま宮中に上がれるわけではない。実際に宮仕えするためには、この上さらに「才試み」という試験に受からなければならなかった。
既に宮廷において楽人として活躍している者達と合奏し、全員からお墨付きを得なければ、その仲間に入ることは決して許されないのである。
取り立てられる前は、同じ楽器を得意とする者の中で一番上手であることが肝要であったが、合奏するとなればそれでは足りない。全体の調和をつくり上げるためには、他を知る必要があった。
伶も倫も器用なほうではあったから、苦しみながらも最初の難関を無事に乗り越えることが出来た。十六歳となった今では、師匠に稽古を受けつつ、東家の下男として働きながら次の才試みを待つ身となっている。
そういった者の中には、いつまで経っても召人になることが出来ず、さりとて自分から諦めることも出来ず、外教坊から出られないまま無為に時間を過ごす者もいた。ただの下男と思って共に働いていた老爺が、外教坊の隅で物悲しく神楽笛を吹いている姿を見つけた時、伶は心底ぞっとした。ああはなるまいと思ったものだ。
そうして、一心不乱に竜笛を奏で、寝る間も惜しんで修業に励んだ挙句――「お主のそれは、俗楽だ」と、師匠に言われてしまった。
楽には魂の色が出る、というのが、師匠の口癖である。
全く同じように育ち、共に励んできた弟と自分。一体どこで差がついたのかと言えば、それはもう、「魂」の差でしかないだろうと伶は思っている。
外見も才能もそっくりではあったが、倫は昔から、伶よりもおおらかな気質を持っていた。
謂われない罵倒を受けた時、怒りに任せて嫌味を返すのが自分で、「どうしてそのようなことを言うの」と不思議そうに問い返すのが弟だった。
人の明るく優しい部分を形にしたかのような魂を持っていて、そんな倫が奏でる音は、奏者の性質を写し取ったがごとく澄んで、清らかなのだ。
――倫のような音は、自分には出せない。
伶は、肌身離さず懐に持ち歩いている竜笛を、ぎゅっと袷の上から握り締めた。
「梅花の宴は、気分を新たにするのにちょうどいいんじゃないかな」
押し黙る伶を励ますように、倫がわざとらしく明るい声で言う。
中庭には、紅白も鮮やかに咲きほころび、清しい香を放つ梅の木が立ち並んでいる。
それを囲む濡縁や透廊に、二人が緋毛氈を敷いているのは、明日にはここで梅見のための宴が開かれるからだ。
「宴って言っても、どうせ俺達は下働きばかりだろ。多少残飯のおこぼれがあるくらいで、ろくな楽しみなんかないさ」
伶が拗ねた声を出すと、倫は緋毛氈の皺をのばす手を止め、ぱちぱちと目を瞬いた。
「そんなことはないよ。今回はただの宴じゃないんだもの。普段なら、絶対聴けないような秘曲だって聴けるかもしれない」
「秘曲ねえ……」
明日の宴では、東分家の姫がここに集められ、楽人としての腕前を披露させられることになっていた。
将来この山内の地を統べる若宮殿下の后選び、いわゆる登殿の儀がもうすぐ始まる。四大貴族を代表する姫が中央の宮殿に赴き、若宮の寵愛を競うわけであるが、その候補者の選定が行われるのだ。
「楽家の姫と言っても、どれだけの腕があるのかは疑問だな」
どうせ血の濃さで候補を選んでいるんだろうし、と呟くと、倫は苦笑した。
「今の若宮殿下は風流人だから、お館さまは、多少縁遠くても腕のある姫を選ぶおつもりらしいよ。そうでなければ、こんなふうに姫君を比べるなんて真似しないだろ」
その言葉に思わず手を止め、まじまじと周囲を見回す。
宴の支度で下男下女がせわしなく行き交う一角には、これみよがしに御簾が下ろされている。
音楽は東家の本分だ。過去には、琴の音に誘われて若宮が訪れ、入内した姫もいるという。
だから東家当主は、家柄がよいだけの中途半端な娘よりも、たとえ入内が叶わなかったとしても、若宮が興味を惹かれそうな娘を選んで送り込むことにしたのかもしれない。
「腕のある姫ねえ……」
東家が、名よりも実を取る性質であるというのは、ここに来てから何度も耳にしていたことである。
東領には、南領のような財力も、西領のような技術力も、北領のような武力もない。文化的にいくら優れていようとも、ある意味、四領の中では最も弱いと侮られかねないのである。朝廷でうまく立ち回らなければすぐに力関係が崩れてしまう立場にあって、しかしそれゆえに、四家の中で最も政治上手なのだと聞いていた。
「まあ、歴代の東家当主さまが柔軟な方だというのは間違いないだろうな」
でなければ、自分達のような平民階級出身の者が、こんな場所にいられるわけがないのだった。
* * *
天候にも恵まれた宴には、候補となっている姫君が滞りなくやって来た。
朝からきらびやかな装飾のされた飛車や輿が途切れることなくやって来るので、下働きをさせられる伶と倫からすれば堪ったものではない。
ただ、姫達が御簾の内側にきっちり隠れてからは宴席の給仕へと駆り出されたので、倫の言うところの「腕のある姫」の演奏は耳にすることが出来た。
東家の姫が得意とするのは、長琴という楽器である。
よく知られる箏や和琴とはやや異なった構造をしており、その音色は、一面で神楽のための一編成に匹敵するとまでいわれている。東家秘伝の楽器とされているが、実際は昔ながらの形を守っているわけではなく、外界からの技術や様式なども取り入れ、貪欲に改良を重ねているらしい。分家ごとに形式も異なり、それを作る職人を囲い込んでいるのだという。
話に聞くことはあれど、双子も長琴を間近で耳にするのは初めてである。そして、御簾内から聞こえてきた演奏に「なるほど」と得心したのだった。
音階が特殊で、高低の幅が異様に広い。
長琴は、姫を際立たせるためのものであって、他の楽器と合奏することはほとんどない。それひとつでどれだけ華やかな音が奏でられるかが肝というだけあって、どんどん弦が増え、構造が複雑化していったのだろうことは想像に難くなかった。
おそらく、この日のために相当練習をしてきたのだろう。
どの姫も年の割に上手だな、とは思う。だが、日頃一流の奏者に囲まれ、音楽をこれひとつと定めて生きている身からすれば、どうしても物足りなさが勝る。
つまりは、巨大化し難易度が高くなっていく長琴に、姫達の手の大きさも体力も、全く追いついていないのだ。
御簾の内側では年端のいかない娘達が息を荒げ、青い顔で演奏しているのが目に見えるようで、どこか憐れでさえあった。
伶がこっそり上座を窺うと、この宴席を設けた東家当主とその嫡男は、隣り合ってよく似た微笑を浮かべていた。微笑ましげに演奏を楽しんでいるように見えなくもないが、宴が始まってから一切表情に変化がないあたり、彼らにとってもあまり思わしい状況ではないのかもしれない。
これじゃ、長琴の演奏で若宮の心を射止めるなど、夢のまた夢だな。
溜息をつくと、近くで酌に勤しんでいた倫が似たような苦笑を向けてきた。考えることはどうせ同じだと思った、その瞬間だった。
突風のような音が吹き荒れた。
けだるげにしていた客人も、そつなく酒をついで回っていた下男も、その場にいた全員がハッと息を呑んで御簾へと目をやった。
一瞬、何の音なのか伶には理解出来なかった。
それほどまでに、これまでの演奏とは明らかに質が異なっていた。
連なる音はなめらかで、拙さを感じる部分はどこにもない。
一音一音が粒立ち、豊かな余韻は響きあい、耳から入って腰が抜けるかと思うほど、甘い震えを聴衆にもたらした。
その音はまるで、艶然と咲き誇る梅を容赦なく吹きこぼしてゆく春風のようでもあり、満ち足りた天上の世界から溢れて出た、光そのもののようでもあった。
――それ一面で、神楽のための一編成に匹敵する音。
なるほど、これが長琴かと、感嘆せずにはいられない。
堂々としているのに、不遜な部分はまるでなく、奏者自身が演奏を楽しんでいるかのような余裕さえ感じられる。
最後の一音の余韻が空気に溶けて消えるまで、誰も彼もが動きを止め、うっとりと聞き惚れていた。
演奏が終わった後も、しばし、声を発する者は誰もいなかった。
「見事なり!」
静寂を破って最初に声を上げたのは、東家当主その人であった。
それをきっかけに、宴に集まった人々は目を瞬き、まるで夢から覚めたかのように顔を見合わせた。徐々にさざなみのような興奮が沸き起こり、口々に御簾内の奏者を褒めだす中、伶はただただ呆然とその場に立ち竦んでいた。
「いやはや、素晴らしい演奏だった。今の奏者は、一体どなたかな」
にこにこしながら東家当主が問うと、中庭の梅の古木を挟んで、反対側に下ろされた御簾がわずかに揺れる。
「お褒めにあずかり、嬉しゅうございます」
控えめに喜びを示したのは、小鳥のように高く澄んだ少女の声であった。
「わたくしは、東清水の浮雲と申します」
* * *
時をおかずして、東清水家の浮雲は登殿に備え、正式に東本家の姫として迎え入れられた。
梅花の宴以降、双子の話題は、もっぱら本邸にやって来た浮雲の姫君のことばかりであった。
「音域からして、長琴がかなり大きいのは間違いない。手の大きさは、努力じゃどうにもならないはずだ」
「だから、替え玉だって言うの?」
「そうとしか考えられないだろ」
伶は、あの演奏をしたのが少女だとはどうしても信じられなかった。
ただの箏を演奏するだけでも、相当に体力が必要なのだ。
年端のいかない小娘がそれ以上の大きさのものを簡単に弾きこなせるわけがなく、御簾の裏側では、熟達した技術を持つ女房を代理に立てていたのではないかと疑っていた。
「でも、長く楽家として栄えている家の出なんだから、生まれつき手の大きな、才能豊かな姫君が生まれてもおかしくはないんじゃないかな」
一方の倫は、奏者はうら若き乙女と信じ切っていた。熱っぽく語る姿には、彼女の楽才に心酔する勢いまでうかがえて、伶にはどうにも面白くない。
「奏している姿を見たわけでもないのに、よくもまあ、そう素直に信じられるもんだな」
「伶こそ何も見てないのに、よくもまあ、そう疑い深くなれるもんだね」
「俺達よりも若いのにあんな演奏が出来るなんて、天才でなけりゃあり得ないだろ!」
「じゃあ、彼女は真実、天才なんだろうよ」
いつまで経ってもこんな調子で、全くらちがあかなかった。
このままでは修業にも差し障りがあるのは明らかで、思いつめた挙句、双子は突拍子もない手段に打って出た。
つまりは、実際に姫が奏している姿を――御簾の内側を垣間見ればいい、ということになったのだ。
正式な楽人にもなれていない、下男同然の身でそんなことをしたと露見すれば、当然ただでは済まされない。最悪の場合、見習いとしての資格を剝奪され、母を悲しませることになると分かっていたが、どうしても好奇心には勝てなかった。
日中はいつも音が絶えない本邸ではあるが、夜になると見習いや楽人達は明日に備えて休むため、しんと静かになる。そうなると、ゆったりと演奏をするのはあくせく働く必要のない貴族身分の者だけになるから、耳を澄ませば、長琴の音を特定することは可能だと思われた。
それが聞こえないかと意識するようになった三日目の夜、とうとう、風に乗って届くかすかな長琴の音を捉えた。
実際、浮雲のものとされる長琴の音はずば抜けて響くものであったから、耳のよい双子にとって、それを追うのは決して難しくはなかった。遠くから響いてくる長琴の音を頼りに、屋敷の警護の兵に見つからないよう、身を隠しながら邸内を行く。
同じ東本家の敷地内とはいえ、外教坊と本家の者が生活する寝殿は遠く離れていたから、随分と長い道に感じられた。
月の明るい晩である。
思いのほか影が伸びることに気付いて焦ったものの、音に近付いていくのを実感している分、恐れよりも興奮が勝った。
相変わらず、聴く者の心を強烈に惹きつけて止まない演奏である。
前栽の陰に隠れるようにしてようやくたどり着いた離れでは、幸か不幸か、少しだけ御簾が巻き上げられていた。差し込む月明かりに、長大な琴と、それを奏でる手元だけが照らし出されている。
綺麗な、白い手だ。
想像していた通り指は長かったが、あのはっきりとした音のまま一曲を弾きこなせるとは思えないほど、跳ねるように弦を爪弾く指先は細くたおやかである。伶は、男のように大きく筋肉のついた、胼胝だらけの手を想像していた手前、なんとも女性らしい繊手に思いのほか動揺してしまった。
顔は見えない。だが、今、そこで長琴を奏しているのが、若い女であることは認めざるを得なかった。
御簾のうちから響く音はとろけるようで、聞いているうちに、ここに来るまでは皓々として恐ろしくさえあった月の光が、急に神聖なもののように感じられてきた。
そうしてぼうっと聞き惚れていた伶は、隣にいた倫がゆっくりと立ち上がったのに、すぐには気付くことが出来なかった。
月光と長琴で構成された穏やかな夜の世界に、急に鮮烈なきらめきが走る。
驚いて顔を上げた伶のすぐ隣には、誰に見つかっても構うものかと言わんばかりに、仁王立ちで竜笛を奏でる弟の姿があった。
一瞬、長琴の主は驚いたように手を止めたが、闖入して来た竜笛が自分の演奏に合わせたものであると気付くや否や、すぐにその動きを再開した。
長琴は、合奏を企図して作られたものではない。
それなのに、倫の竜笛は長琴を邪魔することも、しかしその音に負けることもなかった。明確に主張したまま絡み合い、まるで花祭りの晩に出会い、踊る男女のように足取りを合わせ、音は天へと昇っていく。
竜笛と長琴の音に誘われたように風が起こり、どこからか花びらが舞ってきた。
青々とした月明かりを受け、ほの白く巻き起こる花吹雪の中で行われる演奏はあまりに現実離れして、それでいて美しく、どこか伶にはものおそろしく感じられた。
同時に――この合奏を超えるものは、この先聴くことはないだろう、という予感を得た。
長琴の女が天才であるならば、倫もまた、天才なのだ。
とてもではないが、そこに伶の入り込む隙などなかった。
演奏は、そうなることが決まっていたかのように自然と終わった。
「……こんな音、初めて」
御簾の内側から聞こえた少女の声は、感動に震えていた。
「この夜のことを、私はきっと一生、忘れられないでしょう」
熱に浮かされたような声に、倫は何も答えない。不審に思った伶が口を開こうとした時、この合奏を聞きつけたのか、どこからか足音が近付いて来るのを感じた。
「倫、人が来る」
囁くが、倫は棒立ちのまま御簾を見つめていて、動かない。
「倫!」
焦って弟の手を引っ張ろうとした時、御簾が動いた。
「待って」
耐えかねたように、白い手が綾の縁取りを押しのけ、中からそのひとが現れる。
「また、合奏してくださる?」
ひらりと、一片の花びらが舞った。
つやつやとした黒髪が、血の気を透かして桃色に紅潮した頰に少しだけかかっている。零れ落ちそうな華やぐ瞳は熱く潤み、半開きになった唇は、蓮の花びらに落ちた水滴のような潤いがあった。
好奇心旺盛なよく輝く瞳が、竜笛を持ったままの倫を見て、眼差しが交錯したのを感じた。
――その瞬間、確かに、弟と浮雲の目が合ったのだ。
物音は、すぐ近くまで来ていた。呆けたようになっている弟の手を引き、伶は慌ててその場から逃げ出した。
死に物狂いで走り、人気がないほうへと逃げた結果、二人は東本家の裏手にある山の中へと入ってしまった。
藪の中、木にもたれながら息を整えてしばらくして後、倫がぽつりと呟いた。
「天女だ」
呆然と、どこか恐れるような声音で呟く弟を見て、急に、伶は夢でも見ていたかのような心地が解けた気がした。
あれほどに麗しい女を、伶は見たことがなかった。
それなのに、あんな楽才まで持ち合わせているなど、あまりに出来過ぎている。
「天女というより、物の怪の類だろ」
吐き捨てた声は、負け惜しみのようにむなしく響いた。だが、そんなことはないと怒ってくれればまだ良かったのに、倫は伶の言葉が聞こえていないかのように何も言わなかった。
「帰ろう、倫。まったく、お前が竜笛を吹いたから、ばれてしまったかもしれないぞ」
「ああ、うん……ごめん……」
倫の目があまりにも茫洋としているので、伶は、何か取り返しのつかないことが起こってしまったような嫌な予感がした。
結局、双子が寝床を抜け出して姫君を垣間見したことは、誰にも気付かれなかった。
若い貴族の間で垣間見をするのはよくあることらしいから、案外、そうした者の仕業だと思われたのかもしれない。
ほっと胸を撫で下ろした伶であったが、それとは違った心配を抱えることになってしまった。
あれ以来、倫が、夜にふらりといなくなってしまうようになったのだ。
周囲が寝静まった頃、そっと起きて出て行くのを初めて見た時には、あまりのことにゾッとした。
あの女に会いに行っているのだ、と思った。
伶と倫は、二人で支えあって生きて来た。自分達以外の誰かに対する秘密を共有することはあっても、お互いに対して隠し事をするなんて、これまでだったら絶対にあり得なかった。
何より、密会が見つかれば、倫だけの問題ではなくなるのだ。自分に迷惑をかけ、これほどまでに心をかけてくれた母を裏切り、世話になった師匠達を失望させることになる。一体何を考えているのかと、二人きりになった時に問い詰めた。
しかしそれを聞いた倫は苦笑した。
「大丈夫。伶が思っているようなことは、何もないよ」
気になるならばついて来るといいよと言った倫は、どこかあっけらかんとしている。
その夜、倫は浮雲の君のいる屋敷の一角ではなく、あの夜、二人で逃げ込んだ山の中へとやって来た。
「あまり近すぎると、見咎められてしまうからね」
恥ずかしそうなその言い方は、逢引きでもしているかのようだ。
「ここで十分、合奏になるんだ。こっちでは拍子は外れて聞こえるだろうが、彼女のもとでしっかり音になっていればいいから」
「何を言っている……?」
「ここで竜笛を吹くと、あのひとが返してくれるんだよ」
おおまじめに言う倫を、伶はぽかんと見返した。
「馬鹿を言うなよ。ここからあそこまで、どれだけあると思っているんだ」
じゃあ試してみようと言った倫は、いつも通りに竜笛を奏で、一曲が終わった段階でにこりと笑った。
「ほら、聞こえるだろう。あのひとだ」
「そんなもの、聞こえない」
「いいや、聞こえる。俺と合奏して下さっている……」
とうとう頭がおかしくなってしまったのかと思ったが、何故か弟は自信満々で、少し屋敷に近付いてみるといい、と笑い含みに言い放った。
しかし、半信半疑で浮雲の居室のある方角へ進むと、弟の笛が聞こえなくなっていく代わりに――確かに、長琴の音が聞こえ始めたのだった。
それに気付いた瞬間の衝撃は、言い表しようがなかった。
確かに、二人は合奏をしていた。こんなに離れているというのに。
聞こえていないのは、自分のほうだった。
もともと、伶だって耳は相当に良いのだ。それなのに、今の自分には、倫に聞こえている音が聞こえない。
二人しか――二人の天才しか知りえない合奏ならば、確かに、問題はないのだろう。
凡才である自分に言えることは何もなく、同時に、倫を殴って、目を覚ませと言ってやりたい猛烈な衝動に駆られた。
負け惜しみであると分かっていても、こんなこと、許されるはずがないと思った。
* * *
「お前、どうした?」
初秋の頃、その変化は唐突に訪れた。
いつも通り稽古をつけてもらっている最中のことだ。師匠の鋭い声は、伶ではなく、倫に対して発せられた。
倫自身は、師匠に何を言われているのか分からずポカンとしていた。その変化を如実に感じ、ひやりとしていたのは伶のほうだった。
これまで、静謐で犯しがたい清らかさを持っていた、倫の竜笛。
その音色が、濁った。
春の終わり頃から、時折、音がいつもと違うように聞こえることがあった。気のせいかとも思っていたが、ここに来て、どうにも誤魔化しようがないほどに、音に変調を来たしたのだ。
指摘され、困惑の色を浮かべていた倫は、何度か指摘された箇所を繰り返すうちに、ようやく自分の変化を自覚したらしい。サッと青くなった倫に、「気持ちの問題じゃないのか」と、いつかの意趣返しをしてやる気には、到底なれなかった。
自分のそれよりも、倫のほうが遥かに深刻であると、分かってしまったからだ。
それ以降、音の変化は如実で、他の楽器との合奏の際、周囲の者がぎょっとするほどであった。
――天地を結ぶ音が人の心を動かすことがあっても、奏者の心が音に乗ってはならない。
倫の音は卑俗になった。高尚なそれではなくなってしまったのだ。
「原因は分かっているだろ、倫」
二人きりになった外教坊の裏手で、伶は、他の者には聞こえないよう声を潜めて倫を諭した。
「お前、夏中山に通いつめていただろう。もう、山での合奏は止めるんだ。遅れた拍子に合わせる変な癖がついているし、音に感情が乗り過ぎている。今ならまだ戻れる」
凡人の嫉妬と思われても構わなかった。ただひたすらに、倫の奏でる音を失いたくはないと思った。
皮肉にも、ここに来て伶は、自分は純粋に、弟の竜笛を愛していたのだと気付かされたのだった。
「あのひとは、俺が好きになってはいけないひとだった」
血の気のない顔で、倫は苦しく呟いた。
「最初から叶わない恋なのは分かっているのに、恋をしてしまった。あのひとが自分の音に応えてくれるのが嬉しくて……何よりも、生き甲斐になってしまったんだ。それに、ああ、どうしよう伶。正直、今の俺には、この変わり果てた音も好ましく感じられるんだ」
でも、このままではいけないのも分かっている、と洟を啜る。
「もう終わりにするよ。最後に、あのひとにお別れをさせてくれ」
その言葉が倫のほうから出てきたことに安堵し、伶は静かに弟の肩を抱いたのだった。
その夜、見つかるのを覚悟で、二人は浮雲の君の居室の近くまでやって来た。
ただし、言葉を交わしている所を見咎められては言い訳のしようがないので、築地塀を隔てたところで、倫は竜笛を奏でることにした。
倫は、それで十分あのひとには伝わるはずだと確信を持って言い切った。
いつかよりも、ずっと月の冴える晩である。
月明かりの中、涙を流しながら奏でる倫の竜笛は、やはり、すっかり春のものから変わり果てていた。
山をたった一匹で歩む、牡鹿の求愛の声のような物悲しさ。
恋焦がれ、しかしどうしようもない苦悩と嘆きが籠もった音は、最初にここで演奏したものとは程遠く、笑えてしまうほど卑俗な響きをしていた。
しかし同時に、鳥肌が立つほどの凄みがあった。
伶の愛した倫の竜笛ではないが、これもまた、倫の音なのだろう。
これを聞いて、浮雲の君は何を思うのか。
どうか超然とした音を返して欲しいと、祈るような心持ちで、伶は彼女の応えを待った。目を覚ましなさい、自分にはその想いに応じるつもりはないという、はっきりとした意思表示が欲しかった。
沈黙が続いて、しばし。
息を凝らして待つ双子のもとに返って来たのは、場違いなほどに明るい音だった。
伶は息を呑み、倫はその場に崩れ落ちた。
彼女が返して来たのは、宮廷の神楽とはほど遠い、民草の間で流布しているような音楽であったのだ。しかしそれは、師匠のように「俗楽だ」と切り捨ててしまうには、あまりに素朴であたたかな音色をしていた。
――正道のものとはかけ離れているかもしれないけれど、その音も、私は好き。
伶の耳にも、はっきりとした浮雲の声が聞こえた気がした。
それは明確な、彼女からの慰めであった。
倫は泣いた。身を振り絞るような、苦しい泣き方であった。
「伶。やっぱり、俺にはこの変わり果てた音が愛しく思える。そう思ってしまえる時点で、きっともう、手遅れだ」
「倫!」
馬鹿野郎、と伶は叫んだ。
彼女はあの一曲で、倫にはもう、もとの音が出せないと分かってしまったのだろう。だからこその慰めの曲であると思えば、見限られたような気がして、伶は猛烈な怒りを覚えた。
弟をこんな風にしたのは、あの女なのだ。
目を覚ましてほしいという伶の想いは届かなかったし、彼女が同調したのは、自分ではなく弟の恋心だった。
やはり自分には到達し得ない次元で、この二人は通じ合っている。
悲しい。悔しい。
そして、天才の弟を堕落させた、彼女が憎くて仕方がなかった。
* * *
倫が、再びの合奏を求めることはなかった。
浮雲の君はつつがなく登殿の儀を迎え、中央へと去っていった。
才試みで倫は落ち、代わりに伶が召人として、皮肉にも中央へ向かうことになった。
「これで良かったんだ」
寂しそうに笑った倫は、見習いの身分のまま、東本家の下男となって働くつもりらしい。
楽士としての資格を得たとはいえ、その中でも伶はまだまだ下っ端である。身を立て親族を呼び寄せられるようになるまでは、母も倫に任せることになった。
中央の流儀にならい、めまぐるしく働く一方で、伶は密かに登殿の様子を気にしていた。
宮廷の楽士ともなれば、少なからず若宮の后選びの詳報も入ってくる。あの奇跡のような美貌と才能に恵まれた女が、風流人だという若宮に気に入られないわけがないと思っていた。
「浮雲の君が、東領にお戻りになる?」
だからこそ、それは意外な報であった。
それまで、四家の姫の中でも浮雲は最も覚えがめでたいという噂を聞いていた。一体、何があったのか。
「どうも、南家の姫に一杯食わされたらしい」
「南家」
「おっかない女傑だそうで、若宮を押し倒して、無理やりお子を身ごもっちまったんだと」
「は……」
あまりのことに言葉が出ない伶を見て、先輩の楽人が苦笑する。
「若宮が一番気に入っていたのは東家の姫だったから、南家の姫は面白くなかったんだろう。さっさと宮中から追い出しにかかったようだぞ。東家としても、若宮の正室が決まっちまった以上、南家を刺激したくなかったってところかな」
想像していた以上に、登殿の儀は壮絶なものであったらしい。
――倫がいる東本家本邸に、浮雲の君が戻る。
一介の下男となった弟とかの人が関わりを持つとも思えなかったが、ふと、楽によって、言葉がなくとも通じ合っていた二人を思い出した。
本来であればあり得ないことではあるが、あの二人に限って言えば、あり得ないことでもないのかもしれない。
一度そう思うといてもたってもいられず、しばらくしてまとまった休暇を得た伶は、約一年ぶりに東領へと帰還した。
「おかえり、伶。元気そうで何よりだよ」
城下町で、大喜びの母と共に出迎えてくれた弟は、中央へ向かう自分を見送ってくれた時の憔悴ぶりが噓のように穏やかな顔つきとなっていた。
今でも竜笛は手放さないそうで、里帰りのお祝いに、と笑い含みに奏でてくれた音を聞いて驚いた。
倫の奏でる音は、雅楽とも、俗楽とも言えなかったあの頃とは、全く異なっていた。
朝廷の音楽とは明らかに系統が違うが、感情を表現する音楽としては、非常に完成されていたのだ。明るくのびのびとした、これもやはり天才の音というにふさわしい音である。
「実は、最近じゃ宴席に呼んでもらうこともあるんだ。珍しがられているんだろうけど、もしかしたら特例で、東家のお抱えとして認めてもらえるかもしれない」
「本当か!」
「ああ。この間は、お館さまからも直接お褒めの言葉を頂いたんだ」
やや照れくさそうに言う弟に、「良かったなあ」と伶はしみじみ返した。
浮雲とのことは訊けなかったが、倫の幸せそうな顔に、ひとまず胸をなで下ろしたのだった。
再び朝廷に戻った伶は、任せられる仕事が増えたこともあり、それからしばらくの間、東領へは足が遠のいていた。
中央にいる分、相変わらず、若宮とその正室をめぐるあれこれはよく聞こえてきた。一度は憎いとまで思った女ではあるが、浮雲が早々に東領に帰ったのは、彼女自身のためにも良かったのだろうと思えるようにまでなった。
入内が叶わなかった以上、誰かのもとに嫁がされるかと思われた浮雲は、しかし不思議なことに、そのまま本家に囲い込まれているようだった。
――「好いたひとがいるから」と、本人が語っているためだという。
その噂が流れてきた際、他の者は若宮のことだと信じて疑わなかったが、伶だけは違う者に心当たりがあった。
もしやそれは、彼女と音楽を通して結びついた、自分のよく知る人物ではあるまいか、と。
だが、間違ってもそんなことを口に出せるはずもない。
時折、東領から届く文により、倫が本格的に楽士を目指し始めたことを知った。再びの、違った形での挑戦であるが、伶はそれを心から応援した。
ただ弟が幸せであればとそれだけを祈り、いつしか中央にやって来てから、五年の月日が流れていた。
順調に宮廷の楽士として働いていた伶のもとに、倫が死んだ、という知らせが届いた。
何が起こったのか、全く分からなかった。
知らせを受け、急いで向かった東領において知らされたのは、伶の半身とも言える弟が入水したのだという、にわかには信じがたい話であった。
「何かの間違いでは?」
茣蓙をかけられた遺体の前で、号泣する母の肩を抱きながら呆然と問う伶に、状況を調べたという役人はそっけなく首を横にふった。
「残念ですが、弟御が自ら沼に入ったのは間違いがありません。事故が起こるような場所ではないのです」
「行きずりの強盗などに、害されたとか」
「そのような痕は見られませんでした」
「では、何故、倫は死ななければならなかったのです!」
伶の知る限り、弟は東家お抱えの楽士を目指し、実直に日々を生きていた。誰かともめごとを起こしたという話なども聞いたことがなく、むしろあの人柄から、自分などよりもよほど周囲から愛されていたように思う。
「納得がいきません」
叫ぶ伶に、しかし、周囲の目は決してあたたかくはなかった。
結局、弟は自死であったということは覆らぬまま、埋葬されることになった。
「あの子は、別邸のお姫さまのことを、お慕いしていたから」
記憶の中にあるよりもすっかり小さくなってしまった母は、まだ土の湿った墓前で背中を丸め、ぽつりと呟いた。
「最近、別邸に中央から貴公子がお忍びで通っているという噂があったんだよ。もしかしたらそれで……それを、気に病んじまったのかもしれないねえ……」
身の程も考えずに馬鹿な子だよ、と囁いて泣きじゃくる母に、伶は何も言うことが出来なかった。
しかし不幸は、それに留まらなかった。
母を中央に連れて帰って三月後には、伶は上役から、西領の寺社へ向かうようにと告げられたのである。
愕然とした。
あろうことか、母親と一緒に西領へ向かいなさい、と上役は言ったのだ。
祭りに際しての派遣という名目ではあるが、その命令は、明らかに帰還を前提としたものではなかった。過去に、問題を起こした楽士が同じように厄介払いされたのを目にしたことはあるが、伶に思い当たる節は何もない。
何故かと食い下がる伶に対し、中央にやって来てからこれまで、親身になって世話を焼いてくれた上役は小さくこう言った。
「お前自身のためだ。もう、中央にも、東領にも戻って来てはいけない」
――到底、尋常ではない。
「一体、何が起こっているんです」
しかし、上役はそれ以上、何も言ってはくれなかった。
伶の疑問は尽きない。
何故、弟は死ななければならなかったのか。
何故、自分が東領はおろか、中央からも追い出されなければならなかったのか。
しかし、その時の伶には、命令に従うほかに出来ることは何もなかったのだった。
* * *
「あんた、本当に厨人なの? 包丁が全然手に馴染んでいないじゃないか」
いつでも手に持って慣らしなさいよとからかわれた伶は、ぐっと唇を嚙んだ。
――当たり前だ。俺の手に馴染むのは、包丁ではなく竜笛なんだから。
とはいえ、料理が出来るという触れ込みでここに来た以上、そんな反論など出来るはずがない。からかってきた料理上手の下女を無視し、伶はひたすらに芋の皮剝きへと戻った。
芋についた皮を洗い落とすための水には、染め粉で黒く染めた自分の髪が映っている。
少し小皺が増えたものの、容姿はほとんど変わりがなかったので髪を染めてみたが、幸いにも、今のところ過去に親しかった者達と顔を合わせることもなく、伶が伶だとは気付かれずに済んでいる。
今、伶は名と身分を偽り、東本家の別邸において下働きをしていた。
十年前、西領へと流された伶は、当然、弟の死にも己の処遇にも、全く納得がいっていなかった。
なんとか調べようとはしたものの、中央を挟み、東領の対極にある西領において、漏れ聞こえてくる噂の数は限られていた。
せいぜい分かったのは、浮雲は、伶が西領に流されていくらもしないうちに、東本家嫡男の側室として迎え入れられたらしいということであった。
しかも、側室に迎えられてから、早々に娘を産んだという。
その時期からして、側室となる以前から関係があったのは明らかだった。
もしや、恋敵となった弟を東本家の嫡男が自殺に見せかけて殺したのかとも思ったが、当時、母が浮雲のもとに通って来ていると聞いていた噂は「中央の貴公子」だったことを思えば、いまいち釈然としない。
遠方で噂を集めるだけでは埒があかず、何度か東領に戻ろうとしたが、その度に上役らの妨害が入り、弟の墓参りすら許されることはなかったのだ。
どんな手を使ってでも東領に戻ると思っていたが、それが叶わぬうちに母は亡くなってしまった。自分を西領に閉じ込めていると思っていた上役が代わるのを待ってみたが、誰が上に来ても、許可は下りない。
かくなる上はと覚悟を決め、身分を偽る手段を探し、末端の下働きとして東家に戻ってくるまで、十年もの月日が経ってしまっていた。
「浮雲の御方も馬鹿をやったもんだよねえ」
浮雲は現在、宗家の姫の教育係として、東本家別邸と中央を行ったり来たりしているという。時折、内親王をお忍びで別邸に連れてきて、自身の娘と遊ばせることもあり、その度に厨では下世話な噂が飛び交っていた。
「本当だったらあのひと、教育係なんかじゃなくて、自分が皇子や皇女を産む立場になっていたかもしれないのにさ」
「それは、登殿の儀のことか?」
厨には噂好きな下男や下女が大勢たむろしていて、何気なく水を向ければ、自ら進んで色々な情報をもたらしてくれた。
「登殿で失敗してすぐに家に返されたんだから、最初から入内は望み薄だったんだろう?」
あえてそう言うと、菜っ葉を刻んでいた女は「馬鹿だね」と優越感を漂わせて言った。
「金烏陛下は、若宮だった頃に会った浮雲の御方が忘れられなかったのさ。わざわざ、お忍びで東領まで来たこともあるくらいだ」
「まさか!」
「あんたが知らなくても当然、お忍びだもの」
十年くらい前の話だしねぇ、と言われ、どきりと胸が鳴った。
「あの女、せっかく陛下が通ってくれたってのに、寝所に男を連れ込んでやがったんだぜ」
対面で、ごぼうの下処理をしていた男が下卑た笑いを漏らした。
「陛下とねんごろになる前に子どもが腹にいるとばれちまって、お忍びも止んじまったわけだ」
「お館さまや女房連中の慌てようは相当なもんだったって、奥に仕えている子が言っていたよ」
そりゃそうだよねえ、と呆れたように言う下女に、下男は声をひそめた。
「本人や身近な女房連中は、暴漢に襲われたと主張したらしいが、誰も信じちゃいないさ。だって、子どもが出来たと分かるまで、襲われたとは一言も言わなかったんだから」
隠していたのは、本当は襲われたのではなく、自分から誘ったからに違いない、と下男は嘯く。
「本当は、前々から密通していた男がいて、そいつを庇おうとしたってわけだ」
「ふしだらで呆れちまうよねえ。アタシだったら、陛下が通って来てくれるんだったら、絶対にそんなことしないよ!」
はあ、と熱っぽく息を吐いた下女を「間違ってもあんたにお呼びはかからねえよ」と下男は鼻で笑う。
伶もそれを面白がるふりをしながら、竜笛に代わって持ち運ぶようになった包丁を静かに腰鞘へ納めたのだった。
――当時、浮雲のもとに通っていたのは金烏陛下だった。
だとすれば、金烏陛下の寵愛を受ける可能性がある状態で、浮雲がほかに愛している男がいると主張しても、周囲は受け容れられなかったはずだ。
しかし、弟と彼女は愛し合っていた。
ひそやかな関係だ。音以外に通じるものは何もなく、二人はふしだらな関係などではなかった。だが、そこには確かに、山神より与えられた才を持つ者同士の連帯があったのだ。
倫は、金烏のお忍びの噂を聞き、浮雲を取られたくなくて忍んでいったのかもしれない。
そして、積年の思いを遂げた。
暴漢に襲われたというのは、おそらく、女房や東家内部の者が浮雲を庇おうとしている主張であって、浮雲自身がそう言ったわけではないだろう。
結果として浮雲は倫の子を宿し――それが東家当主にばれて、倫は殺されてしまった。
だとしたら浮雲の娘というのはもしや、倫の娘でもあるのではないだろうか?
思い至った瞬間、閃くものがあった。
浮雲の娘は、体が弱いという理由でほとんど外に出してもらえないと聞く。それはもしかすると、見る人が見れば一目瞭然なほど、その娘と倫がよく似ているからではないだろうか。
その可能性はある。
浮雲に確認したい。なんとかして娘を、自分の姪にあたるかもしれない少女を見たい。
料理人として働きながら機を窺い、ようやく機会がめぐってきたのは、春になってからのことだった。
浮雲との出会いを、いやおうなしに思い出す季節である。
今年は例年になく桜がよく咲き、東本家の周辺はもったりと重みを感じるような、薄紅色の雲で覆われたようになっていた。
別邸でもささやかな花見をするとかで、その道具を本邸から運ぶように命じられたのだった。
諸々の道具の入った漆の箱や葛籠を別邸の敷地に運び入れている最中、思いのほか近い場所で長琴の音がして、心臓が止まるかと思った。
その音色は、浮雲のものにしては拙い。しかしそこには確かに、あの春の夜の音と通じるものがあった。
ついで、手本を示すかのように、滑らかで、手馴れた音が続く。
拙くも明るい調べと、熟練の優しい調べの二重奏に、思わず、涙がこぼれそうになった。
――天の調べだ。
音が止み、きゃらきゃらとした笑い声が聞こえると、もう我慢は出来なかった。
手を動かす下男達に「小用だ」と噓をついて人目を避け、透垣の隙間の大きな場所を探した。辛うじて、覗き見が出来そうな場所を見つけて、目を押し当てる。
前栽の枝葉に紛れ、母親と思しき女はよく見えない。だが、長琴に向かい合う娘の姿は、はっきりと捉えることが出来た。
その面差しは幼いながら、かつて伶が一目見てから、忘れようにも忘れられなかった女の美貌をそっくりそのまま受け継いでいた。
しかし、その髪は風と陽光を受けて、金色に輝いていた。
くるくると靡く特徴的な癖毛は、自分と倫のほかに見たことがない。
母親の、大きく、しかし節ばったところのないたおやかな手が、愛しそうに少女の後れ毛を撫でている。
それに微笑み返す娘の、木漏れ日に輝く清水のようにきらめく瞳。
弟の目だ。
確信した瞬間、全身から力が抜け落ちた。
弟と浮雲の心が確かに繫がっていた証が、そこにあった。
良かった。良かった、本当に。
自分は、心から、あの姫の誕生を喜ぶことが出来る。
今なら認められる。
自分は弟を愛していた。そして、浮雲のこともまた、愛していた。
誰よりも愛しい二人なのに、自分だけはどうしても仲間はずれで、嫉妬して、羨んで、憎んで、でも、それをようやく今、乗り越えることが出来たのだった。
やはり、弟は東家によって殺されてしまったのだろう。さっきまでの自分であれば復讐を考えたのかもしれないが、今はそうしようとは全く思わなかった。
だって、今の自分には、守るべきひとがいるのだ!
ふしだらな女だと下賤の女からも蔑まれる浮雲を、そして、真実愛の結晶である彼女と倫の娘を、何に代えても幸せにしてやらなければならない。
伶はその足で手水場へ向かい、髪に塗りつけていた安い染め粉を水で洗い落とした。
水鏡に映った自分の顔は、少し前まであった険が抜けて、自分でも笑ってしまうくらい、記憶の中にある倫とそっくりだった。十年間の苦労が水に溶けてしまったようだ。
倫は、自分の中に生きていた。あの優しい弟ならば、きっと、復讐よりも自分の妻と子を愛して欲しいと思うはずだ。
浮雲と、愛しい姪に、望むことは何もない。ただ、貴女方を何よりも愛しく思い、死力を尽くして守る男がいるのだということだけは、知って欲しい。
苦境の中にあって、きっと、心強く思ってくれるはずだ。
先ほどの透垣に戻り、多少、音が鳴るのも構わずにそこを乗り越えた。
濡縁では、陽だまりの中、長琴と並ぶようにして美しい少女が居眠りをしていた。
微笑ましく思いながら視線を巡らせれば、桜の古木の下で、花を見上げている黒髪の後姿があった。
ゆっくりと近付き、声をかける。
「浮雲さま。お久しゅうございます」
自然と笑みが浮かんだ。ただ一礼をしてここを去り、以後は、陰ながら彼女達を支えていこう。
振り返った彼女は、あれから十五年もの月日が流れたとは信じられないほど、記憶の中にある姿のままであった。
その肌は瑞々しく、頰は頭上の桜をやどしたかのように、血の色を透かしていた。長く繊細な睫毛に縁取られた瞳は黒く、潤んでいる。
魅力的な大きな目を見開き、彼女はまじまじと伶を見た。
倫にそっくりの、伶を。
それから、ゆっくりと首を傾げて、心底不思議そうにこう言った。
「あなた、だぁれ?」
――そこで伶は、倫は確かに自分から死を選んだのであり、そうさせたのが、この美しい女であることを知ったのだった。
-
『夜に星を放つ』窪美澄・著
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募期間 2025/02/05~2025/02/12 賞品 『夜に星を放つ』窪美澄・著 5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。