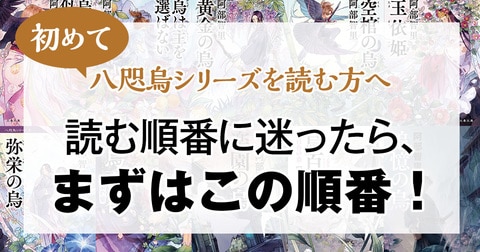累計200万部突破&第9回吉川英治文庫賞を受賞した「八咫烏シリーズ」を原作としたNHKアニメ『烏は主を選ばない』。第14話「禁断の薬」から、本シリーズの第3巻『黄金(きん)の烏(からす)』へとストーリーが進みました!
ぜひ原作小説もお愉しみいただきたく、『黄金の烏』の序章と第1章の全文を無料公開します。これをきっかけに「八咫烏シリーズ」を多くの皆さまにご愛読いただければ幸いです。
八咫烏シリーズ 巻三
『黄金の烏』
阿部智里
序章
あたしがそれを手に入れたのは、ほとんど奇跡みたいなものだった。
「これを、山の手のお屋敷に届けておいで」
そう言われた時、あたしは濡れた布巾で卓上を拭いていた。
古びた卓はいくら拭ってもきれいにはならず、どこかで酔漢が吐いたのか、窓の外からは饐えた臭いが漂って来ていた。酒臭い空気に、いいかげん辟易していたところだったのだ。
あたしの働いていた酒場は、湖に面した街の、裏通りにあった。
表通りには立派な旅籠が並んでいたけれど、裏通りは地元の者や、湖で働く水夫のための店がほとんどだ。客層も当然それに見合ったもので、あたしは毎日のように、酔っ払い達にちょっかいを出されていた。こんなところ、いつか絶対辞めてやると思っていたけれど、真面目に働いていれば、もっと良い働き口が見つかるかもしれないとも思っていた。だから、山の手のお使いにあたしが選ばれたのは、至極当然の事だった。
「お前は、他の者と違ってさぼらないからね。大事な届け物を任せても、大丈夫だろう」
酒場の女店主は、吝嗇家で人使いも荒かったけれど、人を見る目だけは確かだった。
荷物の届け先である山の手は、貴族達の住まう区域だ。場合によっては宮中とされるその一画は、下手をすればあたしなんかが、一生足を踏み入れる事もないような場所だった。
ただでさえ、宮廷のきらびやかな暮らしに憧れていたあたしは、そこに行けるのが嬉しくて、浮かれたまま中央城下と山の手を繋ぐ橋を渡った。
橋の向こうにある中央門をくぐってしまえば、そこはもう別世界だった。
――一歩足を踏み入れただけで、その場の空気の違いは、はっきりと感じ取れた。
貴族御用達のお店の前は丁寧に掃き清められ、水がまかれている。
どこか淀んだ酒場とは違う、澄みきった水の香りがした。
美しく整備された石畳に、お城と見紛うばかりの立派なお屋敷。
行き交う者が纏っている光沢のある上衣は、絹で出来た物なのだろうか。
たっぷりとした袖を揺らし、歩きながら談笑する貴族の子弟達の物腰は、優美な事この上ない。その使用人と思しき男でさえ、あたしが普段暮らしている場所では、滅多に見られないような立派な恰好をしていた。
お屋敷に届け物をする道すがらで、あたしはすっかり打ちのめされてしまった。
山の手は、身分の差が顕著に現れるという意味で、中央で最も残酷な場所だったのだ。
襤褸をまとった自分がみじめに思えて、堪らなくなった。自然と早足になった帰り道で、あたしは母親と思しき女と連れ立った、同じ年頃の娘とすれ違った。
春の光に輝く銀の髪飾りに、ふわふわとした流行りの衣。紅の単の上に、薄絹を何枚も重ねたそれは、淡く繊細な彩を織りなしている。
まるで、朝に咲き初めた、一輪の芍薬の花みたいだった。
ここに来るために、精一杯の身支度をして来た自分が、この上なくみじめに思えた。あちこち擦り切れた薄い着物は、自分が唯一持っている衣だったのに。
つい、顔を俯けるようにして、彼女の横を通り過ぎた時だ。
その娘が、懐から何かを落とした。
拾って見れば、それは黒漆に野の花の螺鈿が虹色に光る、見事な飾り櫛だった。
顔を上げれば、母親と楽しそうに談笑する、あの娘の後姿が目に入る。
寸の間、魔が差しかけた。
ここであたしが声をかけなければ、あの子は、どこでこれを失くしたかも気付かないだろう。あれだけ贅沢な恰好をしているのだ。きっと、同じような物をたくさん持っているはず。ここでこれを自分のものとしたところで、誰も困ったりはしない――。
そう思いながら、ため息をついた。
「もし。今、これを落としましたよ」
駆け寄って声をかければ、振り返った二対の目が見開かれた。
一瞬、粗末な身なりのあたしを見て、嫌な顔をされるかと思ったけれど、こちらの懸念に反して、その子は「あっ」と声を上げただけだった。
「やだ、私ったら」
あたしの手から櫛を受け取った際に触れた彼女の手は、白くやわらかで、まるで労働というものを知らなかった。体が近付いた瞬間にふわりと良い香りがして、水浴びをして来たはずの自分が、汗臭くないだろうかと急に不安になる。
「ありがとう。これは、とても大切なものなの」
そう言って、笑う顔には屈託がない。
「気を付けなさい。せっかく、お父様に買って頂いたものなのに」
「はぁい。ごめんなさい」
眉を寄せた母親の言葉に、首を竦めるようにして答える。「困った子だこと」と苦笑した母親は、その笑みを穏やかなものに変えてこちらを見た。
「本当にありがとうございます。失くしてしまったら、大変でした」
「いえ……。とても、素敵な櫛ですね」
「でしょう! すぐに使うのがなんだかもったいなくて、持ち歩いていたのだけれど、落としてしまったのでは意味がないわね」
その娘は唇に指先を当てて考えてから、それまで付けていたかんざしを抜き取り、代わって、先程落としてしまった飾り櫛を挿した。
「どうかしら。似合う?」
「ええ。とっても」
溌剌とした様子に、胸がつぶれるような思いがした。
ああ、本当に、違う世界の住人なんだなあ、と思う。
無理やり笑って言ったお世辞を、苦労知らずの少女は素直に受け入れた。そして鮮やかな笑顔を浮かべて、たった今抜き取ったばかりのかんざしの方を、あたしの手に握らせたのだった。
「櫛を拾ってくれたお礼よ。私よりも、あなたの明るい髪色の方が、きっとこれも似合うと思うわ」
じゃあね、と軽やかに手を振って、彼女は背を向けて去って行った。
降って湧いたような幸運がすぐには飲み込めず、あたしは手の中に残されたものを見下ろした。
それはとても可愛らしい、海棠の花を模したかんざしだった。
けぶるような花びらは、白糸のように細い銀線と、薄く剥ぎ取られた桃色の水晶で出来ている。花芯の部分には珊瑚の珠が埋め込まれており、ゆらゆらと揺れる銀の葉っぱは、太陽にかざせば、向こう側が透けて見えてしまいそうだった。
ちょっと力を入れれば、すぐに壊れてしまいそうなくらい、繊細な銀細工だ。
それが、水仕事で荒れてしまったあたしの手の中で、確かに燦然と輝いていたのだった。
声にならない歓声が出た。
大急ぎで酒場に帰ってお使いの報告をする間も、あたしの頭の中はずっと、胸元に仕舞い込まれたかんざしの事でいっぱいだった。
今まで以上に頑張って働いて、このかんざしに合った着物を買おう。
いや、何も、このかんざしにこだわる必要はない。
いつか、あの娘の持っていたような飾り櫛も手に入れて、こんな掃き溜めのような場所を出てやるのだ。あたしだって綺麗に着飾れば、良い家の坊ちゃんに見初められて、お嫁入りだって出来るかもしれない。今になって思えば、山の手で目にした青年達は、本当に素敵だった。整った顔立ちもそうだが、何よりも、育ちの良さが垣間見える所作は、この辺りでは絶対に見られないものだ。
そう。紳士的で、優しくて、あたしを心から好いてくれる殿方が良い。
いつか必ず、そんな人の奥さんになってやるのだ。
必ず。
そんな風に思いながら、跳ねるような足取りで、あたしは家に帰った。
裏通りから、さらに一本奥に入った、あまり手入れのされていない区画だ。山の手から帰って来たばかりだと、余計にみすぼらしく感じられるあばら家が、あたしの生まれた家だった。
「ただいま」
声を掛けながらすだれをめくって、しかし、思わず足が止まった。
――そこであたしを待ち受けていたのは、見慣れない、風体の悪い男達だったのだ。
四、五人はいただろうか。
全員が妙にぎらぎらとした目で、あたしの頭のてっぺんからつま先までを、まるでねぶるように見つめていた。
ざわりと悪寒がした。
すぐに逃げようとしたけれども、髪を背後から摑まれて、家の中に無理矢理引きずり込まれてしまった。悲鳴を上げ、必死に抵抗するあたしに向けて男が言ったのは、にわかには信じられない言葉だった。
「大人しくしろ。お前の父親は、もう金を受け取っているんだ」
「潔く諦めな」
「お前は、俺達に買われたんだよ」
下卑た笑い声、憐れみを帯びた声、何も考えていないような、吞気な声。
そのいずれも、興奮した荒い息の中では同じに聞こえた。
あたしは呆然としながら、戸口から逃げるように去って行く、父親の丸まった背中を見た。
――それから自分が何を叫んだかは覚えていない。
ただ、暴れた際に床へ落ちた花かんざしが、毛むくじゃらの足によって、無造作に踏み砕かれたのだけは、やけに鮮明に記憶に残っている。
ぐしゃりと潰された、海棠の花。
無残に飛び散る、銀の欠片。
留め金から外れた珊瑚の玉が、少しだけ転がる。
だが、転がって行く先を見届ける前に、黒い影が覆いかぶさって来たせいで、それ以上、何も見えなくなってしまった。
転がって行った珊瑚の行方は、今も分からない。
第一章 垂氷郷
「雪哉、いいかげんに起きなさい」
肩のあたりを優しく叩かれて、雪哉は目を覚ました。
真っ先に目に入ったのは、こちらを覗き込んでいる、目元に笑い皺の浮かんだ母の顔であった。
「……おはようございます」
寝惚け眼を擦りつつ言えば「はい、おはよう」と、呆れたように返される。
「と言っても、本日二回目のおはようですけどね。もうすぐお昼の時間ですよ」
言われて、雪哉はぽかんとした。
周囲を見回せば、自分が横になっていたのは自室の寝床ではなく、火の気のない囲炉裏端である。開け放された扉から心地よい風が吹き込み、黒光りする板の間には、鮮やかな緑が映り込んでいる。
普段騒がしい兄と弟の姿は見えず、鳥の声以外は、ひどく静かであった。
「兄上とチー坊は?」
「とっくに下に行っていますよ」
「下? 今日って、何かありましたっけ」
「何かって、梅を漬ける手伝いをする約束でしょう」
寝惚けているらしい息子に、母は小さく眉根を寄せた。
「まさかお前、どこか具合が悪いんじゃないでしょうね」
額に手を伸ばされて、雪哉は慌てて飛び起きる。
「体調は大丈夫です。すみません、ちょっとうっかりしていました」
「そう? では、一回顔を洗ってからお行きなさい」
「はい」
草履をつっかけて外に出て、湧き水を引いた水場へと向かう。竹筒の先から落ちる水で顔を洗ってから、岩の窪みに溜まった水面を覗き込んだ。
結い上げられた、やや茶色を帯びた頭髪は、寝癖も手伝って好き勝手な方向に跳ね回っている。寝過ぎたせいか顔はむくみ、普段から間違っても美少年とは言われない顔が、輪をかけて不細工になっていた。
癖っ毛を無理やりまとめてから、強めに顔を叩いて気合いを入れ直す。それから、母屋の裏口から顔を覗かせ、家人と話している母に声をかけた。
「母上、行ってきます」
「行ってらっしゃい。後で差し入れを持って行くから、みなさんによろしく伝えてね」
「はい」
羽織っていた着物を脱いで床に置き、両腕に軽く力を込める。そうすると、薄い靄のようなものが纏わりつき、次の瞬間には黒い衣――羽衣となっていた。何度か飛び跳ね、羽衣を体に馴染ませてから駆け足になると、屋敷の表へと向かう。
雪哉達の住む屋敷の表口は、大烏や飛車が降りたり飛び立ったり出来るよう、広い車場となっている。その先は空に向かって張り出した崖になっているのだが、ここは、郷長屋敷で生まれた子どもにとって、恰好の遊び場であった。
駆け足から徐々に速力を上げ、助走をつける。
人の姿のまま、勢い良く崖から飛び出した雪哉は、空中で体を一回転させ、すばやく体を変化させた。
全身の羽衣は黒い羽毛に変わり、骨格がぐにゃりと引き伸ばされる心地がする。
三本足の大烏へと転身した雪哉は、ついさっきまで両腕だった翼を広げ、緩やかに滑空していった。
眼下には、のどかな田畑が広がっている。
田植えを直前にした田んぼには既に水が入れられており、吹きわたる風に、鏡のような水面を揺らしていた。
山に囲まれた盆地であるこの辺りには、郷長一家が居住する山城――役所として郷政を行う屋敷と、郷吏とその家族が生活するための集落が存在している。
畑の間にはしっかりした家々が並び、穏やかな暮らしぶりを垣間見せていた。
美しい水田を越えた先、なだらかな山の斜面の一角に、目指す梅林がある。
そこから、大きな籠を背負って出て来る一団を見つけて、雪哉は「しまった」と心のうちで呟いた。
「遅いよー、坊ちゃん」
「収穫はもう終っちゃったよ」
彼らの上空までやって来ると、下から、からかい混じりの声を掛けられる。雪哉は地表ぎりぎりで人の姿に戻り、一団の前にすとんと着地した。
「おばさん、ごめん! 何か、二度寝しちゃったみたいで」
「相変わらずだねえ」
「でもまあ、こっちも坊ちゃん達が来る前から、始めちゃっていたからね」
仕方ないと笑うのは、郷吏の妻や母親、娘達だ。
彼女達の多くは、普段は山城のふもとにある郷長所有の田畑を耕したり、郷長一家の身の回りの世話などをして暮らしている。
雪哉はここ、北領が垂氷郷、郷長一族の次男坊であった。一応は彼女らの主家の者に当たるのだが、手伝いが必要な時にはすぐに駆り出されるし、特別扱いはほとんどされてこなかった。彼女達からすれば親戚のようなものなのだろうし、雪哉からしても、それは同じなのである。
「宮仕えから帰って来たら、少しはしっかりするかと思ったんだけど」
「一年ぽっちじゃ、何にも変わらなかったねえ」
「いいさいいさ、のんびりしているのが、坊ちゃんの良いところだもの」
「無理に変わる必要なんかないさね」
口々に言われた言葉に、雪哉は眉尻を下げた。
「本当にごめんよ。来たからには、人一倍頑張るからさ」
「じゃあ、そうしてもらおうかね」
笑い声が明るくなったところで、「雪哉ァ!」と怒鳴る声がその場に響いた。
「お前、遅い」
視線を転じれば、子ども達の集団の中に、兄と弟の姿を見つけた。
兄は、十五になった雪哉よりもひとつばかり年長なだけであったが、小柄な自分よりも頭一つぶん上背があった。頭髪には癖がなく、比較的端整な顔立ちをしている。その隣を歩く末弟も兄とよく似た風貌をしているので、つくづく、血のつながりの分かりやすい二人だと雪哉は思う。
男の中では兄が一番年長なせいか、どうやら子守りを押し付けられたようだ。目を三角につり上げてはいるものの、背中に赤ん坊を背負い、両手に幼児を引き連れたその姿に、威厳は微塵も感じられなかった。
「そう言うくらいなら、起こしてくれりゃ良かったのに」
兄に駆け寄り、赤ん坊を引き受けながら言うと、馬鹿にしたように鼻を鳴らされる。
「まさか、こんな時間まで寝ているとは夢にも思わなかったんでな。大体、朝飯食ってから寝る奴があるか」
「言っておくけど、俺は一応声をかけたからね。それでも起きなかった、雪哉兄が悪いんだぜ」
澄まして言ったのは、チー坊こと弟の雪雉だ。その背中には小さめながら、たっぷりと青梅の入った籠が担がれている。
雪哉は苦々しく呻いた。
「ああもう、俺が悪かったよ」
「分かったのなら無駄口叩かず、きりきり働くんだな」
兄に嫌みを言われながら、この辺りで一番広い水場へと向かう。
次の作業に移るのは午後からという話になり、昼飯を作りに行った女達が、小さな子ども達を引き取って行った。食事が出来るまでの間、手持ち無沙汰になってしまった郷長家の三人兄弟は、一足先に梅の実を洗う事にして、柿の木陰を選んで座った。
まだ蚊も出ていないし、爽やかな初夏の風が、汗ばんだ額を撫でて行くのが気持ち良い。
梅の実に当たって弾けた水飛沫が、木漏れ日を受けてきらきらと光っている。
日光を透かした緑が美しい枝葉の下で、三兄弟は無心に手を動かし続けた。
「しかし、兄上がこんな時間に雑用とは珍しい。父上の手伝いはどうしたんだ?」
弟二人とは異なり、いずれ郷長の跡目を継ぐ長男の雪馬は、いつもなら父の手伝いで表に詰めている時分である。
雪馬は笊に載せた梅を転がしながら「それがな」と変な顔になった。
「街道沿いで問題があったとかで、父上が出て行ってしまわれたのだ」
郷長がいなくても支障のない雑務は、郷吏が引き受けてくれたそうだ。おかげで、雪馬にはやる事がなくなってしまったのだと言う。
「有り体に言えば、邪魔だと言って追い出された。父上が帰って来るまでは、こっちの手伝いでもしておこうかと思ってな」
「それは見上げた心がけだね。今年の梅は量が多かったみたいだし」
そう言った雪哉の横で、目を瞬かせた雪雉が、不意に梅の実をひとつ、つまみ上げて見せた。
「確かに、数は多いかもしれないけどさ。なんか、一個一個が小さいと思わない?」
言われてみれば、収穫した青梅は数こそ多かったが、実そのものは小ぶりである。以前は、もっとずっと大きく、一本の木から採れる数も多かったのにと、収穫の最中で話題になったらしい。
「梅だけじゃなくて、野菜とかも、最近はあんまり出来が良くないんだって。雪哉兄は、中央でそういう話を聞かなかった?」
雪哉はつい二月前まで、中央で宮仕えをしていた身である。
宮廷では地方の特産品の中でも、上等なものしか使われないから、実体験としてそれを感じた事はほとんどない。だが、作物の不作については、耳に胼胝が出来るほど聞いた覚えがあった。
「ああ……。米の出来が悪いってのは、よく言われていたよ」
「やっぱりそうなんだ」
南の方じゃ大水もあったって言うし、嫌だねえと首を振る弟の言葉は、恐らくは女達の受け売りだ。大人ぶっている弟に曖昧な笑みを返して、雪哉は洗い終えた青梅を笊から籠へと移した。
弟は「嫌だねえ」の一言で済ませていたが、中央だったらこの後に「これも全て、若宮殿下のせいだ」という陰口が続いていただろう。
いずれ、この山内の地を背負って立つ日嗣の御子、若宮殿下は、雪哉が中央で仕えていた相手であった。
若宮は、山内で最も尊い貴人でありながら、評判の良かった実兄を譲位させて宗家の後継に収まったという、悪名高い男でもあった。そのため宮廷内に敵も多く、ここ数年の不作や大水までが「本来の則を乱した若宮のせい」にされるという、非常に苦しい立場にあったのだ。
短い間ではあったが、雪哉が仕えている間にも天災の責任を若宮に求める声は多く聞こえて来た。今でもそういった話を聞くと、複雑な心境にならざるを得なかった。
思わず、顔を背けるように視線を遠くへ向けた雪哉は、青く晴れ渡った空の中に、一つの黒い影を見た。
大烏である。
雪哉の視線を追った兄と弟も、すぐにその姿に気が付いた。
「父上が帰って来たのかな」
末弟の言葉に、雪馬が「違うだろう」と返す。
「騎乗している者が見えない。『馬』じゃなくて、鳥形の八咫烏じゃないか?」
雪哉達、八咫烏の一族は、人形と鳥形という、ふたつの姿を持っている。
このうち、鳥形の姿を取る事は、八咫烏にとって「恥ずべき事」「行儀の悪い事」とされていた。雪哉のような武家の地方貴族、里烏、山烏などと呼ばれる平民は、鳥形にも抵抗が無い場合が多かったが、中央貴族である宮烏などは、一度も鳥形になった記憶がないまま一生を終える者も少なくはなかった。
基本的に八咫烏は「人形のまま暮らしたい」と考えるのが、普通なのである。
それというのも、人の姿での生活が立ち行かなくなり、一生を鳥形のままで過ごさなければならなくなった者は、もはや八咫烏として扱ってもらえなくなるからだ。自由に人形になれない代わりに、食事の面倒を見てもらえるよう、飼い主と契約した八咫烏は家畜として働き、『馬』と呼ばれるようになるのだ。
だが、徐々にこちらに近づく鳥影は、馬にしては飼い主が見えず、鳥形の八咫烏にしては、あまりにも落ち着きが無いように見えた。
「……何か、様子がおかしくない?」
かなり離れているはずなのに、ギャアギャアと鳴く声が聞こえる。その上、まるで溺れているかのように、無茶苦茶な飛び方をしている。
「俺、ちょっと見て来る」
雪哉が言えば、よし、と雪馬が頷いた。
「じゃあチー坊、お前は郷吏達に報せて来い。あの分だと、どこか怪我をしているのかもしれない」
「分かった!」
「頼んだぞ。俺は、おばさん達に声を掛けて来る」
兄が駆けだす気配を感じながら、雪哉と雪雉は、鳥形へと転身した。
郷長屋敷へと飛んで行く末弟に背を向けて、雪哉は迫り来る鳥影に向かい、一直線に飛び立った。飛んでみて分かったが、やはり、上空に強い風があるというわけではない。あそこまで羽ばたく必要はないはずである。
不審者の顔を視認出来る所まで近づいて、雪哉はぎょっとした。
飛び方を忘れたように羽ばたく烏は、とても正気には見えなかった。
黒い嘴は開きっぱなしで、舌は垂れ、泡を吹いている。目玉はぐるぐると忙しなく動き回り、意味を成さない奇声は、耳を劈かんばかりだった。
――あんた、一体どうしたんだ。
並んで飛びながらカア、と強く声をかけたものの、聞こえていないどころか、こちらの姿も見えていないようである。大声を怪訝に思ったのか、集落のあちこちから、大人の八咫烏が顔を出し始めた。
――何があった、坊。
弟から話を聞いたらしい、仕事をしていたはずの郷吏が、雪哉のすぐ近くまで飛んで来た。「見ての通りです」と翼を翻せば、異常な様子が伝わったのだろう。わずかに考えた後、郷吏はガア、と声を上げた。
――一旦、地上に下ろしてやろう。手伝ってくれ。
了解の意味を込めて緩やかに降下し、雪哉と郷吏は場所を入れ替わる。
声を掛けながら、ゆっくりと近づいて行った郷吏は、しかし次の瞬間、不審者に組みつかれて怒号を上げた。
――てめえ、何をする!
不審者は三本足で郷吏の体をがっちり摑むと、その喉笛に噛みついたのだ。
翼をまるで手のように使い、郷吏の体を押し包もうとする。当然、そうなればまともに飛べるはずもないのに、まるで、自分が鳥形である事を忘れてしまったかのような動きだった。
――おじさん!
ひと固まりになって墜落する二羽に、雪哉は叫んだ。郷吏は必死になって不審者を振りほどこうとするが、間に合わない。
畑にいた者達が、上空の異変に気が付いて、慌ててその場を離れる。
どしゃん、という鈍い音と共に、二羽は頭から、畑の中に落っこちてしまった。
「おい!」
「あんた、大丈夫かい」
打ち所が悪かったのか、郷吏は呻いたきり、鳥形のまま蹲っている。
駆け寄る八咫烏の姿を見て、雪哉はひやりとした。一緒になって落ちた不審者の体が、わずかに動いたのが目に入る。
――おばさん、近付いちゃ駄目だ!
雪哉の警戒の声とほぼ同時に、不審者が勢いを付けて起き上がった。嘴は割れ、額から血を流している。それなのに、構わず目の前の女達に向けて嘴を振り下ろそうとする姿に、雪哉は覚悟を決めた。
鳥形のまま急降下し、その後ろ頭を思いっきり蹴りつける。
不審者に襲われて腰を抜かした女が、後退りながら悲鳴を上げた。
「坊ちゃん!」
――早く逃げて!
変な姿勢で落ちたせいか、不審者の翼は不自然に歪んでいる。空までは追って来られないと踏んで、雪哉は急降下と急上昇を繰り返しながら、大烏の体にしつこく蹴りを入れ続けた。案の定、飛べなくなったらしい不審者は雪哉の挑発に乗り、ぎこちなく羽ばたきながら後を追おうとする。
もう少しすれば、郷長屋敷から応援が来るはず。それまで粘れば、こっちのもんだ!
雑な攻撃をかわし、宙返りして嘴から逃れた雪哉はしかし、畑の向こうで、呆けている幼児がいる事に気が付いた。逃げおおせた女の一人が、子どもをここから遠ざけようと、駆け寄って行くのが見える。
すばしこい雪哉に苛々していた不審者が、立ちすくむ子どもと、女の背中に顔を向けた。
ああ! くそ、こっちを向け。
雪哉は必死になって蹴りを繰り出すが、不審者は、こちらの攻撃を完全に無視してかかった。八咫烏のものとは思えない、吠えるような鳴き声を上げると、三本の足をがむしゃらに動かし、まるで、獲物を見つけた蜘蛛のように、女と子どもへと襲いかかって行く。
子どもを抱きしめた女が、恐怖にひきつった顔で振り返る。
やられる、と雪哉が思った、その時だった。
――背後から、何かが頭の上を通り越し、雪哉の顔に一瞬だけ薄い影を差した。
凄まじい勢いで飛んで来たのは、今度こそ本物の馬だった。
馬の背中に騎乗していた者が、放たれた矢のような勢いで鞍から飛び出す。そのまま大烏の頭に抱きつき、片手で嘴を鷲摑みにしながら着地したように見えた次の瞬間。
大烏の巨体が、くるりと宙を舞っていた。
黒い羽を撒き散らしながら回転した不審者の体が、地響きとともに土の上にひっくり返る。雪哉が我に返った時、不審者は畑に顔を半分埋めるようにして、がっちりと押さえ込まれていた。
もがこうとする大烏を楽々とねじ伏せるこの男は、あろう事か、飛び込んだ勢いを殺さないまま、頭ごと捻るようにして大烏を投げ飛ばしてしまったのだ。
「怪我はないか?」
落ち着いた様子で声をかけられた女と子どもは、目の前で起きた事態が信じられないのか、あんぐりと口を開いている。だが、やけに聞き覚えのあるその声に、雪哉は目を見開いた。
まさかと思いつつ、急いで人形に転身し、男のもとへと走り寄る。
その顔を確認して、雪哉は大きく息を吞んだ。
「やあ。久しぶりだな、雪哉」
飄々とした物言いに反する強い眼差しは、忘れたくとも、忘れようのないものだった。
「あなたは――」
一体、どうしてここに。
呆然として呟けば、ちらりと、苦笑めいたものが瞳に浮かぶ。
「取りあえず、縄を持って来てくれないか」
話はそれからだと言って、彼は、困ったように腕の中を見下ろしたのだった。
帰宅した郷長を出迎えたのは、怪我をした郷吏と、縄でがんじがらめにされた鳥形の八咫烏、何故か女達から黄色い悲鳴を浴びる、見慣れない客人の姿であった。
最初は現状を把握出来ずに戸惑っていた郷長も、己の留守の間にあった事を聞いて血の気が引いた。
「頭のおかしい男が、襲って来ただと! 被害はどの程度だ」
「畑を荒らされ、郷吏が一人、怪我を負いました」
「重傷なのか」
「幸い、大した傷ではないようです。頭を打ったのは少し心配ですが、さっき目が覚めて、不覚を取ったと、悔しそうにしていましたよ」
不幸中の幸いです、と笑う長男に、郷長は肩の力を抜いた。
「それは良かった……全く、肝が冷えたぞ」
下手人の身柄は拘束してあるし、ひとまず、緊急の問題はないだろうと気を緩めた時だ。
「いえ。安心するのは、まだ早いですよ」
凜と響いた声は、それまで、囲炉裏端で女達からひたすら酌を受けていた、客人のものである。女達の輪から抜け出して来たその姿を、郷長はまじまじと見つめた。
まだ若い男である。それも、とびきりの美青年だ。
年の頃は、長男の雪馬よりも二つか三つ上くらいだろうか。年の割に、大人びた雰囲気をしている。絹糸のような黒髪はすっきりとうなじでひとまとめにされ、肌は、白磁のように白く透き通っていた。その表情はとぼしく、冷やかなほどに整った造作と相まって、まるで人形のような男だと思う。
だが、線の細さに反して、切れ長の目の奥に、弱いところは全くなかった。身に着けているものは粗末であったが、その立ち居振る舞いには宮烏らしい気品が感じられる。
「お初にお目にかかります、垂氷郷郷長殿。私は墨丸と申します。本日、中央よりやって参りました」
郷長が口を開く前に、周囲にいた女達が、墨丸がいかにして自分達を助けてくれたのかを、熱っぽく、一斉にまくし立てた。
垂氷は、もともと武人の多い地方である。
そのせいか、中央貴族風の優男は馬鹿にされ、武骨な男らしい男が好まれる風潮があったのだが、顔が美しい上に腕も立つとなれば、また話は違って来るらしい。
郷長自身、内心では「この華奢な若者が!」とにわかには信じがたい気持ちであったが、郷民を助けてくれた事は疑いようもなく、丁重に礼を述べたのだった。
「しかし、安心するのはまだ早いとは、どういった意味ですかな」
問い返せば、墨丸の瞳がきらりと光った気がした。
「その件で、お話をしたくてまかり越しました。街道沿いで噂の件と言えば、お分かり頂けるでしょうか」
思いがけない言葉に、郷長は、はたと墨丸の目を見返した。
「もしや、さっき襲って来た八咫烏は」
「何の理由もなく、おかしくなったわけではないでしょう。僭越とは思いましたが、郷吏達に頼んで、既に身元を調べてもらっています」
一応、雪馬殿にも了解を頂きましたがと続けられ、郷長は目の前の青年への認識を改めた。
「これは失礼した。中央からというのは、朝廷からという意味でしたか」
はいと、墨丸が素直に頷く。
「此度の訪問も、主の命によるものです。つい二月前まで、雪哉殿とは親しくさせて頂いておりました」
「では、貴公の主というのは――」
郷長が驚きのまま口を開こうとしたところで、妻の梓が、やんわりと間に入って来た。
「色々と、積もる話もおありでしょう。どうぞ、夕餉の席にいらして下さい」
そこでようやく郷長も、興味津々にこちらを窺う周囲の様子に気が付いた。こちらにじっと視線を向ける女達と、戸口で鈴なりとなっている子ども達を見て、墨丸も梓の言葉に頷く。
「では、お言葉に甘えまして」
場所を移し、改めて運ばれて来た夕餉の膳には、女達が張りきったせいもあり、ちょっとした御馳走が並んでいた。
山盛りになった、香ばしい若鮎の塩焼き。
出汁のきいた具だくさんの山菜汁からは、香ばしい味噌の香りが、湯気とともに湧き立っている。朴の葉に載せて焼いたつくねの上には、甘辛いタレと半熟の卵黄がトロリとかかって、今にも零れ落ちそうだった。山で採れた山菜を揚げたてんぷらは、さくさくとした金色の衣に、一ふりの塩をかけるくらいでちょうどいい。
美味そうな料理を前にして、まずは一献、と大ぶりな椀を受けた墨丸は、一息にそれを飲みほして見せた。
「いやはや、見事な飲みっぷり」
「北領の地酒がうまいからでしょう」
「これはどうも、嬉しい事を。北領の者は、みんな酒好きですからな」
「どんどん召し上がって下さいませ。雪哉が、一年もの間お世話になったのですもの。どうぞ遠慮なさらず」
にこにこしながら膳を運んで来た梓の言葉に、墨丸は真面目な面持ちとなった。
「いえ、世話になったのはこちらの方です。ご子息には、色々と助けられる事が多かった。若宮殿下も、雪哉殿が垂氷に帰ってしまうと聞いて残念がっておられましたから」
まあ、と目を輝かせた妻の横で、郷長は苦笑いした。
「そうおっしゃって頂けるのは有難いが、どうか、世辞は止めて頂きたい。あれが若宮殿下から放逐された件は、とっくに承知しておりますので」
「父上!」
突然、咎めるような声を上げたのは、それまで大人しく控えていた長男、雪馬である。
「せっかく、中央の話をして下さるのです。私は、雪哉が中央でどういう働きをしていたのか、聞きとうございます」
見れば、末の息子もムッと唇を尖らせ、梓も困ったように眉尻を下げている。能天気な顔で箸を口に運んでいるのは、あれと呼ばれた本人ばかりである。
「働きと言っても、お前……。どうせ、雪哉の事だ。ろくな話は聞けないだろうに」
苦い顔で言い返せば、一座の者を順繰りに眺めていた墨丸が、小さく首を傾げた。
「それは、どういった意味でしょう」
「実際に何があったかは、雪哉本人から聞いておるのです」
側仕えの数が少なかったため解雇こそされなかったが、雪哉の仕事の出来は、相当酷いものであったという。さんざん周囲に迷惑をかけ、若宮殿下からも呆れられて、最初に約束した一年が来るのを待ちかまえるようにして宮中から追い出されたのだ、と。
「若宮殿下からも、呆れられて」
ゆっくりと郷長の言葉を反芻して、墨丸は何か言いたそうな視線を雪哉に向けた。雪哉は我関せずとばかりに、黙って汁をすすっている。
「恥ずかしながら、愚息三人の中でも、雪哉は特別どんくさい子でしてな」
困ったものです、と頭を振りながら、郷長はいかに雪哉が駄目な息子かを言い立てた。
「武家の子なのに、度胸も剣の腕もない。長男と打ち合っても、まともな仕合になったためしがないのです。頭の血のめぐりも人一倍悪くて」
「まあ、若宮殿下がどうお考えかは、私には分かりません」
延々と続けるつもりだった郷長の言葉を、墨丸が自然な調子で遮った。
「ですが、一緒に働いた私の意見を述べさせて頂けるのであれば、雪哉殿は大変優秀だったように思いますよ」
「お心遣い、痛み入ります」
「本当の事です。だからこそ、こうして私はこちらに伺ったのですし」
やっと本題に入った気配を感じて、郷長は顔つきを改めた。
「と、申しますと?」
「雪哉殿を少しの間、貸して頂きたいのです」
雪哉が、口に含んでいた汁物を噴き出した。盛大に咳き込む当人を無視して、郷長は片方の眉をつり上げた。
「雪哉を、ですか。これはまた、どうして」
「若宮殿下から仰せつかった仕事を、手伝って欲しいのです。中央から北領へ、禁制の薬が流れているようですので」
「禁制の薬?」
げほげほとうるさい次男坊の背中をさすっていた雪馬が、怪訝そうに顔を上げた。
「それは、麻葉とかですか」
「いいや。麻葉などよりも、ずっと性質が悪いものだ。麻葉は、あれはあれで、谷間の連中がきっちり管理しているから」
谷間とは、中央に存在する荒くれ者達のたまり場の事である。
その規模はひとつの街を形成するほどに大きく、朝廷の規制も届かない無法地帯となっている。朝廷の禁止した危険物も普通に流通しているような所だが、谷間には谷間なりの規律が存在している。住み分けが出来ているとでも言うのか、流通経路も販売相手も決まっているから、放っておいてもあまり害はないのだ。
しかし今回のものは違う、と墨丸は言いきった。
「谷間の連中が売買を仕切っているわけではないから、山の手に住まう貴族にまで被害が出ている」
入手経路も、精製場所も不明。現物は手に入らず、その原材料さえ見当が付かない。ただ、薬の犠牲になる者の数だけが、むやみやたらと増えている状況なのだ。
その薬は、使用すると素晴らしい多幸感、全能感を得られる代わりに、数回の服用だけで、人形を取れなくなるらしい。中には、人形に戻れなくなったまま正気を失い、衰弱死してしまった者や、自ら命を絶ってしまった者もいるという。
「それってもしかして、今日の奴みたいな感じ?」
説明を聞いていた末っ子が、堪え切れなくなったように嘴を挟んで来た。墨丸は雪雉に向かい、生真面目に頷いて見せた。
「いかにも。薬の名は『仙人蓋』という」
「仙人蓋……」
「若宮殿下がこの薬の存在を知ったのは、今から十日ほど前でした」
花街からの陳情書に紛れて、気が狂れて、鳥形のまま暴れ回っている遊女がいるという報告があったのだ。不穏な内容に、関係各所に問い合わせをしてみると、ここ半月ばかりの間に、分かっているだけでも二十名以上の八咫烏に同じ症状が出ていると知らされたのである。
「最初は、何らかの病かと思われたのだが、どうにも様子がおかしい。谷間へと行ってみると、原因はすぐに分かった。谷間では、やはり山の手より先に薬が出回っていたらしくてな。二月近くも前から、仙人蓋の売買も使用も厳しく禁じられて、それが周知徹底されていたのだ」
谷間を取り仕切るのは、多くの手下を持ち、それぞれが自分の縄張りを守る親分連だ。
この親分連の間では、定期的に会合が開かれる。会合での決定事項は、ひとつの例外もなく、谷間全てに共通する規則となっていた。
「とはいえ、派閥ごとの利害関係もあるからな。大きな決め事など、近頃はほとんどなかったのに、仙人蓋に関しては満場一致の決定だったとか」
それだけ危険な薬であるとも言えたが、何にしろ、朝廷は仙人蓋への対応において、谷間に完全に後れをとってしまった。結果、中央に住む里烏を中心に被害が広まり、若宮の耳にも噂が届くようになったのだ。
そこまで聞いた雪馬が、険しい顔を父親へと向けて来た。
「……その仙人蓋が、今は垂氷にまで流れて来ているのですか」
「認めたくはないが、おそらくはそうなのだろうな」
先日、街道沿いに怪しげな薬が出回ったという報告が入って来た。郷長屋敷に注意喚起の報せが届いたばかりだったため、郷長は一応中央へも連絡し、今日は様子見に出たばかりだったのである。
「現地で、何か分かりましたか」
身を乗り出した墨丸に申し訳なく思いながら、郷長は首を横に振った。
「それが、通報した者も『こんな薬があるのだが、買わないか』と持ちかけられただけのようで……残念ながら、特に有益と思える情報は、見つかりませんでした。出回った量も少ないのでしょうが、現物も手に入らなかったくらいでして」
その、出回ったわずかな仙人蓋を服用した者が、今日の襲撃者になったのだろう。
「恥ずかしながら、私の認識が甘かったようです。これほどまでに差し迫った問題だとは思いもよらず、のこのこと帰って来てしまいました」
早速、明日からは本格的に調べさせ、郷民に対しても布告を出しましょうと告げれば、墨丸は重々しく頷いた。
「今のところ、中央以外で仙人蓋と思しき被害が確認されたのは、垂氷だけです。一刻も早い対応をお願いいたします。若宮殿下もこの一件に関しては、非常に心を痛めておいでですので」
おそらく、数日中に朝廷が正規の調査を求めて来るだろうが、それでは遅いと考えて、墨丸を派遣したのだと言う。郷長の調べと並行して、こちらも勝手に動いて構わないだろうかと問われ、郷長は快く許可を出した。
「しかしそうなると、愚息に手伝わせるには、いささか荷が重いような気がしますな。墨丸殿さえよろしければ、郷吏をお伴にお付けいたしますが……」
次男坊に多大な不安を抱いている郷長は言葉を濁したが、墨丸はそれを、とんと意に介さなかった。
「お気遣いなく。郷吏の仕事を邪魔するわけには参りませんし、雪哉殿の方が、色々と気安く物事を頼めますので」
「ああ、なるほど」
難しい仕事ではなく、雑用をやらせるつもりなのかと、郷長は納得した。
「そういった事でしたら、どうぞご遠慮なく」
容赦なくこき使ってやって下さいと言えば、仏頂面でそっぽを向いていた雪哉が、苦虫を噛み潰したような顔をこちらに向けた。
「本人の了承もなく、勝手に決めないで下さいよ……」
「お前が拒否出来る立場か、馬鹿息子」
鼻を鳴らした郷長に対し、雪馬が何かを言いかけて、迷ったような様子を見せてから口を噤んだのだった。
食事を終え、一息ついた頃である。
客間前の廊下に跪き、雪馬は静かに声を上げた。
「墨丸殿。遅くなってしまいましたが、湯殿の支度が整いました。お背中をお流しいたします」
すぐに襖が開かれ、驚いた表情の墨丸が顔を出した。
「雪馬殿。お湯を用意して頂いたのは有難いのだが、背中を流すなど、わざわざ貴公にして頂く事ではありますまい」
客人の湯浴みを手伝うのは、本来であれば、下男か下女のする仕事である。百歩譲って雪哉か、雪雉であればまだ分からなくもないが、次期当主である雪馬がやって来るなど、本来ならば考えられない話だった。
雪馬自身、それは重々承知していた。だからこそ今回は、家人にも口止めをして、家族にも内緒で墨丸のもとを訪れたのだ。
「申し訳ありません。ですが、明日の朝には発たれてしまうのですよね」
今しか話せる時間がないのだとほのめかせば、墨丸も、すぐにぴんと来たようだった。
「……分かった。いささか心苦しいが、お願いしよう」
客人の察しの良さに感謝して、雪馬は墨丸を湯殿へと案内した。
とは言っても、この屋敷の湯殿なんてものは、中央のそれとは比べ物にならない。
宗家や、宗家に連なる四大貴族の屋敷には、体を浸せる浴槽もあるらしいと聞いているが、郷長は所詮、地家と呼ばれる田舎貴族である。人が二、三人しか入れない小部屋に、他で沸かした湯を運び込んだものがせいぜいであったが、墨丸は文句ひとつ言わなかった。
熱湯と水を入れた二つの桶を床に置いて、雪馬は湯帷子を身に着ける墨丸に話しかけた。
「お湯をお使いになっている間だけでも、お話しさせて頂いてよろしいでしょうか」
雪哉の件で、と言うと、心得たように頷かれる。
「なんなりと」
雪馬は、空の桶に湯と水を入れ、ちょうど良い加減に調節した湯を墨丸の背にかけた。
「弟が、中央で働きを惜しまれていたというのは本当なのですか」
「本当だ」
間髪を容れない返事であった。
墨丸はそれだけでは不足だと思ったのか、淡々と言葉を続けた。
「雪哉殿は、大変優秀だった。働きぶりも見事なもので、若宮殿下は、特に雪哉殿が朝廷を去るのを惜しまれていた。近習にも取り立てて、最後にはずっと自分の配下でいて欲しいと請うたくらいだ」
それを拒んだのは雪哉の方で、若宮が雪哉を放逐したなど、とんでもない話だと言う。
「郷長のお話を聞いて、こちらが驚いてしまった。雪哉殿は、中央で自分が何をしていたか、お父上には伝えていないのか?」
――やはりそうだったか。
心底不思議そうな墨丸を前にして、雪馬は深くため息をついた。
「雪哉は、自分は中央で何も出来なかった、と言っています」
中央から帰って来た雪哉の報告は終始一貫していた。
若宮殿下のお役に立てず、自分はずっと足手まといだった。人員が足らず一年間勤める事になったが、それもやむを得ずであって、他に側仕えが見つかれば、すぐにでもお役御免になったでしょう、と。
「父は、馬鹿正直にそれを真に受けているのです。ですが、そんなわけはあるまいと、ずっと思っておりました。今回、墨丸殿からお話を伺えて良かった」
墨丸が、問うような視線を寄越して来た。
「詳しくお聞きしても?」
雪馬は、一度深呼吸して覚悟を決めると、墨丸の目を真っ直ぐに見据えた。
「我ら三兄弟のうち、雪哉だけ、母親が違うという話はご存じですか」
雪馬の目を見返した墨丸は、ゆっくりと頷いた。
「知っている」
雪哉の実母は、雪哉を生んで、すぐに儚くなった女である。だが、その生まれは垂氷郷の主家にあたる、北家であった。
なまじ、母親の身分が高かったのが災いした。
年がひとつだけしか違わない事もあって、かつては長男の雪馬を廃し、雪哉を次の郷長にしてはどうかという動きがあったのである。雪哉と雪馬、どちらが次の郷長となるかで、しばらくは揉めていたのだ。だが、主家である北家の顔色を窺い、親戚達の攻撃に耐えかねた父は、結局、どちらを跡目にするとも明言出来なかった。
「ですから、私が跡目として認められるようになったのは、雪哉が私を立てるように振舞ってくれたおかげです。学問であれ、剣の仕合であれ、私と比べられると分かると、あいつはすぐに手を抜くのです。わざとだというのは明らかでした。だって、父が見ていない時の兄弟喧嘩で――口でも腕っ節でも、私があいつに勝てたためしは、一度だってないんですから」
母も末弟も、それは承知していた。分かっていないのは父だけなのだ。
「雪哉が意図してぼんくらを装っているだなんて、父はちらとも考えていないのです。もしかしたら、そうと分かるのが怖くて、あえて考えないようにしているのかもしれません」
雪馬は手を止めて俯いた。こんな事を、自分で言わなくてはならないのが非常に情けなく、それ以上に、雪哉に対して申し訳がなかった。
「きっと父は、安心したいのだと思います。私を跡継ぎにして良かった、自分の判断は間違っていなかった、と。実際は、父が私を選んだわけではなく、雪哉が私を後継ぎにしてくれたというのが本当ですが」
そのため、母も自分も、雪哉に対して後ろめたいような気持ちを抱いてここまで生きて来た。雪哉が、父や親類達が言うような「ぼんくら」でないのは百も承知なのに、次男坊の気遣いに甘えなくてはならない立場にいて、やきもきし続けていたのだ。
だからこそ雪哉の中央入りは、自分や母にとって、心から喜ばしい事だった。
「……父が雪哉を軽んじ続ける限り、雪哉はずっとこのままです。だから、あいつが俺や母上に憚らず、自由でいられるのなら、中央で生きていけば良いと思っていました」
雪哉を厭うているわけでは断じてない。
母は、雪哉を実の子として育てて来たし、家族であるという強い思いは、雪馬も雪雉も同じである。だから、いつまでも垂氷にいて欲しいと思う反面、雪哉がこの小さな地方の郷の中に収まって、自分の能力を無理やり押さえ込んで生きて行くのは、もったいないと思っていたのだ。
「なんで、あいつは戻って来てしまったのでしょう」
他でもない若宮殿下に引き留められたのなら、中央に残っても良かったはずである。むしろ、本人のためにはその方がずっと良かったのに。
助けを求めるように墨丸を見上げれば、中央から来た客人は、何かを思い起こすように視線を遠くへ向けていた。
「若宮に仕える事に、価値を見出せなかったようだ。自分にとって大切なのは家族と故郷だけだと、再三言っていたくらいだから」
「じゃあ、あいつはまだ、垂氷に囚われているんだ」
胸の奥をぎゅっと摑まれたような気分になり、雪馬は服が濡れるのも構わず、墨丸の横に両膝をついた。
「お願いです、墨丸殿。いずれ郷長になる以上、私には弟を救えません。どうか、私に代わって雪哉を、自由にしてやってはもらえませんか」
雪馬の様子をまじまじと見た墨丸は「顔をお上げなさい」と、静かに命令した。
そして、縋るような眼差しの雪馬と目が合うと、やわらかな微笑を浮かべたのだった。
なまじ見目の良い男なだけに、笑うと一気に華やいだ雰囲気になる。
それまでの表情が薄かったせいもあり、まるで乾いた地面から、突然に花が湧いて出たかのような有様であった。しかも、その笑顔は美しいと言うよりも、まるで幼子を見守るように、優しげである。
急な表情の変化に面食らった雪馬に向けて「そう考えるのも早計なのではないか」と墨丸は穏やかに告げた。
「雪哉の、大切なものを守りたいという気持ちに嘘はない。その気持ちを無下にしてしまっては、あまりにあの子が可哀想だ」
雪哉殿は馬鹿ではない、それは貴方が一番よくお分かりだろうと、慰めるように墨丸は言う。
「私は、本人の意思に任せるのが一番だと思う。雪哉殿は聡明であると同時に、とても頑固でもあるから、きっと、他人に何を言われようが気にしないだろう。その代わり、本当に護りたいもの、やり遂げたい目標が見つかれば、君が今まで心配していたのが馬鹿らしくなるくらい、自由に羽ばたいて行くのではないかな」
弟を信じておあげなさいと諭されたような気がして、雪馬はなんとなく恥ずかしくなった。年頃はあまり変わらないはずなのに、こうしていると、まるでずっと年上の八咫烏に相談しているような気分になる。
それを言うと墨丸は、微妙な顔を返したのだった。
「当たらずといえども、遠からずかな」
* * *
――一体、どうしてこうなった。
半ば頭を抱えながら、雪哉は目の前の背中を睨みつけていた。
墨丸と名乗る男が垂氷郷にやって来た、翌日の朝である。
垂氷のぼんくら次男こと雪哉は、笑顔で手を振る親兄弟、郷吏と郷吏の家族達に見送られ、墨丸とともに郷長屋敷を後にした。
墨丸の連れて来た馬に二人して乗り、空に飛び立ってしばらく。
間違っても誰かに話を聞かれる事のない所までやって来て、雪哉はこの一日、言いたくても言えなかった言葉をようやく吐き出せたのだった。
「何が『若宮殿下の使い』ですか」
こんな所に護衛の一人も付けずにやって来るなんて、と雪哉は息巻いた。
「ふざけるのも大概にして下さい、若宮殿下!」
墨丸――もとい、日嗣の御子こと若宮、奈月彦は、真面目くさった顔で言い返した。
「勘違いされては困る。若宮殿下は宮中にて、現在も立派にお役目を果たされている。今の私は、若宮殿下の側仕えである『墨丸』以外の何者でもない」
きちんと戸籍もあるしな、と、肩越しに身分を証明する手形を差し出される。背中につかまったまま、ひったくるようにそれを受け取った雪哉は、内容を確認して呆れ返った。
「よくもまあ、用意周到に……。まさかとは思いますが、中央の皆さんに黙って来たわけではありませんよね?」
敵の多い宮中において、この男の味方になってくれる奇特な人物は宝である。そんな仲間にも黙って出て来たのであればいよいよ救いようが無いと思ったが、若宮はあっさりとそれを否定した。
「そこまでの無茶は出来んよ。心配するな。敵方も、若宮は迎えたばかりの奥さんの所に、入り浸っていると思っているはずだから」
何気なく言われたが、どうやって敵の目を誤魔化しているのか、考えるだに恐ろしい。雪哉が宮中にいた一年の間も、若宮は敵対する勢力に、常に命を狙われていたのだ。
若宮は、八咫烏の族長一家、宗家の嫡男というわけではない。
八咫烏の長は金烏と呼ばれ、その座は、ほとんどの場合世襲される。通常であれば、現金烏とその正妻の間に生まれた長男、兄宮が次の金烏となってしかるべきだったが、若宮は「真の金烏」として生まれたという理由で、次男――しかも、側室の母から生まれた――にも拘わらず、日嗣の御子の座に着く事になっていた。
そもそも族長を表す「金烏」という用語は、実はふたつの存在を指し示している。
ひとつは、金烏の本来の形である「真の金烏」。もうひとつは、真の金烏が存在しない間、あくまで場繋ぎとして代理を務める「金烏代」だ。金烏代が単なる宗家出身の八咫烏であるのに対し、真の金烏は、そもそも八咫烏とは完全に異なる生き物だとされていた。
八咫烏は、夜間に転身を行えない。ところが真の金烏は、日没後も自由に姿を変えられるなど、普通の八咫烏ではあり得ない事が出来るのだとされていた。そして今、雪哉の目の前で馬を駆る若宮は、その真の金烏であると言われている。
若宮が、兄宮を蹴落として日嗣の御子の座についたのはそのためだ。真の金烏以外の宗家の者は、全て「金烏の代理」という扱いだから、宗家に生まれた子が神官によって「真の金烏である」と認められた場合、問答無用で君主の座につかなくてはならないのだ。
しかし、雪哉が若宮に近侍していた一年の間、この男が俗に言う「真の金烏」らしさとやらを見せた事など、ただの一度もなかった。結局のところ、真の金烏だの金烏代だの、そんなのは全て宗家の正統性を主張するための方便なのだと雪哉は思っている。
実際、真の金烏が世に出た代というのは、混乱した歴史が多かったらしい。挙句、実際に大水や干魃などの天災に見舞われれば、「真の金烏は災いを呼ぶ」などと言われても仕方がないように思える。
だからと言って、雪哉には「若宮を殺してしまえば良い」と考える連中の気持ちは全く分からない。そんなどす黒い欲望渦巻く宮中に辟易したからこそ、雪哉は中央の職を辞し、垂氷へと帰って来たのだった。
「……あちらは、相変わらずですか」
意図せずして、呆れたような物言いの中に、寂しげな色が混ざってしまった。それに気付いたのか、若宮は声もなく笑う。
「相変わらずだ」
何しろ変わりようがない、と達観したような若宮の口調が、雪哉には面白くなかった。
「だったら、あまり長く宮中を空けない方が良いでしょうに」
「それが、そうも言っていられない状況なのでな。でなければ、わざわざ私が出向いたりはしないよ」
若宮が大真面目であると気付き、雪哉も顔つきを改めた。
「仙人蓋は、そんなにまずい薬なのですか」
「後天的に八咫烏が人形をとれなくなる薬など、聞いた事もない。それに、お前も昨日の奴を見たから分かっているだろうが、服用した者だけでなく、周囲の八咫烏にまで被害が及んでいる。仙人蓋それ自体はごく少量しか出回っていないのに、影響があまりに大き過ぎる」
それなのに、未だ仙人蓋そのものの正体は全く不明なのだ。
中央の医が総力を挙げて治療法を探しているものの、未だに人形が取れなくなった者が、もとに戻れる方法は見つかっていない。
これは、明らかに異常であった。
今はこの程度の被害で済んでいるが、対応策が見つからない以上、現況は最悪と言って良い。
「とにかく、仙人蓋の現物を確保し、売人を早急に取り押さえる必要がある。さもなければ、仙人蓋はいくらもしないうちに、八咫烏の存続そのものを危うくする存在になるだろう」
既に朝廷が動いているとはいえ、これ以上、後手にまわるわけにはいかない。正規の手段は役所に任せ、若宮は、若宮にしか出来ない掟破りの手段に打って出たのである。
「いざとなった時には、金烏としての権限を使うつもりでいる。山内の民を守るためにも、今、出来る事は全てしておきたいのだ。協力してくれるな?」
暗に「お前を連れ戻しに来たわけではないから、そう警戒するな」と釘を刺された気がして、雪哉はしばしの間、黙りこくった。
「……垂氷に犠牲者が出た以上、これはすでに、僕の問題でもあります。協力するのに力は惜しみません」
「大いに結構。お前の大切なもののためにも、精々励んでくれ」
そう言った後、若宮はまっすぐ前を向いたまま、ひたすらに馬を天翔けさせたのだった。
山内には、朝廷の存在する中央と、それを取り囲む東西南北の、四つの領が存在している。四領は、それぞれ東家、南家、西家、北家の「四家」という四大貴族によって分治されており、一つの領は、さらに三つの郷に分かれていた。
山内の交通網には、中央から地方に向けて延びる放射状の道の他に、十二の郷を横断するように整備された、環状の街道が存在している。
鳥形に転身出来るのだから、街道など不要にも思えるが、その実、この街道の利用者は多い。馬を使った移送は早くて便利な分、一度に運べる荷物の量が少なく、却って運送費の方が高くついてしまうためだ。実際、地方からの年貢米の運搬や、大量の荷物を一度に運ぶ場合は、翼を切られ、特別に脚力を鍛えた馬に荷車を牽かせる場合が多かった。
街道沿いの宿場は、街道を歩く者のための宿屋であると同時に、馬を休ませるための休憩所でもある。大きな市が立つのもこの宿場町がほとんどで、余所から来た商人や旅人は、ここで地方の特産物を仕入れたりするのだ。
若宮と雪哉は仙人蓋が辿った経路を探るべく、まずは田間利という名の宿場町へと向かった。
今朝方、夜明けと同時に帰って来た郷吏からもたらされた情報によって、あの不審者の身元は既に割れていた。郷長屋敷と、田間利のちょうど中間地点の村に住んでいたその男は、もともとは猟で生計を立てている、独り者だったらしい。
山で狩って来た獣を売りに、一昨日の朝、宿場に出て来た事は村民の話から分かっていた。男が田間利で仙人蓋を手に入れたのは、ほぼ間違いない。別段、素行が悪いというわけでもなかったので、村の者は男の凶行を聞き、とても驚いていたという。
結局男は、雪哉と若宮が郷長屋敷を出る時になっても、興奮状態を脱する事はなく、人形にも戻れないまま捕縛されていた。解毒の方法が分からない限り、一生あのままなのかと思えば、昨日の行為に対する恐怖よりも、男に対する憐れみが勝った。
何としても、これ以上の被害は阻止しなければならない。
だが若宮は、なぜか一息に田間利に向かおうとはしなかった。通りがかった村の全てで、ここ最近何か変わった事はなかったかに始まり、村に立ち寄った旅人の様子、村で取引されたもの、最近の村人の体調まで、事細かに聞いて回ったのだ。しつこく質問する余所者を訝しむ者もいたが、雪哉が郷長の次男坊だと分かるや否や、その警戒もあっさりと解かれた。
そこで雪哉にもようやく、若宮が自分を連れて来た理由に合点がいったのである。
「基本的に、地方の者は中央から来た宮烏に当たりがきついからな。手っ取り早いのは、地元の協力者を得る方法だろう」
お前がいてくれて良かったよと悪びれずに言う若宮に、雪哉はこめかみを揉んだ。
似合わない編笠を被り、簡素な羽衣に山賊まがいの大刀を帯びている若宮の姿は、いかにも旅慣れた者の風情である。
幼少の頃から一年ほど前まで、若宮は外界に遊学していたと聞いている。この年になるまで外界に出ており、山内に帰って来てからは中央から出ていないはずの若宮が、どうしてこんなに地方巡りに慣れた様子なのだろうか。
「時間があれば、北領なら酒を一緒に飲むのも一つの手だな。東領なら笛を吹くし、南領なら中央の政情に詳しいとほのめかせば、むこうから歓待してくれる。西領は話を合わせるのが難しいが、基本的に衣と住まいを褒めておけば問題はない」
――あっけらかんと言う若宮に、雪哉はあえて考えるのを止めた。
大した情報も得られぬまま、二人は田間利へとやって来た。
田間利は、垂氷郷において最も大きな宿場である。とはいえ、垂氷郷そのものが北領の中でも辺境とされるような田舎だから、その規模も大したものではない。中央のような店構えの商店はなく、あるのは旅籠と、簡単な飲食の出来る屋台ばかりだ。
市も立っていないこの時分、田間利は閑散としていて、あまり活気があるとは言えない様子だった。そんな中、若宮と雪哉は、宿場の顔役が経営する一番大きな宿屋へと向かった。宿はすでに郷長の派遣した郷吏達の拠点となっており、大々的な聞き込みをしていたので、簡単な情報交換を行おうと思ったのだ。
宿屋に顔を見せた二人を、郷吏達は快く出迎えた。郷長から墨丸に協力するようにという通達が来ていた事もあり、自分達が調べて手に入れた情報を、惜しまずに教えてくれたのである。
郷吏は、若宮と雪哉に茶菓子を出しながら、仙人蓋をこの地にもたらした者の目星について語った。
「商人ですか」
「ええ。話を聞く限り、街道沿いに商売をして回っている、行商人じゃないかと思っとります。地元の八咫烏ではないのは確かかと」
仙人蓋の犠牲となったあの男は、獣の皮や肉を直接客に売るのではなく、特定の業者にまとめて買い取ってもらっていたらしい。そこで金を得ると、毎回、宿場に併設した屋台に入り、他の地域から来た者と酒を飲むのが常だったのだ。
「常連だったので、屋台の親仁が顔を覚えとりました。あいつは余所者の商人と話をしていて、勘定も一緒、屋台を出るのも一緒だったそうで」
親仁は、あの男が最後に一緒だった者を「初めて見た顔だった」と証言した。大きな荷物がなかったので、近くの宿屋の宿泊客かと思ったらしい。
しかし、「ここから先が大変だ」と郷吏は唸った。
「今から、あの男と商人の人相書きを広場に貼り出したり、宿屋の女将なんかに訊いてみようかと思っとるんですが。何分、ここにいる者の八割が旅人ですからなあ」
新しい情報が得られるかは、怪しいものだと言う。
しかも、本当にその商人が仙人蓋をもたらしたという確証もないのだ。屋台を出て、そいつと別れた後、全く違う相手に薬を渡されたのだとすれば、今行っている調べはまるごと無駄になってしまう可能性すらあった。
礼を言い、雪哉と若宮は、郷吏のいる宿屋を出た。
日は、すっかり高くなっている。
いいかげん腹の虫もうるさくなってきたので、二人は広場脇の木陰に腰を下ろし、雪哉の母が持たせてくれた握り飯を頬張った。
「あまり、有益な情報はありませんでしたね」
握り飯の中身は、去年の今頃に漬けた小梅の梅干しである。酸っぱさに目を細め、竹の水筒を渡しながら声をかけると、若宮は「そうでもないぞ」と言い返した。
「最初に、郷長屋敷にもたらされた情報がある。この宿場で売人と接触した者は、少なからずいるはずだ。屋台の親仁殿の証言、最初の情報をもたらしてくれた者の証言――幾人かの証言を繋ぎ合わせれば、自然と答えは見えてくるはずだ」
あやしげな薬の売買をもちかけられたが、結局買わずに済んだ者が他にいるかもしれないのだ。郷吏達が大々的に喧伝し、宿場町の有力者が捜査に協力的であれば、時間はかかっても、必ず売人の姿は浮かび上がって来るに違いないと若宮は言う。
「では、僕達はどうしましょう。郷吏達の手伝いでもしますか」
見上げて問えば、若宮はすぐに「いいや」と首を振った。
「どうせなら、郷吏達には絶対に出来ない方法を試してみよう」
「そんな方法があるのですか」
「まあ、黙ってついて来い」
指についた米粒を舐めると、若宮は寄りかかっていた木から体を起こした。どうするつもりなのかと、大人しく若宮に続いた雪哉はしかし、すぐに首を捻る事になった。それと言うのも若宮は、宿場町に着く前と同じように、最近何か変わりはないかを訊いて回っただけだったのである。
時節による客足の変化や、ここ数年の商品の変遷、酒場で働く女による亭主の愚痴まで、話の種類は多岐に渡った。中には、仙人蓋と絶対に関係ないだろうと思えるものも多かったが、若宮は根気強く話を聞き続けた。
若宮の行動の意味が分からずに、雪哉は完全に置いて行かれた気分になった。この感じは、若宮に仕えていた時にはお馴染みだったものである。
宿場をあらかた回り終え、いいかげん雪哉も疲れて来た頃だった。
飴湯を売る老爺の言葉に、初めて若宮が明確な興味を示した。
「変わった事と言えば、最近は栖合の方で、不知火がよく見えるようになったと聞きますな」
「不知火?」
「ええ。昔は滅多に見られないもんでしたが、ここ十年くらいですか。山の端で、一年のうちに五回も六回も見えるようになったそうで」
――山の端に炎立つ、という。
山の端とは、中央から最も離れた辺境を指す言い方である。文字通り、山内の端であるとされていて、そこを越えてしまうと、二度と帰って来られなくなるという言い伝えがあるのだ。
不知火は、夜の辺境で迷子になったものを惑わす「お化け」であるとされていた。
本来であれば、山の端を越えた先には住む者はいないので、人家の明かりもなく闇夜では何も見えないはずである。ところが、暗闇の中で道しるべを失った者は、あるはずのない光を山の端の向こうに見る事がある。それを民家と思って近付いてしまうと、いつの間にか山の端を越えてしまい、山内では行方が分からなくなるのだ。
運良く惑わされずに帰って来た者が、あるはずのない明かりが見えるこの現象を『不知火』と呼ぶようになったという話は、ひとつの伝承として知られている。
「不知火は、不吉なものとされておりますからな。皆、気味悪がっておりましたよ」
老爺自身は世間話の一環として語ったようだったが、床几に腰かけて飴湯を飲んでいた雪哉は、隣に座る若宮の目つきが今までとは違う事に気が付いた。
「その、栖合という集落へは、どう行けば良い?」
「栖合は、旧街道の終着点でさ。ここいらでは、一番山の端に近い集落ですな」
「旧街道……」
「わしの祖父さん達の時代は、それなりに栄えていたらしいですけどね。新街道が出来てからはすっかり廃れて、今では人の往来なんざほとんど無いですよ」
しかし、一応は整備されていた跡があるため、それを辿っていけば自然に行き着くはずだという。
旧街道の行き着く果て、栖合。
その名前は、先程耳にしたばかりである。雪哉は隣を見上げた。
「確か、今日会う約束をしていた栖合の人が、約束の時間に来なかったとか言っていませんでしたっけ」
とある行商人から聞いた話である。
栖合の者は、普段はめったに宿場へとやって来ないのだが、手に入りにくい入り用の物があると、宿場を通して行商人に注文する手筈になっていた。これまで、行商人が来るのを待っている事はあっても、待たせた事は無かったのにと、不思議がっていたのだ。
若宮は唐突に立ち上がった。
「ご主人。美味い飴湯をどうもありがとう」
もういいのかい、と目を瞬く老爺に二人分の代金を渡すと、若宮は足早に歩きだした。
「ちょっと、若さま」
慌てて飴湯を飲みほし、雪哉は小走りになりながら若宮の後を追った。
「どうしたんですか。仙人蓋と不知火が、一体何の関係があるんです?」
「分からん」
きっぱりと言い放った若宮に、雪哉は一瞬口を噤んだ。
「分からないって……」
「分からんが、どうしても放っておけない気がしたのだ。最初に栖合の名が出た時も気になったが、今ので確信した。手掛かりは栖合にある」
「いや、ちょっと待って下さい」
若宮は大真面目だったが、雪哉にはわけが分からなかった。
今まで、若宮が唐突な行動を取る事は多々あったが、それには説明がないだけで、きちんとした根拠があった。今回のように、まるで意味のない事を言いだしたのは初めてである。
「それって、完全に勘じゃないですか」
戸惑いながら反論するも、若宮はこちらを一顧だにしなかった。
「勘は勘でも、金烏の勘だぞ」
何もないわけがない、と断言する若宮に、雪哉は違和感を覚えて沈黙した。
――『真の金烏』なんてものは、宗家が自分の力を守るために作り上げた、便宜上のものではなかったのか。若宮の言葉を聞いていると、まるで、本人はそう考えていないかのようだ。
さっき栖合について語っていた行商人のいた場所に駆け戻ると、彼はまだそこにいた。どうやら、栖合のために仕入れた商品が捌けずに、これからどうするかを決めかねていたらしい。
「栖合の者のためにここまで持って来たのに、売れなきゃ商売上がったりですよ。届けに行って、帰って来るような時間はないし」
こっちはすぐにでもここを出なくちゃならないのにと、ほとほと困った風の行商人に、若宮は金子を差し出した。
「私がその商品を買い取って、向こうに届けて来よう」
明らかに代金には多い額に、行商人は目を丸くした。
「そりゃ、こっちとしては有難いが、あんたはそれで良いのか」
「ああ。栖合に急用が出来たのでな」
行商人は大喜びで商品と交換し、若宮はその足で、最初の宿へと向かった。郷吏達の方に進展がないのを確認すると、すぐに厩に預けていた馬を引き取って来る。
「このまま、栖合に向かうつもりですか」
「お前は行かないのか」
「いえ」
いずれにしろ、若宮に従う以外の選択肢はないのだ。
馬は、若宮と雪哉を背中に乗せて、田間利を飛び立った。
環状街道を越え、旧街道沿いに飛ぶようになると、一気に家屋の数も少なくなり、周囲は寂れた印象になる。特に村と呼べるような集落もなく、ぽつぽつと民家があるくらいだ。宿の者の話によると、栖合は数世帯が集まっただけの小さな集落であり、栖合より先に住んでいる八咫烏は、まずいないだろうとの事だった。
日が傾き始めた頃になり、異変に気付いたのは、若宮が先だった。
空を飛んでいる最中である。
まだ栖合の影も見えていなかったのに、若宮は不意に顔を上げ、己の背中に摑まっている雪哉を振り返った。
「何か、臭わないか」
雪哉には何も感じられなかったが、若宮の声は緊張を孕んでいた。
「分かりませんけど、どんな臭いです?」
一瞬迷う様子を見せてから、若宮は低く答える。
「生臭い。血の臭いがする」
「血……」
「そう。それも、尋常の量じゃない」
風上は、進行方向だ。
一瞬押し黙ってから、雪哉は曖昧に笑った。
「山奥ですから、猪でも狩って、村で捌いているのかもしれませんね」
もしくは鹿とか、と明るく言い添えたものの、再び前を向いた若宮の頭はぴくりとも動かない。
雪哉にも分かっていた。
もし若宮の予感通り、仙人蓋と栖合の間に何らかの関係があったのだとしたら、住人同士の間で流血沙汰が起こっていたとしても、おかしくはないのだ。
いくらもせず、行く手に集落の屋根を捉えたが、若宮は喜びの声を上げなかった。
「上から様子を見る。何か見つけたら報告しろ」
「承知しました」
鋭い口調で命令されて、雪哉も今度は固い声で答える。
そのまま、集落の上空を旋回する。
時刻は、夕方と言うには若干早い。誰かが働いていてもおかしくはない時間帯だったが、集落にも、ささやかながら開墾された畑にも、村人の姿はひとつとして見当たらなかった。
「誰もいない……?」
雪哉と若宮を乗せた馬のすぐ横を、トンビが吞気な声を上げて通り抜けて行く。
静かだった。
物干し竿には、洗濯物が揺れている。家の軒先には干物がぶら下がっており、誰かが暮らしているのは間違いない。何も載せていない荷車が二台、まるで、さっきまで使われていたかのように放置されていた。
皆、山に出ているのだろうかと思っていると、とある家の前の井戸端に、何かが落ちているのを見つけた。
「殿下」
目の前の羽衣を引っ張って、もう片方の手で下を指し示す。
「あれ。何に見えますか」
井戸の前、掃き清められた土の上に、水たまりのような黒いしみと、丸まった布きれのようなものがある。
「ここからでは、何か分からんな」
「一度、降りてみますか」
若宮はわずかに考えをめぐらせた後、頷いた。手綱を操作して、井戸に近い少し開けた場所へと馬を下ろす。
馬の背から降り立った瞬間、雪哉は顔をしかめて、無意識に一歩足を引いた。
ここに来てようやく雪哉にも、若宮の言う血臭が分かった。確かに生臭い。生き物が、大量に血を流した臭いがする。それから、腐敗の始まった、死肉の臭い。
目の前を横切った蠅を追って視線をめぐらせた雪哉は、井戸の前に落ちた物を確認し、息を吞んだ。
それは、八咫烏の腕だった。
丸まった布切れと見えたものは、右手の肘から先の部分だ。蠅のたかった掌は上を向いており、付着した血液は乾いている。それが、上空からは水たまりと見えた血だまりの中に、ぼとりと一つ、落っこちているのだ。
呆然とその光景を見つめていた雪哉は、すぐに、その血だまりの先にあるものにも気が付いた。腕が落ちている場所から一番近い民家の戸口まで、何かを引きずったような痕がある。
引き戸は、今は閉ざされている。雪哉の総身が粟立った。
声を出すよりも早く、雪哉は若宮によって、戸口から遠ざけられた。
「音を立てるな。すぐに転身出来るようにしておけ」
囁かれ、無言で頷く。
雪哉が離れたのを見計らい、若宮は腰の刀を抜いた。そのまま引き戸に手をかけて、一気に開け放つ。
開かれた扉から射し込んだ光が、室内の様子を照らし出した。
――無残なものだった。
室内に散乱する、ばらばらになった手や足、赤黒い内臓。
頬の部分が齧られた女の顔は苦悶の表情のまま、白目を剥いて土間に転がっていた。囲炉裏端は、今やどす黒い血の海に覆われて、もとの色が分からない。壁にまで飛び散った血痕の下には、肉片の付いた白い骨が山積みにされている。
そして、部屋の中央に蹲った黒い影が、何やら動いているのが分かった。
むっと立ちこめる血なまぐささの中、ぴちゃぴちゃと何かを啜る音が響く。
一拍の後、夢中で手元のものにかかりきりになっていたそいつが、動きを止めた。
背中を丸めたまま、ぽかん、とした表情で振り返った顔は赤ら顔で、八咫烏のものではあり得ない。見開いた目には白目がない。虹彩は金色に光り、血が飛び散った体は、みっしりとした毛皮に覆われていた。
猿だ。
それも、とてつもなく大きい。
信じられないほど大きな猿に、八咫烏が喰われているのだ。
「殿下、逃げて!」
「飛べ雪哉!」
雪哉と若宮が叫んだのは、ほぼ同時だった。
事態を把握出来ずにいたらしい大猿が、その声に、突如として気配を変えた。
しゃぶっていた骨を吐き捨てると、歯を剥き出しにして若宮へと突進して来る。咄嗟に若宮が体を捻り、猿の攻撃をかわした。狙いが外れた猿は、引き戸を派手にぶち抜いて外へと転がり出る。
叫んですぐに鳥形へと転身した雪哉は、上空から、ゆらりと立ち上がった猿の姿を見て絶望的な気分になった。
やはり大きい。七、八尺はあるだろうか。まともに組み合っては、勝ち目が無い。
岩のように盛り上がった巨体の中で、赤い顔だけが浮かんで見える。大きな目は淀んでいて、血の臭いに酔っているように見えた。爪の生えた指先には、先程まで貪っていた八咫烏の血が付着している。
先日の大烏とはわけが違う。向こうは明らかに、若宮を殺すつもりで向かって来ている。
――何をしている、さっさと逃げろ!
そう伝えるつもりで雪哉は鳴いたが、若宮は動かなかった。
大猿に向き合って刀を構えたまま、ただ、低い声で問いかける。
「貴様、何者だ。一体、どこからここへ来た」
それに対し、猿が小さく口を動かした。その一瞬だけ、馬鹿にしたような雰囲気を見せたものの、すぐに問答無用とばかりに若宮に襲いかかって来た。
若宮が舌うちをする。
猿が両腕を振り上げた。醜悪な歯を剥いて、鼓膜を劈くような咆哮が轟く。力ずくで押しつぶそうとしたのか、猿は全身で抱きつくように、若宮へと跳躍した。
それを真正面から受けた若宮は、猿を冷たく睨み据えたまま、右手に持った刀を軽く振り下ろした。
刀身がぎらりと光り、勢い良く血飛沫が弾け飛ぶ。
勝負は、あっと言う間もなく決着した。
若宮と猿の姿が重なったと思った次の瞬間には、猿の首はぽんと、胴体から切り離されていたのだ。
宙を舞った頭部が、歯を剝き出しにしたままで何度か跳ねて、転々と転がっていく。血を噴き出しながら崩れ落ちる巨体に巻き込まれないよう、落ち着いて足を引いた若宮は、地に落ちた頭を冷然と見下ろした。
あまりにあっけない猿の死にざまに、雪哉は我が目を疑った。慌てて地上に下り、人形となって若宮のもとへと駆け寄る。
「お怪我は」
「無い。だが、八咫烏が何人も喰われている。被害の状況を確認したら、田間利まで一旦戻るぞ」
宿場町には自警団が存在しているし、宿場から郷長屋敷に要請をすれば、領内警備の兵が使えるはずである。
「この集落には、四世帯、十三人の八咫烏がいたはずだ。全員殺されたとは思いたくないが……」
濁した言葉の先を察して、雪哉は大きく喘いだ。
「一体――一体、こいつは何なのですか!」
八咫烏を喰らう大猿だなんて、今まで見た事も聞いた事も無かった。得体の知れない猿への恐怖は、仙人蓋で狂った八咫烏どころの話ではない。
半ば恐慌状態で叫ぶ雪哉の言葉に、若宮は険しい面持ちを返した。
「それは、私の方が聞きたい」
とにかく、状況の確認が先である。
「お前はここにいろ」
雪哉を馬の傍に留めると、若宮は他の家屋を調べようと踵を返した。次々と戸を開けて中を検めてゆく若宮の背中を、雪哉はハラハラしながら見守った。生きている者がいて欲しいと願う一方で、情けないと分かっていながら、すぐにでもこの場を立ち去りたくてしようがなかった。
若宮が三軒目の家の中に踏み込み、姿が見えなくなった時だ。背後に何者かの気配を感じて、雪哉は弾かれたように振り返った。
「あ、う」
びくりと体を震わせて、生い茂る雑草に尻もちをついた人影に、雪哉は目を丸くした。
貧相な茶色の着物に、ぼさぼさの髪の毛。怪我をしているのか、体には血がついている。木の陰に隠れるようにしているのは、紛れもない、人形の八咫烏だった。
怯えたように縮こまる姿をまじまじと見つめて、雪哉は安堵の息をついた。若宮のいる方へと体を向け、大声を出す。
「殿下、生存者がいました!」
何だと、と声を上げて、若宮が慌てた様子で家の中から出て来た。
「でも、怪我をしているようです。一刻も早く」
手当を、と続けようとして、雪哉は口を噤んだ。するりと、背後から首に腕が巻きついて来たのだ。
それを訝しく思うよりも先に、表情を一変させた若宮が叫んでいた。
「そいつは、八咫烏じゃない!」
気付いた時にはもう遅かった。
確かに人の形をしていたはずの腕の筋肉が、いきなり太く盛り上がり、瞬く間も無く毛が生える。毛皮の襟巻をきつく巻かれたような感触とともに、雪哉の首がきゅっと絞まった。
これは、首を折られる。
他人事のようにそう思い、為す術もなく体が宙に浮く。
ほんの一刹那が、雪哉にはひどくゆっくりと感じられた。
若宮との間には距離がある。この体勢では抵抗も出来ない。何にせよ、あとほんのちょっとでも力を入れられれば手遅れだ。
若宮と目が合った。
真っ直ぐに雪哉の目を見据えたまま、若宮は流れるような動作で刀を振りかぶっていた。
まるで、何千回、何万回と繰り返して来た動作を行うかのように、滑らかな動きだった。躊躇いはなく、したがって、刀を振りかぶってから投擲するまでの時間は、瞬きひとつ分しか必要とされなかった。
鞭のように全身をしならせて放たれた刀は、風を切り、一直線に雪哉の顔面へ向かって飛んで来る。そして、雪哉の顔すれすれ、こめかみの髪の毛を数本犠牲にした所に、容赦なく突き刺さったのだった。
づどん、という鈍い音が、雪哉のすぐ耳元で聞こえた。
呻き声は上がらなかった。
ただ、雪哉の首を背後から絞め上げようとしていた体がびくんと跳ねて、不意に力が抜けたのが分かった。
必死に毛むくじゃらの両腕から逃れた雪哉は、振り返り、ついさっきまで己を殺そうとしていた大猿の眉間に、深々と刀が突き刺さっているのを見た。
逃げるように猿から離れ――へなへなと、その場にへたりこむ。
心臓が早鐘を打ち、冷汗がどっと噴き出した。
「大丈夫か!」
駆け寄って来た若宮を見上げて、雪哉は無理矢理に、引きつった笑みを浮かべた。
「……この猿よりも、あなたに殺されるかと思いました」
「私が、そんな下手を打つものか」
ふざけた様子もなく言い返し、若宮は鋭く周囲を見回した。
「うかつだった。まだ他にも、猿がいるかもしれないのに」
「あいつ、人形をとっていました。だから僕、てっきり八咫烏かと思って」
「人形をとられたら、お前には八咫烏と見分けがつかなかった?」
「全然分かりませんでした」
厄介だな、と呟くと、若宮は雪哉の首根っ子を摑んで立たせた。
「最後の一軒の中を確認したら、すぐにここを離れよう。外の見張りは構わないから、私の近くを離れるな」
「分かりました。ちなみに……他の家の中は、どうでしたか」
「全滅だ」
若宮の声は沈鬱だった。
猿の死体から刀を引き抜き、最後の一軒へと足を向ける。震える足を𠮟咤して、雪哉も若宮のすぐ後ろに続いた。
しかし、覚悟して足を踏み入れた四軒目の中は、拍子抜けするほどに綺麗であった。
血の臭いもせず、食べかけの死体もない。ただ囲炉裏端に、長櫃が不自然に置いてあるだけである。
大きめの長櫃だった。人形にさえなれれば、身を隠す事も可能そうだ。
若宮は警戒しながら、刀の鞘を使って長櫃の蓋を取りのけた。慎重に中を覗き見て、すぐに、驚いたように目を瞠る。
「何かありましたか?」
「いや……」
若宮は言い淀んだ。
すぐに逃げられるような体勢を取っていた雪哉も、煮え切らない態度を不審に思い、若宮の背後から長櫃を覗き込む。
そして、雪哉も若宮と同様に瞠目した。
長櫃の中に横たわっていたのは、雪哉と同じ年頃――十四、五歳くらいの、小柄な少女だったのだ。
よく眠っているようで、すうすうと安らかな寝息を立てている。
中央の町娘のような恰好であり、とても、辺境の村の住人には見えなかった。
おそるおそる声をかけ、肩を叩くも、全く起きる気配がない。
「……この子も、猿なんでしょうか」
判断がつかなくて若宮を仰ぎ見たが、若宮は「違う」と即答した。
「この娘に、私は何も出来ない。だから、八咫烏なのは間違いない」
「はい?」
妙にきっぱりとした、自信ありげな言い方である。言葉の意味を尋ねる前に、若宮はさっさと少女の体を抱き上げて、馬の所まで戻ってしまった。
「とにかく、急いでここを離れよう。お前は鳥形でついて来い」
若宮が興奮している馬をなだめ、飛び立つ準備をする横で、雪哉は村を見返した。
得体の知れない大猿。
殺された郷民達。
唯一生き残った、この少女。
――僕の故郷で、一体、何が起こっているというのだろう?