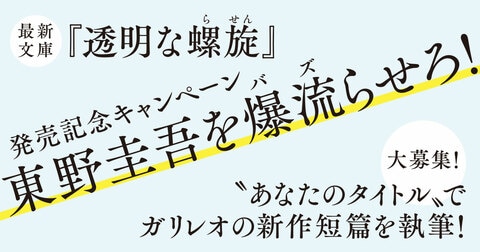弁護士という言葉は「悪徳」という冠詞がよく似合う。
おっと、弁護士会から名誉棄損で訴えられそうなことを書いてしまった。あくまで、ミステリーの世界において、という話である。
『エイレングラフ弁護士の事件簿』は、犯罪小説を代表する大家となったローレンス・ブロックが一九七六年から書いている短篇連作を網羅した作品集である。二〇一四年に刊行されたDefender of the Innocent: the Casebook of Martin Ehrengrafを底本としているが、編集N氏によれば一九九四年にEhrengraf for the Defenseという限定二五〇部の本も出ていたという。その後に発表された四篇を加えたのが完全版である本書というわけだ。
その第一作、「エイレングラフの弁護(別題:成功報酬)」は、ドロシー・カルヘインという女性がマーティン・エイレングラフ弁護士の事務所を訪ねる場面から始まる。カルヘインの息子クラークは殺人罪の容疑で逮捕されたのだが、母親は無実を信じている。不利な証拠は揃っているのだが、エイレングラフはこの依頼を引き受ける。
エイレングラフには他の弁護士とは全く違うところがある。一つは成功報酬であることで、依頼人が有罪判決を受けた場合は一切弁護料を受け取らない。損害賠償の請求訴訟ではごく一般的だが、刑事裁判では珍しいとエイレングラフは毎度宣う。弁護料は高額であり、もしエイレングラフが仕事をやり遂げた場合は一切値切ることは許されない。
もう一つは、エイレングラフにとっては「無罪判決を勝ちとる」のが目標ではなく、裁判にすら持ちこまれず、依頼人を嫌疑なしにすることをいちばんの成功と見なしている点だ。彼は言う。「法廷での丁々発止のやりとりとか、反対尋問の妙技とかは、世のペリー・メイスン諸氏にまかせておけばいい」と。ではどういう手でクラーク・カルヘインを自由の身にするのか、というのが「弁護」の関心事となる。
未読の方に予断を与えることになるので、これ以上は触れない。本篇の結末は鮮やかなもので、一度読んだら忘れられないはずである、とだけ書いておこう。紛れもなく、弁護士ミステリーの歴史に残るべき一作である。
これ以降、エイレングラフはたびたび読者の前に姿を現し、痛快、と言うには衝撃的すぎる活躍を繰り広げることになる。作者はあえて物語の定型を固定し、エイレングラフが依頼人を迎えて、そのためになんらかの手を尽くす、という形ですべての作品を書いている。風貌の描写などもほぼ同じで、そのくり返しに連作短篇ならではの味がある。オックスフォード大学キャドモン会のネクタイが途中からエイレングラフにとっての勝負衣装になる。その理由は「弁護」を読んでいただければわかるはずである。
弁護士ミステリーの歴史は古く、アメリカでは自身も刑事弁護士であったメルヴィル・ディヴィスン・ポーストが一八九六年に発表した『ランドルフ・メイスンと7つの罪』(長崎出版)が嚆矢と言える。法律の穴をついて依頼人を無罪にしてしまうメイスンをポーストが創造したのは逆説的な手法によって法律の脆弱さを明らかにするためだった。同書のまえがきでは「人間の知性が人びとを保護するためにどのような法律を作り出そうとも、人間の知性がまさにその法律をくぐり抜けられる」「邪悪な悪魔はちっぽけではない。善良な聖霊と等しく進化している」(高橋朱美訳)とポーストは指摘している。
弁護士探偵の代名詞といえばひところまではアール・スタンリー・ガードナーが『ビロードの爪』(一九三三年。創元推理文庫)で初登場させたペリー・メイスンだった。もう一組、ドナルド・ラム&バーサ・クールという探偵もA・A・フェア名義で登場させているが、その第一作『屠所の羊』(一九三九年。ハヤカワ・ミステリ文庫)では、ラムが元弁護士であり、人を殺しても有罪にならない方法を開陳したために資格を剥奪されたことが明かされている。ペリー・メイスンもまたラムと同じような奇手を弄する弁護士として初期は設定されたのであり、正義の味方というイメージが後の作品では固定されるものの、『ビロードの爪』の彼はかなりはみ出し者の感がある。初期ペリー・メイスンには、悪徳弁護士の影があるのだ。
ペリー・メイスンはしばしば、自分の依頼人は無実だと信じていると断言する。これを受け継いでいるのが、エイレングラフ弁護士だ。推定無罪は法の基本原則だが、第二話「エイレングラフの推定」では「マーティン・H・エイレングラフの依頼人はみな無罪と見なされる。その推定は、依頼人の予断のいかんにかかわらず、正しかったことがかならず証明される」という宣言が行われる。強気というか、なんというか、いやはや。
弁護士に悪徳の匂いを嗅ぎつける者は各国にいるようで、たとえば日本には、詭弁を弄する者をも指す、三百代言という言葉がある。アメリカのshysterは、いんちき弁護士を指して言うそのものずばりの口語だ。これで思い出すのは戦前に活躍したコメディアン〈マルクス兄弟〉のグルーチョ・マルクスで、弁護士の役柄で登場しては、意味不明のことをまくしたてて金儲けに首を突っ込もうとするのだった。こういう人物像がshysterの最もわかりやすいイメージなのだろう。
マイクル・コナリーに『リンカーン弁護士』(二〇〇五年。講談社文庫)に始まるミッキー・ハラー・シリーズがある。リンカーンの後部座席を事務所代わりにしてロサンジェルス内を駆け巡り、慌ただしく依頼を引き受けていく弁護士の物語だ。こうした人物像が弁護士を揶揄するときの紋切り型で、エイレングラフは高級車ではなく昔ながらの事務所に居を構えてはいるが、金にうるさいという最大公約数の職業人像をやはり背負っている。このへんが職業作家ブロックの老練なところで、隙がない。
話題を転じて、作家自身について書いておきたい。ブロックのデビュー作は、本国版〈マンハント〉一九五八年二月号に掲載されたYou Can’t Loseである。日本版同誌一九六二年四月号に「ガッポリもうけましょう」の邦題で掲載された。一九三八年六月二十四日生れだから、当時ブロックは十九歳、オハイオ州のアンティオック・カレッジを卒業したのは翌年だから、まだ大学生だったということになる。
ブロックはあまり若い頃の話をしない作家で、よくわからない部分も多い。一九五八年には〈マンハント〉二月号に「習慣をやぶった男」(邦訳は日本版同誌一九六二年九月号)。〈オフ・ビート・ディテクティヴ・ストーリーズ〉九月号にMurder is My Business(言うまでもないが、殺し屋ケラーものの「ケラーの最後の逃げ場」とは別の作品)、〈ギルティー・ディテクティヴ・ストーリー・マガジン〉十一月号にThe Bad Nightを発表している。その後数年の間に〈トラップド・ディテクティヴ・ストーリー・マガジン〉、〈トゥー・フィステッド・ディテクティヴ・ストーリーズ〉、〈エド・マクベインズ・ミステリー・ブック〉などのマイナー専門誌に短篇が載っており、あちこちに投稿しまくっていたことがわかる。
駆け出しの頃、ブロックはさまざまな筆名を使って書いていた。ドナルド・E・ウェストレイクと一緒にソフトコア・ポルノも量産していたことは有名で、川出正樹が『ミステリ・ライブラリ・インヴェスティゲーション』(二〇二三年。東京創元社)で、シェルドン・ロード名義の作品が大胆な翻案で日本でも刊行されていたことを突き止めている。邦訳されて埋もれたままの作品にも、もしかすると未発見のブロックがまだあるかもしれない。
ゴーストライターの経験も多いと思われる。小森収が『短編ミステリの二百年2』(二〇二〇年。創元推理文庫)所載の評論で書いているように、クレイグ・ライスの遺作短篇と思われていた「セールスマン殺し」(荒地出版社『年刊推理小説ベスト18』所収。同書は一九六三年刊)は、ブロックの代筆であったことが二〇一八年になって明かされた。遺作の代筆といえば、コーネル・ウールリッチの絶筆となった遺作『夜の闇の中へ』(一九八七年。ハヤカワ・ミステリ文庫)も、ブロックが補筆して完成させている。この本が一九八八年に邦訳された際、ウールリッチといえば古典の域に入る人だと思っていたのでブロックという「現代」作家が書き継いだことを不思議に感じたのだが、なんのことはない。ライスが亡くなったのは、一九五七年。ブロックのデビューはその直後だから、新米のころから上の世代とつながりがあり、万が一の代作を任されるような立場にいたということだ。それを考えれば、後にウールリッチの絶筆を任されたのも自然な経緯のように思われる。フレデリック・ダネイがブロックに悪徳弁護士ランドルフ・メイスン・シリーズの後継を書かせようとしていた、という経緯については本書のあとがきで詳しいので、そちらをどうぞ。
エイレングラフものの第一作「エイレングラフの弁護」は本国版〈エラリー・クイーンズ・ミステリマガジン〉一九七八年二月号に掲載された。同誌への登場は初めてではなく、一九七七年四月号に「泥棒の不運な夜(別題:紳士協定)」(日本独自編纂短篇集『おかしなことを聞くね』所収。ハヤカワ・ミステリ文庫。一九九二年刊)が掲載されている。名無しの泥棒が災難に遭う話だが、同年には泥棒バーニー・ローデンバーものの長篇第一作『泥棒は選べない』(ハヤカワ・ミステリ文庫)も刊行されており主人公は同一人物にも見える。また、同年六月号には「危険な稼業」(日本独自編纂短篇集『バランスが肝心』所収。ハヤカワ・ミステリ文庫。一九九三年刊)が載っている。この二篇を見てダネイが、出来る若手にランドルフ・メイスンを書かせることを思いついた、とすると話は綺麗なのだが、ブロックの記憶によれば一九七六年にはもう依頼があって「エイレングラフの弁護」を書いていたらしい。一年余ほど寝かされていたということになるのだろうか。いきさつはよくわからない。
このころのブロックは、一九七六年に『過去からの弔鐘』(二見文庫)を発表して私立探偵マット・スカダーものを書き始めていたが、シリーズはまだベストセラーとは言いがたい状態だった。ブロックが人気作家になるのは同シリーズの第五長篇『八百万の死にざま』(一九八二年。ハヤカワ・ミステリ文庫)がPWA最優秀長篇賞を獲り、ハル・アシュビー監督による映画化が実現した後のことである。当時のブロックは二十年余に及ぶ雌伏期の最終段階に入っていた。『怪盗タナーは眠らない』(一九六六年。創元推理文庫)に始まるタナー・シリーズや、ノン・シリーズ作品の『ダーティ・ラリー氏の華麗なる陰謀(別題:危険な文通)』(一九七一年。三笠書房)などが、一九六〇・七〇年代の長篇である。ダネイがブロックに目をつけたのも、いまだ代表作といえる長篇がなかったからではないだろうか。
短篇作家としてのブロックは、どちらかといえば〈アルフレッド・ヒッチコック・マガジン〉派だった。同誌一九六三年一月号の「狂気の行方」(『バランスが肝心』所収)を皮切りに、数々の作品が掲載されている。とても短いが切れ味抜群の「おかしなことを聞くね(別題:中古のジーンズ)」(一九七六年八月号)、ブロックの短篇では最も名高い「アッカーマン狩り」(一九七七年七月号。両篇とも前掲『おかしなことを聞くね』所収)など、代表作の多くが同誌に掲載されている。
一九八〇年代に入るとブロックはヒット作が出て長篇中心の作家になるので、一九七〇年代後半が、短篇作家としては最も旬だったのかもしれない。まさにそうした時期にエイレングラフ弁護士シリーズは開幕したのである。
小森収は前出『短編ミステリの二百年1~6』に分載された評論において、小説誌から作家がデビューするのが普通だった時代が終わってペイパーバックの長篇が主流になったため、短篇ミステリーが衰退していった経緯を明らかにしている。その中で、残り火的に実力を発揮した作家の一人としてブロックの名を挙げているのである。ブロックが作家としての下積み時代を送ったのは、短篇ミステリーの良作が狂い咲きのように書かれた一九五〇年代末から一九六〇年代にかけてであり「現役の作家で、その水準が身に染みている唯一の存在」であるがゆえに他の作家とは一線を画しているのだ、と小森は指摘する。その通りであろうと思う。
ブロックはアメリカ探偵作家クラブ(MWA)が毎年発表するエドガー賞の最優秀短篇賞を四回受賞している。一九八四年発表の「夜明けの光の中に」(『石を放つとき』他所収。二〇一一年・二〇一八年の二短篇集の合本版。二見書房)、一九九三年の「ケラーの治療法」、一九九七年の「ケラーの責任」(ともに『殺し屋』所収。一九九八年。二見文庫)、二〇一七年の「オートマットの秋」(『短編画廊』所収。二〇一九年。ハーパーBOOKS)が受賞作である。このうち「夜明けの光の中に」がマット・スカダーもの、最後の一篇を除く二篇が殺し屋ケラーものである。単発作品での受賞の方が少ないというのは時代の趨勢を感じる。短篇が売り物になりづらく、雑誌掲載でもシリーズものが多く書かれるようになった状況を表しているのであろう。
ただしブロックの連作には単発作品とはまた違った楽しみがある。キャラクターがだんだんと変化していくという要素があるのだ。たとえば殺し屋ケラーものは、第一作品集の『殺し屋』を読んだときには、感情を排した本当の意味の非情さをこの作品が実現した、と思ったものである。ケラーが、まったく内面の描かれない空白のような人物として描かれていたからだ。だがケラーは後に切手蒐集という趣味を発見し、キャラクターとして深化を遂げていく。スカダーも同様で、年代別に短篇が配置されている『石を放つとき』を読むと、その心境に迫れるような心地がする。おそらくブロック自身がケラーやスカダー、そしてバーニーを執筆しながら発見しているのであり、その驚きを読者は作者と共有しているのである。それがローレンス・ブロックを読む楽しみでもある。
ではエイレングラフはどうなのか。先に本連作においてはあえて物語の定型が固定されていると書いた。そういう形で書かれる物語ゆえの醸成、同じ器を手がけ続ける陶匠にしか出せない深みというものが本作には感じられるのである。
これ以上の多弁は無用だろう。どうぞ物語をお楽しみいただきたい。弁護士が咲かせる悪徳の花は、鼻孔を糜爛させるほどに濃厚な香りを放つ。耽溺しすぎぬよう、ご用心の程を。