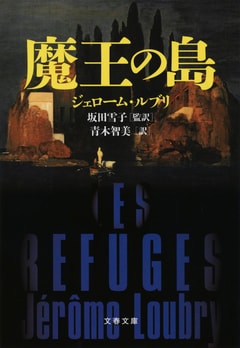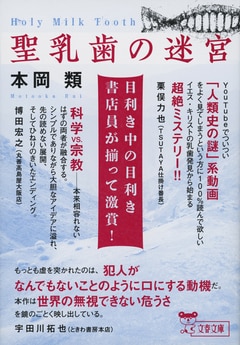極めて大雑把な分け方であることを承知で記せば、勧善懲悪がはっきりした物語を好むアメリカ人に比べ、フランス人は白と黒では割り切れない物語を好むという傾向があるとよく言われている。人間心理のグレーゾーンを描き続けたパトリシア・ハイスミスの小説が、アメリカ本国よりもフランスで高く評価されたことなどがそれを象徴している。ミステリ小説に限っても、フランスの作家はカトリーヌ・アルレーやボアロー&ナルスジャックの昔から、すっきりと割り切れない後味の作品を好んで執筆してきた。
そんなフランス・ミステリの伝統を引き継いでいる作家のひとりが、本書『魔女の檻』(原題Les Soeurs de Montmorts、二〇二一年)の著者、ジェローム・ルブリである。著者は一九七六年生まれで、イギリス、スイス、フランスの外食業界を経て、二〇一七年にLes chiens de Detroit でデビュー、第三長篇『魔王の島』(二〇一九年)で二〇一九年のコニャック・ミステリ大賞および二〇二一年のリーヴル・ド・ポッシュ読者大賞を受賞した。この作品は日本でも、『このミステリーがすごい! 2023年版』の海外部門第十位にランクインするなど注目を集めた。
『魔王の島』はこのような物語だった――一九八六年、新聞記者のサンドリーヌは、祖母シュザンヌの遺品の整理のため、彼女が住んでいたノルマンディー沖の孤島を訪れる。その島では、かつて十人の子供たちが溺死するという悲劇的な事故が起きていた。やがて、サンドリーヌは島の数少ない住人たちが「魔王」と呼ばれる何者かを恐れていることに気づく。一方、並行して語られる一九四九年のパートでは、島の施設で働くことになった若き日のシュザンヌが、子供たちを怯えさせる「魔王」の謎に直面することになる。
最初のうち、「魔王」は果たして人智を越えた超自然的存在なのか、そうでないのか――というのがメインの謎かと思われるのだが、中盤でとんでもない事実が明かされ、それまで読者に見えていた景色は根こそぎ引っくり返されてしまう。しかも、この逆転劇は一度ではないのだ。ミステリとしては反則ではないかという印象を受ける読者もいる筈だが、それなりに伏線は張られており、少なくともサプライズと知的な計算とによって著者の掌の上でいいように転がされる物語であることは間違いない。
では、著者の第六長篇、日本に紹介された作品としては二作目にあたる本書は、どのような内容なのだろうか。
プロローグにあたる部分では、新人記者のカミーユが、極秘の情報を提供するという誘いに乗って、正体不明の女性エリーズとともに車でモンモール村へと向かう。エリーズは、二年前にモンモール村で大勢の村民が謎めいた死を遂げた事件の真相を知っているというのだが……。
このプロローグに続き、いよいよ本筋が始まる。二〇二一年十一月、主人公のジュリアンは、新任の警察署長としてモンモール村に赴任する。警察署は彼のほか、リュシー、サラ、フランクという三人の署員しかいない小さな署だが、どういうわけか最新のパソコンや大型モニターが設置されていた。村長のティオンヴィルからのプレゼントなのだという。モンモール村では二年前、羊飼いのジャン=ルイが羊たちの喉を掻き切って殺害し、その直後に心停止を起こして死亡するという事件があったが、他には些細なトラブルしか起きていないらしい。ジュリアンは二年前の件について事情を聞くため、ジャン=ルイの相棒ヴァンサンの家をサラとともに訪れたが、ヴァンサンは喉を切って死んでいた。やがて、ジュリアンはティオンヴィルから意外な依頼をされる。
物語が進行するにつれて、この小さな村で実はさまざまな事件が起きていたことが明らかになってゆく。村には小規模な刑務所があったが、過去に起こった事故で受刑者は全員死亡したらしい。また、ティオンヴィルがモンモール村に来たのは、重い病を患う次女の治療のためだったが、彼女は岩山の頂上から転落死している。これらの出来事には互いに関連があるのだろうか?
更に遡れば、モンモール村には恐ろしい歴史があった――一七世紀、ルイーズという女性と四人の娘が魔女と見なされ、岩山の頂上から突き落とされて惨死したのだが、その後、村の男たちは女たちを見境なく魔女だと疑うようになり、多くの女がルイーズ母娘と同じように殺害されたのだ。こうして岩山は「死者の山(モンターニュ・デ・モール)」と呼ばれるようになったが、それが時とともに「モンモール」に変化し、今の村の名前になったのだ、と。
このような恐ろしい地で、ジュリアンはティオンヴィルからの依頼を果たすべく、過去の出来事を探りはじめる。しかし、村には不穏な空気が立ち込め、小さなトラブルが大事件へと発展する。相次ぐ惨事には、それを起こした人間が謎の声を聞いていたという共通点があった。やがて声は、ジュリアンたち警察署の面々にも迫ってくる……。
何が起きているのか、事態の全体像がなかなか見えてこない不気味な展開は『魔王の島』とも共通するが、本書のほうがホラー・テイストが濃厚である。何しろ、互いに何の関係もないように見える人々が、正体不明の声が聞こえただけで死へと導かれてしまうのだから。果たしてそれは魔女の呪いなのか。だが本書の不気味さはそれだけにとどまらない。ところどころに、「事実」と称する医学的な説明の断片が挟み込まれているのだが、その意図が謎なのだ。また、プロローグでカミーユに情報を提供しようとするエリーズなる女性が、真相を知っているというからには事件の核心に近いところにいた筈なのに、本筋にあたるパートに一向に姿を見せないのも不可解さを掻き立てる。
読者を絶句させるような絶望的な結末のあと、いよいよ種明かしが行われる。そこで、それまで語られてきた出来事に一応説明はつく。しかし、ここで展開される善悪の反転劇を、読者はどのように受け止めればいいのだろうか。正直、自分の気持ちを持て余す読者が大部分なのではという気がするのだ――恐らく『魔王の島』以上に。
ところで一時期、一部のフランス・ミステリに対して、「フランス新本格」という言い回しが使われたことがあった。トリッキーな仕掛けが用意されたミステリを、日本の新本格との共通性によって表した言葉である。奇しくも日本の新本格誕生と同じ一九八七年に『第四の扉』でデビューしたポール・アルテをはじめとして、『マーチ博士の四人の息子』(一九九二年)のブリジット・オベール、『クリムゾン・リバー』(一九九八年)のジャン=クリストフ・グランジェ、『ネプチューンの影』(二〇〇四年)のフレッド・ヴァルガス、『黒い睡蓮』(二〇一一年)のミシェル・ビュッシらがそこに含まれるだろう。『その女アレックス』(二〇一一年)ピエール・ルメートルは本格というよりサスペンス寄りの作風だが、『悲しみのイレーヌ』(二〇〇六年)あたりは「フランス新本格」に含めて良さそうだ。
では、ジェローム・ルブリは、こうした系列の作家に連なる存在なのだろうか。そうだと言えなくもないし、異なる系列だとも言えそうである。
悪夢のような不可解な事件を提示し、最後には伏線を回収し、トリッキーなやり方で辻褄を合わせる――そういった点は、確かに前記の作家たちと共通している。しかし、著者の作風が本格ミステリ的かというと、首を傾かしげる読者も多いだろう。
サスペンス重視で先が読めない展開を得意とする点はピエール・ルメートルに似ているとも言える。だが、著者の作風の大きな特色として、謎に解決をつける際、精神分析や脳科学といった方面からのアプローチを好む。そういう意味では、著者の作風はスタンリイ・エリンのある長篇や皆川博子のある長篇、または島田荘司のある種の作品を想起させる。
ただ、本書を読んで―というか、『魔王の島』と合わせた著者の二作品を読んで、私はどうもそれ以外の誰かの作風に似ている気がして仕方がなかったのだが、本稿を書き進めているうちに誰なのかに思い当たった。同じフランスのホラー映画監督、パスカル・ロジェである。彼の日本初紹介作品『マーターズ』(二〇〇七年)は、全く先が読めない展開や、超弩級の残虐描写もさることながら、善悪の彼方へと突き抜けた異常な着地が観客を茫然とさせた問題作だった。続く作品『トールマン』(二〇一二年)は、前作のような残虐趣味は影を潜めたものの、代わりにどんでん返し重視の本格ミステリ映画として高い完成度を示している。そして、十六年前の惨劇の記憶に苦しむ姉妹が再びおぞましい出来事に見舞われる『ゴーストランドの惨劇』(二〇一八年)は、『マーターズ』のヴァイオレンスと『トールマン』のミステリ的意外性を兼備している。
不条理かつ不快な展開、それでいて知的な計算によって構築されている物語の全体像――そんなパスカル・ロジェの持ち味は、そのままジェローム・ルブリの作風にも通じている。恐らく、著者の小説は、右記の「フランス新本格」系列の作品よりも、ロジェを代表とする現代フランスのホラー映画に近いのではないだろうか。ミステリとホラーといったジャンル上の区分、あるいは小説と映画という表現媒体の相違を超えて、それは今のフランスの創作物の一部に共通して伏在する傾向なのではないか――。そんな仮説を立てておいて、この解説を締めくくることにしたい。