直木賞作家・朝井リョウさんによるエッセイシリーズ“ゆとり三部作”。
『時をかけるゆとり』『風と共にゆとりぬ』『そして誰もゆとらなくなった』から構成される本シリーズは「頭を空っぽにして読めるエッセイ」として話題を呼び、累計30万部を突破しています。
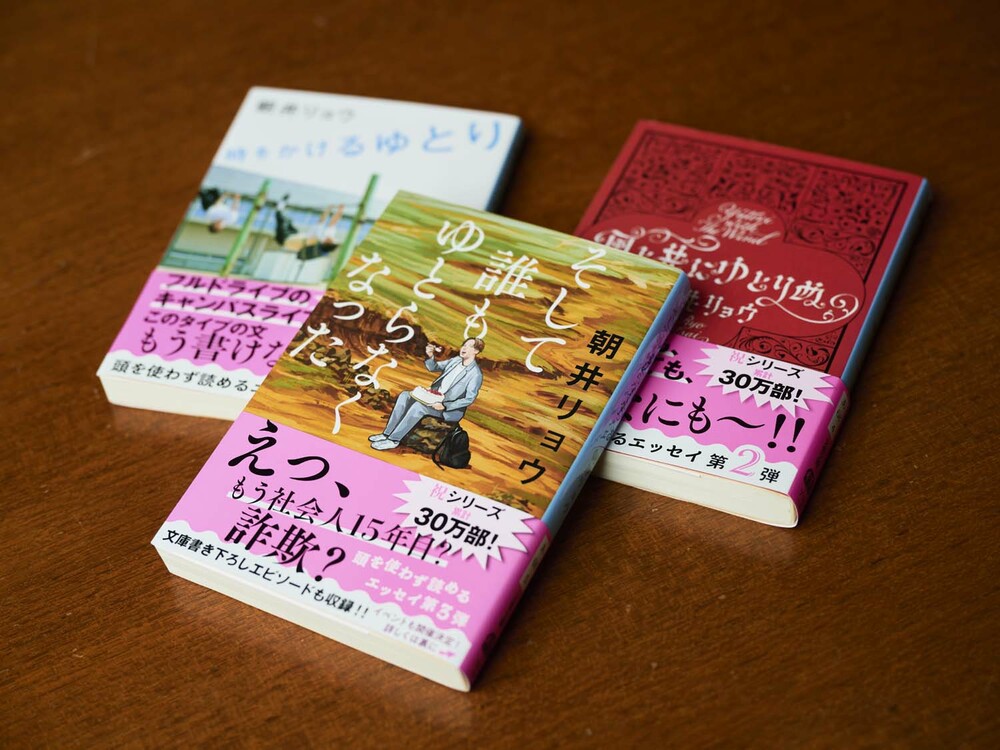
『そして誰もゆとらなくなった』文庫版の発売を記念して、朝井さんが「読み始めに最適な一本」を各巻からそれぞれセレクトして公開します。
第3弾『そして誰もゆとらなくなった』からは、「空回り戦記~サイン会編~」が選ばれました。以下、朝井さんのコメントです。
「私の人生の幹でもある“空回り”は自己愛ゆえのものだと非常によく伝わる文章だと思います。」
こちらの記事は前編です。
◆◆◆
サイン会で読者に「おもてなし」をする作家たち
サイン会、というものを主催する立場になって十数年が経つ。とはいえ未だに、「サイン会かァ……え、私の!?」と新鮮な驚きに包まれる自分がいる。だって、私が新品の本に名前を書くってそれは……ただの記名では?
特に感染症が流行する前は、読者の方々に長時間並んでいただくということも多かった。私のサイン会の場合、参加者が100名に対し約二時間というペースだったため、後半ともなるとかなりの時間待っていただくことになるわけだ。そんなの、その先にビッグサンダーマウンテンとかがないと割に合わない。感染症の流行後はそもそもサイン会を開催することが難しかったり、行列を避けるため集合時間ごとに整理券の番号を分けたりするようになったので“待ち時間”は減少傾向にあるが、それでも、わざわざ来ていただいちゃって記名ってねえ……おにぎりとかお菓子とか持って帰る? みたいな気持ちにはなるものだ。
きっと他の作家の方々も似たような思いがあるのだろう、何度目かのサイン会のころには、参加者の方々に対して何かしらのおもてなしをする作家もいるという話を聞くようになった。このエッセイでも常連の柚木麻子さんは、(もちろん感染症が流行する前の話だが)手作りのケーキポップを全員に配っていた。なぜそれを知っているかというと、私も普通にイチ読者として並び、手作りケーキポップをゲットしたからである。とてもおいしかったしめちゃくちゃかわいかった。前作の「肛門記」にカメオ出演していただいた羽田圭介さんがサイン会で大量のクッキーを振る舞ったというのも有名な話だ。
よく聞くのは、並んでいる最中に読める限定の配布物である。そのサイン会に参加した人だけが読める掌編等を冊子にして配る作家が多いらしい。確かに、サイン会にまで来てくれるような読者にとって最も嬉しいものは“新作”だろう。なるほどなるほど。
「それは名案だ! 恥も外聞もなくパクろう!」と思った私は、早速幾つかのパターンの配布物を作成し、バラまいてみた。並んでいる最中に聴くのにぴったりの一言付きプレイリストだったり(つんく♂作のファンク縛り)、最近身の回りで起きたミニエピソード集を学級新聞のように手書きでまとめたり。数年はそれで満足していたのだが、私の中にふつふつと、こんな感情が湧き起こり始めた。
何かもうちょっと、準備をしたい。熱烈に、準備をしたい――。
だって、配布物は既に多くの作家が実践していることなのだ。何か別のことをして、「朝井リョウさんのサイン会はまた一味違うなぁ!」と思ってもらいたいではないか――と、相変わらずここが私の空回りの原点である。参加者のためではなく自分の評判のために重ねられる試行錯誤。清々しいほどの自分本位。
サイン会が「いつも心苦しい」理由とは
ちょうど、次のサイン会が一ヶ月ほど後に迫っていたころだった。私は、独自にできる準備を見つけ出すため、まずはサイン会をしているときの読者の様子について思い出してみることにした。
やはりサイン以外で喜んでもらえるのは、名前と顔を覚えていること、だろうか。前回も来てくださいましたよね、という声かけには、喜んでいただける確率が高い(ただし、それが正解だった場合に限る。「いえ、初めましてです」と返していただいたときの気まずさは筆舌に尽くしがたいので、初めていらっしゃる方は是非「初めまして」と言っていただけると何かミスがあっても筆舌に尽くせる範囲で収まると思いますすみません)。
中にはプレゼントや手紙を持ってきてくださる方もおり、そのたび本当に「すまないねえ……」という気持ちになる。そして自宅で内容を確認しては、「本当に、すまないねえ……」という気持ちになる。いつもありがとうございます。
手紙というのは、やはり嬉しいものだ。ちなみに、小説家に届く手紙というと本の感想が書かれていると想像するかもしれないが、実態はかなり異なる。本の感想というよりも、本の内容に触発された人が、自分の人生についてあけっぴろげに語ってくれているものがほとんどだ。極端な話、感想にあたる部分は一行や二行、ということも多い。「『○○』を読みました。私もかつて似たような経験があり~」となるわけである。そこからその人の過去が紐解かれ、現在が語られ、未来への展望、または絶望が綴られる。私はそういう手紙を読むことが好きだ。本が思わぬ形の鍵となって、その人の内部がどんどん開かれていく感じにゾクゾクする。
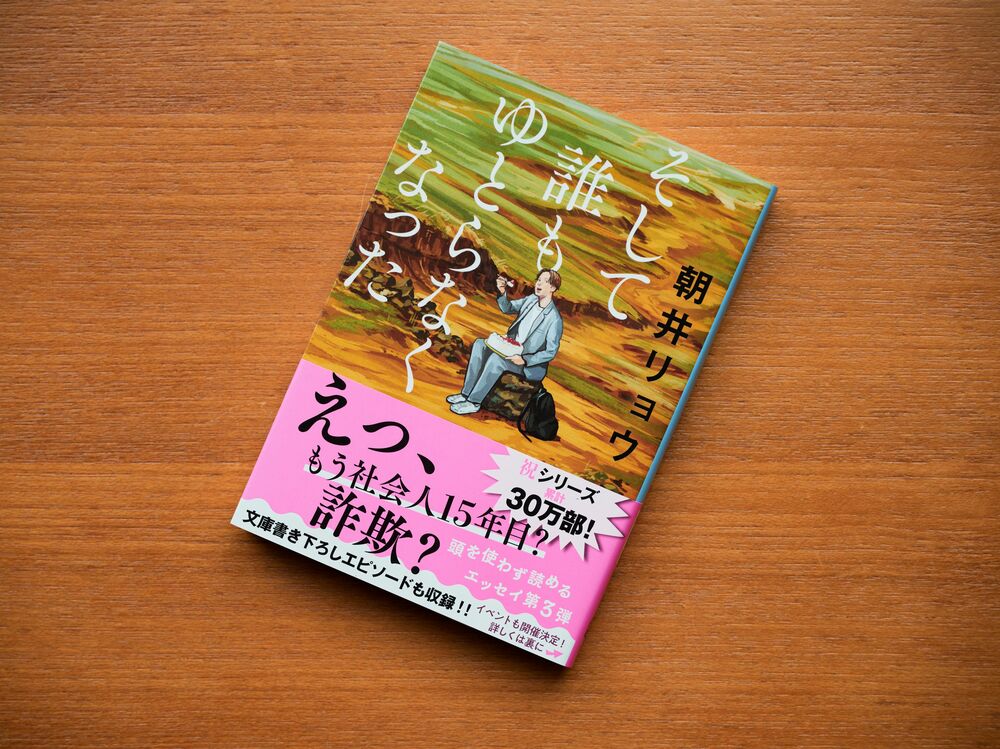
そのような手紙には、本当にいろんなことが書かれている。今日このサイン会のあとに好きな人に告白しにいきます、とか、大切な試験が迫っているなか久々の外出がこのサイン会です、とか、家族や仕事や友人関係の悩みや、ここで例として差し出せないような内容まで千差万別だ。私は読み終えるといつも、この人と手紙のその後について話したいな、という気持ちになる。手紙は時間を閉じ込める。いつ読み返しても、その人がその紙の上にペンを走らせていた当時の時間が私のもとに流れ込んでくる気がする。だけどその人は手紙を書き終えたあとの時間を生きているわけで、ここに書いてくれた告白の行方はどうなったのかなとか、大切な試験の結果は大丈夫だったのかなとか、あの悩みは解決されたのかなとか、生き続けているかなとか、そういうことが気になってしまう。そしてそれが確認できる場は、次のサイン会くらいしかない。
だから私はサイン会中、いつもどこか心苦しい。もし、前回手紙をくれた方が今回のサイン会にも来てくれていたとして、そのことに私が全く気づかずにスルーしていたら。手紙の中でものすごく色んな話をしてくれた人に対して、初めまして、という態度を取っていたとしたら――そんな、答え合わせのしようのない後ろ暗い可能性が、常に耳元のあたりに漂っているのだ。
このあたりまで考えて私は、はた、と思い立った。
私がすべきサイン会への準備は、これかもしれない。というよりも、これに関して熱烈に準備をしておけば、サイン会を開催するたびにうっすら湧き上がる後ろめたい気持ちから少しは解放されるのかもしれない。
というわけで私は、作業に取り掛かることにした。
これまでいただいた手紙をデータベース化するという作業に。
まずエクセルを立ち上げ、簡単な表を作成する。表のX軸は左から、名前、都道府県、手紙の内容の要約。ここに、保管してある手紙について一つずつ入力していくのだ。2014年あたりからは、開催したサイン会ごとにいただいた手紙をまとめて保管してあったので、非常に作業がしやすかった。これで、サイン会のときにまず差し出される為書き用のメモ(サインと共に書いてほしい名前のメモ)さえあれば、その名前からいただいた手紙の内容を検索できるというわけだ。こういう手紙をくれましたよね、この件はあれからどうなったんですか――そんな、夢の会話が現実になるのである。
一ヶ月後に迫ったサイン会は大阪での開催だったので、再会できる可能性の高い関西圏の方からの手紙はとりわけ強く記憶に刷り込むようにして再読した。読み返してみると、改めて、直筆の文字から書き手の思いがびしびしと伝わってきた。カラカラの喉で思い切り水を飲み干しているような、そんな感じだった。そこに書かれている夢や悩みや希望や絶望のひとつひとつが、私の喉元をこじ開けるようにして流れ込んでくる。
最終的に私は、500通近い手紙のデータベース化に成功した。小さな文字でびっしりと埋め尽くされた表は圧巻で、私はパソコン画面をわざと少し遠くからうっとりと眺めたりした。
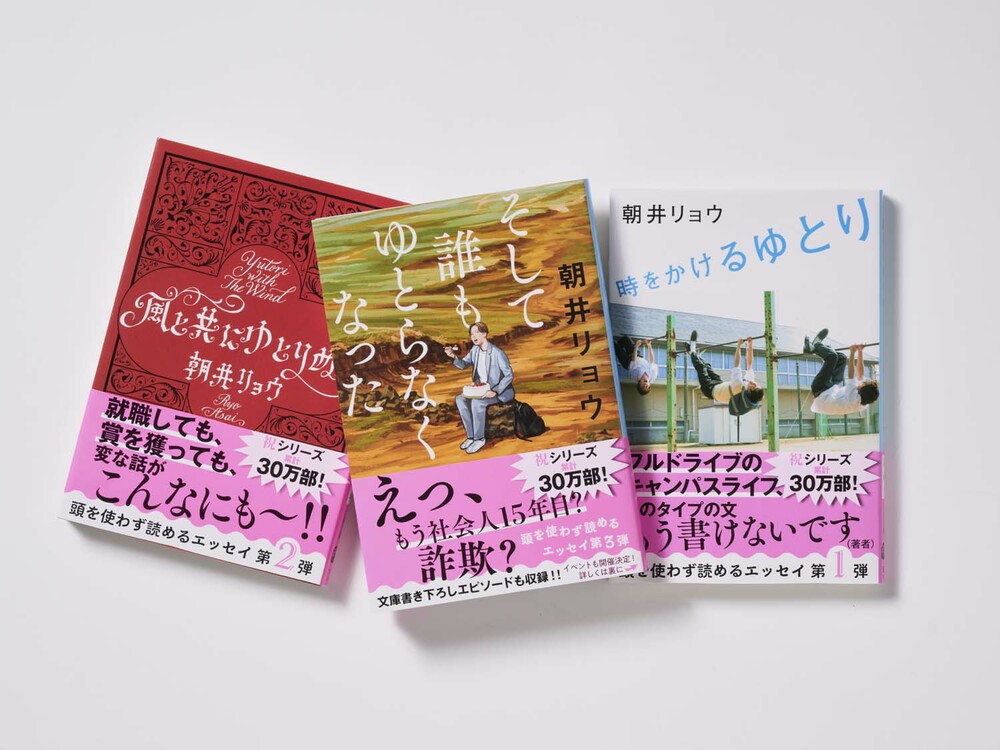
出版社の社員を驚愕させた打ち合わせ
後日、出版社の方々とサイン会に関する打ち合わせが行われた。写真撮影を可にするかどうか、書き添える言葉のリクエストを受けるかどうか、オリジナルのハンコなどを押す作業があるのか、他に何か必要なものはないか――その店舗でサイン会の経験があってもなくても、このような打ち合わせは結構重要だ。100人以上の人間が参加するイベントをスムーズにやりおおせるためには、想像以上に細かいルールが必要になってくる。
「――というわけで、営業部からも数人、お手伝いに行く予定です」
ありがとうございます、と、私は頭を下げる。サイン会というのは存外、人員が必要なのだ。私のそばにいる人だけでも、為書きを参加者から受け取り私に渡してくれる人、本の表紙を開いた状態で押さえておいてくれる人、サイン後に間紙を挟む人、ハンコを押す作家ならば捺印をする人等、それなりに場がゴチャゴチャする。
「えー、朝井さんから他に何か気になる点があればおっしゃってください」
だが今回は、そんなゴチャゴチャする場所にもうひとり、人員が必要だった。
「あのー」
私は口を開く。
「私の隣にもうひとりいてくださると、とても助かるんです」
「もうひとりですか?」と、社員さん。
「はい。ちなみに、その人は立っているんじゃなくて、私の隣に座っていてほしいんです」
はあ、と、社員さんがギリギリ頷く。
「誰でも大丈夫ですか? 何かお手伝いすることがあるんでしょうか」
「あ、えーっと」私は少し思案し、続ける。「じゃあ、できるだけタイピングの速い人でお願いします」
出版社の方々の間に、ん? という空気が流れる。当然である。雇用条件が謎すぎる。私は一息で説明をした。
「その日読者からの手紙をまとめたデータを持ち込むので、為書きが渡されたらすぐにその名前で検索をかけてほしいんです。で、該当する手紙のデータがあったら、私にその画面を見せてほしいんです。その手紙の続きについてお話をしたいので」
私にとってはこれ以上ない説明だったが、その場にはなんともいえない空気が流れていた。ただ私は非常に落ち着いていた。サイン会当日が待ち遠しくて仕方がなかった。
(後編に続く)






















