貫井徳郎の六冊目の短篇集『紙の梟 ハーシュソサエティ』は、二〇二二年七月に文藝春秋からハードカバーで上梓された。本書はその文庫版である。
初見の方のために紹介すると、貫井徳郎は一九六八年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒。第四回鮎川哲也賞の最終候補作『慟哭』で九三年にデビュー。同作は九九年に文庫化され、六十万部を超えるベストセラーとなった。二〇一〇年に『乱反射』で第六十三回日本推理作家協会賞(長編及び連作短編集部門)、『後悔と真実の色』で第二十三回山本周五郎賞を受賞。『愚行録』『乱反射』『新月譚』『私に似た人』で直木賞に四度ノミネートされている。犯罪と刑罰、宗教の功罪、格差社会などのテーマを扱い、サプライズを演出することで支持を得た著者は、社会派サスペンスの名手とされることが多い。しかし大半のミステリ作家がそうであるように、その作風は多岐にわたる。ここでは本格ミステリ作家としての側面を見ていこう。
著者は社会派かつ本格派
あえて乱暴にいえば、著者をコアな本格ミステリ作家と捉える人は少数派かもしれない。社会派のテーマを軸に据え、重い筆致で人々の営みを綴る作品群は、パズル的な謎解きの遊戯とは毛色が異なる。デビューの時期や経緯に反して新本格作家と呼ばれなかったのは、その体裁によるところが大きいはずだ。しかしそれは表層に過ぎない。著者のデビューを後押しした北村薫は、十七年後に「『乱反射』は小説の衣の下に、《本格》の鎧を見事に隠した作なのだ」「推理作家の血と汗と──心意気に眼を向け、評価しえなかったら、《推理作家協会賞》の存在意義はない」と選評に記した。これが本格のスピリットを見抜いた評であることは明らかだろう。
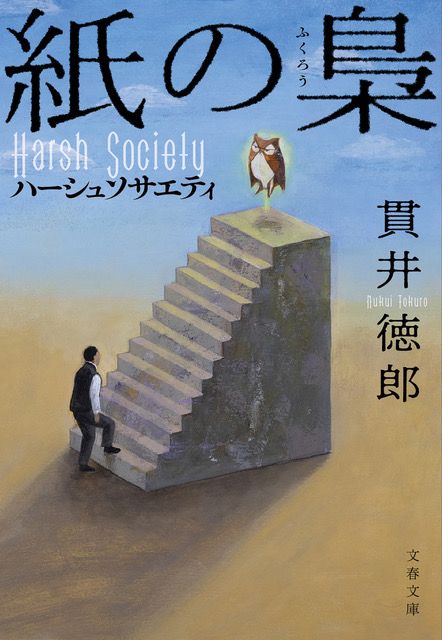
著者は『EQ』(一九九七年三月号)において、モーリス・ルブラン『813』の児童向け版『813の謎』に衝撃を受けた原体験を明かし、「そんな私にとって、ミステリーに最も大事なのは《驚き》です」「私の書く作品はどれも、閉ざされた空間内の事件ではないし、神の如き名探偵も登場しません」「それでも私は、ミステリーが大好きです」と述べている。三十年近く前のコメントではあるが、ここには作家性の核心が窺える。デビュー作をはじめとする諸作の仕掛けは、驚きを伴う本格ミステリと社会派ドラマを両立させる装置なのだ。
野心的な本格ミステリも多数発表
ちなみに著者は本格ミステリ作家クラブの発起人の一人であり、本格ミステリの意匠をまとった作品群も手掛けている。十五歳で初めて書いた小説(第四回横溝正史賞投稿作)を原形とする『鬼流殺生祭』は、明治ならぬ明詞を背景にした時代ミステリ。帝都東京の武家屋敷で青年軍人が殺され、調査を任された公家の三男坊・九条惟親が博学の変人・朱芳慶尚に協力を仰ぐ物語だ。その続篇『妖奇切断譜』は美女のバラバラ殺人が相次ぎ、遺体の一部が稲荷に捨てられる怪事件に九条と朱芳が挑む話。二〇〇四年刊の作家ガイド本『貫井徳郎症候群』では「作者自身の偏愛ナンバーワン作品」とされている。「シリーズ第三弾は『絡繰亭奇譚』というタイトルで構想しています」という文言もあるが、これは未だに執筆されていない。
一章ごとに語り手が変わり、各々が教師殺害事件を推理する『プリズム』は、アントニイ・バークリイの『毒入りチョコレート事件』を踏まえた多重解決もの。傲岸なミステリ作家・吉祥院慶彦を探偵役とする『被害者は誰?』は、パット・マガーの『被害者を捜せ!』『探偵を捜せ!』『目撃者を捜せ!』を発想元として、ユニークな趣向を凝らした軽快な連作集。古典の発展型だけではなく、VRゲームと連続殺人を絡めた『龍の墓』のような作例もある。野心的な本格ミステリも少なからず書いているのだ。
念のために断っておくと、貫井作品には他の系譜もある。心臓移植を受けた大学生が己の変化に気付く『転生』、時を渡る少女が殺人容疑者を救おうとする『さよならの代わりに』、詐欺師と少年が狂言誘拐を企てるユーモアミステリ『悪党たちは千里を走る』、帰国子女の学生生活を爽やかに描く『明日の空』などがそれだ。著作の全体像を把握するには、これらのバリエーションにも留意する必要があるだろう。
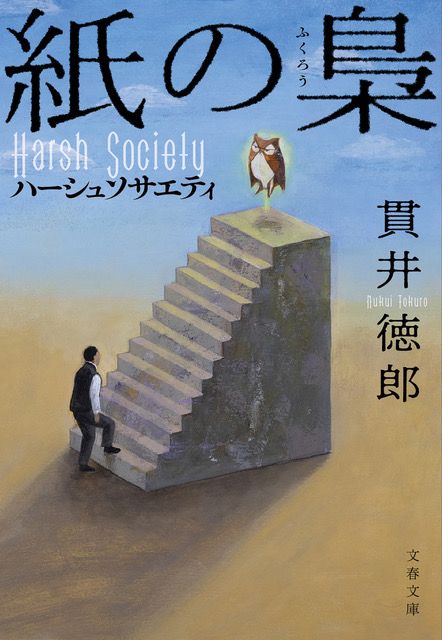
厳罰化が行き着いた社会
本格ミステリ作家・貫井徳郎を理解したところで、改めて本書の話を始めよう。極めて大雑把にいえば、日本の司法界には“一人を殺せば死刑”から“三人を殺せば死刑”に相場がシフトした歴史がある。しかし近年、大量殺人犯が心神喪失を主張し、処罰の軽減や無罪を勝ち取るケースが増えた。これに憤る人は少なくないはずだ。
裁判員制度が無罪判決を増やした結果、再犯と思しき事件が多発し、市民感情に基づく厳罰化が進められ、単純明快な「人ひとり殺したら死刑」というルールが確立された社会。それが本書の舞台である。テーマに合わせて世相を変える着想は、小規模なテロが頻発する社会を描く『私に似た人』を彷彿させる。どちらも冷徹な視座から生まれた予見的なビジョンといえるだろう。
本書所収の五篇は初出時に「ハーシュソサエティ」の副題が付されていた。この連作は『小説推理』(二〇一一年十二月号)に載った「見ざる、書かざる、言わざる」で幕を開ける。ファッションデザイナーが両眼を潰され、両手のすべての指と舌を切られるという残忍な事件が発生した。口封じを試みた犯人が死刑になりたくないから命を奪わなかったと考えた警察は、被疑者たちの話を聞き、やがて真の動機に辿り着く。法制度への疑念で読者を誘導し、意外な解決を取り出すトリッキーな一篇だ。
第二話「籠の中の鳥たち」は文藝春秋のムック本『オールスイリ2012』(一一年十二月刊)に発表された。六人の大学生がオフシーズンの別荘地を訪れ、一人が女性メンバーを襲った浮浪者を撲殺してしまう。彼らは仲間を死刑から守るために死体を埋めようとするが、その矢先に殺人事件が発生する。クローズドサークルの不可能犯罪、消去法による犯人の指摘という定型を使い、この社会ゆえの狂気を描いた意欲作である。
著者は自身のサイトで「人ひとり殺したら死刑、という架空設定で書きました。当初はミステリー味の濃い、ゲーム小説を書こうと意図していました」と本書を紹介している。先述したように著者は本格ミステリの紡ぎ手であり、同時期に執筆された最初の二話はゲーム小説として構想されている。社会派サスペンスのイメージで読み始めた人は、予期せぬ内容に不意打ちを食らったかもしれない。
第三話「レミングの群れ」は別冊文藝春秋電子増刊『つんどく! vol.1』(一三年四月配信)に書かれた一篇。男子中学生がいじめを苦に自殺し、三人の加害者とその家族が姿を消して非難を浴びる中、首謀者とされる生徒が通り魔に刺殺された。自殺志願者の犯人が“社会のダニを殺して国家に殺してもらう”と目的を語り、ネットが肯定派と否定派に割れ、死刑が抑止力を失った社会が暴走する。大衆の挙動を冷ややかに観察するような、思考実験に徹した異色のパニック小説だ。
第四話「猫は忘れない」は『つんどく! vol.3』(一四年五月配信)に掲載された。姉を殺した犯人への復讐を誓った男が、世の少数派である死刑廃止論者の恋人と議論を交わし、満を持して犯行に及ぶ倒叙ミステリだ。第一話と第三話の事件に言及し、他人の立場から感想を述べる場面は、連作を束ねる結節点にほかならない。死刑をめぐる特殊ルールを活かし、皮肉なプロットを練り上げた犯罪小説の佳品である。
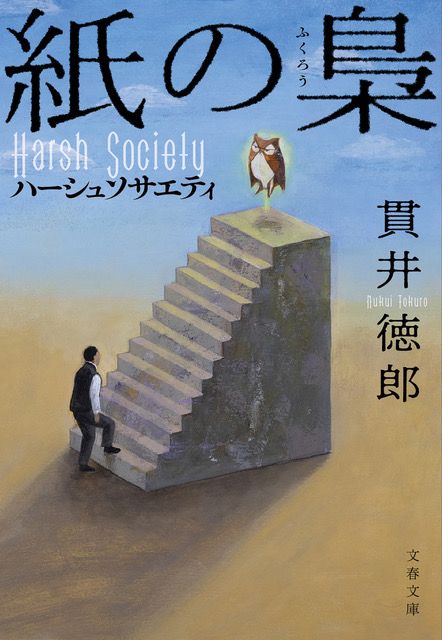
本書の表題作「紙の梟」(『別冊文藝春秋』二一年九月号、十一月号)は、前後篇の形で発表された中篇。作曲家の笠間耕介は恋人・松本紗弥からの着信を無視し、数時間後に刑事から紗弥の死を告げられる。変わり果てた紗弥を目にした笠間は、遺品に折り紙の梟があることに気付く。留守番電話には助けを求める紗弥の声が残されていた。やがて犯人を捕えたという連絡が入り、警察を訪れた笠間は衝撃的な事実を知ることになる。紗弥は住民登録をしておらず、偽造免許証を所持していた。紗弥の正体は紗弥ではなく、彼女に貢いで自殺した男の息子に報復されたというのである。
市民感情vs.死刑廃止論
これまでの四篇とは趣が異なり、本作では市民感情と死刑反対論――処罰と寛容の物語が正面から掘り下げられている。文藝春秋のサイト『本の話』のインタビューで、著者は「思考実験的な感覚でアイデアを練りました」が「僕らをとりまく社会がしだいに感情的になり、不寛容になり、架空の思考実験だったはずの物語設定に、現実のほうが追いついてきたという感覚もありました」と述べている。そして「死刑を扱う以上、正面からテーマに向き合う一作を書かないと、“答えの欠けた本”になるような気がした」と考え、死刑についての本を読み漁り、笠間の思考や行動を描くうちに「『そうか』と腑に落ちる瞬間」に辿り着いたという。「最初の四作が問いかけだとすれば、七年をへて書いた『紙の梟』はそれに対する答えになっていると思います」という言葉は、本書が二部構成を採った理由にも通じるだろう。明確な意志をもって回答を示し、重量感のある着地をもたらした連作の大黒柱である。
犯罪と刑罰、加害者と被害者といったモチーフは、著者がこれまでに幾度も扱ってきたものだ。『慟哭』と『神のふたつの貌』で宗教、『殺人症候群』と『空白の叫び』で少年犯罪の位置づけを変えたように、作品ごとに自分なりの答えを出しながらも、著者は特定の立場に拘泥することなく、新しい観点を模索してきた。これは一つの見方を押しつけず、結論を読者に委ねるスタンスに繋がる。複数の視点から主張を相対化する作品が多いことも、そんな価値観や感性に由来するはずだ。柔軟かつ真摯にテーマと切り結んだ筆歴を辿ることは、貫井作品を深く愉しむための有効な方法に違いない。
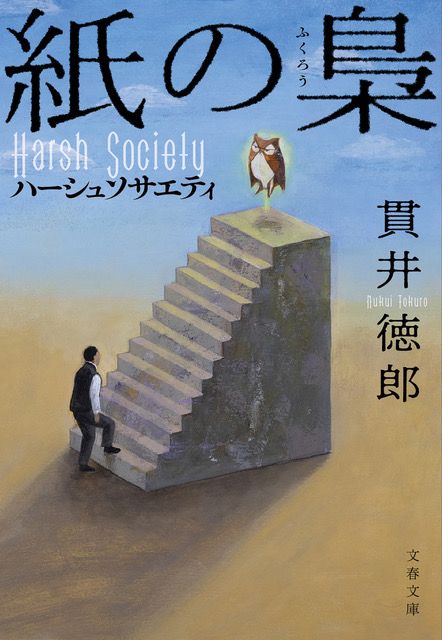
手短に整理していえば、第四話までの「I」は法の運用が異なる社会の推理ゲームと思考実験、間を置いて書かれた「II」は処罰と寛容というテーマに挑む重厚なドラマになっている。現実と地続きの社会派テーマを題材として、本格ミステリとパニック譚を提供したうえで、誠実なストーリーを通じて答えを示す。著者が複数の持ち味を積み重ね、高いレベルで結合させた成果が本書なのである。
世評の定まった作家ゆえに、初刊時に地味な印象を持たれた感は否めないが、本格ミステリと社会派の技量を併せ持つ作家・貫井徳郎の新境地がここにある。文庫化を機に広く読まれることを期待したい。
(書評家)
福井健太
早稲田大学在学中はワセダミステリクラブに所属。おもに書評や文庫解説、コミック・ゲーム関連の原稿を手がける。『本格ミステリ鑑賞術』で第13回本格ミステリ大賞評論・研究部門を受賞。


















