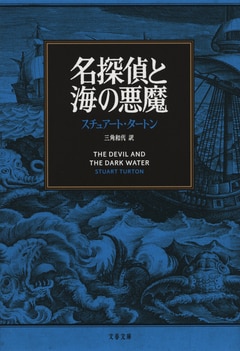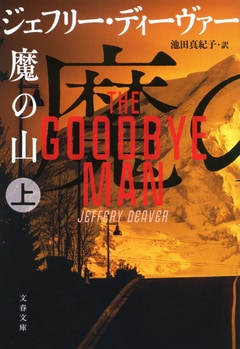フランシスよ、あなた達は何度、この男から奪えば気が済むのか――。
『勝機』の冒頭を目にした瞬間、そんな溜め息が漏れた。フランシスには、本書の著者であるフェリックス・フランシスと、その父ディック・フランシスの両名が含まれる。
『勝機』の主人公、シッド・ハレーは今回が六度目の登場である。そして登場のたび、過酷な境遇に置かれ、大切なものを危険に晒され、あるいは奪われてきた。大切なものが失われるかもしれない恐怖――誰でも身に覚えのある生々しい恐怖に膝をつくまいとする男の姿を、祈るように見守り続ける。「競馬/新・競馬シリーズ」の中でも、とりわけハレー登場作はそんな小説であると言えるだろう。
始めに、ディック・フランシスの「競馬シリーズ」の話をしておきたい。私は実のところ、八〇年代の冒険小説ブームを直接には経験していない。高校生の時、『東西ミステリーベスト100』でその名と『興奮』『利腕』の二作を知った。推理作家や愛好家等の投票によるオールタイムベストランキングで、「週刊文春」で行われたものだが、その二〇一二年版では、前者が35位、後者が46位だった(なお一九八五年版では前者が19位、後者が48位)。
同ベストにランクインした作品を読破する過程で、必然的にこの二作を読み、とりわけ『利腕』に惹かれた。何に、と言われれば、文章に、としか言いようがない。菊池光の翻訳による歯切れの良い文体と、恐怖を堪えようとするハレーの心理描写に魅せられた。それが二〇一二年だから、当時既に、ディック・フランシスは亡くなっていた(二〇一〇年に逝去)。私は徹頭徹尾、後追いの読者であり、まだ競馬場にも行ったことがない。そのギャップを埋めようと、二〇二一年にディック・フランシス作品をまとめて読んだ成果は拙著『阿津川辰海 読書日記 かくしてミステリー作家は語る〈新鋭奮闘編〉』(光文社)の第十四回「ディック・フランシス『不完全』攻略」に書いたので、ここでは繰り返さない。拙稿は、「新・競馬シリーズ」で「競馬シリーズ」に興味を持った新しい読者が、次に読むものを探すために使ってもらえればと思う。
ここで、シッド・ハレーの歩みを確認しておこう。昨年邦訳された『覚悟』の訳者、加賀山卓朗の解説と重なる部分も多いが、これまでのハレーの喪失の過程を辿っておくのは、シリーズ読者にも新規読者にも有用だ。『勝機』では重要な転換点が訪れるからだ。
初登場はディックの長編第四作『大穴』(一九六五)である。「射たれる日まではあまり気にいった仕事ではなかった。その仕事も自分の一命とともに危うく失うところであった」という冒頭の一節は、山場から語りを始めるフランシス特有の技法がよく表れた一節だが、この一節は「山場」というより「谷底」と評した方がいいかもしれない。競馬中の事故により左手を負傷したシッド・ハレーは騎手生命を断たれ、最初の妻ジェニイとは別居中で、調査員になったが仕事をしない無能の男に過ぎなかった。まさにどん底だったのだ。一発の銃弾が、彼をそのどん底から蘇らせた。『大穴』では彼を撃った男を追ううち、競馬界のある陰謀に辿り着くが、ハレーは火かき棒で左手を打たれ、負傷で済んでいた左手を永久に失うこととなった。
二回目の登場は『利腕』(一九七九)である。不正の疑いがあるシンジケートと本命馬が次々と正体不明の負け方をする厩舎という二つの謎と同時に、元妻ジェニイを巡るトラブルまでがシッドを襲う。事件の渦中で右手に猟銃を突き付けられ、手を引けと脅される。この瞬間の生々しい恐怖が、本書の白眉だろう。騎手時代の夢を見る「プロロゥグ」と題された冒頭の二ページは、競馬シリーズの中でもダントツの名調子である。
第三作は『敵手』(一九九五)。彼がここで奪われるのは、一時的には「名声」、あるいは「友」だ。放牧中の馬の脚を切断する残忍な犯人を追いかけたハレーは、その犯人がテレビの人気司会者、エリス・クイントであることを突き止めてしまうが、エリスはハレーの騎手時代の友人だった。ポニイを襲われた白血病の九歳の少女、レイチェルの挿話が効いている。骨髄移植手術を怖がる彼女が、ハレーの義手に触れようとするシーンが強く心に残る。
ディックの作品ではしばしば、ハレーを含む騎手/元騎手だけでなく、競走馬の肉体そのものも脅かされる。『利腕』では馬の「心臓」が脅かされ、『敵手』では脚や肉体が傷つけられる。これがディック作品にゾッとするようなスリルを加えていたのも事実だった。このスリルがあるからこそ、『名門』や『度胸』は今読んでも色褪せないスリラーなのだろう。
第四作『再起』(二〇〇六)のクレジットはディック・フランシスであるが、本書を執筆したのがフェリックスであることが、最近インタビューでも明かされた(『虎口』刊行に際して行われた「名作〈競馬シリーズ〉、復活! フェリックス・フランシス インタビュー 私はディック・フランシスを読んで育ったのです」。ウェブ上で読むことが出来る)。刊行から八年間は著者がフェリックスであることを公言しないこととされていたという。第五作の『覚悟』を読んだ時、シッド・ハレーの精神が見事に受け継がれていることに衝撃を受けたものだが、実はバトンパスは一作前に済んでいたのだ。
失い続ける男、ハレーは、ここで一つのものを「得て」いた。恋人マリーナである。上院議員から持ち込まれた競馬の八百長疑惑を調べる過程で、マリーナが危険に晒される。守るべきものが出来たハレーはどう行動するのか。『再起』の読みどころはそこにある。『再起』が既にフェリックスの筆によるものだったとすると、フェリックス版ハレーの最大の特徴は、マリーナという女性の登場だったと言えるだろう。
第五作『覚悟』(二〇一三)で、ハレーはマリーナとの間に六歳の娘、サシイ(サスキア)を得ている。レースの不正調査を依頼してきたスチュアート卿が変死を遂げ、家族のため調査員をやめたハレーは再度競馬界の不正に首を突っ込むことになる。元アイルランドのテロリストという「敵」を早々にチラつかせながら、「敵」の厄介さを幾重にも書くのが巧い。同作では、ハレーの左手について、新たな展開が示される。手の移植手術である。
ハレーの失われた左手は、これまで、ハレーの喪失の象徴であった。接がれた手のヒーローが二人の親子の間で継がれ、そこに移植というフェイズが来るのは、ただの偶然なのだろうか。どの作品とは明言しないが、事件を経て、ハレーが自分の左手(義手ではない部分)を友人と認めるシーンがある。ハレーにとって自分の義手は、誰よりも身近な“他者”だった。
ハレーはその義手を外す代わりに、また新たな“他者”を招き入れたのである。
だからこそ、本書『勝機』(二〇二二)の冒頭は必然と言えるのかもしれない。新たな“他者”に対する葛藤が、シッド・ハレーのスリラーの最大のテーマなのだから。
「シッド、もう終わり」
「何が終わり?」
「わたしたちの結婚」
だがこれは、やはり衝撃的な幕開けである。フランシス、あなた達は何度、ハレーに喪失の恐怖を味わわせれば気が済むのか。だが、その恐怖が、ヒーローを輝かせる。
作中年代は『覚悟』から三年後に設定されている。マリーナは九歳になったサシイを連れて、オランダ北部のフリースラントにある実家に帰る。マリーナの父の容体も良くないのだ。
一方でハレーは、元騎手の調教師、ゲイリイ・ブレムナーからの電話を取る(このゲイリイは、ハレーが左手を負傷する原因となった馬の騎手だった)。ゲイリイは脅されているとハレーに相談する。ハレーは依頼を受けるより先に、ゲイリイの厩舎が火事に遭い、馬数頭が犠牲になり、調教師の行方が知れないというニュースに接するのだった。
またしても競馬界の不正に首を突っ込むことになるハレー。今回のテーマは「騎手エージェント」である。イギリスでは毎年一万以上のレースが開催され、出走馬はおよそ九万頭にのぼるという。馬と騎手をマッチングする仕事も必要なのだ。
新たなる「敵」との対決。恐怖。マリーナとサシイは遠く離れた地にいるが、ハレーは新たな“他者”をその身に迎え入れている。拒絶反応を抑制する薬を飲むことは欠かせないし、出来る限り傷つけてはならない(作中には新型コロナウイルスについての言及もあり、感染症への恐怖も描かれる)。そんな状況で、新たな敵に立ち向かうのは無謀だろう。しかし、傍観しているだけではいられない。競馬が脅かされているのだから。彼はシッド・ハレーなのだから。ハレーはまたしても、喪失の恐怖に歯を食いしばりながら、危険に身を投じるのだ。
今回のハレーはまた一段とナイーブな一面を覗かせているように思う(13節の末尾などは実に泣かせる)。これまでのシリーズでも「よき義父」として存在感を示してきたチャールズとの対話は、ゆっくりと冷たい心を温めてくれる。
新たな手を得たことによる苦悩と喜び。医師が手を尽くしてもなお、肌の色に差があり、その手で撫でられるたびにぞっとするというマリーナの言葉はひどく生々しく、ディティールの密度が素晴らしい。それでも、得たことによる喜びはある。両手で卵を割るだけで喜びを感じるハレーの姿には涙腺が緩みそうになった。
だが、やはり本書屈指の名シーンは、クライマックスに置かれた静かな「対話」であろう。喪失の恐怖に打ち克って、何者にも奪えないものを得る。その確かな感動があるからこそ、シッド・ハレーの物語は、六十年の時を経てなお、読者の心を打ち続けるのではないか。シリーズでも屈指の名シーンをぜひとも見届けていただきたい。
ディック名義最後のハレー長編となった『再起』と本書には、重要な共通点がある。両作品には共に、他のハレー登場作にはない「エピローグ」が置かれているのだ。それも、ある一点で呼応した二編のエピローグであり、本書を読み終えたら、ぜひとも『再起』も手に取ってもらいたい。
巻末の作品リストにも記載があるが、二〇二五年に刊行されたDark Horseは、シッド・ハレーものの第七作になるようだ。次はハレーがどんな目に遭わされるのか、楽しみでならない。
シッド・ハレーは移植により新たな手を得た。同時に、フェリックスもディック・フランシスの魂を見事に受け継いでいたのである。