全世界で人気を博した名作中の名作、ディック・フランシスの〈競馬シリーズ〉。日本でも作家や各界著名人のファンも多かった伝説のシリーズが、次男フェリックス・フランシスの筆により復活、「先代」に劣らぬ見事な出来栄えに驚きの声があがった。
第1弾『覚悟』につづいて、10月に第2弾『虎口』が刊行された。これを機に、フェリックス・フランシス氏に「伝説の継承」の内幕を聞いた。
――このたび日本で刊行される『虎口』は、〈新・競馬シリーズ〉の文春文庫・第2弾となります。舞台は競馬の聖地ニューマーケットですが、その風景や空気感が見事に描かれていて、馬のひづめの音が聴こえるようでした。ニューマーケットにはよく行かれていたのでしょうか。

ニューマーケットではたくさんの素敵な日々をすごしてきました。自分の小説のための取材はもちろん、レースの観戦も楽しんできましたよ。とくに早朝のウォーレン・ヒルで調教中の馬たちを見るのが大好きで、何度行ったことか知れません。心の躍る景色なんですよ。今のところ、私の小説のうち『祝宴』とNo Reserve(未訳)もニューマーケットを舞台にしていて、今後も登場することは間違いありません。
――『虎口』にはイギリスの本格ミステリの伝統も感じます。ある一家のなかで殺人が起こり、最終的には限られた人物の中から犯人が指摘される。クラシックなフーダニットを意図なさったのでしょうか。
私の作品のほとんどは程度の差こそあれフーダニットですし、家族や血縁は犯罪の完璧な動機を与えてくれるものです。ただ、私なら「クラシックなフーダニット」とは呼ばないでしょうね――『虎口』には不気味な屋敷が出てきませんし、嵐のせいで十何人もの客たちが外界から孤絶することもなければ、次は誰がどんな陰惨な手口で殺されるんだろう? と怯えるようなことにはなりませんから。
――主人公は危機管理コンサルタントのハリイ・フォスター。彼がニューマーケットでの放火事件を調査し、高名な調教師一家の秘密に迫るわけですが、彼は〈シンプソン・ホワイト・コンサルタンシー〉という企業に属しています。元軍人アンソニイ・シンプソン=ホワイトが立ち上げたというこの会社、政界から産業界までさまざまなトラブルを収拾するのが業務で、スパイ小説にでも出てきそうな面白い会社です。続編が書けそうですが。
アンソニイ・シンプソン=ホワイトと彼の会社は純然たる私の想像の産物で、現実には存在しませんが、似た感じのローファームがいくつか実在するのは間違いないでしょう。現時点ではこの会社もハリイ・フォスターも再登場の予定はありませんが、とはいえ、世に「絶対」ということはありませんからね。
――私はお父上の〈競馬シリーズ〉を長年読んできましたが、『虎口』には、〈競馬シリーズ〉にはなかったユーモアの要素を感じました。こうしたユーモアは「フェリックス・フランシスの〈新・競馬シリーズ〉」を書くうえで、意識的に取り入れたものなのでしょうか。
まさしくそうです。私の作品は、父に比べてユーモア味が強いと思いますし、それは意図したことでもあります。たぶん60年を経て、世の中がかつてほどフォーマルでなくなってきたことの反映なのでしょう。
はじめて執筆に関わったのは17歳
――翻訳者・加賀山卓朗さんも〈競馬シリーズ〉の大ファンです。そんな加賀山さんと、『虎口』は『名門』と『黄金』を思わせますね、と話していたのですが。
加賀山卓朗さんにはたいへん感謝しているんです。私には日本語が読めませんが、日本人の友人がおりまして、翻訳がとてもいいと教えてくれたんです。作家というものは翻訳者に多くを依存しています。自分の作品を単に海外に送り出すだけでなく、異なる言語で容易に読めるようにしてくれるわけですから。『虎口』を読んで『名門』と『黄金』を思い出したとうかがって恐縮しています。この2つは私のお気に入りの〈競馬シリーズ〉作品なんですよ。
――他にももしお気に入りがあれば教えてください。
難しいですねえ……全部好きですからね。でも、もっとも偏愛している作品は1971年の『骨折』でしょうか。これもニューマーケットが舞台で、二組の「父と息子」について描いています。息子同士の関係性が深まってゆくことで、父親同士の関係も、それに二つの父子関係も変わってゆく。この作品はフーダニットではありません――最初の章で「犯人」はいわばわかっていますから。『骨折』は「自分はこの問題とどう相対すればよいのか」を描く物語というべきでしょう。シッド・ハレー・シリーズも大好きですよ。自分でも4作品書きましたし、いつかまた彼は登場するだろうと思っています。

――日本では『興奮』が〈競馬シリーズ〉の一番人気なんです。主人公ダニエル・ロークも人気キャラで、「ダニエルはわたしの夫だ」と公言する女性ファンもいます。『興奮』の続編の可能性はあったりしますか?
『興奮』の続編を書くことはないんじゃないかと思いますが、Triple Crown(未訳)という作品で、主人公のジェフ・ヒンクリイは、調査のために『興奮』のダニエル・ロークのように厩舎に潜入していますよ。
たぶん『興奮』は、私が最初に読んだ〈競馬シリーズ〉だったと思います。出版されたとき、私はまだ12歳でした。これも私のフェイバリット作品のひとつなので、いつかダニエル・ロークが帰還しないとも限りませんよ。彼はつねに女性ファンに大人気ですからね! あの作品でも彼に惹かれた女性が何人もいましたよね。
――私があなたの名前を知ったのは1987年、『配当』の献辞にあなたの名前があったためでした。このときはどんなふうに作品に貢献したのでしょうか。そして、いつ頃からお父上の創作に関わっていらしたのですか?
『配当』に出てくる競馬予想プログラムを書いたのが私で、登場人物の物理教師ジョナサン・デリイのインスピレーション源でもありました。私がはじめて父の作品に関わったのは、1970年の『混戦』で、軽飛行機を破壊した爆弾の仕様を書きました。私は17歳で、物理を学んでいました。それ以降、作中の科学的な描写について手伝うようになったんです。典型的な例は『烈風』での気象学ですね。
父のスタイルは、今や私のスタイルに
――あなた名義のデビュー作『強襲』は、2015年にイースト・プレスから邦訳されています。この作品を読んだとき、〈競馬シリーズ〉の根本的な文体/語り口/テーマ/精神がそこにあることに驚かされました。いったいどんなふうに、あなたはお父上の「声」を身につけたのでしょうか?
私はディック・フランシスの小説を読んで育ったんですよ。第1作『本命』は、わたしが9歳のときに刊行されました。ゆえに、あの作風は私にとって身近であり、それを知悉し、理解しているのです。じつのところ『強襲』は私の6作目の小説なんです――はじめて書いたのは『再起』。ディック・フランシス名義で刊行された小説ですね。それから父子名義で4作。意識的に作風を真似たつもりはなく、自然にこうなったんです――父のスタイルは、今や私のスタイルになっているのです。

――『再起』の執筆にはあなたが関わっているのだろうとは思っていましたが、実際どうだったのかは日本の読者にはあまり知られていないと思います。
『再起』の出版から8年間は、公言してはならないという契約があったんですよ。それがもう過ぎたので、いまでは私があの作品を書いたのだと言えるようになりました。もっとも、あの本自体は公式には「ディック・フランシスの作品」として登録されていますが。英米の出版社は当初から、このことを知っていました。
――世界的に人気を博すシリーズを「継ぐ」という決断を下したのはいつだったのですか?
あの決断はちょっとした誤解からはじまったようなところがあります。2005年のこと、私は父の文芸エージェントとランチをとっていました。エージェントは、困ったことになっている、父の作品がこのままだと絶版になってしまうと言ったのです。作品に不足があるからではなくて、最後に新作が出てから5年が経って、読者から忘れられはじめているというんです。
「必要なのは」と、彼が言いました、「新作のハードカヴァーを出して、旧作の売上げを活性化させることです」。私は、「そんな無茶な。父は85歳で、記憶力だって昔のようにはいかない」と答えたのですが、じつはエージェントの真意は、既存のしっかりしたミステリー作家に新たな〈競馬シリーズ〉を書かせる許諾を得たいということだったんですね。
そこで私は、「誰かに打診する前に、私に試させてもらいたい」と言いました。そして書き、うまく行ったわけです。
――相当のプレッシャーがあったのではないかと思うのですが。
これまで私は19作書き、いま20作目を執筆中です。もちろん、かくも高名なシリーズを書き継ぐことにプレッシャーを感じました。いまも感じています。でも、そのせいで意識が集中するんですよ。
勝利への意志と敗北への恐怖
――お父上がご存命の頃は、どのように作品を仕上げていたのですか?
できあがった章を父に送り、チェックしてもらっていました。父は非常にうれしそうで、修正はあってもごくわずかでした。しかし『矜持』のときは父の健康状態が悪化していたため読んでもらうことはできず、亡くなったのは私が半分ほどまでしか書けていないときでした。それでも、あの作品の表紙には父と私の名前が並んでいます。
――それまでは高校の先生でいらっしゃったんですよね。
17年間(1974-1991)、3つの学校で物理学の高等クラスで教えていました。教職は大好きでしたし、最終的には私立のブロクサム校で科学の長になりましたが、父のマネージャーになるためと、ビジネスの世界に入るために辞職しました。学生向けに教育的な旅行を企画するWorld Challenge Expeditionsという企業で、13年間、副会長を務めていたんです。2005年からは専業作家になって、これも大好きな仕事です。
――あなたは〈競馬シリーズ〉を見事に継いでみせたわけですが、一方では『虎口』のユーモアのように、〈新・競馬シリーズ〉にはあなた独自のカラーがあります。ディック・フランシスとは「異なる」ようにしようというのは、どの程度意識なさっていますか。
はじめのうちは、「ディック・フランシス」と「同じ」であろうと努めていました。しかし、時が経つうちに、「フェリックス・フランシス」であることを学んだのです。もちろん、私たちのあいだには「違い」があって、ユーモアもそのひとつです。いまでは自分らしく自由に書いていますが、それでもつねに父のそれと同種のものになりますね――まったく完全に同一ではないとしても。
――ユーモア以外にも「違い」をお感じですか?
本質的には〈競馬シリーズ〉と私の〈新・競馬シリーズ〉に違いはないと思っています。どちらのシリーズも、ほとんどが異なる主人公を立てていて、物語は多彩です。私がいつも言うのは、〈競馬シリーズ〉とは、馬たち(主に競馬ですね)にまつわる道徳的でエキサイティングな物語のブランドで、私はそういうつもりで書いているということです。もっとも、このシリーズは馬についての小説ではありませんが――人間についての小説です。
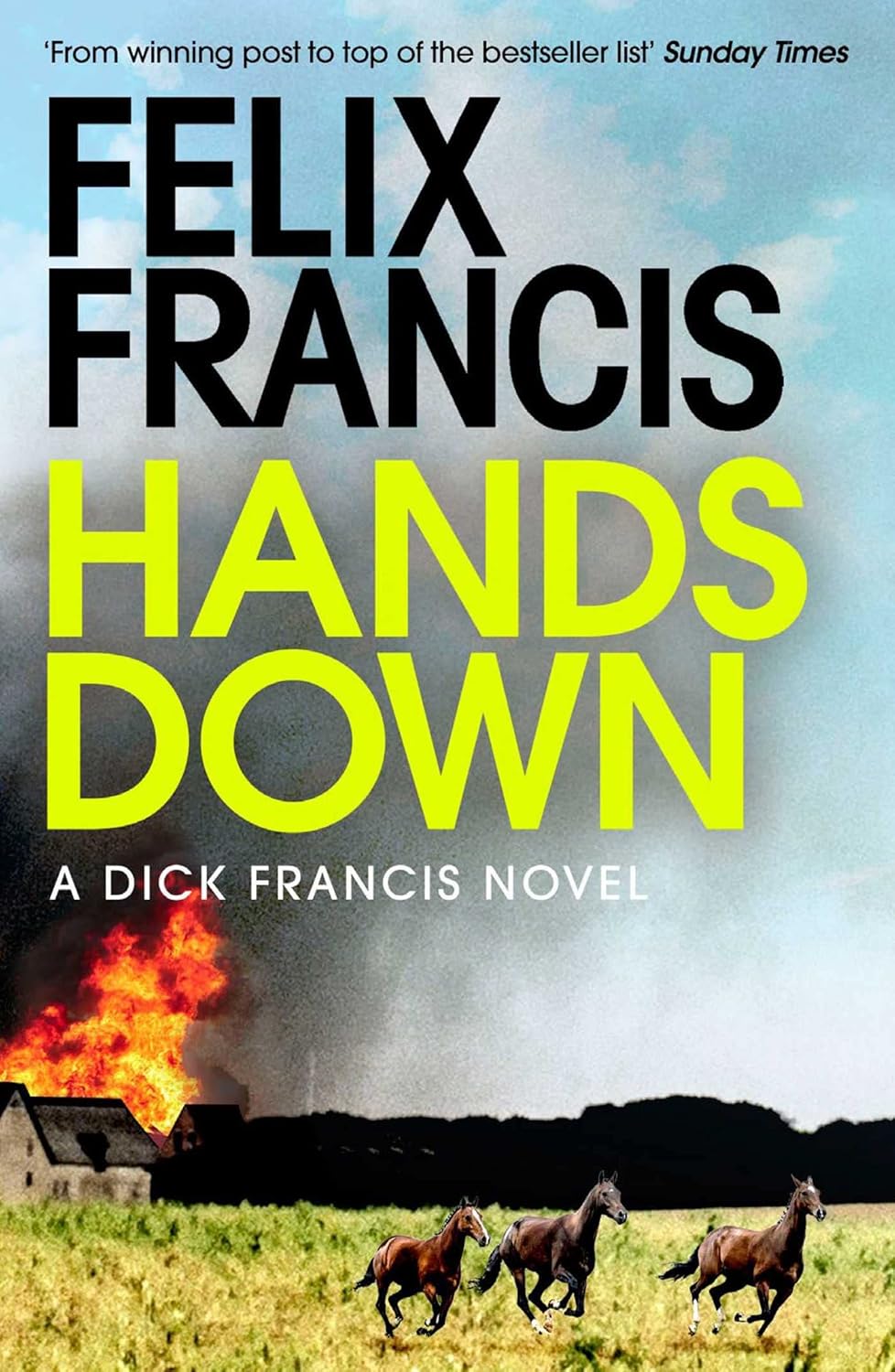
――過去にも「ディック・フランシスの後継者」という触れ込みの著者が出ましたが、うまく行った例はありません。それは〈競馬シリーズ〉の本質を見誤ったせいではないかと思っています。〈競馬シリーズ〉における競馬は、あくまで勝利や不屈の精神を描くための題材にすぎないのではないでしょうか。
父の〈競馬シリーズ〉も私の〈新・競馬シリーズ〉も、馬についての物語ではなく、人間についての物語で、「競馬」はキャンバスです。そこに私たちは人間の物語を描いてきました。しかも、このキャンバスはすばらしく壮大なのです。競馬はきわめてコンペティティヴな世界であり、周囲には賞金と賭け金を合わせた莫大なお金の流れがあって、そのほとんどがキャッシュです。誰もがベストを尽くして自分以外のすべてを負かそうとし、ゆえにそこには勝利をめざす強い意志があり、敗北へのすさまじい恐怖がある。そうした事柄が、私たちの小説の登場人物を「すべきでないこと」に駆り立てるのです――それが物語というものを生み出すのです!
ディック・フランシスを父に持つということ
――お父上は元騎手でもあり、競馬界に縁の深い方でした。競馬場などに一緒に行かれることもあったのではないかと思いますが。
子供の頃は、毎週土曜日には父と競馬場に行っていましたよ。父はもう騎手を引退していて、競馬ジャーナリストをしていたんです。父が亡くなる2010年まで、私は一緒にイギリスの競馬場に行くことを続けました。海外の競馬も見に行ったものでした――メルボルン・カップ、ケンタッキー・ダービイ、ブリーダーズ・カップが私たちのお気に入りでした。香港やドバイにも行きましたよ。チェコのパルドゥビツカ大障害レースにも行きました。でも私のいちばんのお気に入りは、イギリスの小規模な障害レースを父とともに見た日々の思い出です。そういうレースで馬たちを間近に見るのを父は愛していたんです。
――ディック・フランシスというのはどんな人物だったのでしょう。父親として、元名ジョッキイとして、あるいは作家として。
有名人を父に持つというのはどういうものか、とよく訊かれます。私が生まれたときには父はチャンピオン・ジョッキイでしたから、有名人でない父を持つというのはどういうことか私にはわからないのです。
父は1956年のグランド・ナショナルで、優勝目前にして騎乗していたデヴォンロック号がゴールの36メートル手前で突然転倒してしまった一件をきっかけに、誰もが知る有名人になりました。とはいえ、私にとってはもちろん私の父でしかないわけです。愛情にあふれる、いたずら好きな父親でした。とても鷹揚で誰にでも優しく、自分の子供たちが礼儀正しく心優しく育つようにと思い定めてもいました。父が激昂するところを私は一度として見たことがありません。
私はいわば20世紀最大の「小説工場」のただ中で育ったわけですが、それは楽しいことであり、とてもワクワクするものでした。両親は人を楽しませることが大好きで、家はいつも面白い話をしてくれるひとでいっぱいでしたよ。
――これから『虎口』を読む日本の読者に何かメッセージはございますか。
日本の読者は私の小説も、私の父の小説もずっと愛してきてくれました。競馬の長い伝統を持つ国として、日本は私のなかで特別な位置を占めているんです。1995年の5月に東京と京都に旅したのは、とても幸せな思い出になっています。そろそろ再訪してもいい時期かもしれませんね。




















