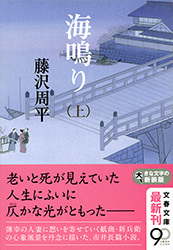主人公は紙問屋を営む小野屋新兵衛。別の紙問屋の内儀おこうとの道ならぬ道へとのめり込んでいく。今風にいえば“ダブル不倫”の物語であるが、不義密通は死罪にもなった江戸期のこと。それへと踏み出すことは抜き差しならぬ切迫感を帯びていて、覚悟の程において今風ではない。
新兵衛は一介の仲買いから叩き上げ、江戸四十七軒で占める紙問屋の株を買い取って伸し上がってきた男だ。新興の小野屋に、大店の老舗が不当な介入や嫌がらせをしてくるが、くじけない。一本筋の通った商人としての気概が、背筋の伸びた人物像をつくっている。
小野屋は上質の白い「細川紙」を売りにしていたが、原料となる楮(こうぞ)の樹皮を収穫し、ふかし、叩き、晒(さら)していく紙漉すきの工程が仔細に記されている箇所がある。
本書の元原稿は、昭和57年、「信濃毎日新聞」などに連載されたものであるが、氏の『半生の記』の年譜によれば、「五月、『海鳴り』取材のため、埼玉県小川町へ紙漉きの工場を見に行く」という一文が見える。綿密な取材がなされていて、江戸期における紙業界の仕組みと模様が生き生きと伝わってくる。
新兵衛は46歳。初老の入口に差しかかっている。商いではひとかどの者となったが、家は荒涼としている。女房おたきとの関係は冷え切り、息子の幸助は遊びごとを覚え、仕事に身が入らない。
髪にふと白いものを見つけ、これまでの自身の歳月はなんだったのかと自問せざるをえない。若い妾をもったこともあるが満たされない。
《いずれは来る老いと死を迎えるために、遊ぶひまもなく、身を粉にして働いたのかという自嘲は、振りかえってみればあまり当を得たものではなかったが、そのころの新兵衛を、一時しっかりとつかまえた考えだったのである。ひとは、まさにおだやかな老後と死を購(あがな)うためにも働くのだ、という考えは思いうかばなかった。
見えて来た老いと死に、いくらかうろたえていた。まだ、し残したことがある、とも思った。その漠然とした焦りと、ひとの一生を見てしまった空しさに取り憑(つ)かれ、酒と女をもとめてしきりに夜の町に駕籠を走らせた。
――だが、救いなどどこにもなかったし……》
自責と自嘲を浮かべる新兵衛の思いが繰り返し吐露されていく。胸の底に巣食う空洞をどう埋めていくのか。心理的なサスペンスの色合いをもった読み物ともなっている。
老いが見えてきたとき、人生の「し残したこと」を自覚しないものは稀であろう。そのようなものをなんとか押し殺して歩んでいく人もあれば、それを埋めんとあがく人もいる。新兵衛は後者だった。