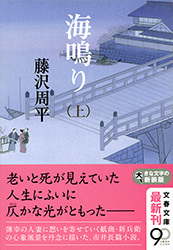辞書には載っていないようであるが、「文品」という言葉を目にしたことがある。真っ先に浮かんだのが藤沢周平氏の作品だった。氏の時代小説は、武家もの、市井もの、歴史ものと多岐にわたるが、ジャンルを超えて小説としての品格がある。氏のファンであり続けてきたのは、「文品」に由来しているように思えたのである。
文品にはもちろん、文体が含まれる。氏の作品でいつも感服するのはごくなんでもない情景の描写だ。やさしい言葉を使いつつ、目の前に光景が浮かんでくる。そこに、心象や暗示が微かに込められているときもある。
本書『海鳴り』には、海や川の情景が幾度か登場するが、抜き出してみると、たとえばこんなところ――。
《そして空は、よく見ればゆっくりと一方に動く黒雲に埋めつくされているのだった。街道には、ほかに人影はなかった。歩いているのはそのころはまだ新助と言っていた、新兵衛ただひとりである。
笠を押さえながら、新兵衛はいくぶん心ぼそい気分になりながら歩いていた。そのとき新兵衛は、見えるところにくだけては散る磯波とはべつの音を耳にした。音は沖から聞こえて来た。
そのときはじめて、新兵衛は海に眼をやったのだが、思わず声を出すところだった。沖の空は、頭上よりも一層暗く、遠く海とまじわるあたりはほとんど夜の色をしていた。音はそこから聞こえて来た。寸時の休みもなく、こうこうと海が鳴っていた。重重しく威嚇(いかく)するような、遠い海の声だった》
《新兵衛はうつむいて、少し凝っている肩をこぶしで叩いた。そのときあたりが急に明るいものに照らされたような気がした。顔を上げたが、四囲は川の闇である。上流の船の灯と、時おり眼につく岸の灯が、かすかにまたたくだけだった。
――気のせいか。
と思ったとき、あたりがまたぱっと明るくなった。一瞬だったが、紫色の光の中に、川波のうねりと両岸の夜景がうかんだ。光はすぐに消えた。
新兵衛は空を見上げ、ついで身体をひねって河口の方を見た。頭上には星がかがやいていた。そして光は背の方から来たように思えたのである。雷が鳴るかと思って耳を澄ましたが、音は聞こえなかった。ゆたゆたと鳴る波の音が、四方の闇を満たしているだけである》
その文体に導かれて、読者は物語へと誘われ行くのである。