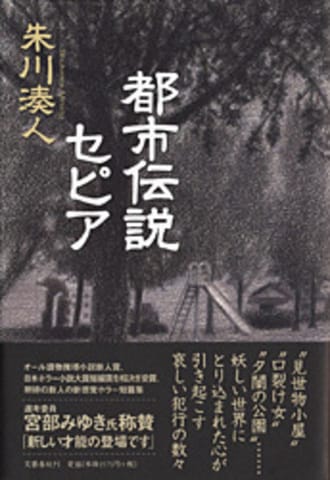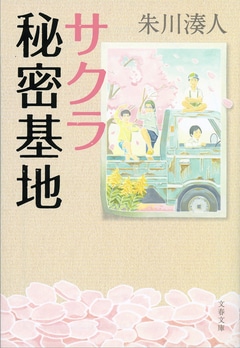いやはやレベルの高さに驚いた。とても新人の第一創作集とは思えないほど粒が揃っている。ここまで完成度が高いのはまれだろう。たいてい一作か二作、数あわせのために水準以下の作品が入っているものだが、ここにはそれがない。全部佳作以上。こんなことは横山秀夫の『陰の季節』(文春文庫)以来のことではないか。
実をいうと僕は、朱川湊人氏が昨年「フクロウ男」でオール讀物推理小説新人賞をとってデビューする以前に、あるホラー系の新人賞の予選委員の仕事で、朱川氏の作品を何本か読んでいる。いまとは異なる変わったペンネームで書かれた、また変わったホラーだった。語り口は滑らかだが、途中からねじれていき、なんとも不思議な味わいを醸しだす。プロットに若干飛躍があって受賞には至らなかったけれど、作品全体にただよう何ともいえない叙情性、そこはかとない哀しみの醸成が胸に残り、次はどんな作品を書いてくれるのだろうかと期待を抱かせた。それは僕だけではなく、ほかの予選委員と編集者も同じで、いずれ賞をとるだろうと思われていた。
だから、その賞の前に、オール讀物推理小説新人賞をとったときには驚いた。裏切られたような気もしたのだが、でも受賞作を読んで納得した。広義のホラーではあるけれど、恐怖を前面に打ち出さずに、より心理をこまやかに描くようになっている。ホラー的題材を極彩色に色付けするのではなく、むしろモノトーンで塗り込めて、ブラックな味わいとやるせない情感をひきだしている。“ホラー作家”の短篇というよりも“小説家”がホラーを書いた印象だった。
というと、語弊があるかもしれない。「フクロウ男」を収めた第一作品集の本書『都市伝説セピア』は、ジャンル的にはホラーになるからである。タイトルが示すように、第一義的には“都市伝説”をテーマにしたホラー集。都市伝説とは、人々の興味と不安をかきたてる「口裂け女」や「トイレの花子さん」や「人面犬」などの伝説のたぐい。あたかも実在するかのように、まことしやかに流れ、人々に恐怖の感情を覚えさせる伝説を、作者はここで新たに提示してサスペンス性を高めている。
または「アイスマン」。少年が神社の夏祭で目にした「河童の氷漬け」。人形を氷漬けにしたものにすぎないと思うのだが、ひょんなことからその正体をまのあたりにして、少年の人生は変転していく。
さらには「月の石」。マンションの部屋にたてかけられたマネキンは、さまざまな“人間”に変貌するという。見る者の後ろめたさが投影された顔になるのだ。
そのほかにも、神秘のベールに包まれた女流画家が一面識もない自殺した画学生との恋を語る「死者恋」、幽霊が出ると噂される公園で少年時代の特異な体験に思いをはせる「昨日公園」が収録されている。
このような都市伝説も面白いが、驚くのは、先にもふれたように作品のレベルの高さである。「フクロウ男」の巧みな伏線とツイスト、「アイスマン」の落ちの切れ味、「昨日公園」の哀切などんでん返し、「死者恋」の不気味で残酷な結末と、実に鮮やかな仕上がりなのである。
しかし本書の最大の魅力は、都市伝説の面白さでも、巧みな小説作りでもない。
「月の石」に顕著だが、全篇にただようノスタルジーである。通勤電車から見えるマンションの一室にいる“人間”。それはマネキンで、ときに会社をやめさせた男に見え、ときに孤独死を迎えさせてしまった母親にも見え、男の不安と恐怖を増幅するのだが、物語の焦点はそこにはない。心の奥底に眠る後ろめたさとやましさにある。死期を迎えた妻をいたずらに延命させるのか、それとも治療をやめさせて死期を早めるのか。どちらを選択しても悔いが残る。この世には選べないこと、つまり正しいことがいくつもある。人は正しいことを同時にいくつも選べない苦しみを抱えながら生きていく。そのことを、亡き母がいちばん輝いた時期と妻との楽しい日々を回想しながら噛みしめるのである。この母や妻との関係を語る挿話がたまらなくいい。
いや、これは何も「月の石」だけではなく、「昨日公園」では父子の愛と友情が切々と、「アイスマン」では少年と少女との交流が淡いながらも優しく語られている。
このノスタルジックな心象風景が、読む者の心を慰撫する。懐かしさを感じさせるような寂しさと哀しみにみちている。このそこはかとない哀しみこそ、朱川湊人の小説の通奏低音だろう。二度と体験できない懐かしい過去の記憶。過去に戻れない寂しさと事実を変えられない哀しみ。ここには人がもつプリミティヴな感情と普遍的な生の情景の数々がある。