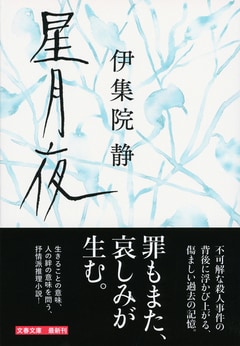同性愛や近親相姦など性的な問題を多く含んでいる小説である。ずいぶん大胆なテーマに挑んでいて、下手をすると通俗に流れかねないのに、宮本輝の筆致は艶やかで清新、淫らがましくも清潔なエロティシズムをかもしだしている。複雑な出自と深い性愛をまさぐる物語は実に読ませるのだけれど、その魅力を語るまえに少し寄り道をしたい。久々に刊行されたエッセイ集『いのちの姿』(集英社)の味わいが濃いからである。
宮本輝は小説に専念するために、懇意の編集者の熱心な依頼も断っていたのだけれど、数年前から年二回刊行の雑誌にエッセイを書き始め、今回七年分十四篇のエッセイをまとめた。ここにはいままでふれられることがなかった異父兄との接近を、晩年の母の台詞を紹介しながら語る「兄」、豆腐屋夫婦の養子となった子供に実父の俤を見る「ガラスの向こう」、『優駿』執筆当時の馬主経験の裏話「殺し馬券」、良き人々の不可思議な出会いと連帯「人々のつながり」、老職人が残した形あるものの真価「消滅せず」など相変わらずしみじみと読ませるものが揃っているのだが、なかでも引き込まれてしまうのは、二十代の不安神経症の日々を生々しく綴る「パニック障害がもたらしたもの」だろう。病気がいかに死の恐怖を覚えさせるかを皮膚感覚で描写していて、まことに鬼気迫るものがある。
実際に宮本は会社通勤が辛くなり、たまたま雨宿りで入った本屋で文芸誌を読み、小説家になることを決意する。作家になればパニックの発作と恐怖を体験しなくてもいいと考えたからだが、書いても書いても受賞には至らない。でも、“私の生と死への思考の問題は、あるとき「自然」とか「風景」とか人間そのものの真の美しさに向かって一歩を踏み出”すことになる。ちょうどその頃、“文学の何たるかを教えてくれる人物とめぐり逢い”指導を受け、“小説とは言葉では説明できないものを言葉によって織り上げていくものだと気づくこと”になる。小説は“私という人間のなかからしか出てこない”、それならば“私という人間を大きくするしかない。この病気は、そのために私の内部から湧き出たのだ。/上手下手はあとからついてくる。心のなかにある風景や自然や人間のさまざまな営みを、愛情をこめて小説として書こう”、宮本はそう決めて、『泥の河』(太宰賞受賞)を書き、次に『螢川』(芥川賞受賞)を書いたのである。
久々に上梓されたエッセイ集を手にすると、『螢川』で芥川賞を受賞して二年後に編まれた第一エッセイ集『二十歳の火影』が懐かしくなる。いま読み返すと初々しくも熱く、文学に賭ける作者の思いがまぶしいくらいだ。
右でふれた文学修業時期の話も書いてあり、『泥の河』『螢川』に深い影響を与えた作品として、吉野せいの『洟をたらした神』をあげている(以下引用は『二十歳の火影』所収「不思議な花火」)。この作品は厳しい自然の中で貧困とむきあった農婦の年代記で、吉野は七十歳を過ぎてから筆をとった。その作品を宮本は偶然町の本屋で見かけ、家で“何度も何度も読み返した。七十五歳の百姓バッパの一言一句は、彼女の阿武隈山脈の一隅にふるいつづけた渾身の鍬の力をもって、私の中の何物かをくつがえしてきた”というのである。くつがえしてきたものは“文章というものの秘密”“決して明らかにはならぬ極意”のようなもので、そこから宮本は本を再読し、原稿用紙に向かうことを何度も繰り返して『螢川』の原型を書き上げることになるのだが、興味深いのは、“渾身の鍬の力をもって、私の中の何物かをくつがえしてきた”という表現である。宮本は吉野せい体験を語っているわけだけれど、これは現代の読者にとっては、宮本輝体験といってもいいのではないか。少なくとも、本書『焚火の終わり』を読む者は、自分の心の中の何物かがくつがえされるのではないかと思う。
物語を紹介しよう。主人公は大阪の土木建設会社に勤務する町田茂樹と京都の呉服屋で辣腕をふるう須川美花の二人である。
町田茂樹が得意先をまわり、社に帰ると机にメモがあった。スガワ様から電話あり、電話をくださいという。京都の須川美花で、茂樹の異母妹だった。
茂樹が電話をかけると、島根の岬の町に住む美花の祖母が心筋梗塞で倒れて危篤だという。二人は急いで島根に向かう。茂樹は二年前に妻に先立たれ、翌年母親も亡くしていたし、美花も母親を亡くして祖母だけだった。岬の町は、茂樹にとっても、幼いころから何度も遊びにいった思い出の土地でもあった。
だが、二人が高速にのってすぐに祖母の訃報を耳にする。そして美花は、自分の父親も母親も本当は別にいるのではないかとおかしなことを言い出す。茂樹は気になって葬儀のあと、自宅に戻り、母の遺品の一つのノートを見いだす。そこには「許すという刑罰」という謎のメモがあった。一方、美花の家には、赤ん坊の美花を抱く男の顔がくりぬかれた異様な写真が一枚残されていた。
茂樹は、美花は本当に自分の妹だろうかという疑問を抱くようになる。茂樹と美花は、出生の秘密を探り、いちだんと絆を深めていくことになるのだが……。
読み始めたら一気だろう。だれもが宮本輝の語りの巧さに言及するけれど、本当にほれぼれする巧さである。先日久しぶりに対談集『道行く人たちと』を手にしたら、芥川賞受賞決定後に行われた田辺聖子との対談「小説のおもしろさ」(初出「文學界」一九七八年三月号)で、田辺に“物語作家の素質があるのかなあ”といわれて、宮本は“ひょっとしたらそうかなあと思うときもありますけど、ただ、それがぼくの場合、吉と出るか凶と出るかまだわからないですね”と答えている。いやはや、芥川賞の段階で見抜く田辺も、それに答える宮本輝もすごいし、実際物語作家としても磨きをかけて大成し、話づくりの巧さは群を抜く。僕は仕事がら国内外のミステリを数多く読んでいるけれど、ミステリ作家を含めた作家たちのなかから語りの名手のベスト5を選べといわれたら、僕は躊躇なく宮本輝を入れるだろう。作品にふれるたびにほとほと感心する。この小説もそうである。
これはまず出生の秘密を探るミステリといっていいだろう。さきほど紹介したほかにも、謎の預金通帳や隠されていた複雑な人間関係が次第にあらわになり(上巻なかばの新聞記事にはびっくりする)、謎が解かれたと思ってもまた別の謎が内包されていて、茂樹と美花の探索は深まり、さらに茂樹と美花の会社人としての仕事と人事の葛藤も加わって、いちだんと物語は重層化していくのである。
上巻の終盤で、“人間ていう存在そのものが、とんでもない謎なんや”、下巻の冒頭には“人間てのは魑魅魍魎です。だからこそ、他の動物にはない精神活動を営み、そこから多くの知恵も湧いてくる”という台詞が出てくるように、いったい父親と母親たちは何をしていたのか、どんな秘密をもっていたのかが、いくつもの相反する証言を検証しているうちに浮かび上がり、茂樹と美花の関係を左右するようになる。二人はいったい兄と妹なのか、それとも血縁はないのかどうかが二人の感情を揺さぶっていくのだけれど、いつしか元に戻れないところまでいってしまう。
この小説では、兄と妹の愛のテーマが大きくしめる。冒頭の場面から、そのテーマをうちだすために、焚火にまつわる情景から、二人のそれぞれの感情を伝えている。まず茂樹は、岬の家で美花と一緒に焚火をして遊ぶことがなぜあれほど楽しかったのかを考える。“人は原始のとき、火がよるべであり、生活のあらゆる武器であり活路であって、だから人は、火が好きなのだという学者の説は”正しく聞こえても、茂樹には“まやかし臭く”思える。なぜなら美花との焚火遊びは、“秘密めいた生への歓びであり、どこか性的なときめきをもたらす火照りの源”だったからである。一方美花は、焚火が好きなのではなく、“焚火の火の前に立っている兄が好きだった”、“安心できる暖かさ”がというのだが、関係が進展するうちに、それもまた微妙にかわっていく。
唐突と思われるかもしれないが、読みながら宮沢賢治の『春と修羅』を思い出していた。『春と修羅』は青春期のはなはだしい動揺と信仰(賢治は熱心な日蓮宗の信者だった)との軋轢で引き裂かれた魂、その内面の修羅の叫びを、豊かな自然との官能を通して描ききった作品だが、その中心となるのは若くして亡くなった妹トシへの激しい思慕である。賢治とトシの間に近親相姦的な関係があったのではないかという説がささやかれ、それを検証する研究本も出ているけれど、重要なのは、ひとりの人間がもつ潜在的な欲望や営みを普遍的なレベルで捉えようとする視点だろう。『春と修羅』の序文にあるように、“わたくしといふ現象は”“風景やみんなといつしよに/せはしくせはしく明滅しながら”灯りつづける“ひとつの青い照明”であり、“すべてわたくしと明滅し/みんなが同時に感ずるもの”、“すべてがわたくしの中のみんなであるやうに/みんなのおのおののなかのすべて”なのである。
先にも引用したように、『いのちの姿』で宮本輝は、小説は“私という人間のなかからしか出てこない”“心のなかにある風景や自然や人間のさまざまな営みを、愛情をこめて小説として書こう”と決意した。それは宮本の“心のなかにある風景や自然や人間のさまざまな営み”がそのまま他者(読者)の心のなかにあるものをうつしとることになるからである。読者は宮本輝の小説を読み、そこにあたかも自らの原風景を見るかのような思いにかられる。小説で描かれる世界や関係にほど遠い環境にありながらも、なにかとても近しく、わがことのような思いにかられる。それは、宮本輝の筆が、吉野せいの渾身の鍬のように、読む者の心のなかの何物かをくつがえしてくれるからである。もっというなら、ときに背徳じみたことも登場人物に堂々といわせて、読者の価値観をゆさぶるのだ。
たとえば、美花が呉服屋の社長の川村に愛人とどんなことをしているのかと聞く場面がある。川村は“人には言えん恥しい浅ましいことや”といい、そのような行為がときおりなければ、自分は自分の奇妙な苛立ちを鎮めることはできないと言い、こう付け加える。“人間だけが隠し持ってる快楽への衝動は、科学でも哲学でも解明できん。しかし、その衝動を燃料にして、そこから聖なる何物かを生みだすのが人間という生き物ではないのか。俺はそんな気がする”
人には言えない恥ずかしい行為。でも、それがなければ内面の苛立ちを鎮めることはできないし、隠し持つ快楽への衝動を燃料にして“聖なる何物かを生みだすのが人間という生き物”なのではないかという言葉が胸に響く。美花もその言葉をうけて、“世間の規範から外れた秘密の悦楽を薪にして、思いもよらなかった聖なる火を創造できる”のではないかと考える。では“聖なる火”とは何か。聖なるものだから、“他人のためになり、他人を歓ばせ、他人の幸福に寄与できるもの”であるはずだと思いめぐらす。
この幸福の問題は、宮本輝の小説の根本的なものであり、デビュー当時から考えぬかれている。芥川賞受賞後に外国の古典を読み返し、あるものは冒険を、あるものは虚無を、あるものは快楽や愛憎のエッセンスをにじませて生き長らえてきたが、それらは“ことごとく部分であり瞬間であり閃光”であった。“部分や瞬間をえぐっていくことで、全体を、永遠をあぶり出していくのが芸術の仕事”であり、“無尽蔵な部分の羅列と混成”が何を志向すべきかと問われれば“私はやはり「人間にとって、真のしあわせとは何か」という一点にたどり着いてしまう”と述べている(引用は『二十歳の火影』所収「文学のテーマとは、と問われて」より)。
そして真の幸福を考えたとき、どうしても無視できないのは、生まれながらついてくる身分、貧富、容貌、頭脳、体力、時代などの差で、それは宿命と呼ぶしかない。“ひとりの人間の宿命を虚構に託して追跡し、そこに人生の意味や味わいをあぶり出すことは、すでに古今東西にわたるあらゆる名作が成しとげた”。新しいものなど何もないが、もしあるとすれば、“それは人間のかかえ持っているどうしようもない根底的な「差」によって生じる悲しみや苦しみや障害を、どのように打ち破り、いかにして自分らしい勝利の物語に転換せしめるかの方途と証しを示す場合にだけ見いだすことができる”(『二十歳の火影』所収「宿命という名の物語」)。同じことが、本書の茂樹と美花の宿命の物語にもいえるだろう。いや、茂樹の会社の元同僚の西口など脇役たちの人生にもいえる。悲しみや苦しみや障害をひとつひとつ明らかにして、打ち破る方法を示していくのである。精神的かつ経済的な勝利も視野にいれ、後半は旅館業を営むための実際的知識も増えて、商売小説としての興趣も起こりわくわくする。
とはいえ、やはり印象的なのは、セックスを含めた命の力だろうか。罪の意識がもたらす異常な愉悦とか、気持ちのいい沼みたいな快楽とか、ふくよかな支配とか、おごそかな何物かに包まれつづけている交合とか、さまざまな性愛が言葉豊かに語られるけれど、性愛以外の生の営みもたっぷりと書きこまれている。つまり、食べて、飲んで、笑って、泣いて、怒ってといった人間たちの姿を生き生きと捉えているのである。しかも、ユーモアを忘れずに。宮本輝の小説がいいのは、至る所にユーモアがあり、和ませてくれることだ。真摯で、切実で、悲しいけれど、でもいつも温かな微笑がそばにある。人物に愛嬌があるからだろう。“愛嬌がないところに福来たらず”という表現が出てくるけれど、愛嬌なきところに物語の愉楽なしといってもいいのではないか。さきほど僕は、宮本輝は、語りの名手のベスト5に入るといったけれど、それはストーリーテリングが卓越しているだけでなく、ユーモアにみちた語り口も加味してのことである。
ごらんのように、本書『焚火の終わり』には宮本輝のエッセンスがあるといっていいだろう。素晴らしい話術にのせられ、僕らは男と女の宿命の物語に深く魅せられ、心のなかの何物かをくつがえされる。作者は世間の善悪にふれつつも、それを仮初め事としてとらえ、もっと深く潜むものを見ようとする。倫理の綱渡りのような、ひじょうに危険で背徳的な部分もあるけれど、命がもつ深い歓びをつかまえて、真の幸福とは何かを力強く問いかけている。開かれた結末も効果的で、何とも忘れがたい小説だ。