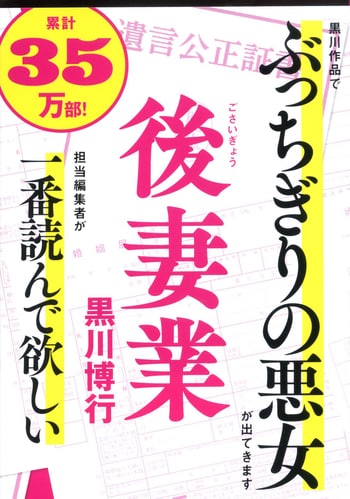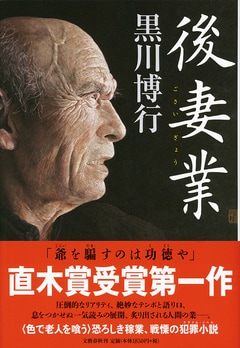実家の玄関を開けると、エキゾチックな風貌の美女を描いた大きな絵が出迎えてくれる。日本画家・黒川雅子さんの若き日の自画像である。その美女が、京都の麻雀荘で爪にレモンイエローのマニキュアを施した指でしなやかな牌捌きを見せていたのだから、当時は狂のつく麻雀好きの黒川博行さんが一目惚れしたのも無理はない。
そのとき二人はともに京都芸大の学生で、雅子さんは日本画、黒川さんは彫刻を専攻していた。二人はすぐに意気投合、というより、黒川さんが猛烈な攻勢に出、ほどなく二十三歳で学生結婚する。
もう二十年以上前のことになる。当時小説誌編集部に在籍していた私は、大阪に出張した折、黒川さんに電話をかけお会いしたい旨を伝えた。それまでは文壇のパーティーで立ち話をした程度で、きちんと話をしたことはなかった。黒川さんは快諾され、羽曳野市にある自宅へ招いてくださった。そこで雅子さんと初めて出会ったのである。
そのとき、黒川さんは雅子さんのことを「ハニャコちゃん」と呼ぶので、私はそれからしばらく「はな子」さんだと思い込んでいた。後で聞けば、戦後すぐ、タイ国から日本へ贈られ、上野動物園で子供たちの人気者になったアジア象の「はな子」のゆったりした動きに似ていると、黒川さんが付けたあだ名だった。
雅子さんは黒川さんのことを「ピヨコちゃん」と呼ぶ。ピーピーとひよこのように騒がしいからだという。
しばらくリビングで三人で話をしていたが、黒川さんが突然麻雀をやろうと言い出した。三人しかいないのでは、と訝しげな顔をする私に、大阪では三人打ちが主流なんや、との説明。簡単なルール説明のあと、手積みで始めた。
ハニャコさんの牌捌きが妙に流麗なのが気になった。たしか高校の美術の先生と紹介されたよな……。六巡目、私が五索(ウーソウ)を捨てると、ハニャコさんが柔らかなのんびりした声で「それ、あたり。大三元」。その晩の結果は書くまでもない。
以来なぜか、私は大阪に出張するたびに黒川邸に泊まる羽目になった。
ここまで雅子夫人と麻雀について書いてきたのは、二つのどちらが欠けても「作家・黒川博行」は誕生しなかったからである。
黒川さんが最初に小説を書こうと思ったのは、一九八二年、三十三歳のときである。当時、黒川さんは大学卒業後勤めていた大手スーパーから高校の美術教師に転職していた。それまで古今東西の文学作品はもちろん、とりわけ二十代後半からはアガサ・クリスティーやエラリー・クイーン、レイモンド・チャンドラー、松本清張からエルモア・レナードまで、ミステリー、ハードボイルドの名作を読み耽っていた。その下地があったので、その年に創設されたサントリーミステリー大賞に応募しようと思い立ち、「おれは推理小説を書く。サンミスに応募するんや」と高らかに宣言したのである。
夏休み中に書き上げようと原稿用紙に向かったが、どうすれば話が展開するのか、皆目見当がつかず、反古(ほご)が出るばかり。ついに音を上げて「あかん。ハニャコちゃん、ギブアップや。おれは小説には向いてへん」
すると雅子さんの柳眉がにわかに逆立ち「男がいったん口にしたことを途中で投げ出すやて、恥ずかしいやろ。最後まで書き」と叱り飛ばした。
この叱咤があったればこそ、サンミス第一回佳作『二度のお別れ』が生まれたのである。さらに第二回佳作の『雨に殺せば』、そして第四回大賞『キャッツアイころがった』に繋がり、「作家・黒川博行」が誕生したのである。恐るべし、雅子さんの“叱咤力”。
大賞受賞後、出版各社から執筆依頼が殺到した。注文を片端から受けたものの、高校教師との二足の草鞋、睡眠時間を削って書くしかなかった。ついに体力の限界が来て、作家専業になることを決心する。三十八歳だった。
「あかん。ハニャコちゃん、体きついわ。学校、辞めてもええか」
「しんどいんやろ、ピヨコちゃん。ええよ」
このとき、黒川さんには、雅子さんが慈母観音に見えたという。むろん、一方では、「しばらく芽が出なくても、ハニャコちゃんの給料で食わしてもらえるやろ」との下心もあった。それらすべてを承知の上で、雅子さんは「ええよ」と微笑んだのである。後顧の憂いのなくなった黒川さんは観音様の掌の上で縦横に活躍し始める。
黒川さんは公言する。
「何十年と麻雀やって役満もいろいろアガったけど、最大の役満は、ハニャコちゃんと一緒になれたことやな」
ご馳走さま。
ちなみに黒川さんの本の多くは雅子さんが装画を描いている。
さて、黒川作品には、『麻雀放蕩記』をはじめとする博打ものと諧謔味溢れる『大阪ばかぼんど』シリーズなどのエッセイ集もあるが、中核をなしているのはミステリーである。そのミステリーも、芸大出身らしく美術界を舞台にしたもの(これにも雅子夫人の内助の功が在ると聞く)とハードボイルド系統に別れ、後者が主流となっている。
作品のほとんどが大阪を舞台に大阪弁の会話で語られ、物語が展開していく。大阪弁を自在に駆使する作家として田辺聖子さんがいるが、ハードボイルドでここまで徹底している作家を寡聞にして知らない。そして綿密な取材に基づいた緻密な描写。そのスタイルはデビュー時から今日まで一貫して変わらない。
黒川さんは大阪にこだわる理由を「大阪を舞台にしているのは、大阪の土地以外よう知らんからや。他の土地のことを調べて書くことはできるけど、リアリティーがなくなってしまう」という。大阪弁を使うのもリアリティー、土地の匂いを出すためだという。しかし実際の大阪弁を使っているわけではない。
「喋り言葉をそのまま使っても大阪人以外は理解できないし、字にすると品がない。せやから“ちゃう”と言うところを“ちがう”と書いたりして、大阪弁の感じを残しながら工夫しています」
デビュー作の『二度のお別れ』(一九八四)に始まる大阪府警シリーズは、新しい刑事像を作ったと評価され、若手の作家たちに衝撃を与えた。それまでの刑事といえば、松本清張作品に代表されるように正義感に溢れ、不平不満を言わず、靴底をすり減らして地道な捜査に従事する、というものだった。ところが、それとは真逆で、大阪弁で給料が安い、やれ暑い、とぼやきながら捜査にあたる惚(とぼ)けた刑事と真面目な刑事の組合せを描いたのである。
当初はトリックを重視した新本格に近い作風だったが、『切断』(一九八九)からハードボイルドサスペンスへと大きく舵を切る。さらに『封印』(一九九二)が吉川英治文学新人賞候補になったことで、ハードボイルド路線の自信を深め、社会派からノワールへと傾斜していく。
黒川さんは、打算的で利害に敏感な、金銭に突き動かされる人間を積極的に描く。悪に手を染める人間の言動にこそ人間の本音、本質が出る、というのである。同時にそれは時代への鋭い風刺となっている。
その後、『カウント・プラン』(一九九六)が日本推理作家協会賞を受賞し、直木賞候補となったことで、一躍注目を集める。
節目となるのが『疫病神』(一九九七)である。建設コンサルタントの二宮啓之が産業廃棄物処理場を巡るゼネコンとやくざの暗闘に巻き込まれ、極道の桑原保彦とともに事件解明に挑む物語である。産廃業界という一般にはほとんど知られていない世界をつぶさに描いているところも読み応えがあるが、なんといってもこの作品を成功させているのは、二人の主人公、二宮と桑原の強烈な個性と大阪弁を駆使した軽妙且つ活き活きしたやり取りとスピード感にある。
会話の中に次に展開するための情報をどう盛り込むか、かといって入れすぎては軽快さが損なわれる。黒川さんはこの会話のテンポを上方落語に学んだという。
主人公設定のヒントになったのは、映画『悪名』の勝新太郎と田宮二郎のコンビである。この映画の勝は河内弁だが、それを大阪弁に置き換えた。
『疫病神』は初めて五万部を超え、この年、収入も初めて雅子さんを超えた。
「作家専業になってしばらくは二百万くらいしか年収がないのに、それ以上飲み代につこうて、私に借用書ようけ書いとったね。あ、ピヨコちゃん、あの借金、まだ返してもろてないとちがう」
「あほ言え。とうに返してる」
ヒット作となった『疫病神』はシリーズとして書き続けられることになる。
その第二作が北朝鮮を舞台とした『国境』(二〇〇一)、続いて『暗礁』(二〇〇五)、『螻蛄(けら)』(二〇〇九)と二宮・桑原コンビは大暴れ。五作目の『破門』(二〇一四)は第百五十一回直木賞を受賞する。
『破門』ではこれまでと違い、大暴れするだけではなく、暴排条例と暴対法施行後にやくざの生活が大きく変わっていく中で苦悩する桑原が描かれる。『破門』は十万部を突破した。
このシリーズはロードムービー的な色彩が強く、そこにはアメリカ、ヨーロッパ製の作品を中心に年間百五十本は見るという映画の影響が見て取れる。
さて、本書『後妻業』(二〇一四)である。これは黒川作品の背骨をなすノワールの大作である。直木賞受賞第一作として刊行された。黒川作品には、佐川急便事件、阪和銀行副頭取射殺事件等、実際の事件に想を得たものが少なくない。この『後妻業』も事件化こそしなかったものの、ある出来事が元になっている。
“後妻業”という言葉は、一部法律家の間では使われていたが、一般には知られていなかった。基本的には、妻に先立たれ一人暮らしをしている金持ちの高齢者と親密になり、内妻として公正証書を作らせたり、後妻に入って財産相続の権利を確保した後、何らかの方法で夫の命を縮めて財産を我が物にする生業をさす。
本書が出た後、それを地でいくような事件が発覚、複数の男性を青酸化合物で毒殺し、総額八億円とも言われる財産を相続した筧千佐子容疑者が逮捕された事件は、記憶に新しい。
黒川さんの知人である姉妹の九十代の父親に七十八歳の内妻がいた。父親が亡くなったとき、内妻は公正証書を出してきて「遺産をすべていただきます」と宣言したのである。驚愕した姉妹に依頼された弁護士が興信所に頼んで調べただけでも、内妻は何度も結婚を繰り返し、夫が次々と亡くなっていた。それでも警察が動くことはなかった。公正証書の効力の前に姉妹はなすすべなく、遺産の大半は内妻のものとなった。
その話を知人から聞かされたとき、黒川さんは「罪悪感もなく、次から次へと人を殺すて、どんな女なんやろ」と、その内妻の内面に強い関心を抱いた。
事の概要は聞いたが、内妻がどんな女性かは全く知らない。人物像を考えることから始まった。そして生まれたのが主人公の武内小夜子である。年は六十九歳、色黒で痩せている。派手好きで、老人を金づるとしか見ていない。金のためならばためらいなく命を奪い、罪の意識は微塵もない。その金をホストにつぎ込みセックスに耽溺する。
小夜子は結婚相談所を根城に、相談所の所長柏木亨と組んで再婚を希望する資産家の老人を物色する。そこで目を付けられたのが九十歳の中瀬耕造である。耕造に気に入られた小夜子は、耕造のマンションにベッドとドレッサーを送りつける。住民票移動にこの家具持込み、地域活動への顔出しは後妻業の必須三条件である。たとえ籍に入っていなくても内縁関係にあると周囲に印象付けるためである。
小夜子は、耕造が服薬している血液の抗凝固薬「ワーファリン」を胃薬にすり替えて病気を誘発させようとしたり、脳梗塞を起こした耕造を炎天下の公園に放置したりと、耕造の寿命を縮めようとあの手この手を使う。
狙い通り耕造は入院、ほどなく死亡する。預金四千万円、時価二千万円の株、不動産が六千万円、耕造の入院中からその財産を巡って騙し騙されの熾烈な争奪戦が繰り広げられる。
内縁の妻を主張する小夜子は、耕造の生前に法的な拘束力を持つ公正証書遺言を書かせていた。葬儀が終わったところで、耕造の遺族である二人の娘はその公正証書を見せられて仰天し、弁護士に相談する。
興信所の探偵、本多の登場によって、遺産相続の話は一気に事件の色を濃くしていく。弁護士の依頼により、本多は、元大阪府警マル暴担当刑事の経験と伝(つて)を利用して小夜子と柏木の過去を調べ上げる。小夜子の周囲では九年間で耕造も含めて四人が不審な死に方をしていた。
そこに金の匂いをかぎつけた本多。愛する女のために、まとまった金がほしかった。つかんだ事実を元に、小夜子と柏木から金を引き出そうとする。一円も出したくない二人、一円でも多く取りたい本多。欲にかられた人間たちの虚虚実実の駆け引き。金が動き、銃声が響き、血が流れる。黒川ワールドが一気に炸裂する。
人物造形の巧みさは黒川作品に共通する。中でも物語を牽引していく本多の造形が成功の鍵となった。むろん、これまで同様、麻雀はもとより、車や食べ物等に関する具体的な情報がさりげなくちりばめられ、物語に奥行きを与えている。
黒川=麻雀というイメージで捉えられがちだが、実は極めて多趣味で、将棋はアマチュアの有段クラス、料理はもちろん、動植物にも詳しい。かつてはカエルを数種類、百匹ほど飼育していたこともある。金魚とめだかとサワガニは今も育てている。羽曳野丘陵はタヌキの生息地として知られており、庭に餌を置いて、そのタヌキすら手懐(てなず)けているのである。家の中では、『疫病神』シリーズに登場し、すっかり有名になった十歳になるオカメインコのマキちゃんが「ピッピキピー」と飛び回っている。羽曳野にお邪魔すると、時々筆者の頭の上にマキちゃんが爪を立てるようにして止まる。動物は好きなほうだが、その度に貴重な髪の毛をわしづかみにして持っていかれそうで、気が気でない。
話がそれてしまった。黒川さんはいつもチノパンで、夏場はアロハシャツ、冬はTシャツにセーター姿で、髭面に葉巻をくわえている。百八十センチの堂々たる体躯に鋭い目付き。その姿で街を歩くと、どんなに混んでいても、彼の前に道ができる。しかし、強面の外見とは違い、その作品は細部まで周到緻密に計算されているのである。
そして特筆すべきは、人間に対する限りない愛情が物語の底流になっていることである。
「人を憎いと思ったことはあんまりない。むしろ、こいつはアホやなと、笑ってしまうことが多いな」という視点から描かれた人物たちは、それ故に、どんな悪人でも哀切と愛嬌を併せ持っているのである。「面白うてやがて哀しき」は、黒川作品のキーワードである。
『後妻業』は黒川ワールドの集大成と言っても過言ではない。人間の業の深さ、大阪弁の面白さ、疾走感を存分に味わっていただきたい。