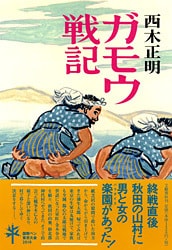深緑のブナ林は清々しい。白一色に凍てついたブナの森は神々しくさえある。だが、新芽が芽吹く直前のブナ林の美しさを、それまで私は知らなかった。
二〇〇二年の春、私は、新潟県と山形県の県境付近にいた。残雪の白と雪解けの茶、新芽の淡い緑によって、まだら模様を織りなすブナの森が、眼下には広がっていた。
麓の里から、硬く締まった残雪の上を歩きはじめておよそ三時間。決して楽な行程ではなかった。
登山道があるわけでもない山襞を、前を行くマタギの長靴がつけた踏み跡だけを頼りに、必死の思いで歩き続けた。
それにしても、マタギと呼ばれる猟師たちの健脚ぶりには、驚きを通り越して呆れてしまう。総勢で二十名ほどの一団の最年長は、とうに七十歳を過ぎた老マタギである。それなのに、二回り以上も若く、山歩きの経験もそこそこある私よりも、はるかに足が速い。
その昔、里の人々は、険しい山稜を縦横無尽に駆ける怪しげな存在を見て、天狗や鬼と畏(おそ)れ戦(おのの)いたという。おそらく山駆け修行の修験者のことだろうと、今までの私は考えていた。
だが、ここに至って認識を新たにした。里の人間に怪異と映った者の正体は、彼らマタギだったのではあるまいか。
そして、これ以上ついて行くのは無理だとあきらめかけたところで、ようやく到着したのが、マタギたちが「クラ」と呼ぶ猟場、クマ猟の谷だった。
彼らが行おうとしている猟は、冬ごもりを終え、越冬穴から出てきたばかりのツキノワグマを狙う「巻き狩り」である。
谷底に配置された勢子(せこ)たちが、「やーほうっ」「よーほうっ」という鳴り声をあげて、遊んでいる(マタギたちは、猟場にクマがいることを「クラで遊んでいる」とか「クラについている」と表現する)クマを峰の方へ、上へ上へと追い上げる。
一方、猟場を見下ろす稜線下では、猟銃を手にした射手たちが、ブナの木立に紛れて身を潜め、身じろぎひとつせずに、藪を割ってクマが現れるのを待ち続ける。
雪解けの季節とはいえ、立っているのは雪面だ。じっとしていれば、たちまち足下から冷気が襲ってくる。残雪を撫でて温度を下げた寒風が、露出している頬に突き刺さる。事実、あれだけ火照(ほて)っていた私の体も、三十分、一時間と待つうちに、歯の根が合わなくなるほど冷え切ってしまった。
ふいに、猟場の一角で黒い塊が動いた。私が立っている稜線からは、せいぜい豆粒ほどにしか見えない大きさだ。直線距離で二百メートルはあるだろう。が、紛れもなく野生のツキノワグマが、マタギたちの包囲網から逃れようとして山肌を駆けている。
血が騒いだ。逃してなるものかと思った。あのクマをなんとしても仕留めてくれと、マタギたちに向かって心の中で叫んでいた。クマに対する憐憫(れんびん)は微塵(みじん)もなかった。ただひたすら、狩猟という行為がもたらす興奮に身が震えていた。
そして、この時こそが『邂逅(かいこう)の森』というマタギ小説を、世に送り出すことができると確信した瞬間だった。
ところで、厳密に言えば、現代の日本にマタギはいない。猟のみで生計を立てることは、もはや不可能な時代になっているからだ。だから、私がマタギと言っている彼らは、ふだんは会社員だったり、公務員だったり、あるいは農業や林業を営んでいる、ごくふつうの人々である。一般人との違いといえば、乙種の狩猟免許を所持していて、猟期になると仕事の合間に猟銃を手にする、いわゆるハンターと呼ばれる人種である、ということだけだ。
したがって、猟をせずとも彼らが飢えることはない。生活が立ち行かなくなる心配もない。しかも、環境保全や自然保護、あるいは動物愛護が声高に叫ばれる昨今、どちらかといえば、肩身の狭い思いをしながら猟をしている。なのに、彼らは、自分たちはマタギであると胸を張り、単なるレジャーハンターとは違うのだとも言う。
正直、それは詭弁(きべん)にすぎないと、私は思っていた。自分たちの猟を正当化するための言い逃れではないかと、意地の悪い見方をしていた。だから、この作品を書きはじめつつも、自分の中には迷いと疑問があった。今の時代に、マタギ小説を書く意味が果たしてあるのだろうかと、不安を抱えながらの作業が続いていた。
そんな折り、取材で入り込んでいたマタギ村の頭領から、クマ猟の同行の許可が出た。おそらく、私の迷いや逡巡を見抜いていたのだろう。あるがままの現場を見て、感じた通りのことを書いてくれればそれでいいと、酒を酌(く)み交わしながら穏やかに笑った。
その結果、野生の動物を追い、自らの手で仕留める興奮と快楽が、狩猟の本質であることを知った。同時に、それによってこそ彼らが生かされていることや、絵に描いたような山間僻地の小さな村に踏み止まり、山と共に暮らしていられることも、私は知った。
彼らに流れる狩猟民の血は、実は、都会に暮らす我々の中にも、等しく眠っている。それが時として暴れだすと、手に負えないものとなり、社会生活の破壊者となってしまう。だが、猟により、その血を解き放つ経験を蓄積しているマタギたちは、人間に潜む野性や獣性、そして欲望を制御する術(すべ)も知っている。
山に入ったマタギは、同じ人間とは思えないほど、里にいる時とは顔が変わる。存在そのものが変容する。そんな人間の生の姿を、私は『邂逅の森』という小説で描きたかった。