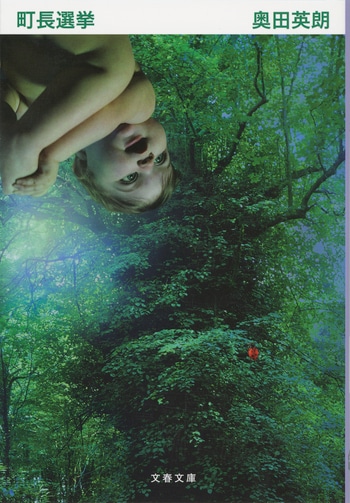読者がどこまでついてくるか
――『野球の国』とか『延長戦に入りました』のように、奥田さんの著作には小説と別にスポーツをテーマにしたエッセイがありますが、今後も書いていきたいと思っていますか。
奥田 そうですね。あれはね、自分を笑う場を持っていたいと……自分を笑うと楽なんですよ。『野球の国』を書くことで、作家奥田英朗が構えないで済むというか。恰好つけると先が苦しいんです。最初にデヘヘというところを読者に見せておくと、あとが楽。なんだ、トロいやつじゃないか、と。
――『最悪』や『邪魔』で読者がイメージする奥田英朗像みたいなものがあると思いますが、それをそんなことはないんだ、と言ってみたいのでしょうか。
奥田 どこかでね。別に計画的にやっているわけではないのだけど、たぶん読者を篩(ふるい)にかけているところがあるのかもしれませんね。どこまでついてくるか、というような。だから毎回作風が変わると言われるのは、無意識のうちにこれも自分なんですけどどうですか、というプレゼンテーションをしているんじゃないかと思います。
――同じ物を書いていると飽きてしまうということもあるのでしょうか。
奥田 それもありますね。常に何か違うことをやりたい、新しいものにチャレンジしたいと。ただ根っこの部分は全部一緒なんですよ。変わるのは表面的なものだけで。
――奥田さんの中で、こういう読者に読んでほしいという希望はありますか。
奥田 僕は、普段あまり小説に馴染んでいない人に読んでほしいのだけど……。小説を読まない人って、つまり作り事の世界に入っていけないわけでしょ。ミステリーなんかでも、一介のOLが殺人事件の捜査を始めるというのはあり得ないだろ、とか(笑)。最初のお約束事というか、台みたいなものがあるわけですよね。その上に上らない人というのは、どうしようもない。僕の場合、そういう約束事がない小説。町の喧嘩だから、派手ではないけど、迫力だけはありますよ。
――今、こういうものを書いてみたい、こんなことに関心があるというのはありますか。
奥田 そろそろ長いのを書かないとまずいな、というのはあるんですけど(笑)。長篇を書いていると自分自身のエクスタシーもありますしね。一千枚クラスを書くと、途中から勝ったと思える瞬間があるんです。ここまで引っ張ってきたから、あとは何をやっても自由だろ、というような。そういうのは長い小説でないと味わえない。
――もう少し具体的に言うと。
奥田 僕はプロットを立てられないから暗中模索で書いていくんですけど、微に入り細に入り描写していき、エピソードをどんどん積み重ねていくと、あるとき巨大な石がゴロンと動く瞬間があるんです。あ、動いた、という。それが嬉しいです。一回動くとあとはどんどん動いていく。それまでは怖いですよね。これ動く? 動かなかったらどうしよう、と。いろいろあっちを押したりこっちを押したりしているうちにゴロッと動くところがあり、あ、ここだ、となる。他の作家もそうだと思いますけどね。最初から動くと分かっていて書く人はそうはいないと思います。いかにプロットを立てたとしても、物語の勢いというのはまた別だから。
――ラストがしっかり決まっていて書き始める方もいらっしゃいますけど、そうでもない。
奥田 ラストなんかまったく決まってないです(笑)。残りがあと五十枚くらいまできてもラストが決まっていないこともザラですから。