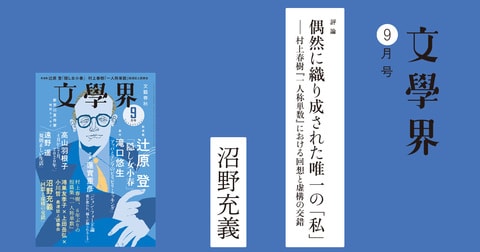村上春樹の『意味がなければスイングはない』は、十章構成で十一人の音楽家(演奏家・作曲家と楽曲)について、レコードやライヴなどでの極私的体感をもとに綴っている。それはクラシックからジャズ(かつてジャズの店をやっていたのだから当然か)、ロック&ポップス、フォーク、Jポップと多岐にわたっている。彼は美味しいところのつまみ食い的な聴き方といった感じの言い訳をしているが、その実、かなりのマニアック指向と思わせる聴き方をしているようである。そこからは、村上春樹の音楽的興味の彼方にいかにも「作家だな」と思わせる音楽への惹かれ方と物語(ミュージシャンの人生)への関心とがみえてくる。
音楽評論に関わる者にとって、これだけ突っ込んだ原稿を「書く場」を確保できたことに羨ましさを感じつつ、彼の音楽体験の発露に、多くの点で「そうなんだよな」と共感し、うなずいてしまう。かつて低血圧の文体といった印象があった彼の文章が、妙に血圧の高い文体で音楽を語っているだけに、「その気になって」音楽と向かい合ってきたのだなと納得。
ここでは、『意味がなければスイングはない』で村上春樹がマイ・フェイバリット・アルバムとして挙げている村上流決定盤を「読み、聴く」うえでの蛇足的なガイドをしてみよう。
まず、ジャズ・シーンでほとんど注目を浴びることのない「存在感の薄いピアニスト」、シダー・ウォルトンへのこだわりを語ることから本書は始まる。七四年十二月に新宿・伊勢丹の駐車場ビルのそばにあった〈ピットイン〉で、二十五歳の村上はシダー・ウォルトンとベースのサム・ジョーンズ、ドラムスのビリー・ヒギンズというトリオ編成での演奏を聴いている。「生の演奏を聴いてみなくちゃわからないものだ」と村上が実感した「ホットで鮮烈」な演奏は、シダー・ウォルトンが意外なほどファンキーで黒っぽく感じられる『ピット・イン』(East Wind PHCE‐2036)に収録されている。

七〇年代のシダー・ウォルトンで村上がもっとも愛聴しているのが、オスカー・ピーターソン・トリオのベーシストとして有名なレイ・ブラウンの七七年のリーダー作『サムシング・フォー・レスター』(Contemporary VICJ‐60789)で、ドラムスのエルヴィン・ジョーンズにシダー・ウォルトンというこれも正統派のトリオ編成での演奏である。花形プレイヤーを向こうにまわして臆することなく見事な呼吸でピアノを弾いているウォルトン。「ウォルトンを加えたピアノ・トリオで録音したいという希望をレコード会社に持ち込んだのはリーダーのレイ・ブラウン」だという。共演したミュージシャンが評価するピアニストであり、かなり通好みの渋いピアニストがシダー・ウォルトンである。
次は六〇年代のアメリカン・ポップスの象徴となったビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソン物語である。同時代に発表されたビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』への絶賛ともいえる評価、それに比べてブライアンがリーダーとして作りあげたビーチ・ボーイズの『ペット・サウンズ』(Capitol TOCP‐66031)は、ビーチ・ボーイズ内部のマイク・ラブに「犬に聞かせる音楽」とまで酷評される(グループ内での対立もあってのことだが)。六六年当時は、難解なポップスといった印象で、大方の評価もそれに近いものだった。いまではビーチ・ボーイズの歴史的名盤とまで再評価されているアルバムだが、既成のポップ・ミュージックからサブ・カルチャーへと移り変わろうとしていた時代の気分を反映したロックが台頭していた頃には、そんな評価しかされなかった。時代は「ロック・ミュージックという音楽領域が生みだした天才の一人である」ブライアンに残酷な仕打ちをした。
ブライアンへの追悼かと思えてくるこのブライアン・ウィルソン物語の背後に流れているのが、未完のアルバムとして有名な『スマイル』である。ビーチ・ボーイズを語るときに常に鍵となるこの未完の名作(?)『スマイル』に収録される予定だった曲を多数含む六七年発表の『スマイリー・スマイル』(Capitol TOCP‐53171)を聴き、ブライアンが目指した世界を想像しつつ読んでもらいたい。一歩踏み込んだポップス・ファンなら、同時代にアメリカン・ポップスのサウンドを完成させたウォール(滝)・オブ・サウンドのプロデューサー、フィル・スペクターに通底する悲しさを、そこにふと思い浮かべるかもしれない。ワーグナーのサウンドのようにポップスを構築したスペクターに感じる頑強なエゴの対極にブライアンを置いてみることも可能だろう。
第三はシューベルトの「ピアノ・ソナタ第十七番ニ長調」D.850である。実はこの曲、魅力的とは言いがたいものである。「他人に聴かせても長すぎて退屈されるだけだし、家庭内で気楽に演奏するには音楽的に難しすぎるし……」という曲である。なんでこんな曲をシューベルトが書いたのか? その謎解きと、村上がこの曲を好きになったきっかけが語られる。「音を素手ですくい上げて、そこから自分なりの音楽的情景を、気の向くままに描いていける。そのような、いわば融通無碍な世界が、そこにはある」という。まるでニューエイジ・ミュージックを聴くかのようにシューベルトを聴く村上の姿がうかんでくる。村上がピアノ・ソナタ第十七番を好きになったきっかけのユージン・イストミンのレコードは、実はCD化されていないのである。
あまり録音されることのなかった七〇年以前、再評価の気運が高まってからの七〇~九〇年、再評価されてからの九〇年以降の現代のものとに分類して紹介し、村上の好みの演奏を挙げている。現代のものでは、ノルウェイのピアニスト、レイフ・オヴェ・アンスネスの二〇〇二年録音の『シューベルト:ピアノ・ソナタ第17番&9つの歌曲』(EMI TOCE‐55568)を「演奏の根幹にあるシンプルでストレートな世界観と、それをひるむことなく提示する若い志のようなものを、高く評価したい」という。初期の演奏では、シリアスでストイックなシューベルトを聴かせる英国のピアニスト、クリフォード・カーゾンの六四年録音の『シューベルト:ピアノ・ソナタ第十七番/楽興の時 他』(Decca UCCD‐7141)を、「ひとつひとつの音が言葉を持ち、ひとつひとつの楽章が物語(ナラティブ)を持ち、それらの物語が集まって、無理なく、ゆるやかに総合的な世界が作られていく」と語っている。