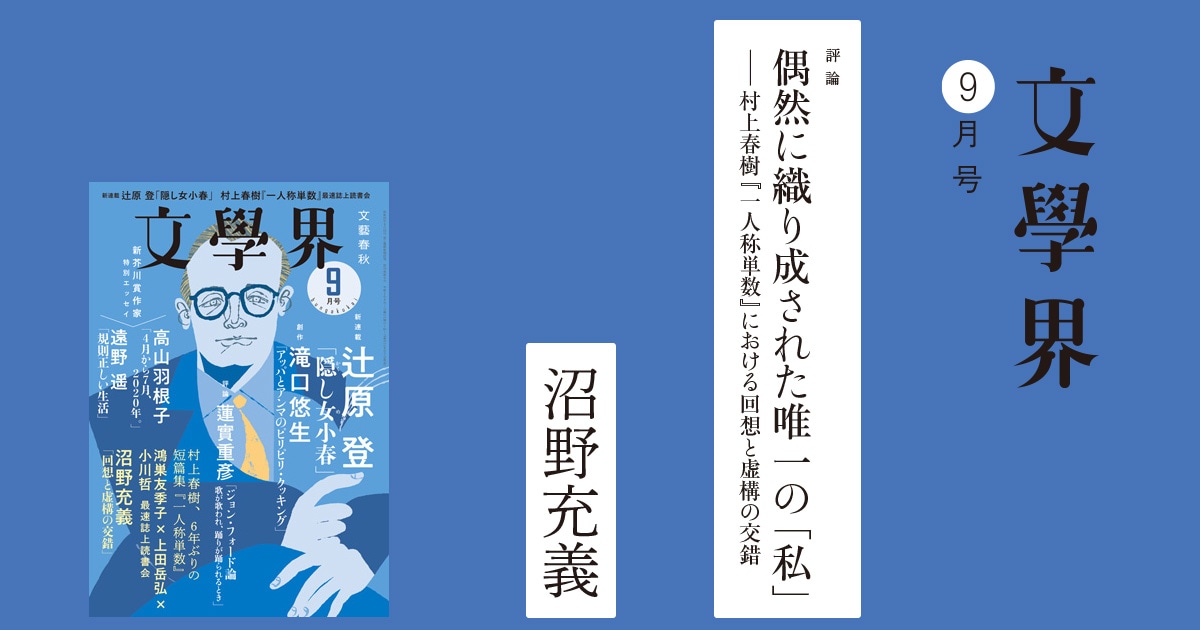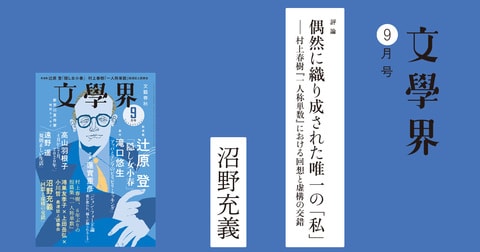前篇はこちら
自伝的回想とフィクションの交錯――『猫を棄てる 父親について語るとき』はノンフィクションなのか?

ここまで『一人称単数』の七編の作品について、やや詳しくそれぞれの内容に即して、フィクションと一人称の回想モードの交錯について見てきた。短篇集を締めくくる八番目の表題作「一人称単数」は毛色の違った作品なので、しばらく措いておき、ここで視点を変えて、同時期に並行的に書かれ、出版されたノンフィクション(であるはずの)自伝的回想『猫を棄てる 父親について語るとき』(雑誌初出『文藝春秋』二〇一九年六月号、単行本二〇二〇年)を取り上げ、『一人称単数』と比較してみたい。
「猫を棄てる」という表題は、「僕」がまだ小学校の低学年で、夙川(兵庫県西宮市)の家に住んでいたころ、父親の自転車に乗せられて、いっしょに香櫨園の浜に猫を棄てにいったというエピソードから取られている。そして、村上は、父が子供時代に親に「捨てられる」ようにして、奈良のどこかのお寺に小僧として出されたことを思い起こし、その経験が父にとって深く残る心の傷(トラウマ)になったのではないかと推測し、父と一緒に猫を棄てにいった経験と結びつける。猫のモチーフは、もう一度、この作品を締めくくる最後にも現れる。子供時代の思い出の一つで、白い子猫が松の木に登ったまま下りられなくなったというものだ(村上はこれを一度、「どこかの小説の中に」書いたのだが、今度は「ひとつの事実」として書く、と断っている)。村上は子猫が高いところで木の枝にしがみついたまま死んでひからびた様子を想像し、「降りることは、上がることよりずっとむずかしい」という――珍しくストレートな――教訓を導き出す。これは現在の作家として名声の階段を昇りつめた村上自身の心境であるのかもしれない。
こんな風に、明らかな「物語的」構成がこの回想には施されているのだが、その一方で、目を引くのはやはり、父親の複雑な軍歴が――著者自身がかなり綿密に調査した成果を盛り込んで、自分が誤解していたこと(つまり自分のうちで「誤った物語」になっていた部分)を修正しながら――詳細に跡付けられていることだ。著者は父親が、南京陥落の際に一番乗りをした、悪名高い歩兵第二十連隊に所属していたと思い込んで、「ひょっとしたら父親がこの部隊の一員として、南京攻略戦に参加したのではないか」という疑念を抱いていたために、父の死後五年あまりも調査に着手することができなかったのだという。そういう事情があったと分かると、村上春樹の南京事件への特別なこだわりも理解しやすい。『騎士団長殺し』では、登場人物の一人、免色の口を通じて、南京での日本軍による行為について、かなり踏み込んだ発言が行われている。
もっとプライヴェートな、家庭内での人間関係の次元に目を転じてみると、『猫を棄てる』では特に父と「僕」の間の長年にわたる性格の不一致からくる確執が生々しく語られている点が目を惹く。九十歳を迎え、病気のために死にかけた父を病院に見舞った息子との間では、ぎこちない会話が交わされ、「和解のようなこと」が行われたとあるが、こういった父子の関係は、『1Q84』の読者にはすぐに、天吾とNHKの集金人であった父との関係を思い出させるだろう。『猫を棄てる』はこのように読むと、自伝的回想でありながら、そこで語られる素材の重要な部分が村上のフィクションに取り込まれ、利用されてきたことが跡付けられる。また、父親の家庭での姿に限って言えば、『一人称単数』の「「ヤクルト・スワローズ詩集」」に出てくる熱烈な阪神ファンであった父の姿や、亡くなる直前の父との「ささやかな和解のようなもの」は、『猫を棄てる』における父に関する記述と完全に一致していることがわかる。