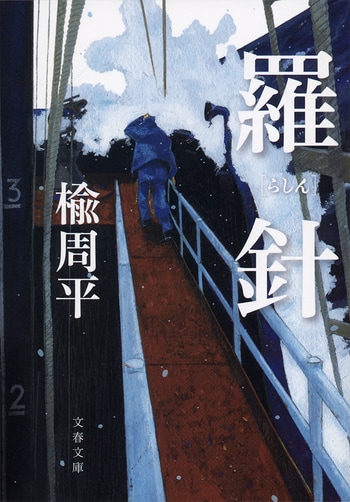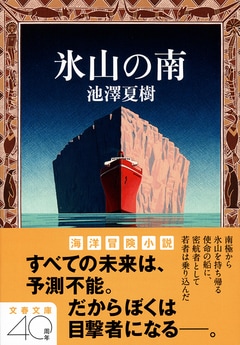板子一枚下は地獄という。船乗りの仕事はそれだけ危険と裏表ということで、序盤はそうした海の男の宿命や荒海の怖さがありありと描き出されるが、もうひとつ注目すべきはその道を選んだ関本源蔵の生きかた。実は彼は好きでこの道を選んだのではなかった。父親の仕事の都合でサイパンに生まれ育った彼は、太平洋戦争の開戦とともに帰国せざるを得なくなる。その帰途、米潜水艦の魚雷攻撃にさらされながらも何とか生還するが、父親は島で亡くなってしまう。かくして彼は帰国後苦労して自分たちを育ててくれた母親の助けになるべく、給料が図抜けていい船員を目指すこととなった。
長男である源蔵は父親のいない家庭でその替わりを務めざるを得なかったが、父親としてどう子供と接したらよいのか、身をもって知ることが出来なかったため、はっきりとした父親像というものをつかんでいなかった。その欠落は息子秀俊との軋轢が顕在化する後半、彼を悩ますことになるのだ。
いっぽう、後半の舞台は南氷洋へと転じる。南氷洋での漁業といえば捕鯨だが、栄進丸での出来事があってから一〇年余、源蔵は捕鯨船団の母船・大鷹丸への乗船が決まる。同じ頃、彼は就職のツテを頼ってきた町の若者、枝川敏雄に捕鯨船に乗るよう奨め、会社に斡旋していたが、自らも同じ船に乗ることになる。ひとつの仕事に落ちつけない敏雄が逃げ場のない船の生活に溶け込めるか、源蔵は心配していたが、一九七三年一一月二五日に無事出港。その後の航海も順調にいった。
敏雄も程なくキツい作業に馴れたようだが、源蔵に自分が田舎の貧しい百姓の家に生まれたことにコンプレックスを抱いていると話す。彼は無名の大学を出たところでロクな就職も出来やしないと学校を中退、半分自棄になっていたが、その反面、いずれは独立して起業する夢も見ているようだった。やがて船団は赤道を越えて漁場に到着、甲板での鯨の解体、保存作業が続く日々が始まる。敏雄はその過酷な労働環境を小林多喜二のプロレタリア文学『蟹工船』にたとえて源蔵を驚かせるが、職場での仕事ぶりは真面目で、上司の話では鯨が噴き上げる潮――「ケ」を見つける目を持っているとのことだった。だが、獲物がイワシ鯨からナガス鯨へと変わってから五日後、船内で事故が起きる。自分にその責任の一端があったと敏雄は意気消沈するが、そのさらに五日後、第三栄潮丸というキャッチャーボート(捕鯨船)の機関長が急病になり、源蔵が代役を務めることに。彼は敏雄も一緒に連れていくが、やがて大時化が彼らを待ち受けていた――。
この捕鯨劇では、何といっても南氷洋における当時の捕鯨の実情がダイナミックに描かれているところにご注目いただきたい。日本では有史以前から各地で独自の技術で捕鯨が行われてきた。江戸時代には鯨組という大規模な組織捕鯨が行われ、鯨を捕獲したのち銛で突くという網かけ突き取り法も開発された。明治時代に入るとさらに欧米の捕鯨技術が導入されて南氷洋に進出、イギリスやノルウェーとともに主要な捕鯨国となっていった。しかし次第に資源が少なくなり、操業も徐々に縮小されていく。七〇年代前半には「捕獲頭数、漁期共に国際協定によって厳密に制限されて」いて、「捕獲した鯨についても、資源調査の資料とするための計測」が義務づけられていたのだ。
様々な約束に縛られながらの操業だったわけだが、源蔵たちが第三栄潮丸に乗り移って初めて捕鯨現場を目の当たりにするシーンは、そんな窮屈さを払拭させてくれるに違いない。捕鯨反対者にはちょっと血腥いかもしれないけれども、銛を打って鯨を仕留める砲手とて「好きで鯨の命を奪っているわけではない」。著者も、彼が「自らが葬った鯨に手を合わせ、しばらく拝むような仕草を」するところをちゃんと描いている。