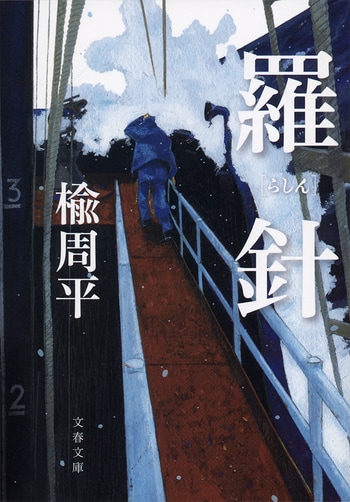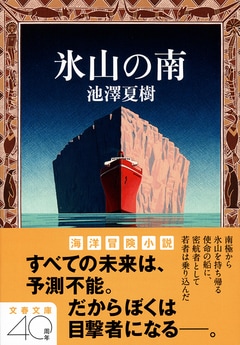そして北洋漁業のときと同様、源蔵たちが再び大自然の脅威にさらされるシーン。気温は氷点下、「ブリッジ直下から船首にかけての甲板は、氷で覆い尽くされている」。しかも風速二〇メートルを超える強風下、大きな山を上り下りするように波を乗り越え進んでいく第三栄潮丸。彼らはしかし、そんな中でも鯨を捕えることをやめない。ついにはスクリューに異常をきたして立ち往生してしまうが、ただ身動きが出来なくなるだけではない。船の周りをパックアイスで埋め尽くされると氷に閉ざされ、助けようにも他の船が近付けなくなってしまうのだ!
おおこれは、舞台も状況も異なるけどまるで『女王陛下のユリシーズ号』ではないか。冒険小説ファンとしては感激の嵐である。『女王陛下のユリシーズ号』とはもちろんイギリス冒険小説の巨匠アリステア・マクリーンの不朽の名作で、してみると本書は対自然サバイバルを描いた正統派の海洋冒険小説としても読み応え充分というべきか。
考えてみれば、著者のデビュー作は『Cの福音』という冒険/ハードボイルド小説系のピカレスクアクションだった。それをスタートにやがて歴史ファンタジーから謀略小説、経済小説へと創作活動を広げていく。いいかえればひとつのジャンルに収まらない、クロスジャンル系のエンタテインメント作家ということである。本書も水産業という側面から戦後日本の軌跡をとらえた経済小説というひとつジャンルに収まっていないのは明らかだろう。
それはまた、捕鯨劇における源蔵と枝川敏雄の関係描写からもうかがえる。源蔵の長男秀俊は高校生になり大学受験を控えていたが、自分の進路については何も語らず、源蔵を苛立たせていた。それは彼が南極海へと旅立つ直前、小さないさかいとなって噴出、彼は心に悔いを残したまま乗船する羽目になる。その後彼は船上でたびたび敏雄と会って話をするが、なかなか噛み合わない。自分に歯向かうようなことをいう敏雄の姿に、彼は秀俊を重ねて見るようになる。敏雄はだが、捕鯨体験を通してたくましく成長していき、彼もその姿を見て、改めて羅針としての父親の自覚に目覚めることになるのだ。
源蔵と敏雄の疑似父子劇は、下降線をたどり始めている水産業界への挽歌としても捕鯨劇と呼応していよう。源蔵は「仮に、捕鯨がこれから先も存続できることになったとしても、若い乗り手が現れなければ、漁そのものが成り立たなくなる。おそらくそれは捕鯨だけじゃない。漁業、農業、林業と、日本人の生活を支えてきた産業のことごとくがそうなってしまうんじゃないのかな」と悲観的なセリフを吐くが、だからといってただそこに身をまかせることはしない。捕鯨船に乗った後は機関長への昇進が決まっていたが、会社はすでに水産事業と海運事業を分割して別事業化することを決定、源蔵は最新技術が学べる海運事業会社のほうに進むことになっていた。彼自身、新たな時代の到来に前向きな身の振りかたをちゃんと選んでいるのである。
水産業の端境期をとらえた経済劇と父子の世代交代劇。著者は捕鯨や氷上のサバイバルでハラハラドキドキさせつつ、戦後社会の変化をも多彩な物語で紡ぎ出してみせた。
著者は本書のほかにも、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京』シリーズや文春文庫収録の『骨の記憶』で戦後社会の内幕やそこに生きてきた人々の軌跡を描いてきた。一九六四年の東京五輪は高度経済成長の象徴となったが、二〇二〇年には二度目の東京五輪開催が決定、次の五輪は日本社会の何を象徴することになるのだろうか。著者には時代の最先端を描くクロスジャンルのエンタテインメントに挑むと同時に、今後も高度成長期のバックステージものを継続させていっていただきたいと思う。