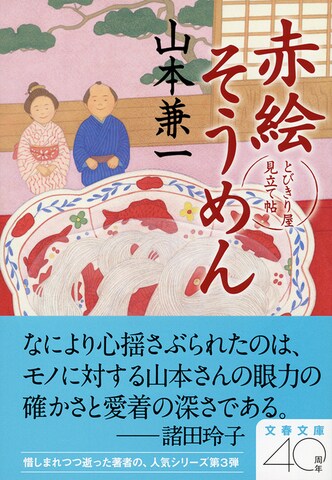ここに一枚の写真がある。
写真の一方の端では、スタンドマイクを前に私がしゃべっている。目線の先、反対の端には山本兼一さんがおられる。両手を胸元で合わせてすくりと立っている姿は少し緊張しているようにも見えるが、照れくさそうに微笑んでいる横顔には誇らしさと幸福感がにじみ出ている。
山本兼一さんは二〇〇九年一月、『利休にたずねよ』で第140回直木三十五賞を受賞された。写真はその授賞式のあとの、銀座の某レストランにおける祝賀会のヒトコマである。
二〇〇四年に『火天の城』で松本清張賞を受賞され、同作品が直木賞の候補になって一躍時の人として脚光を浴びてから五年、直木賞受賞は候補三度目の快挙だった。デビューが一九九九年だから順調にひとつの頂点を極めたわけで、それだけ実力が横溢していたあかしである。かたわらを颯爽と駆けのぼってゆく山本さんを驚嘆の目でながめていた歴史・時代小説作家達が、やっかむどころか、こぞって祝賀会に集まり、我が事のように喜んでいたのは、山本さんの生真面目で謙虚で温かなお人柄によるものだろう。
私は、松本賞を受賞される前にお会いしている。京都に仕事場を構えている先輩作家の安部龍太郎さんに案内していただいて、上七軒のお茶屋にいったときだった。地元の作家仲間、と紹介された山本さんは寡黙で温厚な方で、このときはあまり個人的な話ができなかった。感じのよい人、という他は印象に残っていない。
ところが、ほどなく山本さんからご著書が贈られてきた。『戦国秘録 白鷹伝』という小説で、私が御鳥見役を主人公にした連作を書いていると話したことを覚えていて下さり、「ご参考になればと思い、お送りいたします」と丁寧なお手紙が添えられていた。初対面の、さほど懇意でもない私のために、役に立てばとご著書を贈ってくださる心配りは、長年、編集者やライターをしている間に培われたものかもしれない。もちろん、生来のやさしく細やかな性格があればこそ、である。
これをきっかけに、互いの著書を贈り合ったり、パーティーで立ち話をしたり、というおつき合いがはじまった。といっても、京都在住でいらしたのでお会いする機会はめったになかった。そもそも作家同士は、対談の企画でもなければゆっくり話ができない。それでも、贈っていただいたご著書の数々を拝読して、私は山本さんの活躍を身近に感じていた。綿密な取材と徹底した勉強に基づいた歴史小説、心血をそそがれた作品はいずれも重厚で、よくぞここまで……と拝読するたびに感嘆させられたものである。