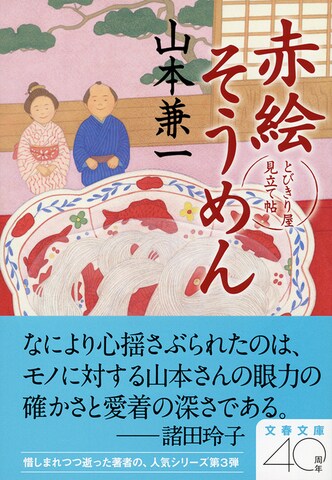真之介が大切にするのはモノだけではない。人との縁、とりわけゆずとの夫婦愛は読者の胸に温かな灯をともしてくれる。お会いしたことはないが、山本さんご自身も、きっと真之介とゆずのような愛情あふれるご家族に囲まれていらしたのだろう。
山本さんと最後にお会いしたのは、昨年末、二〇一三年の十二月だった。パーティーの席上で立ち話をした山本さんは、いつものようにひかえめにたたずみ、柔和なまなざしでにこやかにお話をして下さった。が、いかにせん、お顔の色が悪かった。このときはもう病気のことを聞いてはいたが、『利休にたずねよ』の映画公開に先立ち、モントリオールまでいらしたともうかがっていたから、「あれ、どうしたのかな」と首をかしげただけで、さほど深刻には考えなかった。年明け早々、共通の担当者から入院なさったと教えられたときも、二月にはいったん退院なさると聞き、お見舞いもしないまま、今ごろはもう元気に書いていらっしゃるかなァなどと暢気な想像をしていた。
そんなわけで、ご逝去の報は青天の霹靂だった。私だけではない、山本さんの友人知人は皆、茫然としたはずだ。
今、もう一度、本書を読み返してみると、山本さんが引用されている「人生別離足る」という言葉がひとしお身にしみる。珠玉の六篇はどれも傑作ぞろいだが、「笑う髑髏(しゃれこうべ)」の中の文章はなにより胸に迫る。
真之介が寝ころがって髑髏をしげしげと眺めている場面だ。「人は死ねば髑髏になる」と感慨にふけり、「生きているあいだに、頑張れということや」と述懐する真之介。
短期間に傑作の数々を生みだし、病床でも死の間際まで書きつづけていたという山本さんの生涯は、まさに「頑張り抜いた人生」といえるだろう。
「死んでもこんなに笑うていられるのは、よっぽど満足して生きたからや。人間は、こうありたいもんやで」
真之介の台詞から山本さんのお声が聞こえてくるような――。
早すぎる死が悔しい。悲しくてやりきれない。でも私は、真之介のこの台詞を胸に刻んで、山本さんの柔和なまなざしだけをいつまでも心に留めておこうと思っている。
山本兼一さんの分身である本書を、読者の皆様が堪能し、宝物にして下さることを祈って……。