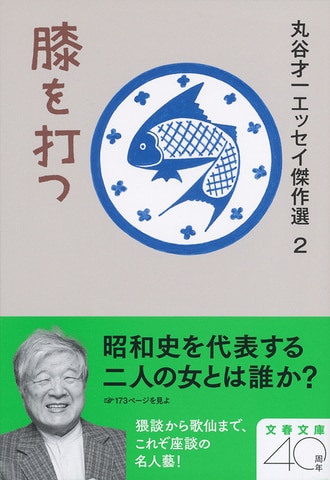のっけから妙なことを書く。わたくしは丸谷さんが喜寿を迎えたとき、ごく簡単な祝宴で挨拶をさせられた。このとき丸谷さんを見習ってあらかじめ話すことを原稿用紙に書いて、それを読むような読まざるような形でお祝いの言葉を述べた。それが手もとに残っているので、あらためてここに書き写すことにする。つまりわたくしの丸谷才一論である。
《いまを去ること七年前、古稀になられた丸谷さんから我々は大料亭に招かれ大そう御馳走になりました。こんど丸谷さんの喜寿をお祝いしてそのお返しをさせて戴こうという趣旨でありますが、そも喜寿とは何のことでありましょうか。
古稀はわかるんです。杜甫の詩に由来をもちます。「朝(ちょう)より回(かえ)りて日々春衣を典じ/毎日江頭酔を尽くして帰る/酒債尋常行く処あり/人生七十古来稀なり」これであります。何でもかんでも質に入れ、大いに酔っぱらって、あっちを向いてもこっちを向いても酒代の借金ばかり。これが尋常の日常になってしまった。しかし、わしも七十まで生きることはできんのじゃ、わしが余生の楽しみを許し給え。
たいして喜寿は喜の草書は七十七と読むことができる。そこからきた賀の祝い、ということぐらいは私にもわかる。が、それ以上のことはわからない。そこで『大言海』を引いてみると、その長寿ならんことを祝って、もともとあった四十、五十、六十、七十、八十、九十、百の賀に加えて、「足利時代の末より、六十一歳(本卦回・還暦)、七十七(喜寿)、八十八(米寿)なども起これり」とあるだけでありました。やっぱりわかっていなかった。
ま、古稀にくらぶれば目出たさも中くらいなり、というところでありまして、お返しの会が大料亭にくらべれば大分落ちますが、そんなわけでありまして、丸谷先生、どうぞお許し下さい。
さて、こんなどうでもいいことを喋って終りにしようかとも思ったのでありますが、そうもまいりません。それで昨夜、もう一度泉鏡花賞にかがやく『輝く日の宮』を読み直そうかと思ったのですが、老来すぐに瞼が落っこちてしまうので、とても無理と考えて、そこで久し振りに、まあ短い『横しぐれ』を読むことにしました。いやあ、傑作ですね。父と国文学の恩師と、種田山頭火との、伊予・道後の一日の関係を探索する。丸谷さんならではの文学の面白さ、かなしさがあざやかに表現されている。山頭火の奇矯な人物像を炙(あぶ)り出すために、幾重も罠のように仕掛けられた小説的趣向は、まるで推理小説を読むようでありました。
と、同時に、横しぐれの一語を起点に、時雨にふれる短歌や俳句の日本的感受性の世界の奥へと尋ね入っていくのです。そして「しぐれ」という言葉には、「死暮れ」という意味がこめられているのではないか、という言葉遊びをやるあたりから、急速に死の世界があらわれて、死に憧れたこの放浪の俳人のイメージが定着していく。その藝たるや、見事なものですねえ。
まさしく知的な遊びの面白さなんですが、その面白さは謎解きのスリルなんかじゃないのです。むしろ美的な論理の構築の面白さというもののようでした。どうでしょうか、皆さん。これはまた『輝く日の宮』の面白さに通じていませんか。私の勝手読みかもしれませんが、昨夜は『輝く日の宮』へと大きく華ひらいた『横しぐれ』の面白さの発見に、しばし興奮して眠れなかったといったら嘘のように聞こえるでしょうか。
それにしても丸谷さんの、男性自身的にはどうか知りませんが、文学的な若さにはほんとうに驚かされます。心からの讃辞を呈するために、私は丸谷さんがかつて書かれたある一文を、ここに皆さんにご紹介してみたい。それは「慶応三年から大正五年まで」という短い、夏目漱石について書かれた文学エッセイなんですが、そのいちばん最後の結びの部分です。
「彼は、偉大な知識人でありながらしかも優れた小説家であつて、つまり一文明の知的指導者であつた。かういふ位置を、彼ほど長い期間(おそらく今日まで)保ちつづけてゐる文学者はほかには見られないのである。ここには、小説家の社会的機能としての、いはば理想的な形がある」
どうでしょうか。この「彼」を丸谷と置き換えてみれば、そのまま丸谷才一論の結びになるのではないでしょうか》
以上が私の祝辞というか挨拶であったが、どうも性来の胴間声に加えて発音明瞭ならざる喋り下手もあって、多くの人に感銘を与えるというわけにはいかなかったようであった。私なりに丸谷さん直伝の文学的趣向の限りをつくしたつもりであったのに、それが解ってもらえず残念な想いを噛みしめていたら、当の丸谷さんからは、「半藤さん、キミのいい藝をみせてもらいました。とても気持がよかった」といわれたのである。これで気をとり直したことを、いまもありありと思いだせる。のみならず、こっちもすこぶるいい気分になり、その後の酒のうまかったことも覚えている。
*
対談集の解説のはずなのに、てんで解説になっていないじゃないかと叱られそうであるが、これでもかなり意識して座談の名人といわれた丸谷さんの対談の味わい方をそれとなく語っているつもりである。それに、そもそも文庫に解説不要論者なのである。が、やっぱりここはきちんと居住まいを正して本書の魅力について説かねばならないか、と思うのではじめると――。
まずは、丸谷さんの対談・鼎(てい)談の心得の条を聞こう。
「相手がよくなくちやできない。なかにはどんな相手でも平気な人がゐるかもしれないが、わたしはさうではない。
じつくり語り合はうといふ気のない人や、荒つぽい人はもちろん苦手だが、それだけではなく、論理的な精神に欠ける人、用語の明確ではない人も、閑談の相手には向かない」(『言葉あるいは日本語』構想社刊「あとがき」より)
これを逆にいいかえると、対談の相手となる丸谷さんその人が文学的感受性に恵まれ、思考に長(た)け、表現の明確な人ということになる。そのような人がぴたりと呼吸が合う相手を選んで語り合うというのであるから、その対談はすべて高みと面白さと香気をめざしてどんどん話が広がっていく、という読者にとってはこよなく読みごたえのあるものとなるのは当然である。
とにかく丸谷才一という小説家は座談の達人であり、その挨拶は滅法面白い、というのが定説になっている。では、その特色を説明するとなると、寿司の大トロの味を言葉で説明するみたいなもので、曰く言い難しということになる。そこを敢てするなら、この小説家は稀にみる教養人ということをまず挙げなければなるまい。ところがこの教養人はそこが教養ある所以(ゆえん)とするのであるが、決してその教養をひけらかしたりはしない。そもそもがひけらかしては教養にならない。読むほうは鼻白むだけである。で、その示しどころが難しいのであるが、丸谷さんはユーモアで包み、あるいは冗談めかして一席ぶつのである。そこに丸谷さん一流の藝の力をみせるのである。
さらには語り口のうまさがある。これも藝のうちに入るのであろうが、長々と語っていながら実に印象的な落とし所を心得ている。その面白さは、うんと誉めていうならば、磨きぬかれた落語の語りと同じということになろう。面白さが語られる内容を超えて自立しているから、何度読み返してもその都度違った面白さで読むことができる。
もう一つ、そうした藝の力をもちながら、丸谷さんは大の勉強家なのである。行き当りばったりというところが寸毫(すんごう)もない。対談の席につく以前に、きちんとテーマにそった話題をたっぷり仕込んで、準備万端おさおさ怠りなしで乗りこんでくる。そして相手の意表をつくことを特技とする。本書でも、野坂昭如さんとの対談で、江戸を代表する女は八百屋お七、東京の女はだれか。「明治維新後今日までをひとりで代表させるとしたら、なんといっても阿部定ということになるんじゃないか」とやって野坂さんをびっくりさせた。本書にはないが、私も昭和史対談で、いきなり「昭和前期というのは誠にくだらなく、無意味な時代であった。あの時代においてただ一つ栄光とすべきことは、『源氏物語』を発見し、それを宣揚したことである」と口火を切られて、しばしアッケにとられて黙りこんだことがあった。
また、編集者としてその席にはべって、山崎正和さんとの対談「日本の町 金沢」の司会をしたとき、丸谷さんがいきなり前田利家は片目であったという話をはじめて、山崎さんともども私は思わずひっくり返ったことが思いだされる。
山崎さんが片目なら伊達政宗だと応じると、丸谷さんは即応した。以下は――、
丸谷 ええ、二人とも片目なのに、一人は片目を売り物にする。もう一人はそれを隠す。そういう前田利家の心の配り方になにかみやびやかなものを感じるんですよ。
山崎 なるほど。うまいところから話を始めるなあ(笑)。
という具合なのである。
*
こうした仲のいい名人・達人同士の対談に、私は編集者として、多分四十回以上も立会ったことになるであろう。その当時、流れるようなやりとりを聞きながらいちばん心に残ったのは、そうか、これが現代日本がすっかり失ってしまったかにみえるレトリックの妙というものではないか、ということであった。念のためにいうが、言辞をいたずらに弄するという意ではなく、言葉の風情というもの、品というもの、文学を論じるにも、歴史や芸能を論じるにも、趣味のよさを存分に示し、知的であり、さりとて高踏すぎて難解ということはない。むしろわかりやすい。交換されることで高められる言葉のうちに、深い内容がこめられてくる。そしてだんだんに常識的な枠組がはずされ、通説あるいは俗説がものの見事にくつがえされ、考えてもみなかったオリジナリティのあるものの見方が提示されてくるのである。それが丸谷対談の妙といっていい。
思えば、その席にはべることができたということ、それこそが編集者冥利につきるというものであった。
ただ一つ、閉口したことがある。対談がすんで酒を汲みながらの閑談に入ると、玩亭の俳号をもつ丸谷さんがきまって連句を巻こうよといいだすことである。何となくみやびやかな気分になっているときであるし、逃げるのも卑怯ならんかとただちに連衆となったが、きまって酒のほんわかとした酔いはどこかへすっ飛んでいった。
銀座のバアで、玩亭センセイを宗匠に、山崎正和さんと私とで、半歌仙を巻いたときの初表の三句がすぐに想いだせる。
元日や玩具の店の薄明り 玩亭
春の時計はちと遅れて打つ 正和
いっせいに銀座の蝶の飛び立ちて 一利
あとは忘れた。天国で玩亭センセイは「相変らず粗雑だね」と怒り給うているやもしれぬが。