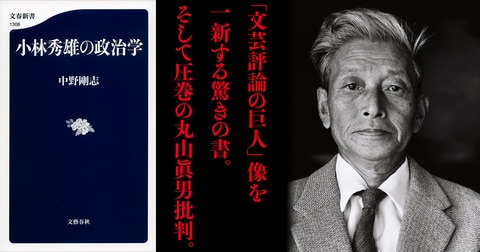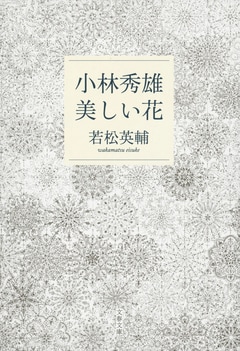I
ここ数年来、私と福田逸氏との間には親交がある、と書くと誤解を与えるかもしれないが、それは、単純に逸氏が私の福田恆存論を評価しているからということではない。この本を読んだ方ならお分かりだろうが、それは、おそらく福田恆存との「距離」の問題なのだ。
私自身は、幸か不幸か福田恆存に会ったことはなく、死後十年以上を経て、自分の読書遍歴のなかで勝手に「福田恆存」を発見したという人間だが、そのために、恆存の政治評論が持っていた同時代的なインパクトや、それゆえの論壇的威光などには、ほとんど興味がない。福田恆存に対する畏敬の念はもちろんあるが、要は「恆存ファン」ではないのである。
しかし、それを言うなら、福田恆存の家族こそ「恆存ファン」になることのできない最たるものではなかろうか。言葉という舞台で恆存が演じて見せた「福田恆存」に魅せられるのがファンなのであれば──それ自体が福田恆存の凄みなのだが──、一方で、魅せられるばかりでは生活が成り立たず、恆存が隠そうとした楽屋までも共にせざるを得ないのが家族であろう。とはいえ、福田恆存抜きで自分たちの生活があるわけではない以上、その家族が、単なる好き嫌いで「福田恆存」を処理することなど、なおさらできるはずもない。そこに、恆存と最も親密に付き合い、その言葉を最も深く理解しながら、しかし、単なるファンではあり得ない独特の「距離感」、家族だけが強いられる宿命的な関係が現れることになる。
その点、本書の言葉が、偶像破壊の嫌らしさから全く無縁なのも、その宿命的な関係に、ということはつまり、福田恆存と、それを父とした自分自身の宿命に徹底的に忠実たろうとしているからだろう。本書は、福田恆存という特異な文学者を父に持った息子による一世一代の文芸評論、そう言って大袈裟に聞こえるなら、人が一生に一度きりしか書けない、亡き父に向けた、長い長い「手紙」である。
II
実際、『父・福田恆存』のなかには多くの「手紙」が登場する。まず第一部で示されるのは、親子の間に、まだ「決定的な亀裂」がもたらされてしまう以前の風景、「友達のやうな親子」(丸谷才一)だと評されるまでに仲の良かった父と子の信頼関係であり、また、それを支えてきた福田恆存の家族に対する「優しさ」である。
かつて、福田恆存は「家庭の意義」というエッセイのなかで次のように書いていた。
「人が人を信頼できるというのは、一人の男が一人の女を、あるいは一人の女が一人の男を、そして親が子を、子が親を信頼できるからではないでしょうか。それをおいてさきに、国家だの社会だの階級だの人類だのという抽象的なものを信頼できるはずはありません。それゆえにこそ、家庭が人間の生きかたの、最小にしてもっとも純粋なる形態だといえるのです。信頼と愛とが、そこから発生し、そのなかで完成しうる、最小にしてもっとも純粋なる単位だといえるのであります。」(『私の幸福論』ちくま文庫、所収)
しかし、この「純粋なる単位」を筆一本で守っていくことは並大抵のことではなかったはずだ。洋行前に「茶の間で両親が真剣な顔で我家の経済状態を話してゐた」という話は生々しいが、なかでも、舞台稽古と同時進行で進められていた『ハムレット』翻訳の話は驚きであるという以上に、筆で食べていくということのある種の「すさまじさ」を感じさせる。
これは年譜を調べれば誰でも分かることだが、福田恆存が『ハムレット』に取り組むのは、例の平和論争や洋行後の日本人論(「日本および日本人」)などに取り組むのとほぼ同時期の昭和三十年前半のことであり、さらに言えば、『ハムレット』の翻訳直後に恆存は、自身の主著となる『人間・この劇的なるもの』や『幸福への手帖』(『私の幸福論』に改題)の連載、あるいは、国語国字論争や『マクベス』翻訳の仕事にまで手を付け始めているのだ。それらの仕事がほぼ同時並行的に進められていたことを考えると、福田恆存の「やつつけ仕事」は、ほとんど奇蹟のレベルだと言いたくなる。が、それらの仕事の背後に、福田恆存の「家庭」への気遣いがあったことを想うと、その奇蹟にも妙に納得がいくのである。
そして、第二部で、鉢木會の友人たち──大岡昇平・中村光夫・吉田健一・三島由紀夫・神西清など──との関係を見るに及んで、読者は、恆存の気遣いが、「同じ輪(和)の中に互ひを閉ぢ込め合」うような日本人的性向からも自由だったことを知るだろう。
かつて、福田恆存は、大岡昇平の言葉──「『鉢木會』の連中はみんな孤独である。徒党を組むなんて、殊勝な志を持つた者は一人もゐない」(『わが師わが友』)──を引き合いに出しながら、鉢木會メンバーのことを、「自分の孤独の始末をつけるのに友達の手は借りぬ人たち」(「鉢木會」)だと評していたが、第二部の手紙が示しているのも、まさに、そんな大人の文学者たちの、馴れ合わぬ乾いた友情の姿だろう。
「仮面の使ひ分けを一つの完成した統一体として為し得るものが人格なのである」(「防衛論の進め方についての疑問」)という福田恆存自身の言葉を借りれば、まさに、第一部から第二部にかけて描かれているのは、生活者の「仮面」と同時に、演劇人の「仮面」や、文学者の「仮面」を操る、福田恆存の「人格」の姿だと言えよう。