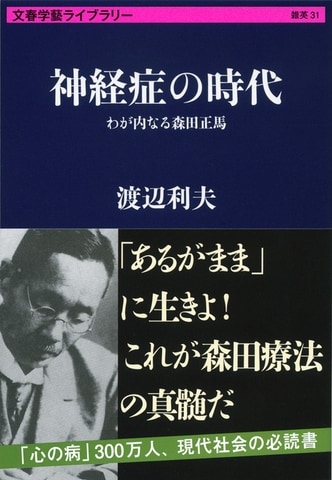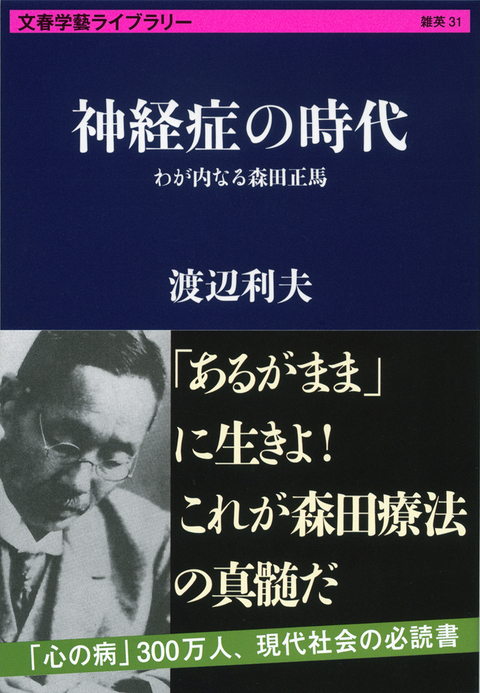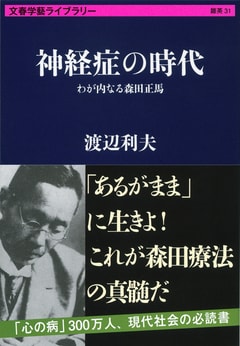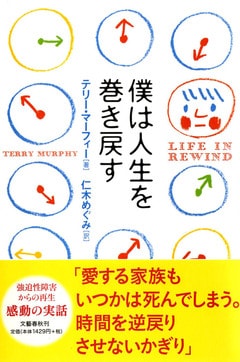森田正馬が臨床に立ったのは、急速な近代化のもと、伝統的な価値観が揺らいで人々の不安が高まり、「神経衰弱」が国民病として大流行していた明治後半である。神経衰弱は十九世紀の末、アメリカの競争社会に挫折して神経過敏になった人々に対して便宜的につけられた症状で、その後ドイツに渡って疾病概念として確立し、日本に移入された。不眠、胃痛、耳鳴り、赤面恐怖や不潔恐怖など、現在、不安障害とか強迫性障害と呼ばれる症状がある。
ところが森田はこれを病ではなく、ある特殊な気質の人が陥る状態にすぎないと考えた。神経が薄弱なのでも、神経が過敏なのでもなく、誰にでも起こる不安や恐怖の感覚をふと気にし始め、そのことばかりに執着するあまり苦悩から逃れられなくなる。内へ内へと囚われていくこの気質を神経質と名付け、神経衰弱という病名を否定した。病気は外から他動的に引き起こされるものと考えられているが、神経症は自分の心が自動的に招くもの。手を洗わずにはいられなかったり、際限なく計算を繰り返したりと、症状は多様だが、発症の道筋はどれも同じ。それが、森田の考える神経症の出発点であった。西洋医学とは真逆の発想である。
近代西洋医学が誕生した十九世紀末以降、心は次のように考えられていた。心と個人の内面は同一のもので、自分の心を知るのは自分だけ。しかし、自分にも知らない部分があって、それを無意識と呼び、無意識を意識化させることによって症状を取り除くことが回復につながる。神経症の本質は本人も知らない不安にあると考えて精神分析による治療法を編み出したフロイトの名前を挙げるまでもなく、心を物質や身体と切り離し、無意識を解決すべき問題とすることが精神疾患を考える際のベースにあった。
それに対して、フロイトの弟子であるユングと同世代だった森田は、帝国大学で近代西洋医学の教育を受けながらも、独自の道を模索した。意識は善、無意識は悪と捉えて無意識の意識化を目指した西洋医学に対し、身体と心を切り離さずにあるがままを受け入れる。西欧的二元論ではなく、心身一元論で理解する。すなわち、意識の無意識化を目指したのである。「自然生命体としての人間は生得的に生の欲望において強い存在」であり、不安や恐怖は必然的に生じる人間本来の精神に内在するもの。取り除くことができないのであれば、そのまま放置するしかない。ひたすら耐えて、苦悩を「ひと昇り、ひと降り」させる臥褥療法は、多くの患者の観察と実験によって生み出された、じつは科学的な治療法なのであった。