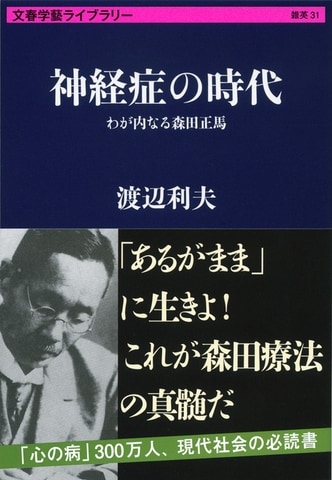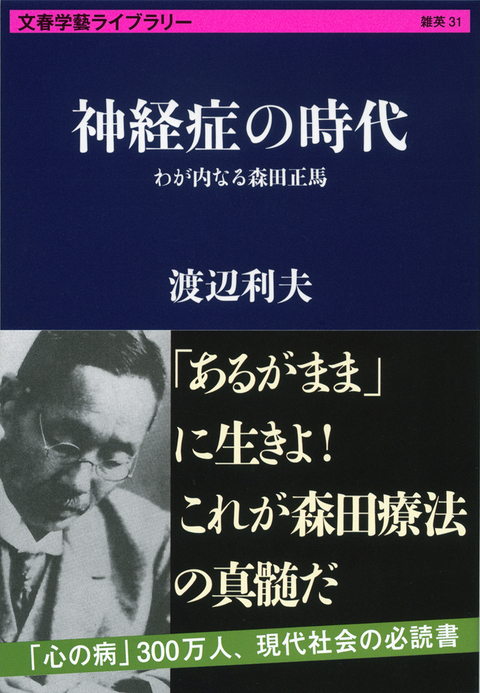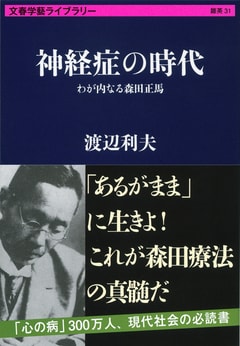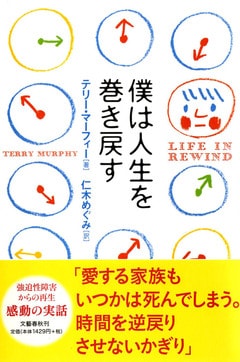しかし、ドイツ医学を教師とする日本の精神医学界で、森田療法を評価する声は少なかった。脳科学や神経医学、遺伝学など生物学的な研究の進展に伴い、論理よりもありのままの感情を神経症の課題とした森田療法は宗教のようなもので、科学ではないと異端視する者もいた。それでも弟子たちによって受け継がれて多くの患者を完治させてきたが、薬物治療の成果が上がり、国際的な医療標準化の波が押し寄せると、従来の神経症は不安障害やパニック障害、強迫性障害、解離性障害など細かく分類され、神経症という診断名自体が消えてしまった。森田療法は一子相伝の奥義のようなものと見られ、一部の理解者以外には顧みられることはなくなっていった。
注意しておきたいのは、標準化は決して負の改革ではないということだ。医師によって診断名が異なるような現場の混乱を収拾し、患者にはだれが診察しても大きな違いはないという安心感を与え、精神科治療の全体的な底上げにつながった。名医でなければ診られないという事態はなくなったのである。ただ、国際的な基準は、病の原因は問わず症状に着目する診断法なので、病気ではない人にまで病名がつくという弊害があった。私が以前、取材したある臨床心理士は、「日本人は間(ま)やあわいを大切にする民族なのに、DSMによって患者ではないのに患者にさせられた人はたくさんいる」と語っていた。パソコンの画面ばかり見て患者の顔を見ない医師が増えたのは、標準化以降である。
だから本書が一九九六年に刊行されたとき、文化も言語も死生観も異なる国の心の病を同じ基準で診断することに違和感を抱いていた臨床家の中に、これまで森田正馬の名を一顧だにしなかったことを自責の念とともに思い起こし、自らのアイデンティティを問い直した人はいたのではないか。河合隼雄は「日本人である限り、どのような学派に属していても森田療法的な観点や技法から何かを学んでいる」(「森田療法ビデオ全集」)と述べているが、国際的な診断基準を頭の片隅に入れながらも、患者と向き合うときは苦痛の本体が何であるか、病の向こうに人を見ようとする臨床家はいたはずだ。
ただ、それだけで本書が十万部ものベストセラーになるわけはない。ベストセラーというのは、本来想定されていた読者以外の人にまで拡がって初めて生まれるものである。医学の動向も、診断基準も知らない人々に本書が広く読まれたのはなぜだったのだろうか。もしかすると、神経症という言葉は彼らにとり生々しい現実だったのではないか。身に覚えのある不安感や緊張、恐怖心など、ノイローゼと呼ばれる精神状態を思い浮かべ、救いを求めて手にとった人が多かったのではないか。腰痛を抱えた私がそうであったように。