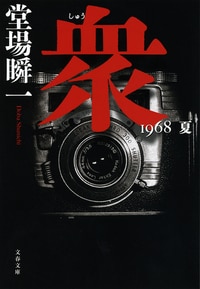
学生運動という言葉はもはや死語なのだろうか。
学生運動とは、学内の問題はもとより、政治や社会問題に対して学生たちが組織的に行う批判運動のこと。日本では明治時代からすでにあったようで、「明治期から中学校、高等学校では学校騒動は年中行事のようにくり返されていた。夏目漱石が松山中学校へ赴任したのは明治二十八年四月だが、その直前に生徒のストライキがあって、数人の教員が転任した穴埋め人事に漱石がくることになったようだ」(秦郁彦『旧制高校物語』文春新書)というのはほんの一例。
大正時代になると、東京帝国大学に新人会、京都帝国大学に労学会という学生運動団体が設立され、学生、労働者による社会主義思想の啓蒙や普通選挙運動が行われた。学生たちはその後労働運動や農民運動など学外の社会運動と連携し、一九二二年(大正一一年)一一月には学連(学生連合会)も設立された。二五年四月の治安維持法の公布以後、第二次世界大戦が終わるまで、学生運動は冬の時代が続くが、戦後間もなく復活。各地で学園民主化運動が活発化し、四八年(昭和二三年)九月には全学連(全日本学生自治会総連合)が結成される。
当初は日本共産党の指導下にあった全学連だが、共産党は一九五五年七月の六全協(第六回全国協議会)で自らの武装闘争路線を否定して大幅な路線転換を断行、これをきっかけに学生たちは共産党から離れていき、五八年一二月、新たにブント(共産主義者同盟)を結成してプロレタリア革命を目指すこととなる。
ちなみに五五年生まれの筆者が学生運動という言葉から思い浮かべるのは「安保反対」と「全共闘」だが、前者は六〇年の安保(日米安全保障条約)改定をめぐる反対運動を指す。このときは五九年一一月二七日の国会突入デモを端緒に、岸首相(当時)の渡米を阻止しようとした翌六〇年一月の羽田闘争、さらに東大生・樺美智子さんが亡くなった同年の六・一五国会突入等大規模な騒乱が続いた。
いっぽう後者の全共闘は全学共闘会議の略称。六〇年安保闘争ののち学生運動はいったん下火になるが、ベトナム戦争反対運動の高まりとともに再活発化。新左翼系組織はブント、中核派など三派系全学連や革マル派など各党派に分裂して闘争を続けるが、やがて各大学でセクトを超えた運動組織が生まれる。六八年に日大全共闘、東大全共闘が相次いで結成され、学内をバリケード封鎖する闘争形態は各地の大学へと波及していった。
前置きが長くなった。本書『衆』はその全共闘運動の活動家だった初老の政治学者を主人公にした長篇サスペンスである。
鹿野道夫は六三歳、マスコミでも名の知られた選挙を専門とする政治学者だ。地方の名門私大である母校・麗山大学に新設された地域政治研究所の初代所長に抜擢され、彼は久しぶりに古巣に戻ってくる。かつては「都会の発展にすっかり取り残された田舎町」だった麗山市も高速道路が出来、大規模開発が進むなど変貌を遂げていた。
そんな街を散歩中、彼はかつての仲間・実川誠の姿を見かける。四三年前、麗山大学は全共闘運動の拠点だった。鹿野は革青協麗山支部執行委員会の幹部として、医学部の学費値上げ反対闘争に端を発する騒動の中心にいた。実川はそのときの闘争副委員長だったが、戦略家の彼は大学側との団交を意図的に拒否。バリケードを挟んだ学生たちと警察側との睨み合いは鹿野の投石がきっかけになったように激しい衝突へと転じた……。
いっぽう、鹿野のかつての教え子で今は麗山市市議会議員である石川正は、若手議員の板橋から麗山南高校の校内で麻薬のやり取りが行われているという情報を得ていた。そのとき鹿野の再就職のことも知らされる。程なく当の鹿野から呼び出された石川は久しぶりに恩師と再会、彼の用件は麗山市の過去の選挙を研究するための協力要請だった。そしてもうひとつ、四三年前に麗山大で学生と機動隊の衝突があった際、ひとりの高校生が亡くなった事件――「麗山事件」の真相追求にも協力を乞われるのだった。
そのとき死亡したのは市内在住の高校一年生、石川智英。鹿野は彼の死は武装した機動隊によるものだという疑いを捨てていなかった。「警察は一応捜査したのだが、石川に致命傷を負わせたのが誰か分からない、と結論を出しただけで、早々と事件を閉じてしまったのだ」。鹿野は長らく釈然としないものを抱えて生きてきたが、そんなとき舞い込んだのが麗山大での新たな仕事だったのである。
かくて物語は鹿野の麗山事件の追求を軸に進んでいくが、それにしても、著者は何故全共闘世代を主人公にした話を書こうと思いついたのか。「自著を語る」によれば、「この小説を書き始めるきっかけは、雑談でした。同世代の編集者と、団塊の世代に対する恨みつらみで盛り上がってしまった。世代論は『上から下』へ語られることが多いですが、逆パターンを狙って、時代の空気を切り取れないかと考えたのです。実は、団塊の世代は苦手。社会人になったころ、仕事でつき合うことが多かったのですが、私たちは新人類とレッテルを貼られ、いびられました(笑)。彼らは何かが起こると、一斉に同じ方向を向く。それがバブル経済と、その後の日本の凋落の原因かもしれません。接することが多かっただけに、あの世代の考えや行動パターンについては、ずっと疑問を抱いていたのです」(「オール讀物」二〇一二年六月号)。
なるほど鹿野が全共闘運動に参加したのは、権力による差別や弾圧への反発、是正であり、社会の改善をこいねがう純粋な動機に駆られてのこと、権力との闘いに正面からぶつかっていった情熱的若者だった。一九六八年には、フランスで学生と労働者が組んだ民主化運動――五月革命が起こり、日大、東大で結成された日本の全共闘には党派に属さない学生たち(ノンセクト・ラジカル)も数多く参加、運動は全国規模に拡大していった。鹿野の政治的な情熱には、そういう時代的な影響もあったろう。
だが麗山事件を契機に運動から脱落するや、彼はさっさと街を逃げ出し、東京で新たな道を見出した。麗山市議会の七〇歳議員・牧田にいわせれば、「勢いだけで突っ走って、結果がどうあろうがそれは気にしないっていうかさ。子どもが玩具(おもちゃ)で遊んでるようなもので、遊んでる間は夢中なんだけど、絶対に玩具を片付けない」迷惑千万な輩ということになる。実際には鹿野はもうちょい複雑で、事件を放り投げたことに引け目を抱き、事件の真相にもこだわり続けていたのだが、教え子の石川からすると、昔から自信たっぷりで箴言めいた台詞を吐く癖があって、学生同士の討論に割り込み独演を始める独善的な面も持っていた。二律背反的というか、確かに厄介なキャラクターというべきか。
著者はそんな鹿野の捜査ぶりと、自分と同世代の石川の章とを交互に描き出すことで事件の真相をあぶり出していく。鹿野は当時の学生仲間や元警察官等に聞き込みに回り、石川は石川で麻薬事件の調査で私立探偵を雇って実川の動きを見張るといった塩梅で、やがて鹿野との関係も浮かび上がってくるが、特に驚愕の演出が凝らされているわけではなく、ミステリーとしてはオーソドックスな展開といえよう。著者自身、「書いた本人としては、ミステリだという意識は薄い。これは、新人類世代が、団塊の世代をどう見ているかを、様々な角度から語る物語なのである」(「本の話」二〇一二年六月号)と述べているように、本書の読みどころは、麗山事件の顛末それ自体よりも、事件に関わった様々な人々の個々の生きざまが明るみに出されるところにある。
団塊の世代や全共闘運動を題材に描いた作品は同世代の作家よりも、むしろ後の世代の作家に多いのではないか。野沢尚『反乱のボヤージュ』や楡周平『宿命 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京』等はほんの一例。世代間の対立劇があれば、波乱万丈の出世劇もありといった具合にその中身も多彩だが、全共闘運動に身を投じた人や彼らの輝いていた時代にはそれだけ興味深い題材が潜んでいるということなのだろう。してみると「この小説を書くまで、団塊の世代の頭の中は、まったく理解不能でしたし、書き終えた今も、実は分かっていないと思います。ただ、理解したいという思いが、一冊の小説を書かせたのは事実。難しいテーマを選んだことで、作家としての視野が広がり、これから書き続けていく上での貴重な糧になりましたね」(「オール讀物」二〇一二年六月号)と著者が執筆動機を語る本書はひと際異彩を放つ一冊といえようか。
ちなみに著者は本書ののち、政治家と小説家というふたりの男の軌跡を通してバブル期以後の時代像をとらえた『解』(集英社)や、バブル前夜にある社会情報研究所に就職した学生の運命を描いたピカレスクロマンの『グレイ』(同)等の単行本作品を刊行している。堂場瞬一といえば、本文庫収録の『アナザーフェイス』を始めとする警察小説の旗手であるが、濃密な人間ドラマを通して現代という時代相を浮き彫りにしてみせるノンシリーズもののドラマにもぜひご注目いただきたい。



















