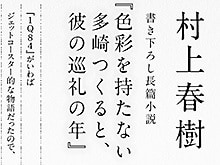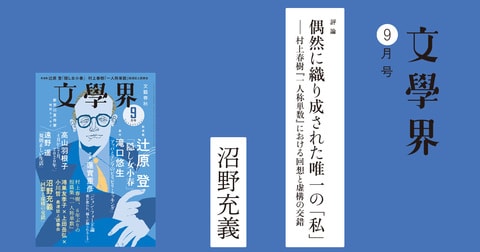二〇〇〇年の春と夏、日米のふたりの作家と会った。
四月にテキサスの自宅を訪ねたアメリカ人作家は、一九四六年生まれのベイビーブーマー世代に、七月に東京のオフィスで対面した日本人作家は、一九四九年生まれの団塊世代に属した。
後者は村上春樹だった。学生運動が盛んだった頃に青春期を過ごした村上は、運動が沈静化、さらには挫折へと至り、人々を鼓舞するために叫ばれ続けた言葉の無力さを感じたと話した。
そして、前者の作家、ティム・オブライエンも若かりし頃、六〇年代という大きく社会が変動する時代の中で、挫折を味わった点で共通する。出身地ミネソタ州のカレッジを卒業後徴兵され、翌年、つまり本書の時代背景となる一九六九年に、ヴェトナム戦争に従軍した。
祖国を愛すればこそと、銃を取った異郷の地で彼が目の当たりにしたのは、明確な目的もなく、敵・味方ともに人の命があっさりと朽ち果てる現実であった。
「爆撃により、戦友の身体が藪の中に飛んで行った光景は、私の記憶でいまでも繰り返される」という本人の言葉、あるいは、自宅で見せてもらった当時着用した式典用の軍服は、ひとりの兵士としての戦争体験が、彼のその後の人生に大きな影を落とすトラウマの証である。
けれど、オブライエンは想像を絶した苦難の日々を胸に秘めず、言葉の表現によってなぞろうと努めてきた。デビューを飾った自伝的作品『僕が戦場で死んだら』を皮切りに、全米図書賞を獲得した『カチアートを追跡して』、名作の誉れ高い『本当の戦争の話をしよう』など、代表作と言われるどれもがヴェトナム戦争を題材として扱っている。
となれば、ヴェトナム戦争専門の作家と位置づけしたくもなるのだが、それではオブライエン文学の本質を見誤ってしまう。この作家が対峙するのは、戦争よりさらに向こうに存在する「過去」という概念である。
「書くことで、過去は現在へと姿を変える。私にとっての過去は過ぎ去りしものではなく、常につきまとう存在だ。過去を通じて語りたいのは、愛、悲哀、恐怖心といった人生に不可欠な永遠なるテーマであって、特定の時間枠についてではない」
と、会ったとき訥々(とつとつ)と話したオブライエンだが、彼が語る「過去」には、無力と知りつつ、運命への服従を拒み、抵抗しようともがき苦しむ人間の有り様と、時間の推移がもたらす人生の変容が孕まれる。健気というよりは、むしろ強迫観念に引きずられるごとく、オブライエンはこれらのテーマの言語化にひたすら身を捧げる。
本書のあとがきで、訳者である村上が、オブライエンの「文学的下手っぴいさ」に共感をおぼえると書いているが、その「下手っぴいさ」とは、執拗なまでにひとつの事を追い求めずにはいられない、作家オブライエンの不器用なまでの真摯な性格と同義語のような気がする。
たとえば、本書の一編〈ルーン・ポイント〉において、同じ大学に通った不倫相手とともに出かけた旅先で、五十二歳になる人妻は、「一九六九年の、あのどたばたした理想主義と幻想」と、シニカルに学生時代を振り返る。一方で、彼女の現状はと言うと、「満足しているわけではないし、希望を抱いているわけではないし、何らかの道義的目標を目指しているわけでもない。一九六九年に、自分がそうなるかもしれないと想像した人間でもない」と、「ではない」が混在する生活を送る。
ところが、不倫相手が湖で溺死してしまい、その事情聴取をする警官から、彼女自身も含めてリアルであるものを認めるべきだと指摘される。
実際のところ、人妻の過去に対する思いは、シニカルでありつつロマンティックなものだ。満足はしていないけれども、だからといって、現在の生活が不満ばかりというわけでもない。夫は、“それなりに”愛情を注いでくれる。けれど、彼女は何かが欠落していると考えている。本書に登場する他のキャラクターも一様に、過去のどこかでやり残したことがあったのか、それとも、知らず知らずのうちに間違いをおかしてしまったのか、と疑念を持っている。
五〇年代、六〇年代の日本で、学生運動に没頭した人々が昔を懐かしむように、若かりし熱狂の頃へのノスタルジックな思いを描く物語は数多いが、本書がこれらと似ているようで異なるのは、人々の現在の立ち位置をしっかり見据えている点にある。〈ルーン・ポイント〉で、先の警官が、「世界はナンセンスな回り方をしています。ひとつ事実として言えるのは、誰が非難してもしなくても、それと無関係に世界は回り続けるっていうことだ」と話すが、自分はいつまでも同じ人間だと思い込んでいても、世の中は、時代は、否応なしに変化を遂げる。
だが、ここに出てくる登場人物たちは、その現実を直視できないでいる。熱狂し、歓喜した度合いが大きければ大きいほど、時間を隔てた今日このときが空虚に思えてくる。
さらに始末が悪いのは、自分自身ですら変わってしまったことに、彼らは気づいていない。過去へは帰れず、人生は一からやり直しがきかないのに、人々は時間が戻ることを欲しようとする。オブライエンが言った、人生の悲哀とはそこである。
そんな彼らを、物語の担い手となるオブライエンは突き放さない。過去との決着も決別もできないでいる人々の心情を丁寧にすくい取り、読む人間が感情移入し得る文章へと置き換える。
日本語となった本書を読みながら、「そうだ、そうだったな」とうなずきつつ、オブライエンの書き綴った言葉をひとつひとつ噛みしめながら訳す、同時代の作家、村上春樹の姿が思い浮かんだ。