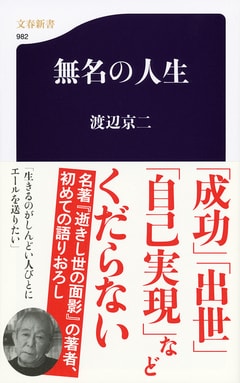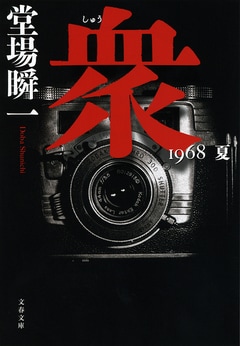少し前のことだが、病院でMRIなどという物々しい検査を受け、後日結果を聞きに行くことになった。その病院はいつも混んでいて、二時間待ち、三時間待ちもざらであった。本好きにとって待ち時間というものは、読む本さえ手元にあればそれほど苦痛ではない。むしろ「他にできることがなくて本を読んでいればいい」という状況は、どちらかといえば幸せに近いくらいだ。しかし、さすがに「検査の結果待ち」という気の重いシチュエーションで、そんな能天気な気分にはなれなかった。どんな本を持って行こうと考えても、暗い話や後味の悪い話は論外。心がへたれているので、読むのに知力体力が必要な本格ミステリや冒険小説も無理。魂を揺さぶる感動の名作!を読むのもしんどい。しみじみした名作佳編、というようなものならよさそうだが、そういうコンディションのときだと、うっかりするとしみじみしんみりじめじめうつうつ、と落ち込んでいくのではないかと心配だ。こんなときに読みたいと思える本は意外に見つけにくいと実感した。
その点、このエッセイ集『時をかけるゆとり』を手に取った方は運がいい。誰もの人生に、形は違えど必ず訪れるだろうそんな時間を救ってくれる本だ。何の予備知識もないまま、どこからどう読んでも楽しめる。とにかく面白い、おかしい。何度も噴き出しながら読み終えた後、心がほんのりと晴れている。もしあなたが、これから憂鬱な待ち時間を過ごさねばならないというときに店頭でこの本を手にとったのだったら(そうでなくても)、迷わずレジへゴー、である。
作者の朝井リョウさんについては今更紹介するまでもないだろうが、早稲田大学在学中に『桐島、部活やめるってよ』で第22回小説すばる新人賞を受賞してデビュー。同作は映画化もされて大ヒットしている。大学卒業後は会社員として働きつつ執筆、『何者』で第148回直木賞を受賞(男性作家としては史上最年少)。直木賞受賞後第一作の『世界地図の下書き』では第29回坪田譲治文学賞を受賞。まだお目にかかったことはないが、著者近影を拝見するに極めて爽やかなイケメン。ご本人は本書の中で自分のことを「馬顔」と何度も書いておられるし、確かに面長でいらっしゃるが、それがどうしたというのだ。我が敬愛するクラウス・ハインツ・フォン・デム・エーベルバッハ少佐だってベネディクト・カンバーバッチだって、堂々たる面長で、れっきとした二枚目である。何の話だ。
いやつまり何が言いたいかというと、朝井さんがキャリア・外見ともにまばゆいばかりの存在である、ということなのだが、本書を読んでいるとおそらくそんなふうには思えまい。主に学生時代を中心に(本書が単行本として出版された際のタイトルは『学生時代にやらなくてもいい20のこと』であった)、カットモデルを務めたり、コンセプトカフェに行ったり、二日がかりで百キロ歩いたり、六日がかりで東京から京都まで自転車で走ったり、どこにでもいそうな(ちょっとだけ無謀な?)若者がやりそうなエピソードが満載だ。だがもちろん、それを描くのが作家・朝井リョウだから、どこにでもある話にはならない。
朝井さんの書く小説は、現時点では作者自身と同年代の「青春」を描いたものがほとんどだが、あえて一歩引いたような視点が印象的だ。たとえば直木賞受賞作の『何者』では、主人公が「そんなの絶対無理だろう、と、どこか冷めた目で自分たちのことを見ている自分がいた」「自分たちから漂う痛々しさを、俺は、どうしても見過ごすことができなかった」(新潮社単行本『何者』一三〇ページ)と語る。朝井さんの作品が持つ「若々しさ」「瑞々しさ」の魅力は言うまでもないが、私にとって一番魅力的なのは、自分で姿が見えていない青春まっただ中の若者たちの姿を、同年代でありながら冷静に腑分けするその観察力である。その観察力がこのエッセイ集のなかでは自分の行動に対していかんなく発揮され、えもいわれぬおかしさを呼ぶ。いい話になりそうになると自分でツッコミを入れてしまうのも、この冷めた目のなせるわざだろう。今回文庫になった機会に追加された社会人篇では、直木賞受賞の際に書かれたエッセイに「直木賞を受賞しスかしたエッセイを書く」とタイトルですでにツッコミを入れてあるし、あまつさえすぐ次には「痔」を患ったエピソードが置かれている。恰好をつけることがカッコ悪いと感じてしまう、含羞がなんとも微笑ましい。
朝井さんの文章、表現力がまた、いい。この本の最初のエピソードのタイトルは、「便意に司られる」である。「司る」、この荘重な動詞が、「便意」と共に用いられたことが、日本語の長い歴史の中でかつてあっただろうか。ない、多分ない。しかし読んでみると、ああまさにこの状況は「便意に司られ」ているとしか言えない、と思わされる。
さらに、ピンク映画を見に行った大学時代の朝井青年が「でーい! でーいでーい!」と心の中で悲鳴をあげるエピソードがある。ここを読んだとき、ちょうど電車の中だったが、この表現が笑いのツボにはまって往生した。確かにこういうときにあげる悲鳴は「でーい!」だな、と納得してしまうのだ。
それまで使われたことがないが、使われてみるとそれしかない、と思わせる表現。それを思いつくことができるのが「天賦の才」、天才というものだろう。挙げた例が便意とピンク映画なのが、我ながらちょっとアレだけれども。その前は痔だったし。
ところで、本書『時をかけるゆとり』というタイトルの意味を担当編集さんに聞いてみたところ、「ゆとり世代の著者が子供のころから今にいたるまで、変わりばえせず、馬鹿馬鹿しく可笑しい日常を過ごしている、というようなニュアンス」だと教えてくれた。なるほどそうか、朝井さんは「ゆとり世代」なのだなあと改めて認識した。
「ゆとり世代」については、世間的にはどうもロクな言われ方をしない。「ゆとり世代」の当事者たちからも、あまり肯定的な自己評価を聞かない気がする。
でももし、朝井さんの冷静な観察力と、恰好をつけることを良しとしない含羞が、ある程度この世代の「ゆとり」から来ているものだとしたら……。これはかなり素敵な世代が育っているのではないか? と、朝井さんのお母様とおそらく同世代であろう私としては、自分の手柄でもないのに嬉しく思ってしまうのである。