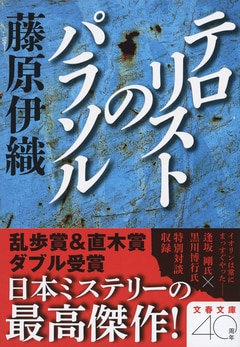いおりんこと、藤原伊織との縁(えにし)は古い。
何度か書いたので、詳しい経緯は省かせてもらうけれども、かつていおりんとわたしは〈小説現代〉の新人賞で、同時期に最終候補に残ったことがある。今から、二十七年も前の話である。二人とも、のちに直木賞を受賞する巡り合わせになったが、初めて対談をしたおりにその事実を、いおりんに教えられた。
それを聞いたとき、かたや電通、こなた博報堂という立場も含めて、わたしは何か因縁のようなものを感じた。もっとも、いおりんは大のばくち好き。一方わたしは、手相見から「賭けごとだけはおやめなさい」と諭され、麻雀から足を洗ったほど博才のない人間だから、日常的に付き合いがあったわけではない。しかし、パーティや会合で顔を合わせるたびに、いつも年来の友人のごとくやり合う、不思議な関係だった。お互いに、広告業界に身をおく者同士の、独特のにおいといったものが、親近感を抱かせたに違いない。
いおりんの、直木賞受賞の二次会パーティでは、二人で業界漫才を演じた。事前に打ち合わせをしたわけではなく、祝辞の順番が回ってきたわたしがいおりんを呼び上げ、即席でやったのだった。二人とも酔っていたから、何を話したかもう覚えていないが、大受けに受けたことだけは確かだ。
今回〈名残り火〉を読んで、なつかしいことを思い出した。
ある人物が、自分の敬愛する元上司と酒食をともにしたあと、路上で別れるシーンがある。その人物は、本編の語り手堀江にそのときのことを聞かれ、「わかれたあと、ふりかえりもしなかった」と説明する。それに対して堀江は、敬愛する元上司と別れる際に後ろ姿を見送りもせず、振り返りもしないのはありえないことだと指摘し、その人物の嘘を鋭く追及する。
いおりんは、わたしの『あでやかな落日』の文庫本の解説で、次のように書いた。
「(前略)対談の二度目は、最初のものからさほど間をおかずしてあった。そのころ、まだ私は初々しかったのだが、ホテルでの対談が終わり、表にでたときのこと。われわれはタクシーを待つ長い列に並んだ。ようやく順番がきて、当然、私は大先輩に「おさきにどうぞ」と申しあげた。ところが逢坂さんは「いえ、わたしは地下鉄で帰りますから」とおっしゃった。なんと逢坂さんは、ペイペイのこの私がタクシーに乗るまで、いっしょに列に並んで見送ってくださったのである(後略)」(講談社文庫『あでやかな落日』解説)