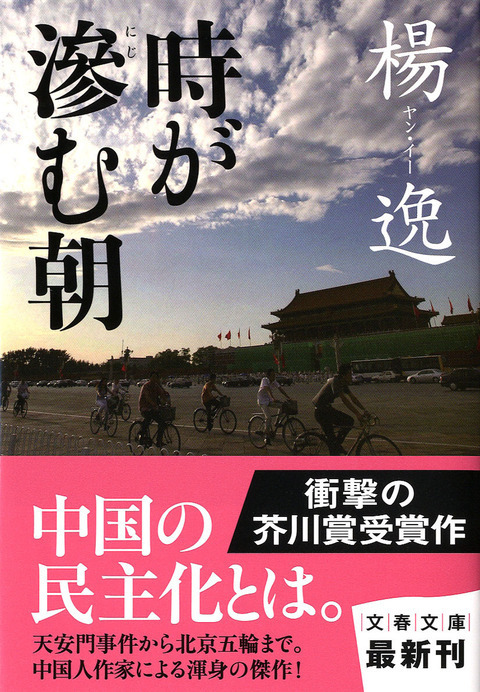――楊さんは一九八七年に来日されている。ということは、八九年の天安門事件は日本で知ったわけですね。
楊 はい。五月の初めぐらいから騒ぎだして、いろいろな噂が耳に入りました。私は好奇心が強いので、是非帰ってみたい、とにかく北京へ行ってみたいと思いました。「眠れる獅子(しし)」に譬(たと)えられていたように中国は本当に重苦しくて、自由にものが言えない時代がずっと続いていました。ですから、「あ、これは変わるかもしれない」という期待感がありました。二十四、五歳で何にもわからなかったけれど。
――それまでの楊さんの家庭環境の中では、自由な空気というのはなかったんですか。
楊 なかったですね。とくにうちはずっと抑圧されてきた階級だったし、私が生まれてから家庭生活が安定した時期というのはあまりなかった。
――お父様は、どういうお仕事だったんですか。
楊 父も母も、教師で。母は小学校で、父は大学で教えていました。だから、政治的な季節が来れば、うちはいちばん最初にターゲットになってしまう感じ。それともう一つは、出身がよくなかったんですね。出身階級というのがあって、母の家は地主の出身で、親戚には海外に行ったりした者がいて、外国と関わりを持つ人たちはまず信用されない社会でしたので、なおさら問題にされる環境でした。
――楊さんにとって毛沢東はどのような存在だったんですか。
楊 多分教育の問題もあって、私の時代ですと、毛沢東はすでに神様みたいな感じになっていました。私は一度も神様だと思ったことはないんですけれども、後になって反省すると、一応政治的体制として中国は社会主義ですけれども、宗教的になっていましたね、多分。
――九六八年には、フランスでは五月革命があって、中国では紅衛兵、アメリカではブラック・パワーとヴェトナム反戦運動、日本では東大紛争……それこそ三十歳を過ぎた人間は信用しないというような雰囲気があった時代です(笑)。楊さんの世代はその時代を知らないだけに、毛沢東に対する感じ方は多分、お父様とはだいぶ違うのではないですか。
楊 うちは迫害された階級なので、父は決して毛沢東を偉大な人物とは思っていませんね。私が五歳のときに我が家は下放されて、大変な田舎に追いやられてて、電気も何もないようなところでした。私の記憶だと、そこへ行くのにバスでまる一日。前のバスが事故でひっくり返って、死傷者が出たり、道をふさいだりしていて、ずっと夜通し立ち往生して……。毛沢東が死んだときは、私は小学校の五、六年生ぐらいだったと思うんですけれども、突然ある日、「ハルビンに帰りましょう」と、父の勤め先からトラックがやって来て、そのまま、またハルビンへ連れ戻されたんです。でも、以前に住んでいた家は没収されて住むところもなくて、学校の教室でずっと暮らしていたんですよ。そのあと火事があったり、いま考えると人間が生きる環境じゃなかった。