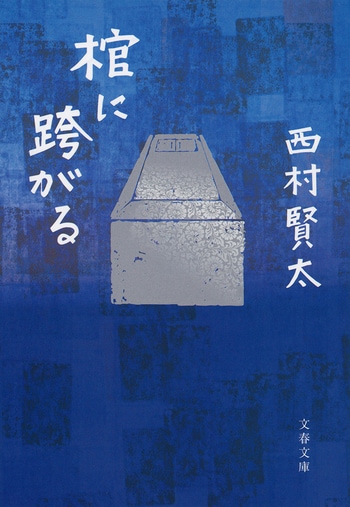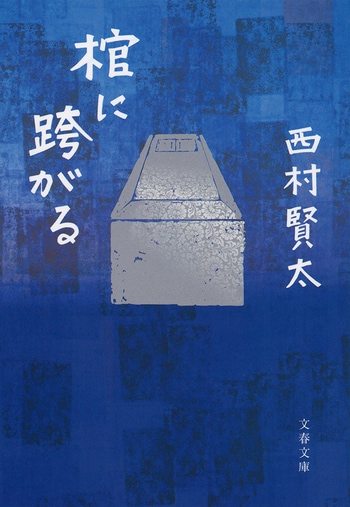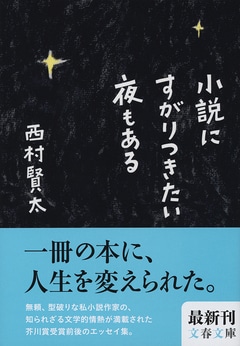作者自身の言葉によれば、なんと、もう「秋恵もの」は完結となるらしい。
嗚呼。
「秋恵もの」とは、定職もなくモテない主人公の男(多くは北町貫多という名)が一度だけ同棲した女性「秋恵」との、日々悪化する関係を描いた、ゆるやかな連作シリーズで、貫多の暴力癖やひねくれ根性を含め、人間の卑劣さ、醜悪さ、みみっちさ、いじましさ……要するにあなたの奥底にもきっとあるイヤ~な部分を、泥浚いするがごとく味わい尽くせる作品集です。
西村賢太のデビュー単行本『どうで死ぬ身の一踊り』、『暗渠の宿』の表題作、『小銭をかぞえる』、『廃疾かかえて』の表題作や「膿汁の流れ」、『人もいない春』の三篇、『寒灯』、『痴者の食卓』(「夢魔去りぬ」を除く)、『無銭横町』の「邪煙の充ちゆく」といった作品で、貫多に罵倒され、殴られ、蹴られて、それでもジメジメと応戦してきた秋恵さん。
この同棲カップルの泥仕合がもう読めなくなるのだろうか?
ふたりのやりあう姿は見苦しく、また、現代フェミニズムの立場からしたらとんでもない。女性の心身への暴力の酷さ、情けなさでいえば、日本の西村賢太の秋恵ものか、ウルグアイのスペイン語作家フアン・カルロス・オネッティの『屍集めのフンタ』かというものだ。貫多とフンタで韻まで踏まなくてもいいじゃないかと思うが、ちなみにこのオネッティという作家は、一時は忘れられていたが、後世の作家たちの熱い支持で再評価されるようになったらしいので、西村さんが敬愛する藤澤清造とちょっと似ている。
いや、そんなことはともあれ、いやだいやだと思うのに、目が釘付けになってしまう。それが西村賢太の世界だ。
「虫歯を噛みしめるような快感」
という表現をどこかで読んだ覚えがあるが、西村賢太の私小説を読む「快さ」はそれに近い。堪え性がなく、暴力癖があって、自尊心の高い男が、その性分ゆえにますますダメになっていく。にぶく疼く虫歯は苦痛だし、鬱陶しいし、できれば忘れていたい。とはいえ、どうでも去らない痛みなら、もういっそ、ぎりぎりと噛んで病んだ部分を痛めつけ、もっともっと痛い思いをしてやれ、歯ごと砕いてやれ……というような、自滅的快感である。
西村賢太の主人公にとって、おのが「性分」とは叩き直せるようなものではなく、不治の宿痾だ。作中には「根が~」という言い方が始終出てくるが、今ちょっと本をひらいてみても、「根が人一倍見栄坊にできてる」「根が意志薄弱」「根が歪み根性にできてる」「根が案外の寂しがり」(『苦役列車』)、あるいは「根が機嫌伺いにできて」いるくせに「根がムヤミと誇り高く」「根はかなりのインテリ」でもあり、しかし「根がへまにできて」いるうえ「根が人一倍懦弱」、ところが「根がかなりのスタイリスト」で「根が坊っちゃん気質」(『寒灯』)という矛盾のかたまりのような貫多。どっちを向いても、おのれの根性に首をしめられてしまう。
たしかに、性根というのは努力で変えられない部分もあり、稟性のもたらす痛みは天災めいている。しかし、ここで痛みの理不尽さに打ちひしがれるだけなら、それは惨めたらしい、ともすれば自己憐憫のまじる悲劇となり、あまり読みたくないが、虫歯を執拗に噛むところから笑いが生まれる。笑いは、痛みとの距離をつくる。
虫歯をいかにスタイリッシュに噛むかというところに、西村文学の本領はあるのだ。
そして、そこに日本文学の私小説の再生もある。