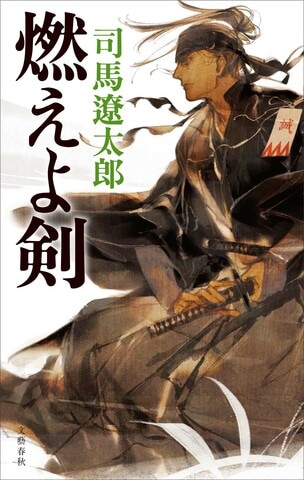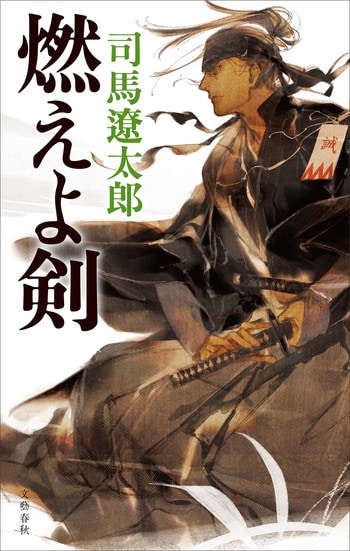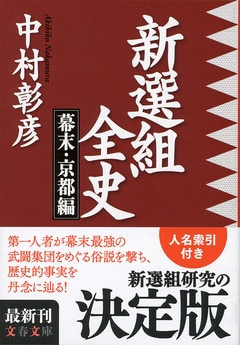小松エメル
こまつえめる/1984年東京都生まれ。2008年、『一鬼夜行』でジャイブ小説大賞を受賞してデビュー。著書に、新選組の無名隊士たちを描いた連作短篇集『夢の燈影』がある。
偏愛とは、「ある物や人だけをかたよって愛すること。また、その愛情」を意味する。これは、新選組好き歴十八年の私にぴったり当てはまる言葉である。
きっかけは覚えていない。ともかく(これだ!)とピンときた私は、ありとあらゆる関連書籍を読み漁った。当時は今ほどブームではなかったが、それでも数は多かった。その中で、司馬遼太郎作品を読んだのは、比較的遅い時期だった。
新選組をテーマにした小説といえば、『燃えよ剣』か『新選組血風録』のどちらかが挙がることが多いだろう。そんなメジャーであるにもかかわらず、真っ先に手に取らなかったのには理由がある。
新選組のことが知りたかった私は、毎日図書館に通い、検索機で見つけた本を頭から――つまり、五十音順で借りていった。その結果、両作にたどり着くのが遅くなったのだ。
先に手に取った『新選組血風録』は、十五の作品が収録されている短篇集だ。冒頭は、篠原泰之進を主役に据えた「油小路の決闘」である。
油小路の変は、慶応三年十一月に起きた、新選組の内部抗争事件だ。近藤勇率いる新選組が、分隊した伊東甲子太郎たち御陵衛士を一掃しようとしたのだが――そこに至るまでの事情は割愛するが、新選組は内部抗争や粛清が非常に多い隊だった。さらに次に載っている「芹沢鴨の暗殺」も、粛清にまつわる話だ。
新選組を調べれば調べるほど分かるのは、驚くほどに血腥(ちなまぐさ)く、ドロドロしている点だろう。司馬さんはそうした史実をモチーフにしつつも、実にさらりと描いている。だから、凄惨な事件が起きても、登場人物たちの動向や感情に心が動かされるのだろう。
時代小説は、史実をただ記したものではない。そこには多分に作者による創作が混じっているのだ。しかし、司馬さんの小説を読んでいると、虚実の判別がつかなくなることがある。物語だと承知の上で、(本当にこうだったのかもしれない)と思えてくるのだ。
そんな作家司馬遼太郎の説得力が存分に発揮されているのが、『燃えよ剣』だと私は思う。「土方歳三のイメージは?」と問われた時、大勢がこの土方を思い浮かべるに違いない。何しろ、この作品の土方はとてつもなくかっこいいのだ。
宿敵である七里研之助との戦いは、読者である私も拳を握りしめ、固唾を飲んで見守った。戦い一辺倒かと思えば、オリジナルキャラクターのお雪との純愛にはほろりとさせられた。『燃えよ剣』の土方は、実に人間臭い。泥臭く、熱く、バラ餓鬼と呼ばれていたほどやんちゃでありながら、ぞっとするほど冷徹だ。乱世を生き抜いた男の輝きが存分に描かれている。
この話を最初に読まなかった私は、幸運だった。もし、これを先に読んでいたら、私の中の新選組像は、司馬さんが描いた通りのものになっていただろう。
新選組を描いた小説を数多く読んできた私は、楽しみつつも、不満があった。それは、多くの作品が司馬さんの影響を色濃く受けているように見えた点だ。もっと違う新選組の話が読みたい――私はずっとそう願ってきた。
近年、浅田次郎さんや木内昇さんによって新しい新選組像が描かれたが、残念ながらそうした作品は少ないままだ。しかし、それは仕方がない話なのかもしれない。
『燃えよ剣』の土方は、やはり飛び抜けてかっこいい。近藤が愚かで役立たずな男として描かれている点は少々不満だが、沖田総司は明るく愛嬌がありつつも、ちょっと不気味で魅力的だ。
『新選組血風録』では、それぞれの隊士から見た新選組像が面白い。隊士といえど、皆が同じ方向を見ていたわけではない。それぞれの人生が見えてきて、彼らもまた一人の人間だったのだと思えた。これも司馬遼太郎の説得力が為せる業なのだろう。強引さも多々感じるものの、その自由さがまたいいのだ。
それに比べて他の新選組作品は、不自由なものが多い印象である。司馬さんが作った新選組像から逸脱してはならない――または、正反対のものを描かなければならないと思い込んでいるのかもしれない。
その疑いは、何年経っても晴れなかった。だから、私はこう思ったのだ。読みたいものを自分で書けばいいのだと――。
そうして書いたのが『夢の燈影(ほかげ)』という連作短篇集だったのだが、果たして司馬さんの呪いから逃れられたのかは分からない。分からないまま、今度は新選組の長編を書いている。
私は新選組を偏愛するあまり作家になったわけだが、実のところ一番後押ししてくれたのは「司馬遼太郎の呪い」だったのかもしれないと思った次第である。