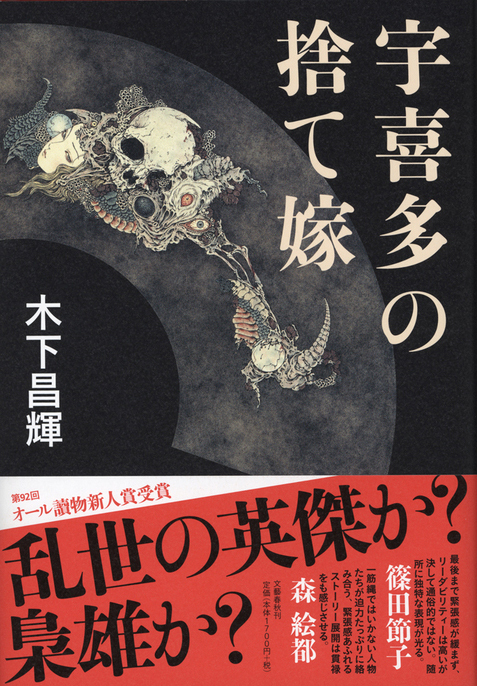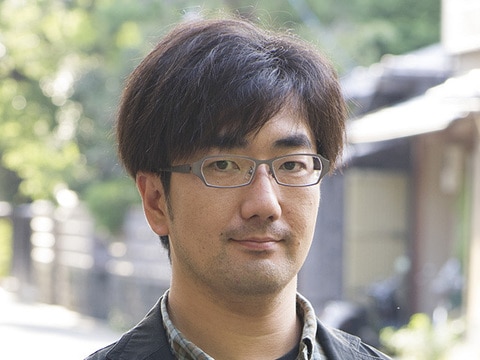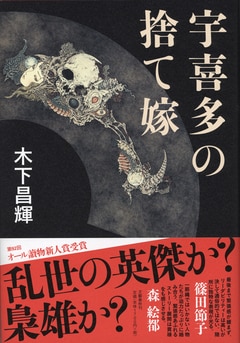「備中、備前、美作はまつろわぬ国々です。碁にて、三国の形勢を教えていただけぬか」
自分の声に安東相馬を試す悪意が隠しきれていないことを自覚しつつ、於葉は「碁の用意を」と侍女に声をかけた。
「碁盤は不要です」
於葉が振り返った時、すでに安東相馬は平伏していなかった。懐から碁石袋を取り出していた。普段から碁石を持っているとは、よほど碁が好きなのだろう。
「盤がなければ、碁もうてないでしょう」
「姫がおられる備前も、我ら後藤家がいる美作も、碁盤のように四角くはありませぬ」
碁石袋を開き、白石をひとつ取り出した。それを畳の目へと打ちこんだ。畳の目ひとつが、碁盤の一目ということだろうか。
「ここが宇喜多家のおわす備前、そしてこちらが我が後藤家の美作」
白石を上下にふたつ打った。その間隔から一畳を碁盤と見据えているようだ。
「まず北に尼子(あまご)」
備前と美作を示す二つの白石の上に、黒石をひとつ置いた。さらに「西に三村(みむら)、毛利」と口にして黒石を左に二目。「東にかつては赤松(あかまつ)、今は織田」と右に一目。中央にある備前、美作の白石ふたつを、黒石が囲みきってしまった。
西の毛利、北の尼子は謀略でのしあがった下剋上の代名詞ともいうべき戦国大名。東の織田家も、もとは守護代家臣から成り上がった勢力だ。そして、於葉の父宇喜多直家の形式上の主家・浦上家も主君を傀儡(かいらい)とすることでのし上がった過去を持つ。今、中国の覇権を争う大名たちはみな、主家を血祭にあげてきたのだ。
於葉のいる中国ほど下剋上の激しかった地はない。尼子、陶(すえ)、毛利、浦上、宇喜多の謀略を上手とする大名が鎬(しのぎ)を削り、そこに新興の織田が苛烈な圧力をかけてきた。結果、最も国が乱れたのが後藤家のいる美作だ。大勢力が何度も大兵で乱入し、その度に周辺土豪の旗幟(きし)が乱れた。“境目(きょうもく)の国(国境線のある地)”とも呼ばれるゆえんだ。
何気なく置かれた碁石だが、毛利、尼子、宇喜多と呼んで打ちこまれると、白黒の石から禍々しい臭気が立ち込めてくるようだった。
「もはや尼子は滅び、三村は弱体化し、毛利、織田、浦上、宇喜多が争っております。要となるのが浦上家と、その家臣である宇喜多家」
安東相馬は、備前の白石の位置を右手の人差し指と中指で微かに調整した。
「中でも宇喜多家が、中国十五ヶ国の争乱の鍵となりましょう」
安東相馬の目が妖しく光り、「沼城(ぬまじょう)、砥石山城(といしやまじょう)、龍ノ口城(たつのくちじょう)、金川城(かながわじょう)」と口にしながら次々と白石を備前の周辺に打ちこんだ。十数個の白石が一畳の中に広がる。
「まず、中山信正(備中)の沼城」
一番最初に置いた備前の石の左下の白石をとり、めくった。
「あっ」と於葉は小さく声を出した。
ただの碁石ではなかった。白石を裏返すと鮮やかな朱色に彩られていたのだ。
「次に島村盛実(貫阿弥)、砥石山城」と口にして、沼城の下方の白石を裏返す。また、目に鮮やかな朱石。さらに安東相馬が続ける。
「続いて、龍ノ口城の穝所元常(治部)」
「さらに金川城、松田親子」
「そして石山城、金光宗高(与次郎)」
一旦、安東相馬の手が止まった。白石の中に鮮やかな朱色の石が何個も混じっている。まるで白壁についた血痕を見ているかのようだった。
於葉は感情が顔に現れないように苦慮した。今、安東が口にした名前は、全て父である宇喜多直家が仕物した武将たちである。
それもただの仕物ではない。下剋上でのしあがった侍たちが唾棄するような、卑怯な方法であった。最初の沼城・中山“備中”信正は宇喜多直家の妻の父、つまり於葉の実の祖父にあたる。宇喜多直家の妻、つまり於葉の母の富は、夫が父を仕物したという凶報を聞き、自害してしまった。
そして、金川城・松田家と、その部下である虎倉城(こくらじょう)・伊賀久隆(いがひさたか)は於葉の実の姉二人の嫁ぎ先である。まず宇喜多直家は娘婿の伊賀久隆を籠絡(ろうらく)して、彼に主筋であり同じ宇喜多家の娘を娶(めと)った松田元賢(もとかた)を攻めさせたのだ。姉妹が敵味方として戦ったのである。滅びた松田家に嫁いだ長女の初は自害し、滅ぼした伊賀久隆に嫁いだ次女の楓は精神を失調し錯乱してしまった。
自分の娘を道具のように扱う謀略は、敵はもちろん味方や家臣からも忌み嫌われていた。