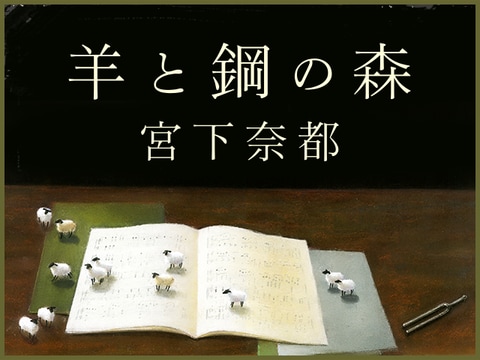『羊と鋼の森』(宮下奈都 著)
羊の毛のフェルトでできたハンマーで弦を叩くと、ポーンと音がなる。それがピアノの原理だ。タイトルにある「羊と鋼」とはこの鍵盤楽器の象徴だ。
北海道の山間部で育った外村(とむら)は十七歳の時、学校に来た調律師が生み出すピアノの音色に魅せられ自らも同じ道を進もうと決意。専門学校で学び、かつて自分を魅了した調律師、板鳥のいる楽器店に就職する。個性のある同僚や顧客たちとの交流を通し、彼は少しずつ成長していく。
外村の一人称視点で進むため、小さな出来事ひとつひとつに音叉のように心を震わせる青年の心情が細やかに描かれていく。調律と仕事を愛する気持ちは人一倍だが、ピアノも弾けない、音感が優れているわけでもないマイナスからのスタートは、この控えめで素直な性格の青年を不安にさせている。時には一人称だからこそ、彼の自意識が肥大して感じられるが、そこにこそ特別な才能を持たない人間の愚直さが現れており、心を寄り添わすことができるのだ。だから彼が先輩に言われる「才能っていうのはさ、ものすごく好きだっていう気持ちなんじゃないか」という言葉に、何の特殊な才能も持たずに生きている自分も、いつしか励まされている。
読み進めるほどに際立ってくるのは、決して登場場面が多くはない板鳥の魅力である。海外の演奏者からも信頼を寄せられる凄腕の持ち主でありながら、この北の町に留まり、ごく普通の高校の体育館にあるピアノの調律にも赴く男だ。高校生だった外村が弟子にしてくれと頼んだ時、「私は一介の調律師です。弟子を取るような分際ではありません」と、かわりに専門学校を教えてくれるような男なのである。外村が職場の後輩となった時にも「焦ってはいけません。こつこつ、こつこつです」「ホームランを狙ってはだめなんです」と諭してくれる。自分の才能に驕ることなく、地道に純粋に仕事に愛を捧げている人物像が浮かんでくるではないか。素敵。
その分、外村の自我が強く感じられてしまうわけだが、物語の終盤、そんな彼がピアノを美しく響かせることを優先させて、咄嗟に〈僕の恥などかまわない〉と思う場面では、成長を感じて胸が熱くなったのだった(まあ、恥をかくか考える時点で無我とはいえないが、それはおいといて)。
無粋なことを言えば、この小説に出てくる「音」や「ピアノ」は、すべて「文章」や「小説」に置き換えられそうだ。著者の、作家としての真摯な、強い思いが溢れているようにも思えてくる作品である。