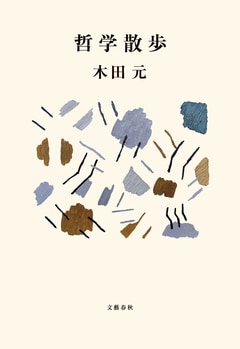私は木田先生とカルチャーセンターの企画者と講師という関係でおつきあいさせていただいたのが始まりで、その後、どう説明すればいいかよくわからないがとにかく先生の奥様、私の妻も含めた家族ぐるみのおつきあいをさせていただくことになった。ついでに言えば、拙著『季節の記憶』の蛯乃木という男のモデルの多田もそこに一枚も二枚も噛み(多田の奥さんも噛み)、みんなでカラオケに行ったり、花火大会を多人数で観に行ったり、先生との思い出は尽きない。
木田先生には生松敬三さんという、五十代で亡くなった大親友の哲学者がいらし、私と多田が先生とあんなに親しくさせていただいたのも、親友・生松敬三がいなくなった大きな穴があったからではないかと思う。
本書『哲学散歩』は不本意にも最晩年となってしまった数年間、思うに任せない体調の合い間を縫って書いた文章で、先生ご自身のまえがきに「二十三回」とあるが収録されているのは二十一回分しかないのは、連載の担当をした森さんに問い合わせたところ、二回分は気に入らず収録しないことにしたためだそうだ。
それゆえ本書では本業の、存在論とハイデガーの“思想”については書かれていない。そこに踏み込むにはやはり体力に自信がなかったのだろうと思う。思考というのは辛抱強く練り上げるもので、それには体力がいる。先生のお宅の庭には東京オリンピックで使われたのと同じ仕様の高鉄棒があり、先生はその鉄棒で大車輪ができた。だから体力といってもただの体力ではない。長男の反抗期には、
「庭へ出ろ!」
と言って、高校生の長男を背負い投げした。投げられた長男だって、高校で一人でボクシング部を立ち上げたような猛者(?)だ。
それで先生は小ネタのつもりで、一回ごと読み切りの文章を書かれたわけだが、アウグスティヌスやジョルダノ・ブルーノやプラトニズムや『薔薇の名前』の四回にわたる各回が木田先生のこれ以前の本では、最も専門と遠いと言えばいいのか、私は先生が書かれたものを読んだ記憶のないところで、ここで先生の別の面を見ることになった。
私たちの世代なら哲学事典の項目とウィキペディアをつなぎ合わせるか、多少の記憶と知識をもとに私見を書いて終わらせるところだが、木田先生はこれだけの長さの文章を書くために毎回何冊もあらためて専門書(先生から言わせれば入門書)を読んでいる。これは大変な手間だ。しかしきっと木田先生は、笑いながら「いやあ、たいしたことない」とか「文章書くんだからこれぐらいはあたり前だ」と、おっしゃっただろう。