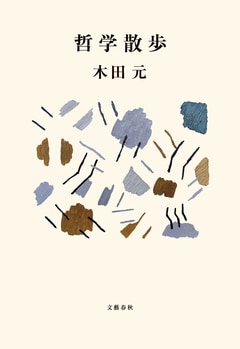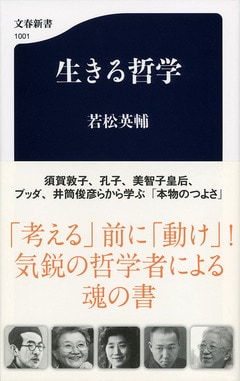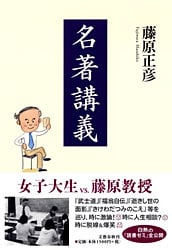もう四十年近い昔のことになるが、青土社社長の清水康雄さんが「もう、哲学教授はいらなくなってしまうね」と、溜息(ためいき)まじりに若年の小生に向かって呟(つぶや)いたことがある。一九七〇年九月、木田 元(きだ げん)著『現象学』が刊行されたときのことだ。社長といっても社員はまだ小生のみの二人だけの会社。「現象学のことをあんなに分かりやすく説明されてしまったら、大方の哲学の教師は失職してしまうよ」。苦笑しながらそう呟くのにはもちろん理由があって、自身、早稲田の哲学科出身で、酔うと「ヘン・カイ・パン(ギリシア語で一にして全という意味らしい)」と叫ぶのが常だった、つまり相当な哲学青年だったのである。
清水さんの呟きは誇張ではない。世はサルトル全盛の頃だったが、それでもなお哲学というものは分からないものだと相場が決まっていた。そのまた三十年ほど前、小林秀雄が西田幾多郎の哲学を指して「日本語では書かれて居らず、勿論外国語でも書かれてはゐないといふ奇怪なシステム」(「学者と官僚」)と述べているが、事情はその後もたいして変わってはいなかったのである。木田元が登場したのはそういう時期であって、二十代の青年の眼にも四十前後の中年の眼にもじつに新鮮に映った。何といっても日本語で読める哲学書が登場したのである。それも、フッサール、ハイデガー、メルロ=ポンティといった「難解な」哲学をめぐる入門書だったのだ。
哲学の本が「日本語で」書かれるようになったのは木田元以後である、と言いたい。感謝しなければならないのだ。
木田先生の新著『なにもかも小林秀雄に教わった』を読んで、当時の記憶が油然(ゆうぜん)と蘇ってきたのは、先生のこの本自体が読書回想録だからだ。先生は敗戦を江田島の海軍兵学校で迎えられた。十六歳である。だから広島の原爆投下を目撃しておられる。幼少年期を過ごしたのは満洲で、家族は彼の地にあった。記述に暗さは微塵(みじん)もないが、その後、並大抵ではない苦労をされた。何よりも本に飢えていた。新著には、どこでどんな本をどういうふうに読んだか、誠実に書いておられる。少年は、本が簡単には入手できない時代に、芥川、茂吉、朔太郎、芭蕉、蕪村、安吾、太宰といった文学者の本を次から次へと読んでいるのだ。