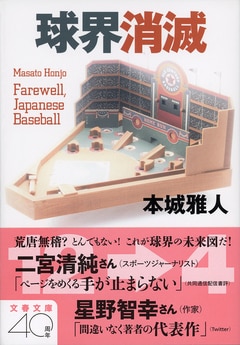手を繋いだまま咲子が同じように天を見上げた。
藤村と咲子の三人でたっぷりと水分を含んだ雪の上を歩き、赤の広場のレーニン廟の前まで移動する。高い壁の向こうにあるクレムリン宮殿を眺めるには、ここが一等地だ。
「アメリカの記者はいますけど、日本の記者はうちだけみたいですよ」
藤村が周囲を見ながら言った。
「そんなことより、今はその瞬間を見ようじゃないか」
土井垣はモスクワの漆黒の夜空から視線を動かさなかった。
――きょう、クレムリンのソ連国旗が降ろされるぞ。
ゴルバチョフ大統領が辞任の意向を固めたという一報が出て以来、取材に駆けずり回っていた土井垣に、この日の夕方、一人のウオッカ友達がそう教えてくれた。土井垣はそのシーンを目撃したかったし、日本から応援に来た二人にも見せてやりたかった。歴史的瞬間に立ち会い、それぞれの目で目撃することが東洋新聞の財産になる。
「おお、間に合ったか」
桑島が白い息を吐きながら走ってきた。
「あっ、あれじゃないすか」
藤村が手袋を嵌めた指を差し、叫んだ。
クレムリンの屋根に二つの人影が現れたのだ。
土井垣はふと思って、コートの袖をまくり左腕に嵌めた腕時計を確認した。秒針がちょうど十二の数字を通過したところだった。二つのシルエットはドームの上をするすると駆け上がり、ソ連国旗を降ろし、そして白青赤のロシアの三色旗を引き上げていく。土井垣が旗から目を離した時には彼らは姿を消していた。わずか三十五秒の出来事だった。
「あのソ連がついに終わったのね」
咲子が感慨深そうに呟くと、桑島は「まるで幻想の世界にいるようだな」と旗から目を離すことなく言った。土井垣も夜空に翻るロシア国旗を見ながら夢を見ているようだった。四年八カ月に及ぶモスクワ特派員としての仕事が頭の中を駆け巡っていく。
「みんなでウオッカを一杯、ひっかけてから帰ろうか」
土井垣が言うと、藤村が「原稿を送らなくてもいいんですか? まだたくさん残ってますよ」と心配顔で尋ねてきた。
「きょう起きたことはすでに東京本社も知ってることだ。今見た光景だけ、俺があとで送っておくから」
ソ連と日本の時差は冬時間で七時間、東京は夜中の二時半だからすでに朝刊は降版している。記事は明日の夕刊に間に合うように、支局に戻ってから書けばいい。
赤の広場から、グム百貨店の横を抜けて、最近できた西洋風のバーに向かう。
「こっちが近道だ」
前を歩く桑島のコートを引っ張り、土井垣が右折すると、十メートルほど先の十字路を二人組の男が横切るのが見えた。
「やっぱり真っすぐ行こう」
戻りかけたところ「あの男、政治局の人間じゃないか」と桑島が、二人組の年配の男を見て小声を出した。
二人は話に夢中で土井垣たちに気付いていなかった。年配の男は以前、土井垣も取材したことがある。ゴルバチョフが進めた新連邦条約に動いていた人物だ。
だが土井垣が気に留めたのはもう一人の、隣を歩いていた若い男の方だった。なぜ彼があの男と一緒にいるのか――。