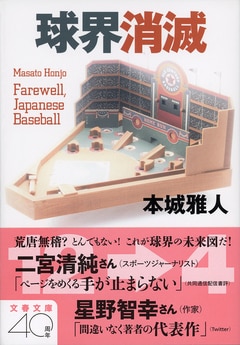プロローグ
〈親愛なる皆さん、独立国家共同体が形成された結果、私はソビエト連邦の大統領としての活動を停止します。私は不安を残してここから去ります〉
東洋新聞モスクワ支局のブラウン管テレビに、ミハイル・ゴルバチョフ大統領が苦渋に満ちた表情で会見している姿が映し出されていた。ソビエト中央テレビに目をやりながら、土井垣侑は日本から応援取材に来た同期の桑島佳樹と、三期下の藤村信一との三人で、この日起きた一連の事柄について、原稿用紙に書き綴っている。
一九九一年十二月二十五日、午後七時。三十一日をもってソビエト社会主義共和国連邦が消滅するとゴルバチョフが発表した。八月クーデター以降、ベルリンの壁の崩壊など東ヨーロッパにも多大な影響を及ぼしたペレストロイカはすでに頓挫し、ゴルバチョフが望んでいた連邦制の維持を断念せざるをえなくなったことは周知の事実だった。この日は、激動の中で歴史が転換する節目の一日となった。
三人で分担した原稿のうち、土井垣は自分の分は書き終えた。
「おい、桑も藤村も早くしろ。間に合わなくなるぞ」土井垣はウールのコートのポケットにペンやメモ、カメラを入れながらせっつく。
「まだまだ書かなくてはいけないことがたくさんあって、時間がかかりますよ」
後輩の藤村が真剣な目で取材メモを見ながらそう言った。
「会見は日本にも衛星中継されてるんだ。通信社もきょうはたっぷり配信するだろうから、細かい記事は東京本社の内勤に任せとけばいいんだよ」
「土井垣と藤村は先に行っててくれ。俺もとっととやっつけて、すぐに追いかけるから」
一面本記を任せた桑島がボールペンを走らせて言った。
コートを羽織り、手袋を嵌め、シャープカを頭に被って支局を出ると、隣の自宅から妻の咲子が出てきた。土井垣同様、コートにシャープカを被り、首にはマフラーを巻いている。
「寒くない恰好をしてきたか?」
「セーターを二枚重ね着してきたから大丈夫」彼女はお腹に手を当てて笑った。
タクシーは赤の広場の近くで停まった。ドアを開けると冷気が顔に当たった。地面に足を下ろす。靴の半分が一瞬で雪の中に埋まった。両足で踏ん張って立ち、車から降りてきた咲子が転ばないように手を取って支えた。
ロシア正教のクリスマスは一月七日とあって赤の広場に賑わいはなかった。隣接するグム百貨店には若い客が出入りしていて、六十九年間続いた祖国の崩壊に誰も関心を持っていないように思えた。六年前、ゴルバチョフの登場とともに沸き上がった改革への熱気などとっくに薄れている。インフレと品不足、国民の政治への期待は消え、もはやここには冷やかな感情しか残っていない。
顔を上げて、クレムリンの赤い星の横、ソ連閣僚会議ビルのドームに立つ国旗に目をやった。真っ赤なソ連旗が風に靡いている。
「まだみたいね」