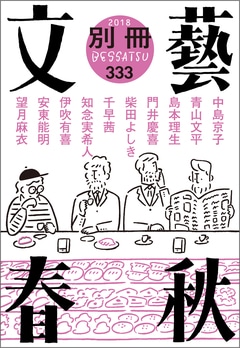序章
「お迎えに上がりました」
男は、黒いシルクハットを手に頭を下げた。
初老の紳士だ。右目に片眼鏡、黒いスーツの胸ポケットにハンカチ、手には白い手袋、足許には黒い革靴が光っている。おそらく、胸ポケットの留め金は懐中時計だろう。
まるで英国紳士のような出で立ちであり、そんな彼の背後には、誂えたかのような大正時代を思わせるアンティークな高級車が待機している。
車の色も黒であり、彼の靴同様、光るほどに磨かれていた。
何もかもが、少し時代錯誤のように感じたが、彼は京都からの使者。
古今混同している都の人間は、こんな感じなのかもしれない。
それにしても、東北の三月はまだまだ寒く、決して春とはいえない。
雪も残るような中、この車で大丈夫だったのだろうか、と思わず訝ってしまう。
「まあまあ、置屋から迎えが来てくれたなんて、良かったねぇ、ありす」
叔母が心からホッとしたように、少女・ありすの肩に手を載せる。
ぼんやりと立ち尽くしていたありすは、叔母の言葉に我に返り、曖昧に頷いた。
おさげにした髪が、揺れる。
ありすの髪は長い。
伸ばしているのではなく、なんのことはない、美容室に行かせてもらえなかったからだ。
ある程度伸びると、自分で切り、その雑さが目立たないように二つに編んでいた。
初老の紳士は、そんなありすを前に、にこりと目を弓なりに細める。
田舎のみすぼらしい少女だと思っているのだろう。
微笑みながらも、こんな冴えない子に務まるのかと思っているのかもしれない。
居たたまれなさにありすが俯きかけたその時、声を聞きつけた叔父が「なんの騒ぎだよ」と家の前に出てきた。
「あなた、ありすにお迎えが来たのよ。良かったわ」と叔母は胸に手を当てる。
「へぇ、迎えが来たなら、交通費返せよ、ありす」
叔父は、頭をぼりぼりとかきむしりながら、大きな手をありすの前に出した。
「もう、京都までの交通費は、ありすが自分で貯めたものなのよ」
「これまで俺が世話してやったんだ。使うはずだった交通費をこっちに寄越すくらいの気持ちがあってもいいだろ!」
「いい加減にして頂戴!」