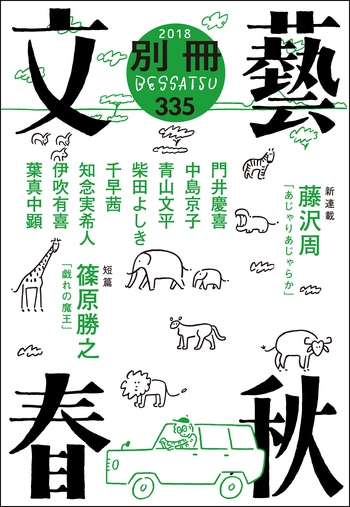稲刈りも終わった農道はだらだらと緩い登り坂で、向かい風に喘ぐ様を周囲に覚られまいと必死でペダルを漕ぐ。田んぼの草取りをしているジジババは、目深に被った編み笠からちゃんと見ているのだ。立小便すらウッカリ出来ない。
一番キツくなるY字路にさしかかろうという辺りで、あろうことかバッテリーが切れた。
「何てこったバカたれが!」
自転車を降りて思わずサドルに毒づく。大根の葉っぱが顔をだす籠を取り外して背負い、重い鉄のカタマリと化した電動式自転車を押して歩く。
しばらくするとオレの背後に、何かが低速で迫って来る気配がした。ふと振り返ると、黄色とオレンジが入り混じったビタミンカラーの毛糸の帽子を被ったバアサンが何食わぬ顔で、電動式四輪車に座ったまま悠々とオレを追い越していく。
『チキショーめ』
心の中で吐き捨て、あんなものの世話になぞ絶対になるものかと、二輪車を押す手に力が入る。
最近、作業場の敷地にヒッソリと作ったオレの畑に野生の泥棒どもが入り込んでくるようになっていた。猿を筆頭に、鹿、イノシシ、タヌキ、キツネ、ハクビシン……。
ケシカランことに喰いごろになったオレのトマト、ナス、スイカ、イチジクなどをかっぱらっていくのだ。買い物弱者のオレにとっては死活問題である。
初めは果実の一つ二つが減っている程度なのだが、群れの斥候役の若い猿が深夜から明け方にかけて調査にきて、目をつけていた果実が旬になると真っ昼間からお構いなしの大群でやってくる。
奴らは初モノを前にして喜びが飽和状態になると、鳥みたいな甲高い声をあげて群れで貪り喰うのだ。そうなるともうお手上げだ。野鳥類なら木刀を振り回して簡単に追っ払うが、有限の体力と時間を獣との小競り合いに浪費させるのもバカらしい。
オレは仕方なく作業場二階のコクピットと呼んでいる書斎兼寝床に潜んで、備え付けの双眼鏡でウオッチングする。奴らはオレになど目もくれず、狙いのモノから目を離すことはない。
奴らは果実を咀嚼するときに口元と連動して鼻や耳を痙攣させる。その様子をじっと眺めていると、あらぬ方に向けられているまっ黒な眼差しが見据えるのは、辺りの景色などではなく壮大な宇宙だというコトに気づかされる。双眼鏡のレンズの中に宿る野生。その眼差しを作物の代金に換えてやってもイイとさえ思う。オレが食う分を少しだけ残してくれたらあとはいいのだ。
そんな獣らをのぞけば、最近は訪ねてくるヒトも殆どなく、宅配便の配達人、プロパンガスの交換や水道検針のオバヤンぐらいだったが、その日は舞踏家のマロが作業場に来ることになっていた。