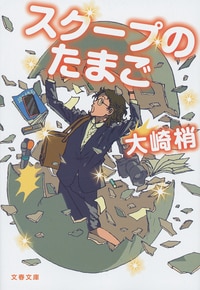
二〇〇六年に書店員を主人公にしたミステリ『配達あかずきん』(創元推理文庫)でデビューした大崎梢は、その後も出版社や移動図書館など〈本の周辺〉を舞台にした作品を多く発表、読書好きの熱い支持を得ている。
その中でも注目されているのが、老舗出版社・千石社を舞台にしたシリーズだ。女子中学生向けファッション誌編集部に異動した男性社員の奮闘を描く『プリティが多すぎる』(文春文庫)、惚れ込んだ小説をなんとか出版したいと奔走する文芸編集者が主人公の『クローバー・レイン』(ポプラ文庫)。それぞれ独立した作品ではあるが、続けて読むと「出版社」という大きな組織を構成する顔のひとつひとつが見えてくる。
その千石社シリーズ三作目が、本書『スクープのたまご』だ。
だが少々毛色が違う。他の作品は、その仕事に励む主人公を読者は無条件に応援してきた。ファッション誌の意外な裏側に驚き、文芸単行本のシビアな現実に慄きながら、彼らが〈いい仕事〉をして、立派な編集者になる過程を見守ったものだ。
しかし『スクープのたまご』は、読む前から、主人公を応援できるだろうかという不安があった。この主人公が為すべき〈いい仕事〉が何なのか、わからなかった。
なぜなら、週刊誌編集部の話だから。
不幸に群がり、人の秘密を暴き立て、容赦なく叩き、時にはその対象が社会的に抹殺されるまで追い込む。そんなイメージがつきまとう週刊誌編集部の話だから。
いやあ、正直に書かせてもらうと、どうしても好きになれないのだこの手の週刊誌って。自分も書評などを寄稿している立場だから言えた義理ではないのだが、SMAP解散のきっかけを作られた恨みは忘れない。そこの話なのかあ。うーん。
でもその一方で、大崎梢という名前は〈本の周辺〉小説に関しては信頼と実績のブランドである。本と、それを生み出す人々に対する愛情に満ちた多くの作品を何冊も届けてくれている。そして大崎梢本人は、下世話なスキャンダルやバッシング記事には眉を顰める、とても穏やかで優しい女性だ。
その大崎梢が週刊誌編集部をどう描くのか。その興味が私にページをめくらせた。
主人公は千石社に入社二年目の信田日向子。入社時の配属はPR誌で、企画を出すのも記事をまとめるのにもようやく慣れてきた。そんなとき、国内トップクラスの部数を誇る千石社の看板雑誌「週刊千石」に配属された同期が体調を崩したと知らされる。しかも本人に話を聞くと、やられたのは体よりメンタルの方だという。結局その同期は他の部署に異動することになり――日向子にお鉢が回ってくる。
事件を追う班に入れられ、わけもわからず先輩の指示に従う日々。幼い見た目を利用し高校生になりすまして情報を入手したり、アイドルのやばい写真を持っているというタレコミに対応したりしながら、日向子は少しずつ週刊誌という仕事の何たるかを知っていく――というのが、物語の骨子だ。
巧い、と思ったのは日向子の設定だ。日向子自身が、週刊誌を苦手にしているのである。日向子は「週刊千石」を「朝昼のワイドショーよりえげつないと思っていたし、売らんがためのねつ造記事もあると思っていたし、暴かれたことで傷つく人がいるのは気の毒以外の何ものでもない。良心はないのか。品格はないのか。義憤にかられるのはしばしばだった。長いこと憧れ続けた出版社の、唯一の難点だ」と考えている。
だよね、だよね、と頷いてしまう読者は少なくないだろう。なのに彼女は、その週刊誌の編集部に配属されてしまうのだ。うわあ、どうするんだろう……最初の嫌悪感はどこへやら、初手からがっつり日向子を「応援」する気にさせられているのだからたまらない。すっかり著者の術中である。
次に読者を驚かせるのは、週刊誌編集部の仕事の実態だ。本書を書くにあたって著者が取材したのは「週刊文春」である。もちろん変更や脚色はあるだろうが、編集部の構成や仕事の方法などについては、多くを参考にしていると考えていいだろう。
どのようにネタを決め、どのように取材し、どのように記事にするのか。その具体的な描写もさることながら、注目すべきは記者たちのスタンスだ。たとえば、取材や執筆を担うのは外部のフリー記者ではなく、ほとんどが社員だという。いい加減な記事を書いたり一発大ネタ狙いの賭けに走って失敗したりしたら、会社員としての将来が閉ざされる。だから必ず裏を取る。真実だと自信のある記事しか載せない。それだけの責任を持って雑誌を作っている、と。
蒙を啓かれた思いがした。なるほど意外と真面目に作っているのだなと認識を若干改めた。だが日向子も読者も、それで簡単に懐柔されたりはしない。やはり戸惑いと不信は払拭できない。だって悪名高き週刊誌だもの。
それがもうひとつの読みどころだ。日向子は悩み続けるのである。
主人公が週刊誌の記者ということは、本来なら、いくらでも主人公や他の登場人物の口を借りて週刊誌の正当性を主張させることができるはずだ。週刊誌は素晴らしい仕事なんですよ、といくらでも書こうと思えば書けるはずだ。
だが大崎梢は、それをしない。その代わり日向子にアイドルのスキャンダルを担当させ「ひとりの女の子が真っ暗な穴の底に転落していく。止めるどころか背中を押すまねをして、いいんですか」と先輩社員に食ってかからせる。取材対象に「人の家の不幸に群がって」「恥ずかしくないんですか」と罵らせ、日向子に「恥ずかしかった」「ずっと思ってる。こんなことをするために大人になったのではない。東京に出てきたのではない」と泣かせる。そんな日向子の逡巡を、葛藤を、闘いを、そしてそんな仕事の中にはからずも時々喜びを見つけ始める様子を、読者の眼前に突きつける。
大崎梢がそこに込めた思い。それは週刊誌は普通の人が作っている、という当たり前の、けれど忘れがちな事実だ。下衆なハイエナでも斜に構えたアウトローでもなく、普通の人が、ときには悩みながら、ときには泣きながら、ときには自負を持って、ときにはプライドを賭けて、仕事に向き合っている。
普通の人である日向子が「週刊千石」編集部で見出したものは何か。なぜ週刊誌というものが必要なのか、大きく動く事件の最前線で日向子がたどり着いた答えは何か。本編でじっくり確かめてほしい。ゴシップだろうと事件だろうと、自分には関係ないと思うような事件だろうと、「本当は誰にとっても無縁ではない」と日向子が考える場面がある。その意味がとても重い。本書は決して週刊誌を礼賛も擁護もしない。ただ、相手を選ばず、こうと見込んだら徹底的に追及する週刊誌だからできることがある。週刊誌にしかできないことがある。それがまっすぐに伝わってくる。
週刊誌は好きになれない――そんな人にこそ本書を読んでほしい。好きにはなれなくても、少し、見方が変わるに違いないから。
千石社シリーズはすでに四作目が「オール讀物」に掲載中である。次なる舞台はスポーツ雑誌編集部。主人公は本書にも登場した、日向子の同期で友人の目黒明日香だ。またこれまでとは違った出版社の顔を、けれどそこにある共通する思いを、読者に届けてくれることと思う。楽しみにお待ちいただきたい。

















