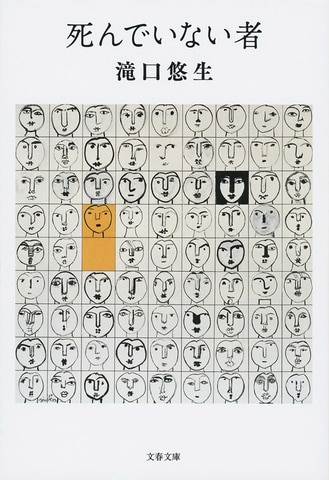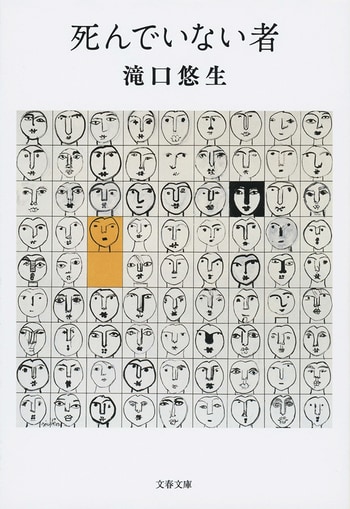とても大きな小説を読んだ、という感想だった。文庫で一八〇ページほど、ある一族のほぼ一夜という短い時間を描いた「死んでいない者」という小説は、その分量と扱う時間の短さに見合わない、大きさと高い密度を持っている。死んでいなくなった者、未だ死んでいない者たちの間をゆっくりと移動していく語りはいつのまにか、読み手を人間の間を移動する旅へと送り出すようでもある。
一人の故人の五人の子供、五人の子供のさらに子供たち、その子供の子供、という、大人数ではあるけれども特に大きな変哲のない一族が、亡くなった人物の葬式を待っている。親族が亡くなった夜は、たとえば八十歳を過ぎた祖父母の機能停止にも似た死のように、あらかじめ予想されたものであればあるほど、悲しみと同時に俯瞰的な感情がわき上がってくる。筆者が祖父母を喪ったときもそうだった。「たくさんの人間が、一人の死をきっかけに続々と集まってくる」という状況が、なんというか滑稽なのだ。普段はそんなに行き来もない親戚同士なのに、葬儀会場の広い控え室に集まって、悼んでいるのかどうかわからないおじさんがいばっていたり、おばさんがうろちょろといろんな人の輪の中を移動している。「地元の葬儀屋に町内の有志が加わって昼から行った花輪の設置や、祭壇や斎場の設営、宴会の準備などはみな慣れたもので、息の合った連係や作業の手際は見事だったし、浮き浮きとさえして見えた」と滝口さんは葬儀の前の様子について書いていて、筆者の場合はすべて葬儀会場を経営している企業がやってくれたわけだけれども、まったく想像に難くない。人の死によって日常についたどこか妙な起伏を年長者たちは乗りこなしていて、人の死に慣れない若い者は少し遠い場所で状況を持て余している。祖父母の一連の葬式で涙が出たのは、母親の友人たちからあたたかい言葉をかけられた時で、親族たちはむしろ、死者と対比的に振る舞うように生き生きしているか、ぼんやりしているかだった。