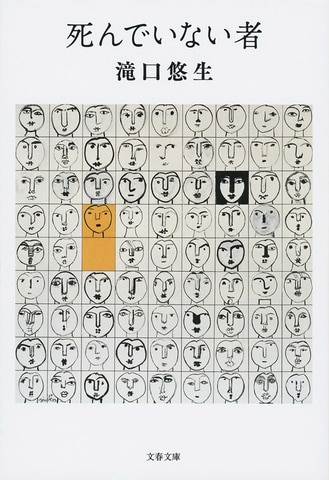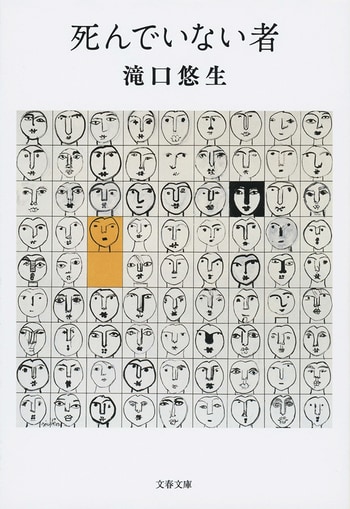怒っているんじゃない。奇妙だったのだ。奇妙な夜は数時間だが永遠でもある。ある人物が亡くなった通夜はもう二度と来ない。本書には、そのかけがえのない経過を取り巻く人々の、親族の死によって喚起される心境と過去、そしてあの日常と切り離された夜の空気が余すことなく書かれている。たとえば故人の孫の一人がアメリカ人のダニエルと結婚しているということであったり、二人のまだ子供の兄弟をおいて失踪している父親がいたり、すこし変わっていることや不穏なことはありつつも、故人の死を取り巻く人々はおおむね普通だと思う。けれども、彼ら一人一人の心持ちとプロフィールが軽重をつけずすべて同等の体験として集合する時、それはある種の壮大なモザイクとして唯一のものになる。
妻が栓抜きを使わずに瓶ビールのふたを開けられることを知る、寝ずの番を前に近所の温泉施設にみんなで出かける、孫より下の世代の者たちが集まって飲みつけない酒を飲んでいる、いとこが猫をなつかせることが上手であるということを初めて知る。本書では、誰の身の上にも起こり得ることでありながら、小さな非日常が頻出する。そこには確かに、外側から眺める分には浮き浮きするような感覚もある。親族たちが連れ立って温泉施設に行くくだりなどはそれの最たるもので、故人の孫の紗重(さえ)の夫であるダニエルは、小説全体を通してその感覚の中を鷹揚にさまよっているように見える。「お酒飲んで、温泉入って、旅行みたい」という高校生の知花(ちか)の疑問に、メキシコではお葬式はお祭りなんだという答えを持っているダニエルは、故人の義理の息子である血のつながりのない親族と風呂に入りながら、義理とは何かについて考え、妻との間にこそ義理があると思い至り、湯あたりする。初めての湯あたりを体験した風呂も温泉も好きなダニエルが「しかしこういうふうに、そこに身を浸してみなければ何が起こるかわからない。ひとつとして同じお湯はないのだ、それが温泉の魅力なのだ」と考える場面の、のんきな深遠さはとても味わい深い。親族の死という出来事によって限定される思考と、そこから解放されるまでの時間の長さが感じられる。