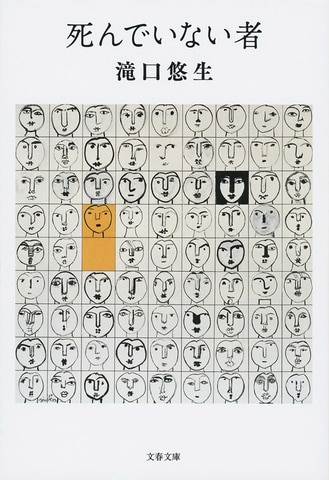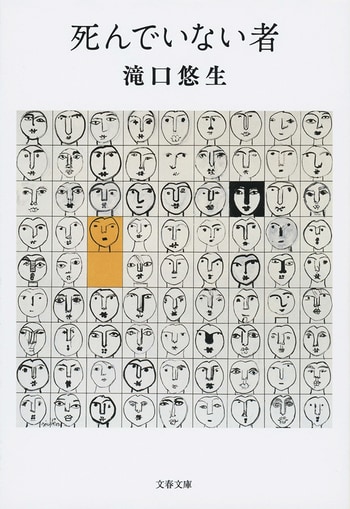大学を中退して結婚し、働き始めたもののうまくいかず酒に溺れていた寛が、体調の悪い妻を家に残して、一人祖母の葬式に電車で向かいながら、川を見て不安や心配が取り払われたような気持ちになり「もう一度川が見えたら、その瞬間の気持ちを絶対に忘れないようにして、酒もやめて、ちゃんと生活を送る。仕事もする。家族を幸せにする」と考えるけれども、川が現れないまま目的の駅に着くという巡り合わせは痛切に思える。また「自分よりも弱い者を前にしただけで、まるで自分が強い者であるかのように振る舞わなくてはならないことになり、一緒に弱くなれない」という一文に続く、息子たちへの寛の思いが綴られる部分は本当にすばらしい。この部分の、今まで誰も語れたことがなかった父親という人たちの嘆きは、おそらく小説でしか集約できず、描くことのできない感情なのではないか。すごいと思った。
死んでいない者は親族以外にもいる。故人の友人のはっちゃんは、故人と出かけた敦賀への二人旅のことを思い出す。理由も経緯も思い出せない旅について、はっちゃんと故人が会話をする場面には、ゆるやかに忘れ去りながらも、確かに記憶そのものが自分の中に横たわっているということの愉悦がある。それは故人が殊更に何かを成し遂げなくても、ただ「いた」ということに意味があるのにも似ている。
併録の「夜曲」では、そのはっちゃんと故人が通っていたかのような、事情のありそうなママのいるスナックでのやりとりが描かれる。開店十周年を祝う客たちの寄せ書きの色紙がすでに十年近く前のものになる、というスナックで交わされるママと客たちとの、ゆるいようでわずかな緊張をはらんだやりとりがおもしろい。「同じようでいて同じ会話は二度とない」という言葉には、本書全体の主題が表れているように思える。