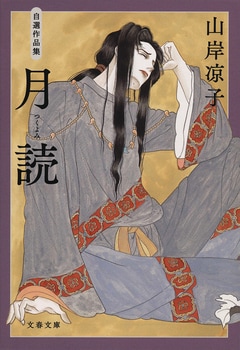山岸凉子さんの作品に出遭ったのは、私の娘が中学一年のときでした。夢中で読書しているので、何の本かとのぞいてみると、それが山岸さんの『日出処の天子』。それで私もすっかりハマってしまって、聖徳太子に興味が湧き、それが昂じて奈良の法隆寺に家族旅行までしてしまいました。
主人(篠田正浩監督)は日本の歴史に関しては専門と言えるほどで、著書もあり、夢殿や玉虫厨子を主人の解説で見学して廻りましたが、帰り道で娘が何か見るのを忘れた、と言って泣き出したりして、タクシーでまた引き返すほど母娘で熱中したものでした。
山岸作品のどこにそんなに魅了されたかと言えば、歴史上の人物の大胆な解釈――この時代は史実もそれほどはっきりしないでしょうから、自由に大胆に描けるその面白さ。厩戸皇子がBL(ボーイズラブ)であったり、近親相姦や超能力、そういった普通でないこと、異常なことを描きながらも、普遍的な、誰もが持っている感情に突き刺さってくるんですよね。厩戸皇子には、母親の愛情をまったく受けられなかったという究極の悲劇があります。山岸さんの作品には、得体の知れない怖さがあって、そこにとても惹かれましたが、その根底には人の胸にグッと迫る切実さがある。
そして、想像力を駆使して自由に作りこむ一方で、時代考証などはとてもきちんとしていらっしゃる。アクセサリーや衣裳ひとつとっても史料を見ながら描いておられることにも感心しました。
『ハトシェプストⅠ』に登場する姉妹。姉が石の一種であるメヌウ、妹が花のセシェン(水蓮)、という名前なのもとても象徴的だと思う。日本の神話(古事記)にも、姉が石長比売、妹が木花佐久夜毘売という設定があって、山岸さんは別の作品でこれを現代の物語として描いておられますね。
メヌウとセシェンの姉妹は、妹は美人で色っぽくてやたら男の人に目が行く。私はそういう女をふりかざしてるような女性は苦手で、姉のメヌウのような知恵の人に好感を持ちました。
そのメヌウが、エジプトに唯一人いたという女性のファラオ、紫色の瞳を持つハトシェプストに強く惹かれていくわけです。この、平和を愛したというハトシェプスト王の時代は、二十何年間か、長く続いたようですが、その死後は実子でない者が跡を継いだので、まったく歴史の舞台から抹殺されていて、三千年ののちに発掘によって甦った、というのも、興味深いことです。これも山岸さんの作品世界によく出てくる肉親間の醜い権力闘争の結果と言えますね。
それで、メヌウとセシェンですが、妹のほうがイメージで出血を止めることができる。でも、ハトシェプストの父王の死で、罰として形だけの死刑が行われると、セシェンは本当に死んでしまう。イメージで血を止められる者は、死をイメージすることで死んでしまう、ということなんですが、この発想はさすがです。思わずハッと息を呑むほどですね。
そして『ハトシェプストⅡ』は、ハトシェプストがお転婆だった少女時代に遡ります。
ここに登場するのが、ミケネ(クレタ島)の巫女(みこ)ロドピス(薔薇のかんばせの意)という不思議な女性。少年のようなハトシェプストも、やがて成人して初潮を迎える。自分の体が女らしくなっていくことへの激しい拒絶感から蓮池で水浴びをしていると、そこにロドピスが現れて、激しく抱擁する……。
「わたしがあなたを、女でありながら男にしてあげる」「あなたの生き残れる道は、王(ファラオ)になることよ」というシーン。ハトシェプストの裸体に、蛇がスーッと這い登る、あの官能的な絵がとても印象的でした。
つまりは、女が女と交わることによって、少女は男性性を植えつけられる。
「たとえ王妃でも女はしょせん男の道具でしかないわ」「どんな手を使ってでも王になるの」「この国の絶対の権力者、何者にも口をさしはさませぬ者」「それには自身(みず)から王(ファラオ)になること」というロドピスの台詞がありましたが、ハトシェプストはここで絶対的な権力者、王(ファラオ)の精神性を植えつけられたのでしょう。その後、紫の瞳の色がさらに濃くなった、というそのイメージ表現がすごい! と思いました。
『イシス』を読んだとき、うわぁ、私これ、若かったら舞台で演じたかった! とまず最初に思いましたね。前に映画で演じた『卑弥呼(ひみこ)』と非常に通じるものを感じたからです。
イシスは魔力を持つ高貴な女性で、でも、髪は白髪で、眼は血の色をしている。兄であり夫であるオシリスが、双子の弟セトに二回にわたって殺されても、それを蘇生させる超能力を持っている。口から白い煙のようなものを吐き出して、あれがイメージを形づくっていくんでしょうね。
でもそれを成功させるたびごとに自分は若さを失って、老婆のように衰えていく。最終的にはつかのま蘇生したオシリスと、美人の妹ネフティスを交わらせて、生まれたホルスという男の子を、自分の子として育て上げる。そしてオシリスの仇、セトを討たせるのだけれども、セトに片眼を刺されたホルスの傷を治すのに魔力をすっかり使い果たして、イシスは消え入るように死んでいく。すると、その死体がみるみる若く甦って美しくなっていく……。このシーンは、演じる者としてゾクゾクしますね。
ここで私のことを少し話しますと、『卑弥呼』は出産三カ月後に演じましたけど、母乳で育てようと思っていたのですが、退院十日後にシナリオを渡されてそれを読み始めたら、ピタッと母乳が止まってしまいました。撮影中は、まだ赤ん坊だった娘はちょうど三カ月くらいで、うっすらぼんやり人の顔が見えるようになっていたんですが、私が部屋に入っていくと、ウワーッて泣き始めるんです。娘を抱くこともできなくなってしまって、あれはすごく悲しい思い出でした。役作りのために眉を落としてはいましたが、でも泣いたのはそれだけではなかったように思います。私は役にのめり込むたちですし、卑弥呼を演じているときは、卑弥呼の霊気や妖気のようなものが私の中に漂っていたんだと思います。赤ちゃんってすごく敏感だから。
また、役作りのために、ある霊媒師さんのところにも行きました。そしたら私の両側に座った事務所の二人にすぐ霊が降りて、ものすごい声を上げながら畳をかきむしる。私はそれを薄眼で観察して、演技にすごく参考になって、有難かったです。
私、子供を生む前は、かなり不思議なことがよくありました。映画のロケーションに行って、自室に入ると、「あ、このお部屋の右側にお墓があるわね」と言って、マネージャーが窓をあけると本当にあったりとか。
また別のロケのとき、ホテルの部屋で歯を磨いてたら鏡の中の黒シャツの男が、ニーッと笑いかけてきて、金歯が一本見えたんです。「何でしょうか?」って振り向いたら誰もいなくて、ドアチェーンもちゃんとかかってた、とかね。実はそこも真下がお墓だったんです。
私のそういう霊的な感覚というのは、どうも父方の祖母から受け継いだものらしくて。
三歳のころ、私は病気で、脈も止まって、「ご臨終です」とお医者さまに言われたそうですが、おばあちゃんだけが諦めないで、足の裏に何か薬草を練ったものを塗って、ずっとマッサージを続けてた。そしたらポツンと脈が戻ってきて、私が目をあけて、「お花が綺麗……」と言ったそうです。
その祖母は私が小学校四年のときに亡くなるんですけど、おばあちゃんが戸板に乗せられて、十人くらいの小人の男がダアーッと運んで行く夢を明け方に見たんです。その一時間後に祖母は亡くなりました。
私も出産するまでは本当にいろいろな体験をして、疲れましたよ、とにかく。だからイシスが何かを蘇生させるために全部の気力をそこに集中させて、そのたびに衰えていく……というのがすごくよくわかるんです。私もそうした超常現象にあうとすごく疲れて、若い頃はダウンしてしまうことがありましたから。
私は高校のころ、精神科医をめざしてガリ勉して、身体をこわしたことがありました。
それは今思うと、人間の精神の奥底を覗いてみたい、という興味からだったと思う。
考えてみると、女優というのも人間の心理を分析して役を構築していきますから、精神科医と似たところがあるような気がします。
山岸作品というのも、人間の精神の奥底を分析して、深く掘り下げて、そこに想像の翼をひろげて、ちょっと思いも寄らないような素晴しい作品世界を展開させていく。
私も山岸さんと同じで、日常的な普通の役柄にはぜんぜん興味がないんです。どこか異常で、変わったものに惹きつけられる。『魔の刻(とき)』(1985年・降旗康男監督)という母子相姦の映画に出演したときも、私が作家の先生(原作の北泉優子さん)にじかにお電話して実現したんです。母子相姦というテーマが日本人には受け入れられなくて、興行的には決して成功したとはいえませんが、私にとっては、記念すべき、演らせてもらってよかったなと思っている作品です。
山岸さんの作品にもタブーが存在しないですよね。近親相姦あり、同性愛あり、超能力あり……刺激的で大好きです。狂気の淵を覗くような、そんな興味をそそられます。
おそらく山岸さんて、狂気の世界と健全な世界を行ったり来たりしながら、それを作品に昇華させているのだと思う。つまり、作品にできるからこそ、また健全な生活に戻れるんでしょうね。
女優という仕事もまったく同様です。今回、山岸さんの作品を読み返すことで改めてそのことに気づかされ、大変面白かったです。
〔取材・構成 関容子〕