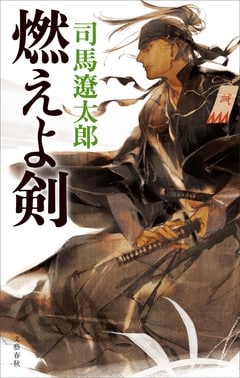司馬遼太郎の対談集『歴史を考える』は、一九七二(昭和四十七)年初めから一九七三年七月にかけて発表された対談の記録である。半世紀近く前のことになるが、時の流れに耐えていると思う。
萩原延壽(のぶとし)との対談「日本人よ“侍”に還れ」は「文藝春秋」七二年二、三月号に掲載された。山崎正和との対談「日本宰相論」は文藝春秋社の論壇誌「諸君!」七三年一月号に、綱淵謙錠(けんじょう)との「敗者の風景」はおなじく文藝春秋社の小説誌「オール讀物」七三年四月号に、山崎正和との再度の対談「日本人の世界構想」は「諸君!」七三年七月号に掲載された。その単行本化『歴史を考える』の刊行は七三年十月であった。
萩原延壽は一九二六(大正十五)年生まれだから司馬遼太郎の三歳下、旧制最後の東京帝国大学法学部政治学科から大学院に進み、のちペンシルベニア大学とオックスフォード大学で学んだ。学術性と文学性を兼ね備えた新しい領域というべき評伝『馬場辰猪(たつい)』(吉野作造賞)をはじめ、『陸奥宗光』『東郷茂徳』など日本近代史の主役とはいえないが、その人なしには近代史そのものが成立しなかったであろう重要な脇役の評伝に力を注いだ。
いくつかの大学からの誘いを断り、在野の歴史家として生きた萩原延壽に対する司馬遼太郎の信頼は篤く、この対談を行った時期の萩原は、七六年から長期にわたって朝日新聞に連載される『遠い崖 アーネスト・サトウ日記抄』の準備中であった。それは幕末の日本に長期滞在した英外交官、アーネスト・サトウが見た激動の明治革命とその後の記述であった。
司馬遼太郎との対談「日本人よ“侍”に還れ」は七一年十一月末、京都嵐山にある「大河内山荘」で行われた。そこはかつて時代劇俳優・大河内伝次郎の別荘で、広い庭園に囲まれた静かな料亭旅館であった。対談は午後四時から九時にまでおよんだが、もっぱら司馬遼太郎の能弁が目立ち、萩原延壽は要所要所で、とつとつと、かつ粘っこく発言した。この慎重さとゆかしさを司馬遼太郎は愛したのである。『遠い崖 アーネスト・サトウ日記抄』(朝日新聞社)の最終第十四巻の刊行は二〇〇一年十月十二日、その十二日後、萩原延壽は七十五歳で不帰の客となった。
本書に「日本宰相論」「日本人の世界構想」と二本の対談を提供した山崎正和は、一九三四(昭和九)年生まれ、旧満洲からの引揚者で、対談時にはまだ三十八、九歳であった。萩原延壽、綱淵謙錠は司馬遼太郎の同世代人といえるが、対談時に四十九歳から五十歳であった司馬遼太郎は十一歳下の山崎正和にも礼を尽くした話しぶりで応じた。彼は、若く才能ある人を「発見」し、対話することを好む人であった。
山崎正和は京都大学文学部哲学科を卒業したあと、同大学院美学美術史学専攻博士課程を修了した。六三年、二十九歳で戯曲『世阿弥』(岸田戯曲賞)を発表して演劇関係者を驚嘆させた彼は、六四年からフルブライト教授研究員としてイェール大学演劇科に学び、同大学講師、コロンビア大学客員教授をつとめた。
六六年帰国、七〇年に戯曲『野望と夏草』、七一年に評論集『劇的なる日本人』を書き、七二年、評伝『鷗外 闘う家長』、七三年には戯曲『実朝出帆』を発表して文芸界・演劇界の若き第一人者と目された。六〇年代後半の初対面以来たびたび司馬との対談を重ねた山崎正和は、本書収録の対談時には関西大学助教授であったが、七六年から九五年まで大阪大学文学部教授をつとめた。この間にも多くの戯曲と評論を発表し、また地方自治体と協働した演劇運動にも積極的に関わった。
対談「敗者の風景」の相手、綱淵謙錠は二四年、樺太(からふと)に生まれた。旧制中学を樺太で卒業して戦時中の四三年、旧制新潟高校に進んだ。ここで旧制高校最後の自由を短く味わったのち、四五年初め、勤労動員された富山から学徒出陣で旭川の歩兵連隊に入営した。四六年、東大に進んだものの貧窮にあえいで休学、職を転々とした。父はソ連軍占領下の樺太で死に、母と妹は戦後二年目に命からがら引揚げてきた。
五〇年、旧制高校卒の資格で特例として中央公論社を受験したが失敗、五一年、東大に復学した。卒業の五三年、再度中央公論社の試験を受けて入社した。編集者として谷崎潤一郎、子母澤寛を担当し、かたわら長谷川伸、海音寺潮五郎らの人と仕事に興味を抱いて、後年時代小説作家となる素地を養った。
七〇年十一月に自刃した三島由紀夫の葬儀を最後の仕事に、七一年春、退社した。一年間だけ、と阿川弘之、川端康成に懇請されてペンクラブ事務局長をつとめたあと作家として自立、七二年『斬(ざん)』で直木賞を受けた。『斬』をはじめ、『苔(たい)』『狄(てき)』『濤(とう)』など、漢字一字、音読みの作品題が四十八ある。一九九六年四月没。
司馬遼太郎が、日露戦争をえがいた長大な小説『坂の上の雲』を擱筆(かくひつ)したのは本書対談中の七二年七月であった。その一九七二年は、二月に連合赤軍の大量の仲間殺しが明らかになり、五月にテルアビブのリッダ空港で日本人青年三人が無差別発砲で多数を殺害、また九月にはミュンヘン五輪の選手村にパレスチナゲリラが侵入してイスラエル選手ら十一名が殺害されるという穏やかならざる年であった。
六八年四月、産経新聞紙上に連載開始された『坂の上の雲』は、司馬自身の言葉を借りれば、日本の青年たちの頭に「マルクス主義の電灯が灯って」、いっせいに走り始めた時期と重なる。そんな青年たちにいわせれば、日露戦争は「侵略戦争」で、その作家は「反動」にほかならないはずだが、『坂の上の雲』の連載時も文藝春秋社が単行本を次々刊行したときにも、左翼テロはおろか反対運動は起こらなかった。たんに作品を読まなかったか、あるいは司馬遼太郎の実証性に説得された結果であろう。
対談時期のなかばにあたる一九七三年四月初めから二週間、司馬遼太郎は南ベトナムを旅した。その年三月をもってアメリカ軍の撤退が完了した直後である。ベトナム全土が共産化すれば東南アジア全域が共産化するという「ドミノ理論」ゆえにアメリカはベトナム戦争に介入したのだが、犠牲の大きさに対し、得たものはあまりに少ないと苦く認識した結果の撤退であった。
帰国した司馬遼太郎は産経新聞紙上に「人間の集団について」と題した連載記事を書いた。その第二回には、こんなくだりがあった。
「自分で作った兵器で戦っている限りはかならずその戦争に終末期がくる。しかしながらベトナム人のばかばかしさは、それをもつことなく敵味方とも他国から、それも無料で際限もなく送られてくる兵器で戦ってきたということなのである。この驚嘆すべき機械運動的状態を代理戦争などという簡単な表現ですませるべきものではない」
「大国はたしかによくない。/しかしそれ以上によくないのは、こういう環境に自分を追いこんでしまったベトナム人自身であるということを世界中の人類が、人類の名においてかれらに鞭を打たなければどう仕様もない」
「他国」とは北ベトナムに武器援助した中国とソ連、南ベトナム側に立って直接介入したアメリカを指すのだが、非難の矛先(ほこさき)は南北ベトナム、おもに北ベトナムに向けられている。
日本を含む世界の大半が北ベトナムと民族解放戦線に心情的に味方し、かつ「民族主義」が肯定的にとらえられていた当時の時代相を回想するなら、これは「不敵な挑戦」以外のなにものでもなかった。だが、この原稿も幸か不幸か「黙殺」された。戦中派作家にして流行に惑わされず「歴史」を考える人という司馬遼太郎の本質に、まだ読者は気づいていなかった。
七二年夏、『坂の上の雲』を書き終えた司馬遼太郎は、初めてヨーロッパへ出かけた。同行したのは文藝春秋社の池島信平、文芸評論家の江藤淳であった。
池島信平は司馬遼太郎の十四歳年長、創業者の菊池寛から戦後に看板を譲ってもらい、文藝春秋新社を創業した十一人の中心人物であった。いわば「仲間立」の版元として文藝春秋社のプラグマティックな空気を司馬遼太郎はかねてから好んでいたが、池島信平と起居をともにしてさらに信頼はつのり、新聞のように世論をあおらない「文藝春秋」誌を、日本社会の平衡感覚維持に欠かすことのできない「大工さんの水準器」と評した。
江藤淳は司馬遼太郎より十歳年少である。すでに気鋭の評論家として名高かった六八年、座談会の席で司馬に、駐日アメリカ大使をつとめた日本研究者エドウィン・ライシャワーからの疑問「なぜ日本人は大久保利通ではなく、西郷南洲(隆盛)が好きなのか」を伝達したことがあった。
日本人は乃木希典、江藤新平、西郷南洲が好きで、ことに西郷が大好きだ、とライシャワーはいい、さらにこうつづけた。彼らは、うっかりすれば国を滅ぼしたかもしれない連中だろう。日本を今日まで何とか維持してきたのはその対極にあったリアリストたち、児玉源太郎であり、大隈重信であり、大久保利通ではないか。自分は何十年も日本を勉強してきたけれど、いちばんよくわからないのはこのことだ。
それは日本人自身にとっても謎だろう。その謎解明への情熱は司馬遼太郎の中にしぶとく生きつづけ、七二年一月、西郷を主人公に西南戦争をつぶさにえがく『翔ぶが如く』の連載を毎日新聞紙上で開始するのである。
樺太生まれの故郷喪失者、綱淵謙錠は西郷に関して、対談「敗者の風景」で司馬にこう語った。
「現在の旧樺太島民で、おそらく樺太が日本に戻ってくると思っている人は誰もいない」
「ではぼくたち故郷を失った者のたった一つの訴えは何かというと、樺太は正統的には日本の領土であったけれども、いまは国際的力関係で仕方がないんだ、と日本政府がはっきり言ってくれ、そうでないと、祖父とか親父たち、あるいは本人じしんが樺太で苦労したのは単なる帝国主義的侵略の尖兵をつとめたにすぎないことになり、これじゃあみんなが浮かばれない、ということなんです」
「ですから、日本政府が、お互いここで泣こうや、と言ってくれれば……。おそらく西郷隆盛だったら言ってくれたんじゃないか、と思うのです」
そんな述懐に司馬遼太郎は、こうこたえた。
「なるほど、そういわれてみると、西郷は敗者の代表だなあ」
この対談集の重要な主題のひとつが、ここに端的にあらわれた。