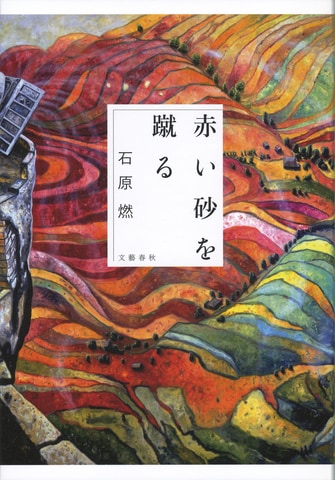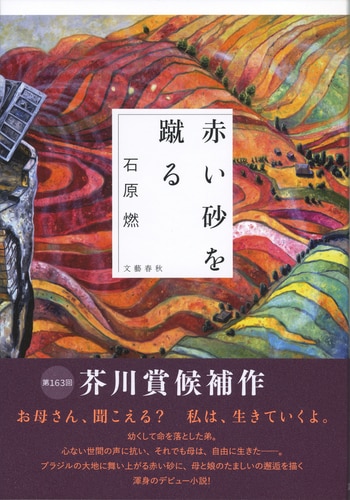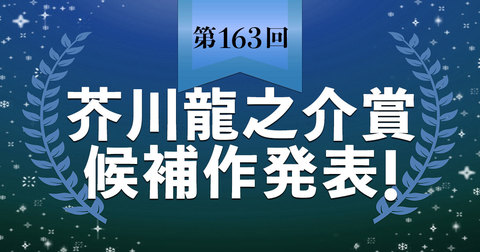けれど、この作品は娘からの母の告発では、まったくない。むしろ、ある時期は強い反発とともに距離を置いた母親を、自分を譲ることなく受容していく過程である。その受容は、この小説を書くことに踏み出したからこそ起こった、と私は思う。
最初に引いた解説文「人の声、母の歌」で、石原さんは娘としての立場から弟さんや津島さんとの記憶を書いているうち、突如、津島さんに乗り移られたかのように、津島さんの発していない津島さんの言葉を表し始める。津島さんの目となって、津島さんの言葉自体になって、自分である娘のことを語る。
その文章を読んだとき私は、石原さんの言葉が小説として離陸している瞬間を目撃したように感じた。小説の言葉になったから、石原さんの言葉の中にあって、津島さんの言葉が語り始めたのだ。
おそらくそれは、石原さんが津島さんの小説の言葉を飽和するほどに読み込んだからだろう。津島さんが亡くなってから、石原さんは津島さんの小説を、それまでとは異なる境地で繰り返し読んできたそうだ。そうやって津島さんと語っていたのだと思う。喪失と、それがもたらす豊かさについて。
石原さんの中に、言葉に姿を変えた新たな津島さんが生きるようになって初めて、石原さんは母の言葉も、自分自身の言葉も、はっきりと見出せるようになったのかもしれない。それらが響き合いながら共存しているのが、この小説だと思うのだ。
さらに本作では、津島さんが果たせなかった、芽衣子さんの声を小説の言葉として表すということが、石原さんによって実現されている。それが可能になったのも、石原さんが小説の言葉を獲得したからだろう。自分の声もその一つとして、言語として聞き取られずにいる他者の声が、初めて言葉として誰の目にも耳にも捉えられるようになる場が、小説なのだから。
実際にこの小説には、津島さんが息子さんを書いた作品群の言葉が、そこここに入り込み、千夏の言葉、芽衣子の言葉、恭子の言葉をつないでいる。私は混乱しながら、作品として生きている津島さんの命を感じ、津島さんを失ったことから誕生した関係と文学に、喜びと感謝を覚える。
それぞれ立場も内容も異なるものの、家族の関係に傷つき、喪失を生き、構造的には同じ理不尽を背負わされてきた三人の女たちは、「ひとくくりにはできない。でも、なにか同じものと戦っている」。そこには、石原さんが参加し続けているフラワーデモの感覚も、息づいているかもしれない。
最後に千夏が見出すのは、その理不尽が親子に強いてきた歪みを、「仕方なかった」と諦念によって受け入れるのではなく、それに屈しない形で選択したのだとして、それぞれの選択の結果として尊重するあり方だ。その尊重こそが、互いに我慢し合うがゆえに恨みを募らせるような関係から、人を解放する。そしてそのあり方は、母の発しえなかった母の言葉として、千夏から語られる。
踏み出す足取りの力強さを、私は寿ぎたい。