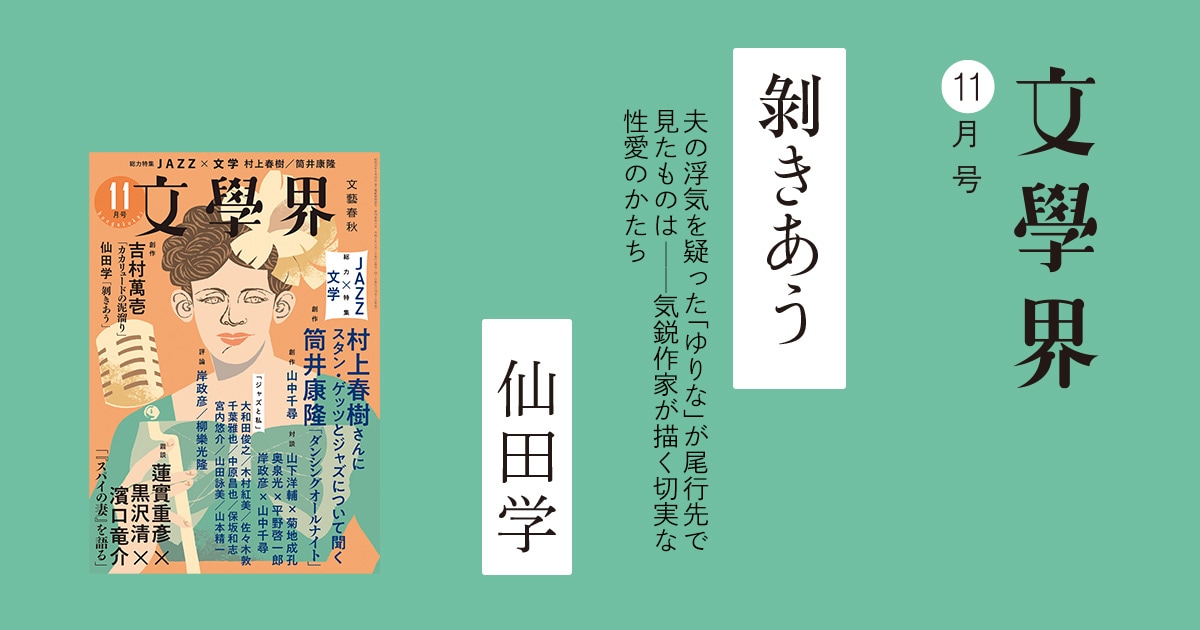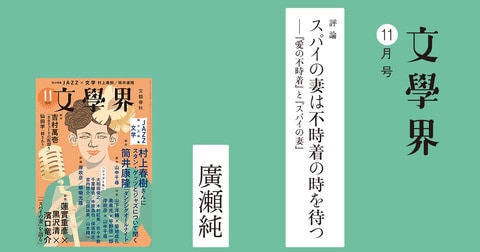時計の針は十時少し過ぎを差していた。窓の外では、蜜柑の木の葉が揺れていた。いくつかなった実の淡い黄色が、柔らかく目を撫でる。布団のなかで足を滑らせ、シーツのまだ冷えているところをゆっくりと探るうちに、少しずつ体の感覚が戻ってくる。
ベッドから降りると、ゆりなはベランダの窓を開けて乾いた風を入れた。麻地の薄いパジャマの襟元や袖口から冷えた空気が這いこんでくる。ベランダの洗濯機に洗濯物を放りこんでスイッチを押し、窓を開けたままベッドのそばに戻って、壁に立てかけてある掃除機を手に取った。
三、四日に一度、休みの日に掃除をするのはゆりなの役割だ。床をざらつかせていた埃を取り除き、足の裏で直に感じられる冷たい床の感触に集中する。
掃除機を一旦止めると、ゆりなはリビングルームの床に散らばっている秀樹のパジャマとパーカーを拾って、浴室のドアの横に置いてある脱衣かごに入れた。テーブルの上には、秀樹が朝食を摂った後の皿とマグカップが残っている。鼻をかんだらしいティッシュペーパーがその横に二つ転がっていた。
――三十年近く公務員やってて、毎晩必ず六時に帰ってくる。酒もギャンブルもいっさいやらない。休みの日にはずっと本読んでる。親父がそんなだったからさ、つまんないな、こうはなりたくないなって思ってたんだよね。
散らかした物の後始末をさせられてばかりいることをゆりながぼやくと、秀樹は決まってこう言い返した。父親が公務員であることと、身の回りの片付けをしないことにどんな関係があるのかを、ゆりなが訊き返したことは一度もない。
リビングルームと台所に掃除機をかけ終わると、ゆりなは顔を洗い、味噌汁を火にかけた。冷蔵庫から夕飯の残りの煮物を出して電子レンジに入れてから、ご飯を茶碗に盛る。皿と箸をお盆に載せてリビングルームに運び、ソファーに座って、軽く手を合わせてから味噌汁を啜った。喉から腹に降りていく。全身に熱が広がるのを感じながら、ゆりなはリモコンを手に取り、テレビをつけた。