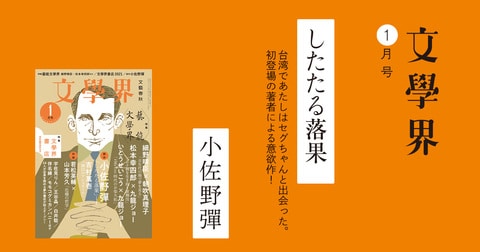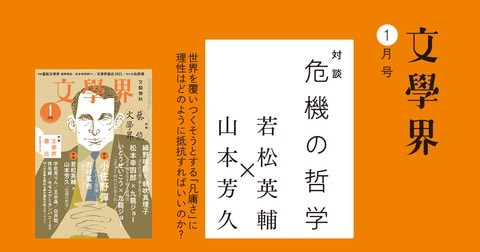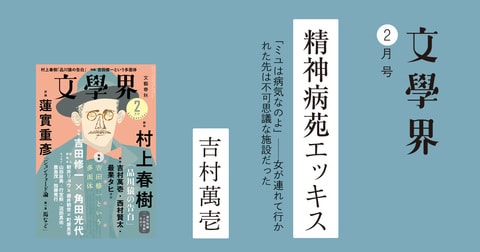殿村優一が初めて女体を知ったのは、大学三年のゴールデンウイーク中だった。
二年生の終わりの三月に、同じ学年の谷原みどりに声を掛け、映画を観て食事した帰りに「付き合って下さい」と言うと、その言葉を予想していたのか彼女は間髪を容れずに頷いた。それと同時に固い金属音が鳴り響いたので、殿村優一はビクッとして斜め後ろを見た。背後には駅前の駐輪スペースがあり、制服を着た一人の男子中学生が自転車の鍵を外したところだと分かった。殿村優一と目が合うと、中学生は反射的に下を向いた。「付き合って下さい」という言葉を聞かれたに違いなかったが、中学生らしい照れ、若しくは礼節から知らん振りを決め込んだのだなと殿村優一は思った。しかし突然駐輪場から自転車を引っ張り出し、乱暴に後輪を引き摺って車体の向きを変えたその中学生が、一瞬睨むような目で殿村優一と谷原みどりの顔を一瞥するやひょいとサドルに跨って走り去っていったその後ろ姿を見送ると、制服の黒い背中から薄っすらとした侮蔑の気配が立ち上り、渦を巻きながら尾を引いているのがはっきりと見えた気がした。
殿村優一は、周りのことなど一切目に入らずにはにかんでいるらしい谷原みどりの俯き加減のニキビ面に目を向けた。その時、谷原みどりの頭頂部の髪が薄く、脂ぎった地肌に駅前のネオンライトが反射しているのに気付いた。殿村優一はその時、中学生が感じたであろう腹立ちの感情が何となく理解出来た気がした。「付き合って下さい」という言葉に谷原みどりが頷いた時、金属音を聞いて思わず振り向いたのは、それが巨大な錠前が掛けられる音に聞こえたからだと彼は認めざるを得なかった。この先何ヶ月ひょっとすると何年かの間、殿村優一はこの玉子の殻に適当に落書きしたような顔の、目の小さな下半身デブの谷原みどりの彼氏、という牢獄に自らを閉じ込めたのである。それは同じ男ならば赤の他人の中学生でさえ腹立たしく感じるほどの、酷く軽率な行為だったのかも知れないと彼は思った。
それでも、髪を手で掻き上げ、「よろしくね」と手を差し出してきた谷原みどりのやや分厚い掌を握り返した時、遠からず自分のものになるに違いない目の前の女体の実在感に、一杯だけ飲んだビールの酔いも手伝って彼の頭はクラクラし始め、周囲の色とりどりのネオンの瞬きが自分達二人を祝福しているようにさえ感じたのだった。
所詮大人の色恋の妙味など、中学生如きには想像の外に違いないのだ。
翌日、大学の仲間達に首尾を報告すると、彼等は谷原みどりのことを蟻地獄だと言って笑った。殿村優一はさしずめ、穴に転がり落ちた蟻ということらしい。
その日の夕刻、殿村優一はマンドリンクラブの練習室に、新しい恋人を迎えにいった。彼の顔を見た谷原みどりは、周りを気にしながら微笑んだ。練習室から立ち去っていく二人に向かって、既に事情を知っているらしい女性部員達が笑って手を振るその中に、殿村優一が最もセックスしたいと願う均整の取れた体を持つ三宅百合菜の美人顔もあった。
谷原みどりとは、大学の近くの喫茶店でケーキを食べた。谷原みどりがクラブの合宿や定期演奏会のこと、家族のこと、単位のことなどを話している間、殿村優一は窄まったり伸びたり膨らんだりする彼女の分厚めの唇を眺めながら、下の唇の色や形状はどうなっているのかと盛んに考えていた。
「お婆ちゃんが、早く曾孫の顔が見たいと言うのよ」谷原みどりはそう言うと小指を立ててグラスを持ち、唇を尖らせて水を啜った。二人のコーヒーカップは、とうに空になっている。
「谷原さんは、お婆ちゃん子なんだな」
「そういうわけではないのよ」笑うと谷原みどりの目は黒ゴマのように小さくなった。
「え、そうなの?」
「お婆ちゃんは孫を甘やかすタイプではないから。でも私はお婆ちゃんが好き」
「どんなところが?」
「うーん、背筋の伸びたところとか」
「あ、それ、分かる気がするよ!」
この続きは、「文學界」1月号に全文掲載されています。